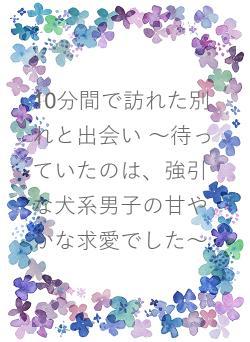***
「――あの人とは、仲がいいの?」
「え? あの人って……高崎先輩のこと?」
帰り道。すっかり歩き慣れた道を、並んで歩く。
気になって直球で聞いてみれば、音無さんはきょとんと目を瞬いてから、にこりと笑った。
「うん、そうだね。わたしが一年生の時から高崎先輩も図書委員で、いっしょだったの。優しくてすごく頼りになる先輩なんだ」
「……へぇ。そうなんだ」
「……あの、浅羽くん? 何か、怒ってる?」
前に向けていた視線をとなりに移せば、音無さんが不安そうな目をしていることに気づいた。
「いや、べつに怒ってないけど」
「ほんとに?」
「うん。ただ……」
――音無さんの笑顔が、俺だけじゃなくて、あの先輩にも向けられていたことが、面白くないって思っただけで。
音無さんが笑いかける相手が俺だけじゃないなんて、そんなの当たり前のことだ。分かってる。
だけど、それでも……音無さんの笑顔を一番近くで見れる権利がほしい。
胸の中にあるモヤモヤの正体が、そんな独占欲にも似た感情であることに、気づいてしまったんだ。