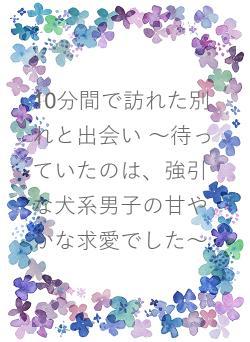「音無さんは、どこかに行くところ?」
「ううん、わたしは前の授業の先生にたのまれて、教務室にノートを届けてきたところだよ!」
「へぇ。俺だったらぜったいに断ってると思うけど……音無さんはえらいね」
ちょっぴり口角を上げて微笑んでいる浅羽くんが、わたしのことをほめてくれた。
別にだれかにほめてほしくてお手伝いを引き受けたわけではないけれど……好きな人にほめてもらえるのは、ものすごくうれしい。
それにお手伝いをしたおかげでこうして浅羽くんと会えたわけだし、声をかけてくれた先生には、むしろ感謝したいくらいかも。
「全然、えらくはないと思うけど……」
「十分えらいよ。音無さんは、もっと自分のことをほめてあげたほうがいいと思う」
「うっ……ありがとう、浅羽くん」
「え、何でお礼?」
「……浅羽くんにえらいって言ってもらえて、うれしかったから?」
「ふっ、そっか。それじゃあ、どういたしまして」
廊下のはしっこで立ち止まって、浅羽くんと他愛のない話を続ける。
――少し前までは、こんな風に浅羽くんとおしゃべりできるようになるなんて、考えてもみなかった。
それだけでも、わたしにとっては奇跡みたいにすごいことだ。
(こんな時間が、ずっとずっと続けばいいのに)
そう思っていれば――鈴の音をならしたように可愛らしい声が、浅羽くんの名前をはっきりと呼ぶ声が聞こえてきた。