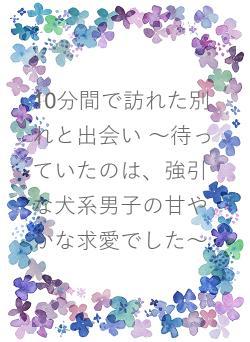「……意味わかんねぇ」
ポツリとつぶやいた声は、だれの耳にも届くことなく消えていった。
そして宣言通り、彼女は次の日も俺に声をかけてきた。
「浅羽くん、おはようございます!」
「……何で普通に話しかけられるわけ?」
「え? だって昨日、声をかけるって言いました、よね?」
「言ってたけど……振られた相手に普通に声をかけるとか、正気じゃないよね?」
「あはは、たしかに正気じゃないかもしれないですね。でも、その……わたしは、浅羽くんのことが好きなので!」
音無さんは、昨日と同じく、俺のことが「好き」だと言う。
――そこでようやく気づいた。
彼女が緊張していたのは、罰ゲームで嫌々告白することになったからだとか、そういうことじゃなくて。
本当に俺のことが好きで、思いを伝えてくれていたんだなって。
昨日はすぐに背を向けてしまってろくに顔を見ることさえしなかったけれど、よく見れば、音無さんの顔は真っ赤にそまっていた。