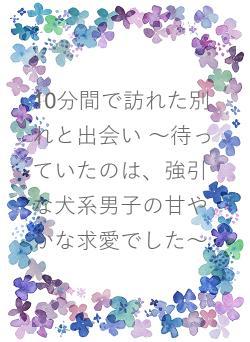「俺は、あんたのことを知らない。それなのに好きとか付き合ってとか言われても、無理だから。あと……罰ゲームなのか知らないけど、嫌なことは嫌ってはっきり言ったほうがいいんじゃない?」
ひどい言葉をぶつけたという自覚はあった。
普通の女子だったら、その場で泣いてしまうか、怒って走り去ると思うし、その後だって、俺のことを避けるだろう。
だけど、音無さんは違った。
「罰ゲーム? が何のことかは分かりませんけど……たしかに、そうですよね。ごめんなさい!」
「は?」
すでに背を向けて歩き出していた俺は、耳に届いた明るい声に、思わず振り返ってしまった。
音無さんの顔は、俺の予想に反して、涙にぬれてはいなかった。
むしろそこにあったのは、きらきらとした笑顔で。
「でもわたし、諦めませんから! これから浅羽くんにわたしのことを知ってもらえるように、がんばります! また声をかけますね!」
音無さんは礼儀正しく頭を下げると、俺を追いこして校内に走って行ってしまった。