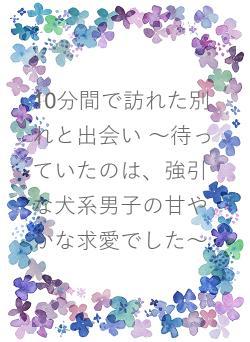「……いい加減、泣きやめば?」
「っ、うん、ごめんなさい……」
「いや、別に怒ってるわけじゃないから」
安心したら、涙が出てきて。だけど、ぜんぜん止まってくれなくて。
涙を手の甲でぬぐっていれば、そんなわたしを見た浅羽くんは、困ったような顔でため息を吐いた。
「っていうかさ、何でこんな時間に一人で歩いてたわけ? 親とかいっしょじゃないの?」
――見た目的に、多分、わたしと同い年くらいだよね? それは、きみにも言えることじゃないのかな?
そう思ったけど、あえてそれは口にしないで、わたしが一人で夜の街をふらついていた理由を話した。
「わたし、塾に行きたくなくてサボっちゃって……行く当てもないままふらふらしてたんだ。だから、罰が当たったんだと思う」
「ふーん。でもサボったのは、何か行きたくない理由があるんじゃねーの?」
「……どうして分かるの?」
「どうしてって……アンタ、見るからに真面目そうだし。理由もなくサボるようなやつには見えなかっただけ」
浅羽くんは無表情だったけど、その声がすごく優しく感じられたから……だれにも言えなかった気持ちも、気づけば言葉にしてしまっていた。