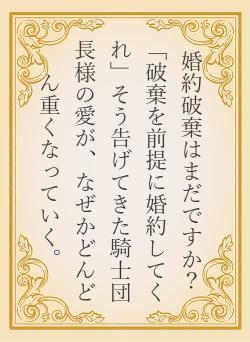エピローグ
私はノートパソコンを閉じ、ゆっくり伸びをする。
思ったよりも完成までに時間がかかってしまった。まさか、こんなぎりぎりになるなんて。
まあ先月まで受験勉強の合間にやっていたから仕方ない、と自分に甘い言葉をかける。
正直、出来はあまりよくない。気がする……。それでも卒業までに完成したことの安心感はあった。
私は藍にメッセージを送る。『完成した。明日読んで』
返事はすぐに返ってきた。『明日?! 急だな。いいけど』
卒業式の前日にわざわざ、素人が書いた、しかも本人はさほど興味もない小説を読んでくれるなんて本当に良い親友だ。彼女がいたからこそ今の私がいるのだと思う。そして、悲しいきっかけではあったけれど、そんな彼女と出会わせてくれた先輩には感謝している。
私は印刷した小説を鞄に入れ家を出る。
自転車に乗って向かうのは、学校の裏側にある墓地公園。少し丘を登り、入口に自転車を停める。斜面に並ぶお墓の三列目を迷うことなく進んでいく。
先輩が眠っているお墓の前で立ち止まり、手を合わせる。そういえば、何年も前に、私のお墓の前で泣かないで、そこに私はいない、っていう歌を聞いたな。たしかにここに先輩がいるわけではない。そもそももう、この世界のどこにもいない。でも、ここで手を合わせたくなるのが残された側の心情だ。それは、亡くなった人をいつまでも覚えていたい、想っていたいという気持ちがあるからだと思う。だから、先輩はここにいる。ずっと私の心の中に。
私は供台に印刷してきた小説をそっと置く。目を瞑り、先輩の顔を思い浮かべる。
先輩、今日は報告に来ました。先輩が書こうとしていた『終わりゆくこの美しき世界で』完成しました。
あんなに熱く語ってたのに、全然プロットもできてないし何を書こうとしていたかも分からないし、本当に苦労しましたよ。先輩の書きたかったものが書けたかはあまり自信がないですけど、まあそれなりにできたと思います。
そうだ先輩、クレーターを見に行くって書いてましたけど、隕石が落ちたらもう登場人物たちはいなくなるのでクレーターを見るような描写なんてありませんよ。
私、南アフリカに行くなんて言ってバイトもはじめて意気込んでたのに。結局行けませんでしたけど。先輩はクレーターを見てなにを書こうとしていたんですか。それだけがどうしてもわかりません。もしかして、世界が滅亡したあと再生した地球を書こうとしていたんですか? 私には書けませんでした。あと、先輩は主人公を男子生徒にするつもりだったと思いますけど、難しくて主人公は女子生徒になりました。だって、カズハの想いが溢れて溢れてしかたなかったんです。おおめにみてくださいね。
藍はこの物語を読んで、泣いてくれますかね――。
そして私は、いつか先輩と見た夕焼けの街を眺めてから家へ帰った。
翌日、卒業式を明日に控えた、午前で終わった学校の放課後。
誰もいなくなった教室で机に向かい、真剣な表情で紙を一枚ずつめくる私の親友。
そんな彼女を私はただじっと見つめ、待っていた。そして、どれくらいの時間が経ったのか、彼女はゆっくりと顔をあげる。
「なんか、らしくないね。荒削りというか」
「私もそう思う」
「あと、なんか設定詰め込み過ぎじゃない?」
「私もそう思う」
「でも、それがお兄っぽい感じもする」
「それは、よかった……」
読み終えた藍の顔を覗き込むけれど、涙は滲んでいない。やっぱり、泣けるような物語は私には書けなかったか。先輩すみません、と心の中で謝罪する。
廃部にはならなかったけど、部員が増えることもなかった。藍のことを泣かせることもできなかった。私はなにひとつ先輩の想いを継ぐことができなかったんだ。
「このお話、泣けないよね……」
思わず溢していた。藍は肩を落とす私を見てフッと笑う。こんな表情は初めて見る。
「私、泣かないって決めてるから」
「え、どうして?」
「もう、一生分泣いたからね」
「そう、なの? いつ?」
「お兄が死んだあとだよ。いっつも一人で喋ってさ、私を笑わそうとしてるのか変な話きかされたり、毎日騒がしかったのが、急にいなくなったんだよ。本当、生活が一変した。お兄がもういないんだと思ったら見える景色が暗くなった」
でも、と続ける藍は項垂れる私の頭を優しく撫でる。
「私より泣いてる一花を見て、泣かなくなった。だから、私の涙はお兄のところに置いてきたの」
私は、藍の泣いているところを見たことはなかったけど、そうだよね。お兄さんが亡くなったんだもん。あんなに妹思いだったし、先輩はとっても素敵な人だ。そりゃ泣くよね。
先輩、藍は泣いたそうですよ。見てましたか? 自分が死んで泣かせるなんて先輩は悪い人です。
私も泣かせたかったです。いつか絶対に泣かせます。もちろんいい意味で、です。
「次はもっと感動させられるお話書くから」
意気込む私に、すごく面白かったよ、と本心かどうかはわからない言葉を受け取る。
でも、それ以上はもう何も聞かなかった。
「一花、ありがとう」
そう言って満面の笑みを浮かべてくれた藍に、この笑顔を見られたことが、私の青春を捧げた一番の意味だと思った。
私はノートパソコンを閉じ、ゆっくり伸びをする。
思ったよりも完成までに時間がかかってしまった。まさか、こんなぎりぎりになるなんて。
まあ先月まで受験勉強の合間にやっていたから仕方ない、と自分に甘い言葉をかける。
正直、出来はあまりよくない。気がする……。それでも卒業までに完成したことの安心感はあった。
私は藍にメッセージを送る。『完成した。明日読んで』
返事はすぐに返ってきた。『明日?! 急だな。いいけど』
卒業式の前日にわざわざ、素人が書いた、しかも本人はさほど興味もない小説を読んでくれるなんて本当に良い親友だ。彼女がいたからこそ今の私がいるのだと思う。そして、悲しいきっかけではあったけれど、そんな彼女と出会わせてくれた先輩には感謝している。
私は印刷した小説を鞄に入れ家を出る。
自転車に乗って向かうのは、学校の裏側にある墓地公園。少し丘を登り、入口に自転車を停める。斜面に並ぶお墓の三列目を迷うことなく進んでいく。
先輩が眠っているお墓の前で立ち止まり、手を合わせる。そういえば、何年も前に、私のお墓の前で泣かないで、そこに私はいない、っていう歌を聞いたな。たしかにここに先輩がいるわけではない。そもそももう、この世界のどこにもいない。でも、ここで手を合わせたくなるのが残された側の心情だ。それは、亡くなった人をいつまでも覚えていたい、想っていたいという気持ちがあるからだと思う。だから、先輩はここにいる。ずっと私の心の中に。
私は供台に印刷してきた小説をそっと置く。目を瞑り、先輩の顔を思い浮かべる。
先輩、今日は報告に来ました。先輩が書こうとしていた『終わりゆくこの美しき世界で』完成しました。
あんなに熱く語ってたのに、全然プロットもできてないし何を書こうとしていたかも分からないし、本当に苦労しましたよ。先輩の書きたかったものが書けたかはあまり自信がないですけど、まあそれなりにできたと思います。
そうだ先輩、クレーターを見に行くって書いてましたけど、隕石が落ちたらもう登場人物たちはいなくなるのでクレーターを見るような描写なんてありませんよ。
私、南アフリカに行くなんて言ってバイトもはじめて意気込んでたのに。結局行けませんでしたけど。先輩はクレーターを見てなにを書こうとしていたんですか。それだけがどうしてもわかりません。もしかして、世界が滅亡したあと再生した地球を書こうとしていたんですか? 私には書けませんでした。あと、先輩は主人公を男子生徒にするつもりだったと思いますけど、難しくて主人公は女子生徒になりました。だって、カズハの想いが溢れて溢れてしかたなかったんです。おおめにみてくださいね。
藍はこの物語を読んで、泣いてくれますかね――。
そして私は、いつか先輩と見た夕焼けの街を眺めてから家へ帰った。
翌日、卒業式を明日に控えた、午前で終わった学校の放課後。
誰もいなくなった教室で机に向かい、真剣な表情で紙を一枚ずつめくる私の親友。
そんな彼女を私はただじっと見つめ、待っていた。そして、どれくらいの時間が経ったのか、彼女はゆっくりと顔をあげる。
「なんか、らしくないね。荒削りというか」
「私もそう思う」
「あと、なんか設定詰め込み過ぎじゃない?」
「私もそう思う」
「でも、それがお兄っぽい感じもする」
「それは、よかった……」
読み終えた藍の顔を覗き込むけれど、涙は滲んでいない。やっぱり、泣けるような物語は私には書けなかったか。先輩すみません、と心の中で謝罪する。
廃部にはならなかったけど、部員が増えることもなかった。藍のことを泣かせることもできなかった。私はなにひとつ先輩の想いを継ぐことができなかったんだ。
「このお話、泣けないよね……」
思わず溢していた。藍は肩を落とす私を見てフッと笑う。こんな表情は初めて見る。
「私、泣かないって決めてるから」
「え、どうして?」
「もう、一生分泣いたからね」
「そう、なの? いつ?」
「お兄が死んだあとだよ。いっつも一人で喋ってさ、私を笑わそうとしてるのか変な話きかされたり、毎日騒がしかったのが、急にいなくなったんだよ。本当、生活が一変した。お兄がもういないんだと思ったら見える景色が暗くなった」
でも、と続ける藍は項垂れる私の頭を優しく撫でる。
「私より泣いてる一花を見て、泣かなくなった。だから、私の涙はお兄のところに置いてきたの」
私は、藍の泣いているところを見たことはなかったけど、そうだよね。お兄さんが亡くなったんだもん。あんなに妹思いだったし、先輩はとっても素敵な人だ。そりゃ泣くよね。
先輩、藍は泣いたそうですよ。見てましたか? 自分が死んで泣かせるなんて先輩は悪い人です。
私も泣かせたかったです。いつか絶対に泣かせます。もちろんいい意味で、です。
「次はもっと感動させられるお話書くから」
意気込む私に、すごく面白かったよ、と本心かどうかはわからない言葉を受け取る。
でも、それ以上はもう何も聞かなかった。
「一花、ありがとう」
そう言って満面の笑みを浮かべてくれた藍に、この笑顔を見られたことが、私の青春を捧げた一番の意味だと思った。