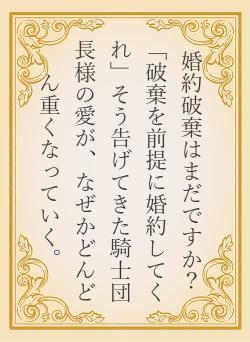『終わりゆくこの美しき世界で』 花森 カズハ
夜行バスに乗り、十二時間かけて目的の場所へとやってきた。太平洋の水平線から昇る日の出を見られる場所。
「カズハちゃん、もう来てしまってなんだけど、こんな遠いところまできてご両親は心配しないの?」
「大丈夫です。心配はしてるかもしれないですけど、私がやりたことになにも反対はしないので」
元々厳しい親だったわけではない。その上、一年後に世界が滅亡することが決まっている今、好きなことをすればいいと言われている。それは自分たちも子どもを放って好きなことをしているからではあるが。私はそれが嬉しいわけでも寂しいわけでもなく、ただ本当に好きなようにしている。今回の旅も行きたいと言えば、行ってらっしゃいと言われた。さすがに男の先輩と二人きりでとは言っていないけれど。
「先輩こそ大丈夫ですか? けっこう厳しいお家って聞きましたけど」
「大丈夫。何も言わずに出てきたから」
「ええ?! それ全然大丈夫じゃないと思いますよ。連絡した方がいいんじゃないですか?」
「今連絡したらすぐ帰らないといけなくなるからね。帰ってから存分に怒られるからいいの」
本当に大丈夫なのだろうか。私に付き合っているせいで怒られるなんて申し訳ないが、先輩はずっと大丈夫と言っていた。親の雷なんてたいしたことない、隕石が落ちてくるより怖いものなんてないでしょ、なんて笑いながら。
夜行バスを降りたバス停から路線バスに乗り換え、やってきたのは太平洋が一望できる海岸だった。田舎ではあるけれど、観光名所になっていて人もそれなりに多い。ご飯屋さんやお土産屋さん、大きくはないが水族館まである。
バスを降りてまずは浜辺へ出てみた。岬と岬の間に広がる弓状の砂浜を先輩と並んでゆっくりと歩く。相変わらず気温は高いけれど、海風が気持ちいい。
天気も良くて、どこまでも続く海の青と、雲一つない澄んだ空の青が遥か向こうで溶け合っている景色は、今まで私は見てきたどんなものよりも綺麗だった。きっと、明日の朝焼けはもっと綺麗だろう。
「いいところだね。カズハちゃん、連れてきてくれてありがとう」
「そんな……こちらこそ一緒に来てくれてありがとうございます」
きっと、先輩がいるからこんなにも綺麗に見えるのだと思う。
岬の端には小さな神社があり、海上安全や商売繫盛などのご利益があるらしい。あまり自分たちには関係ないご利益だね、なんて言いながらもこの場所の神様に挨拶をかねてお参りした。そして私は全然関係ないことをお願いした。叶うことのない願い。いつまでもこの綺麗な世界が続きますように。
岬の神社でお参りした後は、休憩所のベンチに座りひと息つく。少しずつ、日も傾きつつある。朝日が見えるということは夕日はここからは見えない。この水平線に沈んでいく夕日も見られたらいいけれどそんな都合よくはできていない。残念だけど仕方のないことだ。
そのまましばらく海を眺めていた。何の予定も立てず目的の場所に来たけれど、朝日を見るまでまだ相当時間がある。というより、夜を明かさなければいけない。いったん街へ行ってどこかに泊まる? 漫画喫茶とかで早朝まで時間潰す? でも、それではここに来るためのバスは動いていないし、街から歩いて来られるような場所ではない。どうしようと考えていたら、先輩がおもむろに立ち上がった。
「展望台、行こう」
「え? もう行くんですか? 夕日とかは見られませんよ?」
「それでも、綺麗だと思う」
歩き出す先輩について浜辺から山側へ登っていく。展望台は比較的新しくできたもので、元々は灯台のある場所として知られている。坂道を登るとその灯台が見えてきた。そして広場に出ると丘を囲む柵の前に、高さ三メートルほどの展望台があった。他には何もなくて、この時間帯人もいなくて、ただ静かに佇んでいる。そんな展望台だった。
二人で展望台に登り、さっきとは違う目線で海を眺めた。夕日は見えないけれど、赤く染まった海が少しずつその灯りを消していく様子をじっと見つめる。
「綺麗、ですね」
「そう言ったでしょ」
先輩はフッと笑う。いつの間にか日は沈み、空には星たちがキラキラと瞬いている。
「先輩がくれたこのラピスラズリみたいです」
私の左腕にはラピスラズリのブレスレットがつけられている。お守りの効果なのかはわからないけれど、このブレスレットを見ると心が落ち着いた。
先輩は、空を見上げたまま私の左手をそっと握る。
「ねえ、小説の最後のシーンって、どんなシーンなの?」
「えっと……ヒロインが幼馴染の彼氏に病気を告白するんです。病気だから別れようって言うんですけど、彼氏は絶対に別れないって。病気はきっと治るし、もしだめでもずっとそばにいるって、朝日を背に抱きしめるんです」
ちょっとベタすぎますかね、と笑ってみたが、先輩は真剣な表情で握る手の力を強めた。
「カズハちゃん、俺、帰ったらもう連絡とれない。学校も辞めるし」
「え?! どうしてですか?!」
突然の告白に私は驚きを隠せずに、勢いよく先輩の方を向く。たしかにあと一年を好きに生きると言って学校を辞めていく生徒もたくさんいる。でも、先輩はそんなことは全く言っていなかったし、あと一年、今まで通り過ごすのだと思っていたのに。それに、連絡すらとれないなんてどういうことだろう。
「俺、風邪気味なんだよね」
呟いた先輩の言葉に心臓が跳ねる。風邪なんて、だれでもひく。でも、うるさいくらいにどんどん鼓動は早くなる。
「そ、そうなんですね。私も、先月風邪ひきましたよ」
「もう、一ヶ月くらい治らないんだ」
「それは随分と手強い風邪ですね。こんなところにいないで早く帰って休んだほうが――」
「家には帰るつもりない」
「え……?」
それが、なにを意味しているのか、なんとなくわかった。でも気づかないふりをした。
先輩は星空を見上げたあと、ぎゅっと手を握り、ゆっくりと私の方を向く。今にも泣き出しそうな悲しい笑顔で私を見る。
『手をつないで、お互いだけを見つめて、笑い合って迎えます』
「先輩、私は笑いませんよ。だって、最後の瞬間はまだです。あと一年もあります」
「俺は、明日で終わりにするつもり」
やっぱりそうだ。先輩はきっと自分で死ぬつもりなんだ。この旅が終わったら帰らずに命を終えようとしているんだ。四年前から自殺者は急激に増えている。ゾンビウイルスに感染していると気づいた人がゾンビになるくらいならと、どうせ世界は滅亡するんだからとその命を終わらせる。
自我をなくして人を襲うような生き物になるって怖いと思う。そんなのなりたくないに決まっている。でも、まだ自分を保ったまま死ぬなんてもっと怖いはずだ。それに、死んでしまえば本当にこの世界からいなくなってしまう。
「知ってますか? 自分で命を絶ったら生まれ変われないらしいですよ」
「生まれ変わった時、地球はあるのかな」
「恐竜が絶滅するくらいの巨大隕石が落ちてきても、こんなに生命に溢れてるじゃないですか」
「でも、太陽が膨張していつか地球は飲み込まれて消滅するよ」
「それは、もっともっともーっと先です」
「これ以上暑い地球に生まれるのは嫌だな」
「私は、先輩がいなくなるのが嫌です。たとえ、違う場所にいたとしても、私のことがわからなくなったとしても、先輩と同じときに最後を迎えたいです」
「俺は、俺のままで終わりたいよ。カズハちゃんを覚えているまま死にたい」
「嫌です……嫌ですっ! 先輩じゃなくなってもいい! 私のこと覚えていなくていい! 先輩に、この世界にいて欲しいです! 死にたいなんて言わないで!」
私は泣きじゃくった。わんわん泣いた。私の泣き声がどこまでも続く海の果てまで届くのではないかと思うほど。先輩は私をぎゅっと抱きしめた。気づけば、水平線の向こうから朝日が滲んでいた――。
この世界はどうせ終わる。それなのに、あがいていたい自分がいる。目に映る景色が、まだこんなにも綺麗だったから。
それから始発のバスに乗って駅まで向かい、帰りは電車を何本も乗り継いで帰った。
私たちはもう何も話さなかった。それでも、繋いだ手は離さなかった。
いつものように家まで送ってくれた先輩。最後に、私の左手を取り、ラピスラズリをそっと撫でる。『最後の瞬間、俺を思い出してね』そう言って先輩も自宅へと向かって帰っていった。
私はそれから部屋に引きこもった。しばらく開いていなかったノートパソコンを開く。
そして夢中で物語を綴った。書きたい。書かなければ。今まで見てきたこと、感じたこと全てを詰め込みたくなった。
先輩が私に教えてくれたこと、残してくれたことを無駄にはしたくない。
先輩と見た景色が、先輩の悲しく笑う顔が、目に焼き付いて離れなかった。
夏休みが明けて学校行くと、二年生の先輩たちが『高屋くんが入所したらしい』と噂していた。私は自分のエゴを先輩に押し付けてしまったかもしれない。先輩にとって酷な選択をさせてしまったかもしれない。先輩に申し訳ないことをしたかもしれないと思いながらも、ほっとしている自分がいた。
会えなくても、私のことを覚えていなくても、先輩は、まだこの世界にいる。
理不尽なこと、苦しいこと、悲しいことは続いていくのかもしれない。それを仕方ないと言って受け入れるしかないのかもしれない。
だって、どうせ世界は終わる。
それでも、全てが終わるその瞬間まで、私は生きる意味を探してもがいていたい。胸を張って終われるように。それが、エゴを押し付けてしまって先輩に、私ができることだと思うから。
『終わりゆくこの美しき世界で』 完
夜行バスに乗り、十二時間かけて目的の場所へとやってきた。太平洋の水平線から昇る日の出を見られる場所。
「カズハちゃん、もう来てしまってなんだけど、こんな遠いところまできてご両親は心配しないの?」
「大丈夫です。心配はしてるかもしれないですけど、私がやりたことになにも反対はしないので」
元々厳しい親だったわけではない。その上、一年後に世界が滅亡することが決まっている今、好きなことをすればいいと言われている。それは自分たちも子どもを放って好きなことをしているからではあるが。私はそれが嬉しいわけでも寂しいわけでもなく、ただ本当に好きなようにしている。今回の旅も行きたいと言えば、行ってらっしゃいと言われた。さすがに男の先輩と二人きりでとは言っていないけれど。
「先輩こそ大丈夫ですか? けっこう厳しいお家って聞きましたけど」
「大丈夫。何も言わずに出てきたから」
「ええ?! それ全然大丈夫じゃないと思いますよ。連絡した方がいいんじゃないですか?」
「今連絡したらすぐ帰らないといけなくなるからね。帰ってから存分に怒られるからいいの」
本当に大丈夫なのだろうか。私に付き合っているせいで怒られるなんて申し訳ないが、先輩はずっと大丈夫と言っていた。親の雷なんてたいしたことない、隕石が落ちてくるより怖いものなんてないでしょ、なんて笑いながら。
夜行バスを降りたバス停から路線バスに乗り換え、やってきたのは太平洋が一望できる海岸だった。田舎ではあるけれど、観光名所になっていて人もそれなりに多い。ご飯屋さんやお土産屋さん、大きくはないが水族館まである。
バスを降りてまずは浜辺へ出てみた。岬と岬の間に広がる弓状の砂浜を先輩と並んでゆっくりと歩く。相変わらず気温は高いけれど、海風が気持ちいい。
天気も良くて、どこまでも続く海の青と、雲一つない澄んだ空の青が遥か向こうで溶け合っている景色は、今まで私は見てきたどんなものよりも綺麗だった。きっと、明日の朝焼けはもっと綺麗だろう。
「いいところだね。カズハちゃん、連れてきてくれてありがとう」
「そんな……こちらこそ一緒に来てくれてありがとうございます」
きっと、先輩がいるからこんなにも綺麗に見えるのだと思う。
岬の端には小さな神社があり、海上安全や商売繫盛などのご利益があるらしい。あまり自分たちには関係ないご利益だね、なんて言いながらもこの場所の神様に挨拶をかねてお参りした。そして私は全然関係ないことをお願いした。叶うことのない願い。いつまでもこの綺麗な世界が続きますように。
岬の神社でお参りした後は、休憩所のベンチに座りひと息つく。少しずつ、日も傾きつつある。朝日が見えるということは夕日はここからは見えない。この水平線に沈んでいく夕日も見られたらいいけれどそんな都合よくはできていない。残念だけど仕方のないことだ。
そのまましばらく海を眺めていた。何の予定も立てず目的の場所に来たけれど、朝日を見るまでまだ相当時間がある。というより、夜を明かさなければいけない。いったん街へ行ってどこかに泊まる? 漫画喫茶とかで早朝まで時間潰す? でも、それではここに来るためのバスは動いていないし、街から歩いて来られるような場所ではない。どうしようと考えていたら、先輩がおもむろに立ち上がった。
「展望台、行こう」
「え? もう行くんですか? 夕日とかは見られませんよ?」
「それでも、綺麗だと思う」
歩き出す先輩について浜辺から山側へ登っていく。展望台は比較的新しくできたもので、元々は灯台のある場所として知られている。坂道を登るとその灯台が見えてきた。そして広場に出ると丘を囲む柵の前に、高さ三メートルほどの展望台があった。他には何もなくて、この時間帯人もいなくて、ただ静かに佇んでいる。そんな展望台だった。
二人で展望台に登り、さっきとは違う目線で海を眺めた。夕日は見えないけれど、赤く染まった海が少しずつその灯りを消していく様子をじっと見つめる。
「綺麗、ですね」
「そう言ったでしょ」
先輩はフッと笑う。いつの間にか日は沈み、空には星たちがキラキラと瞬いている。
「先輩がくれたこのラピスラズリみたいです」
私の左腕にはラピスラズリのブレスレットがつけられている。お守りの効果なのかはわからないけれど、このブレスレットを見ると心が落ち着いた。
先輩は、空を見上げたまま私の左手をそっと握る。
「ねえ、小説の最後のシーンって、どんなシーンなの?」
「えっと……ヒロインが幼馴染の彼氏に病気を告白するんです。病気だから別れようって言うんですけど、彼氏は絶対に別れないって。病気はきっと治るし、もしだめでもずっとそばにいるって、朝日を背に抱きしめるんです」
ちょっとベタすぎますかね、と笑ってみたが、先輩は真剣な表情で握る手の力を強めた。
「カズハちゃん、俺、帰ったらもう連絡とれない。学校も辞めるし」
「え?! どうしてですか?!」
突然の告白に私は驚きを隠せずに、勢いよく先輩の方を向く。たしかにあと一年を好きに生きると言って学校を辞めていく生徒もたくさんいる。でも、先輩はそんなことは全く言っていなかったし、あと一年、今まで通り過ごすのだと思っていたのに。それに、連絡すらとれないなんてどういうことだろう。
「俺、風邪気味なんだよね」
呟いた先輩の言葉に心臓が跳ねる。風邪なんて、だれでもひく。でも、うるさいくらいにどんどん鼓動は早くなる。
「そ、そうなんですね。私も、先月風邪ひきましたよ」
「もう、一ヶ月くらい治らないんだ」
「それは随分と手強い風邪ですね。こんなところにいないで早く帰って休んだほうが――」
「家には帰るつもりない」
「え……?」
それが、なにを意味しているのか、なんとなくわかった。でも気づかないふりをした。
先輩は星空を見上げたあと、ぎゅっと手を握り、ゆっくりと私の方を向く。今にも泣き出しそうな悲しい笑顔で私を見る。
『手をつないで、お互いだけを見つめて、笑い合って迎えます』
「先輩、私は笑いませんよ。だって、最後の瞬間はまだです。あと一年もあります」
「俺は、明日で終わりにするつもり」
やっぱりそうだ。先輩はきっと自分で死ぬつもりなんだ。この旅が終わったら帰らずに命を終えようとしているんだ。四年前から自殺者は急激に増えている。ゾンビウイルスに感染していると気づいた人がゾンビになるくらいならと、どうせ世界は滅亡するんだからとその命を終わらせる。
自我をなくして人を襲うような生き物になるって怖いと思う。そんなのなりたくないに決まっている。でも、まだ自分を保ったまま死ぬなんてもっと怖いはずだ。それに、死んでしまえば本当にこの世界からいなくなってしまう。
「知ってますか? 自分で命を絶ったら生まれ変われないらしいですよ」
「生まれ変わった時、地球はあるのかな」
「恐竜が絶滅するくらいの巨大隕石が落ちてきても、こんなに生命に溢れてるじゃないですか」
「でも、太陽が膨張していつか地球は飲み込まれて消滅するよ」
「それは、もっともっともーっと先です」
「これ以上暑い地球に生まれるのは嫌だな」
「私は、先輩がいなくなるのが嫌です。たとえ、違う場所にいたとしても、私のことがわからなくなったとしても、先輩と同じときに最後を迎えたいです」
「俺は、俺のままで終わりたいよ。カズハちゃんを覚えているまま死にたい」
「嫌です……嫌ですっ! 先輩じゃなくなってもいい! 私のこと覚えていなくていい! 先輩に、この世界にいて欲しいです! 死にたいなんて言わないで!」
私は泣きじゃくった。わんわん泣いた。私の泣き声がどこまでも続く海の果てまで届くのではないかと思うほど。先輩は私をぎゅっと抱きしめた。気づけば、水平線の向こうから朝日が滲んでいた――。
この世界はどうせ終わる。それなのに、あがいていたい自分がいる。目に映る景色が、まだこんなにも綺麗だったから。
それから始発のバスに乗って駅まで向かい、帰りは電車を何本も乗り継いで帰った。
私たちはもう何も話さなかった。それでも、繋いだ手は離さなかった。
いつものように家まで送ってくれた先輩。最後に、私の左手を取り、ラピスラズリをそっと撫でる。『最後の瞬間、俺を思い出してね』そう言って先輩も自宅へと向かって帰っていった。
私はそれから部屋に引きこもった。しばらく開いていなかったノートパソコンを開く。
そして夢中で物語を綴った。書きたい。書かなければ。今まで見てきたこと、感じたこと全てを詰め込みたくなった。
先輩が私に教えてくれたこと、残してくれたことを無駄にはしたくない。
先輩と見た景色が、先輩の悲しく笑う顔が、目に焼き付いて離れなかった。
夏休みが明けて学校行くと、二年生の先輩たちが『高屋くんが入所したらしい』と噂していた。私は自分のエゴを先輩に押し付けてしまったかもしれない。先輩にとって酷な選択をさせてしまったかもしれない。先輩に申し訳ないことをしたかもしれないと思いながらも、ほっとしている自分がいた。
会えなくても、私のことを覚えていなくても、先輩は、まだこの世界にいる。
理不尽なこと、苦しいこと、悲しいことは続いていくのかもしれない。それを仕方ないと言って受け入れるしかないのかもしれない。
だって、どうせ世界は終わる。
それでも、全てが終わるその瞬間まで、私は生きる意味を探してもがいていたい。胸を張って終われるように。それが、エゴを押し付けてしまって先輩に、私ができることだと思うから。
『終わりゆくこの美しき世界で』 完