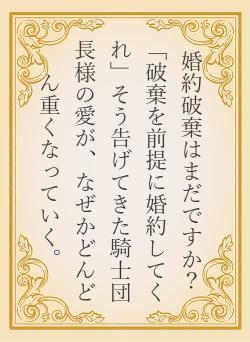『終わりゆくこの美しき世界で』 花森カズハ
「えー、風邪にはくれぐれも気を付けてください。少しでもおかしいと感じたらすぐに医療機関を受診し――」
終業式が終わり、あとはホームルームで担任の話を聞くだけだと思っていたら、校長先生の話よりも長い話を聞かされている。しかも同じことを何度も何度も。
風邪に気を付けなさいって言っているけれど、本当は風邪のことではない。ゾンビウイルスに気をつけろと言っている。そんなの、気をつけようがないのに。
ただ、感染した初期症状として風邪症状があるらしい。はじめは風邪かなと思っていたら、なかなか治らず、一ヶ月ほど経つと意識が混濁しはじめ、そしてゾンビ化する。
私も先週風邪で熱を出したとき、もうだめだと思った。このままゾンビになって自我をなくして施設に入れられてなんの感情もないまま最後の日を迎えるんだと。でも、薬をのんで一日寝ていたら次の日には頭はスッキリしていて、なにごともなく今に至る。
空気感染でも飛沫感染でも血液感染でもないゾンビウイルスは、もはや宇宙人が人間を選別して感染させているのではないかという噂まで飛び交っている。まさに運としか言いようのないウイルスだ。
そんなことを考えているうちに担任の話は終わった。私は荷物を持って、急いで先輩と待ち合わせ場所である校門へと向かう。きっと、待たせているはずだ。と思っていたら下駄箱を出たところで先輩と会った。先輩も急いでいたらしく、少し息が切れている。そんなお互いの様子に顔を見合わせ笑った。
学校を出て、電車に乗って、遊園地にやってきた。今日まで学校ということもあり、人はそこまで多くない。それと、昼間は常に熱中症アラートが発令されている。小さな子どもや体調に心配のある人たちはこの時間帯に遊園地などの外での施設で遊ばなくなっている。
太陽の膨張により、地球温暖化が急速に進んでいるのだ。宇宙人襲来と関係があるのかはわからないけれど、これも四年前からだ。
制服も冷感の長袖シャツだし、露出部の日焼け止めは絶対に欠かせない。水分はいつも持ち歩いているし、鞄には冷却シートも入っている。こんな習慣ももう四年になれば、慣れてきた。この暑さにはあと一年で慣れることはないのだろうけど。
それでも、汗をにじませながら、煌めく空間にキラキラとした目を向ける先輩の横顔を見るとこれくらいの暑さなんてまだまだどうってことないように思える。
「先輩、すごく嬉しそうですね」
「実は遊園地めちゃくちゃ久しぶりなんだよね。ワクワクしてる」
「私も楽しみにしてました。行きましょう!」
「まずはジェットコースターからだね」
「いきなりですか?!」
なんて言いながらもジェットコースターは私も好きだ。あの爽快感は何度乗っても飽きない。それこそ暑さなんて吹き飛ぶほど。
私たちは何度もジェットコースターに乗った。コーヒーカップもメリーゴーランドも空中ブランコも。ずっと楽しくて、先輩も楽しそうで、それだけで笑顔になれる。本当にここは魔法の場所だと思った。
何時間も遊び、日も傾きはじめたころ、最後に観覧車に乗ることになった。
揺れるゴンドラへ支えられながら乗り込み、向かい合って座る。なんだか照れくさくてすぐに外の景色を眺めた。
「わあ、きれい……」
夕日に照らされた街の景色、その向こうにある山々、茜色の空。目に映る全てのものが輝いている。
「ほんと、きれいだね」
先輩も景色を眺め、優しい笑みを浮かべていた。
「私、本当はもう書けなくてもいいかなって思ってたんです。書く意味あるのかなって」
「うん」
「でも、やっぱり書きたくなりました。書きます私」
視線を先輩に戻すと先輩も私を見ていた。そして、やっぱり優しい笑みを私に向ける。
「カズハちゃんなら、きっと書けるよ。きみの、純粋で真っ直ぐで、それでいてどこか危なっかしい感情が隠れてる、そんな話は人の心を動かす力を持っていると思う」
きっと先輩は、私が行き詰ってるだけじゃなく、書く気力を失っていることにも気づいていたはずだ。それでも捨てきれずにもがいている私のことも。
私が小説を書き始めたのは、中学生になったころだった。当時は謎のゾンビウイルスにより、学校へ行くことも、外へ出ることさえ制限されていた。私は家で本を読み漁った。没頭した。いつしか自分で書き始めていた。自分だけの物語を。ドキドキしてワクワクして、苦しくて切なくて、それでも心はときめいて、書き終わったときにはなぜか涙が溢れていた。読み返すと文章はめちゃくちゃだし、なにが言いたかったのかよくわからないけれど、書いているときだけはたしかに私は物語の中に生きていて、その世界を駆け抜けていた。
謎のウイルスが空気感染しないとわかると日常は戻ったけれど、次は隕石が落ちて世界は滅亡するなんて言われた。神様はよほど地球が嫌いみたいだ。いや宇宙人か。
それでも私は物語を書き続けた。でも、続けられなかった。それから一年がたち、刻一刻と世界滅亡が近づいてくるとだんだんと書けなくなった。書きたいのに、書けない。
そんな中、入学した高校で文芸部があることを知った。説明会でもらったパンフレットには載っていなかったのに。おそるおそる訪れた文芸部で先輩と出会った。私は今まで書いた中で一番出来がいいと思う小説を先輩にみせた。
『このお話を読むと君のことがよくわかるよ』それが先輩の感想だった。
それから平凡な部活動が始まった。お互い机に向かって作業をしながら世間話なんかをする。先輩はたくさん原稿用紙に執筆しているけれど、私はノートに種書きしたり相関図を書いたり謎の詩を書いてみたりしているだけ。それでも、穏やかな時間が流れるこの部活が好きだった。
だから先輩が『執筆、行き詰ってるの?』と聞いてきたことには驚いた。そういうことは言わないのかと思っていた。入部して三ヶ月、一度も書いていない私にずっと何も言ってこなかったから――。
「カズハちゃん」
先輩は私の名前を呼ぶと、鞄から手のひらほどの小さな箱を取り出し差し出してくる。
「これは……?」
「プレゼントだよ」
「プレゼント? どうして? 私誕生日でもなんでもないですよ」
「でも今日俺たちは幼馴染カップルでしょ。恋人にプレゼントするのに理由なんていらないよ。開けてみて」
すごく無理やりだなと思ったけど、プレゼントがあるなら事前にいって欲しかった。だったら私もなにか用意できたのに。まあ、普通言わないか。私は箱を受け取り、そっと蓋を開ける。
「これは……ラピスラズリ?」
紺色の地色にパイライトがちりばめられた綺麗な石。それを組み紐に通してブレスレットにしたものだった。
「そう、恐怖を払うお守りらしい。この前、どうやったら最後の瞬間怖くなくなるかって言ってたから。気休めにしかならないかもしれないけど」
困ったように笑う先輩。あの時私が言ったこと、気にしてくれてたんだ。先輩は真剣に書いていたし、返事は適当だったからこんなに考えてくれていたなんて思っていなかった。
「ありがとうございます。嬉しいです! もう、肌身離さす着けておきます」
ラピスラズリはネガティブなエネルギーから解放され、強力な厄除けをしてくれる石だそうだ。
そして真実を受け入れ、持ち主を自分が進む道へと近づけてくれる、と添えられたカードに書かれてあった。
先輩が、私のことを思ってこのブレスレットを選んでくれたんだということがよくわかる。だから私もその思いに応えたい。ちゃんと前を向かないと。
「先輩、私取材に行きます」
「急にすごくやる気だね」
「水平線から昇る朝日が見たいんです。最後のシーンに必要なんです」
「水平線ってここらでは見られないんじゃない?」
「はい、だから遠征してきます。行きたい場所があるんです」
「随分と思いたったね。僕も付き合うよ」
先輩はやはり自分にとっても取材だからと、一緒に行くと言った。それに取材をすると言い出したのは自分だから最後まで見届けたいんだと。
観覧車を降り、そのまま遊園地を後にした。そして帰りながら、遠征の計画について話し合った。
一週間後、私たちは朝日を見に行く――。
「えー、風邪にはくれぐれも気を付けてください。少しでもおかしいと感じたらすぐに医療機関を受診し――」
終業式が終わり、あとはホームルームで担任の話を聞くだけだと思っていたら、校長先生の話よりも長い話を聞かされている。しかも同じことを何度も何度も。
風邪に気を付けなさいって言っているけれど、本当は風邪のことではない。ゾンビウイルスに気をつけろと言っている。そんなの、気をつけようがないのに。
ただ、感染した初期症状として風邪症状があるらしい。はじめは風邪かなと思っていたら、なかなか治らず、一ヶ月ほど経つと意識が混濁しはじめ、そしてゾンビ化する。
私も先週風邪で熱を出したとき、もうだめだと思った。このままゾンビになって自我をなくして施設に入れられてなんの感情もないまま最後の日を迎えるんだと。でも、薬をのんで一日寝ていたら次の日には頭はスッキリしていて、なにごともなく今に至る。
空気感染でも飛沫感染でも血液感染でもないゾンビウイルスは、もはや宇宙人が人間を選別して感染させているのではないかという噂まで飛び交っている。まさに運としか言いようのないウイルスだ。
そんなことを考えているうちに担任の話は終わった。私は荷物を持って、急いで先輩と待ち合わせ場所である校門へと向かう。きっと、待たせているはずだ。と思っていたら下駄箱を出たところで先輩と会った。先輩も急いでいたらしく、少し息が切れている。そんなお互いの様子に顔を見合わせ笑った。
学校を出て、電車に乗って、遊園地にやってきた。今日まで学校ということもあり、人はそこまで多くない。それと、昼間は常に熱中症アラートが発令されている。小さな子どもや体調に心配のある人たちはこの時間帯に遊園地などの外での施設で遊ばなくなっている。
太陽の膨張により、地球温暖化が急速に進んでいるのだ。宇宙人襲来と関係があるのかはわからないけれど、これも四年前からだ。
制服も冷感の長袖シャツだし、露出部の日焼け止めは絶対に欠かせない。水分はいつも持ち歩いているし、鞄には冷却シートも入っている。こんな習慣ももう四年になれば、慣れてきた。この暑さにはあと一年で慣れることはないのだろうけど。
それでも、汗をにじませながら、煌めく空間にキラキラとした目を向ける先輩の横顔を見るとこれくらいの暑さなんてまだまだどうってことないように思える。
「先輩、すごく嬉しそうですね」
「実は遊園地めちゃくちゃ久しぶりなんだよね。ワクワクしてる」
「私も楽しみにしてました。行きましょう!」
「まずはジェットコースターからだね」
「いきなりですか?!」
なんて言いながらもジェットコースターは私も好きだ。あの爽快感は何度乗っても飽きない。それこそ暑さなんて吹き飛ぶほど。
私たちは何度もジェットコースターに乗った。コーヒーカップもメリーゴーランドも空中ブランコも。ずっと楽しくて、先輩も楽しそうで、それだけで笑顔になれる。本当にここは魔法の場所だと思った。
何時間も遊び、日も傾きはじめたころ、最後に観覧車に乗ることになった。
揺れるゴンドラへ支えられながら乗り込み、向かい合って座る。なんだか照れくさくてすぐに外の景色を眺めた。
「わあ、きれい……」
夕日に照らされた街の景色、その向こうにある山々、茜色の空。目に映る全てのものが輝いている。
「ほんと、きれいだね」
先輩も景色を眺め、優しい笑みを浮かべていた。
「私、本当はもう書けなくてもいいかなって思ってたんです。書く意味あるのかなって」
「うん」
「でも、やっぱり書きたくなりました。書きます私」
視線を先輩に戻すと先輩も私を見ていた。そして、やっぱり優しい笑みを私に向ける。
「カズハちゃんなら、きっと書けるよ。きみの、純粋で真っ直ぐで、それでいてどこか危なっかしい感情が隠れてる、そんな話は人の心を動かす力を持っていると思う」
きっと先輩は、私が行き詰ってるだけじゃなく、書く気力を失っていることにも気づいていたはずだ。それでも捨てきれずにもがいている私のことも。
私が小説を書き始めたのは、中学生になったころだった。当時は謎のゾンビウイルスにより、学校へ行くことも、外へ出ることさえ制限されていた。私は家で本を読み漁った。没頭した。いつしか自分で書き始めていた。自分だけの物語を。ドキドキしてワクワクして、苦しくて切なくて、それでも心はときめいて、書き終わったときにはなぜか涙が溢れていた。読み返すと文章はめちゃくちゃだし、なにが言いたかったのかよくわからないけれど、書いているときだけはたしかに私は物語の中に生きていて、その世界を駆け抜けていた。
謎のウイルスが空気感染しないとわかると日常は戻ったけれど、次は隕石が落ちて世界は滅亡するなんて言われた。神様はよほど地球が嫌いみたいだ。いや宇宙人か。
それでも私は物語を書き続けた。でも、続けられなかった。それから一年がたち、刻一刻と世界滅亡が近づいてくるとだんだんと書けなくなった。書きたいのに、書けない。
そんな中、入学した高校で文芸部があることを知った。説明会でもらったパンフレットには載っていなかったのに。おそるおそる訪れた文芸部で先輩と出会った。私は今まで書いた中で一番出来がいいと思う小説を先輩にみせた。
『このお話を読むと君のことがよくわかるよ』それが先輩の感想だった。
それから平凡な部活動が始まった。お互い机に向かって作業をしながら世間話なんかをする。先輩はたくさん原稿用紙に執筆しているけれど、私はノートに種書きしたり相関図を書いたり謎の詩を書いてみたりしているだけ。それでも、穏やかな時間が流れるこの部活が好きだった。
だから先輩が『執筆、行き詰ってるの?』と聞いてきたことには驚いた。そういうことは言わないのかと思っていた。入部して三ヶ月、一度も書いていない私にずっと何も言ってこなかったから――。
「カズハちゃん」
先輩は私の名前を呼ぶと、鞄から手のひらほどの小さな箱を取り出し差し出してくる。
「これは……?」
「プレゼントだよ」
「プレゼント? どうして? 私誕生日でもなんでもないですよ」
「でも今日俺たちは幼馴染カップルでしょ。恋人にプレゼントするのに理由なんていらないよ。開けてみて」
すごく無理やりだなと思ったけど、プレゼントがあるなら事前にいって欲しかった。だったら私もなにか用意できたのに。まあ、普通言わないか。私は箱を受け取り、そっと蓋を開ける。
「これは……ラピスラズリ?」
紺色の地色にパイライトがちりばめられた綺麗な石。それを組み紐に通してブレスレットにしたものだった。
「そう、恐怖を払うお守りらしい。この前、どうやったら最後の瞬間怖くなくなるかって言ってたから。気休めにしかならないかもしれないけど」
困ったように笑う先輩。あの時私が言ったこと、気にしてくれてたんだ。先輩は真剣に書いていたし、返事は適当だったからこんなに考えてくれていたなんて思っていなかった。
「ありがとうございます。嬉しいです! もう、肌身離さす着けておきます」
ラピスラズリはネガティブなエネルギーから解放され、強力な厄除けをしてくれる石だそうだ。
そして真実を受け入れ、持ち主を自分が進む道へと近づけてくれる、と添えられたカードに書かれてあった。
先輩が、私のことを思ってこのブレスレットを選んでくれたんだということがよくわかる。だから私もその思いに応えたい。ちゃんと前を向かないと。
「先輩、私取材に行きます」
「急にすごくやる気だね」
「水平線から昇る朝日が見たいんです。最後のシーンに必要なんです」
「水平線ってここらでは見られないんじゃない?」
「はい、だから遠征してきます。行きたい場所があるんです」
「随分と思いたったね。僕も付き合うよ」
先輩はやはり自分にとっても取材だからと、一緒に行くと言った。それに取材をすると言い出したのは自分だから最後まで見届けたいんだと。
観覧車を降り、そのまま遊園地を後にした。そして帰りながら、遠征の計画について話し合った。
一週間後、私たちは朝日を見に行く――。