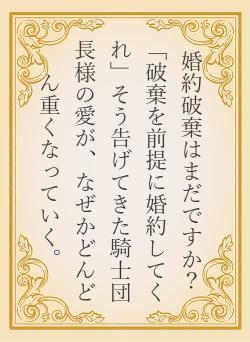――七月二十五日 宮園 一花
先輩が、事故にあって、亡くなった……?
私の頭の中は真っ白で、先生に言われたことを理解することも、受け入れることもできずにいた。
終業式の校長先生の話もホームルームの先生の話も全く頭に入ってこないまま、気づけば西日が差し込む部室にいた。
先輩が、死んだ? そんなわけないよね? 昨日だって、夏休み楽しみだねって話してたのに。
今日、終業式が終わったら遊園地に行こうって約束してたのに――。
滲んだ視界を遮るように目を閉じる。生暖かい雫が頬を濡らす。私はこれから、どうしたらいいの。先輩のいないこの世界に、私は何を見つければいいのだろう。
先生に、お葬式に行きたいと言ったら、ご家族だけで済ませるそうだから行けないと言われた。お別れもできない。
もう、先輩の姿を見ることはないんだ。先輩の優しく笑う顔も、一花ちゃん、と呼ぶ声も、もうなにも……。そう思うと涙が溢れて止まらなかった。毎日泣いて、泣いて泣いて、また泣いた。
つらくなることを分かっていて、夏休み、毎日部室へ行った。何をするわけでもなく、先輩と過ごした日々を思い出しては一日中泣いた。
そんな夏休みのある日、今まで誰も訪ねてくることがなかった部室のドアが開いた。
突っ伏して泣いていた顔を上げると、少しだけ見覚えのある女子生徒がいた。
彼女はたしか、隣のクラスの人だ。美人で成績もよくて、それでいてクールな性格で、高嶺の花だ、なんて男子たちが噂をしていたのを聞いたことがある。でも、どうして彼女がこんなところに?
「宮園一花さん、だよね? これ兄の鞄に入ってたの。あなたのでしょ?」
「え……兄?」
渡されたのは一冊のノート。先輩に読んでもらった、私が書いた小説。読んだあとに感想は聞いたけれど、ずっと先輩に預けていた。もう少しじっくり読むからと。
そうだ、彼女の名前は守屋藍さん。まさか、彼女が先輩の妹だなんて知らなかった。妹がいるとは聞いていたけど、私と同い年で同じ学校だったなんて。
私はノートを受け取ると、さらに涙が溢れてきた。そこには先輩の字で書かれた付箋がたくさん貼られていたからだ。
『ヒロインの心情がよくわかっていい』『この葛藤に共感する』『会話のテンポ最高!』『胸キュンだ』『このセリフ泣ける』
拙くて荒い文章に、独りよがりな物語なのに、先輩はたくさん褒めてくれている。
涙を拭い、鼻をすすっていると、守屋さんがポケットティッシュを渡してくれた。頭を下げて受け取ると、守屋さんはなぜか私の向かいに座った。
「お兄は小説が好きだった。書くのも読むのも。だから文芸部に宮園さんが入ってきてくれてすごく喜んでたよ。同じように小説が好きな子がきてくれたって」
その言葉にせっかく拭いた涙と鼻水がまた流れてくる。
守屋さんはその後何も言わず、私が泣き止むまでただそばにいてくれた。
「これ、わざわざ持ってきてくれて、ありがとう……」
「あなたのものなのに、勝手に捨てるわけにはいかないでしょ?」
困ったように笑うその表情は、どこか先輩に似ている。妹は感情がなくなったみたいだ、なんて言っていたけれど、そんなことはない。すごく優しい表情をする人だ。
「先輩と、よく話しをしてたの? 部活のこととか」
「話しをしてたというか、一方的に聞かされてたって感じだけどね」
少し呆れたように話す彼女は、きっと先輩のことを思い出しているのだろう。
落ち着いてきた私は、また付箋に目を落とす。 一つ一つの言葉を嚙み締めながらページをめくっていると、ノートを破ったメモ書きが挟まっていた。
『やることリスト』そこに書かれていたのは、先輩が小説を書く前にやりたい、取材をしたい、と言っていたことだった。
『俺、次は終末系書くわ!』
『終末系、ですか?』
『一花ちゃんはあまり興味ないジャンルだから知らないかな? 世界滅亡だよ』
『いや、それはわかります。あまり読んだことはないですけど。SF小説ですよね? 匠先輩がSFなんて珍しいですね』
『書くのは難しくて挑戦したことなかったけど、好きなんだよね。滅亡の危機に直面した人々の人間模様が描かれた作品とか。絶望を目の前にあがいて苦しんでそれでも限りある時間の中で成長する姿とか育まれる愛とか友情とかさ! 絶対に感動すると思うんだよね』
『たしかに、そういう青春物語は匠先輩好きそうですね』
『俺、絶対に書きあげるから一花ちゃん付き合ってね。取材とか資料集めとか』
『それはもちろん。私もたくさん付き合ってもらったんで、できることならしますよ』
『ありがとう! 一花ちゃんは頼りになるな』
『私、匠先輩の書く物語好きなんです。だから、楽しみにしてます』
『この話を完成させて、学校で配ってさ、部員増やしたいよね。学年変わる前に部員が三人以上にならないと廃部とか辛すぎ。せめて一花ちゃんが卒業するまでは存続させないと。あと、妹を泣かせないとね――』
先輩、次は世界滅亡系の話書くって言ってた。いったいどんな話を書くつもりだったんだろう。
「守屋さん、先輩の鞄に『プロット』って書かれたノート入ってなかったかな?」
「ああ……たぶんあったと思う。なんのノートだろうって思ったのがあったんだよね」
「それ、譲ってもらうことはできる?」
「いいと思うよ。一応親にも聞いて明日持ってくるよ」
翌日、彼女はちゃんと先輩のプロットノートを持ってきてくれた。
私は先輩のノートを開く。……ん? なんだこれは、と思った。中はプロットじゃなくて設定案らしきものを書き連ねただけだった。世界が滅亡する原因をいくつかあげてみただけ? それとも全て詰め込むつもりだったのだろうか。
それは分からないけれど、私はやることリストに書いてあったことを実行してみることにする。
先輩が残したノートとメモを元に、私はこの小説を完成させる。先輩が書こうとしていたこの世界滅亡に向き合う人たちの小説を。先輩がやりたかったことをやり遂げるために。
それが、今私にできるただ一つのことだと思うから。
まず守屋さんに頼んで先輩の持ってる小説を全部借りた。
そしてコンビニでバイトも始めた。取材をするための費用が必要だったから。夏休みはバイトに明け暮れ、合間で小説を読んだ。たまにバイトが休みの日は映画を観た。目的はなくても散歩をしてみたりもした。どれも、今まで先輩としてきたこと。しようと言っていたこと。
夏休みが明けるとまた部室に通うようにした。土日はバイトをして、平日の放課後は先輩がいた頃と同じように過ごす。ただひたすら小説を読んでいるだけの日もある。時々、先生が部室を覗いてきては私を心配そうに見つめて去っていくこともある。何しに来たんだろうという疑問は四回目から湧かなくなった。たぶん、私の様子を見に来ているだけだ。私がなにかおかしなことをしないかとでも思っているのかもしれない。
「一花、顔怖いよ。少し休憩したら?」
声をかけられ、ページをめくる手を止めると、藍がパックのカフェオレを机に置いて渡してくれる。自分の分もあるようで、彼女もパイプ椅子に腰掛けると、パックにストローをさして飲みはじめた。
「藍、ありがとう」
小説に栞を挟んでから閉じ、私もカフェオレを飲む。
あれからお互いに名前で呼ぶようになっている。夏休み、先輩の小説を借りるために何度か家を訪ねることもあった。お葬式には行けなかったけれど、仏壇の前で先輩に手を合わせた。その流れで一緒にお昼を食べたり、お互いのことをゆっくり話すこともあった。
そうしているうちに自然と一花と呼ばれるようになった。先輩がずっと家で一花ちゃんと言っていたから、一花で定着しているそうだ。『だから、一花も藍って呼んで』そう言われてから、名前で呼ぶようになったのだ。
「ねえ、一花大丈夫?」
「え? なにが?」
「もっとさ、好きなことしていいんだよ。自分がしたいことをさ」
先輩が言っていたように、たしかに藍は感情をあまり表には出さない。でも、すごく優しくて面倒見がいい。こうやって、いつも私のことを心配してくれる。そんな藍のことが私は大好きだ。先輩と同じように私も藍を泣かせたいと思う。笑って欲しいし、時には怒って欲しい。だから、私は小説を書く。世界滅亡という心乱される物語を。たとえ高校生活、青春を全て捧げることになっても。きっとそれが私の青春になるから。
「藍、ありがとう。でも、これが私のやりたいことだから」
気がつけば、先輩が亡くなってから三度目の夏がきていた。
私はずっと、先輩の見ていた世界を追い続けている――。
先輩が、事故にあって、亡くなった……?
私の頭の中は真っ白で、先生に言われたことを理解することも、受け入れることもできずにいた。
終業式の校長先生の話もホームルームの先生の話も全く頭に入ってこないまま、気づけば西日が差し込む部室にいた。
先輩が、死んだ? そんなわけないよね? 昨日だって、夏休み楽しみだねって話してたのに。
今日、終業式が終わったら遊園地に行こうって約束してたのに――。
滲んだ視界を遮るように目を閉じる。生暖かい雫が頬を濡らす。私はこれから、どうしたらいいの。先輩のいないこの世界に、私は何を見つければいいのだろう。
先生に、お葬式に行きたいと言ったら、ご家族だけで済ませるそうだから行けないと言われた。お別れもできない。
もう、先輩の姿を見ることはないんだ。先輩の優しく笑う顔も、一花ちゃん、と呼ぶ声も、もうなにも……。そう思うと涙が溢れて止まらなかった。毎日泣いて、泣いて泣いて、また泣いた。
つらくなることを分かっていて、夏休み、毎日部室へ行った。何をするわけでもなく、先輩と過ごした日々を思い出しては一日中泣いた。
そんな夏休みのある日、今まで誰も訪ねてくることがなかった部室のドアが開いた。
突っ伏して泣いていた顔を上げると、少しだけ見覚えのある女子生徒がいた。
彼女はたしか、隣のクラスの人だ。美人で成績もよくて、それでいてクールな性格で、高嶺の花だ、なんて男子たちが噂をしていたのを聞いたことがある。でも、どうして彼女がこんなところに?
「宮園一花さん、だよね? これ兄の鞄に入ってたの。あなたのでしょ?」
「え……兄?」
渡されたのは一冊のノート。先輩に読んでもらった、私が書いた小説。読んだあとに感想は聞いたけれど、ずっと先輩に預けていた。もう少しじっくり読むからと。
そうだ、彼女の名前は守屋藍さん。まさか、彼女が先輩の妹だなんて知らなかった。妹がいるとは聞いていたけど、私と同い年で同じ学校だったなんて。
私はノートを受け取ると、さらに涙が溢れてきた。そこには先輩の字で書かれた付箋がたくさん貼られていたからだ。
『ヒロインの心情がよくわかっていい』『この葛藤に共感する』『会話のテンポ最高!』『胸キュンだ』『このセリフ泣ける』
拙くて荒い文章に、独りよがりな物語なのに、先輩はたくさん褒めてくれている。
涙を拭い、鼻をすすっていると、守屋さんがポケットティッシュを渡してくれた。頭を下げて受け取ると、守屋さんはなぜか私の向かいに座った。
「お兄は小説が好きだった。書くのも読むのも。だから文芸部に宮園さんが入ってきてくれてすごく喜んでたよ。同じように小説が好きな子がきてくれたって」
その言葉にせっかく拭いた涙と鼻水がまた流れてくる。
守屋さんはその後何も言わず、私が泣き止むまでただそばにいてくれた。
「これ、わざわざ持ってきてくれて、ありがとう……」
「あなたのものなのに、勝手に捨てるわけにはいかないでしょ?」
困ったように笑うその表情は、どこか先輩に似ている。妹は感情がなくなったみたいだ、なんて言っていたけれど、そんなことはない。すごく優しい表情をする人だ。
「先輩と、よく話しをしてたの? 部活のこととか」
「話しをしてたというか、一方的に聞かされてたって感じだけどね」
少し呆れたように話す彼女は、きっと先輩のことを思い出しているのだろう。
落ち着いてきた私は、また付箋に目を落とす。 一つ一つの言葉を嚙み締めながらページをめくっていると、ノートを破ったメモ書きが挟まっていた。
『やることリスト』そこに書かれていたのは、先輩が小説を書く前にやりたい、取材をしたい、と言っていたことだった。
『俺、次は終末系書くわ!』
『終末系、ですか?』
『一花ちゃんはあまり興味ないジャンルだから知らないかな? 世界滅亡だよ』
『いや、それはわかります。あまり読んだことはないですけど。SF小説ですよね? 匠先輩がSFなんて珍しいですね』
『書くのは難しくて挑戦したことなかったけど、好きなんだよね。滅亡の危機に直面した人々の人間模様が描かれた作品とか。絶望を目の前にあがいて苦しんでそれでも限りある時間の中で成長する姿とか育まれる愛とか友情とかさ! 絶対に感動すると思うんだよね』
『たしかに、そういう青春物語は匠先輩好きそうですね』
『俺、絶対に書きあげるから一花ちゃん付き合ってね。取材とか資料集めとか』
『それはもちろん。私もたくさん付き合ってもらったんで、できることならしますよ』
『ありがとう! 一花ちゃんは頼りになるな』
『私、匠先輩の書く物語好きなんです。だから、楽しみにしてます』
『この話を完成させて、学校で配ってさ、部員増やしたいよね。学年変わる前に部員が三人以上にならないと廃部とか辛すぎ。せめて一花ちゃんが卒業するまでは存続させないと。あと、妹を泣かせないとね――』
先輩、次は世界滅亡系の話書くって言ってた。いったいどんな話を書くつもりだったんだろう。
「守屋さん、先輩の鞄に『プロット』って書かれたノート入ってなかったかな?」
「ああ……たぶんあったと思う。なんのノートだろうって思ったのがあったんだよね」
「それ、譲ってもらうことはできる?」
「いいと思うよ。一応親にも聞いて明日持ってくるよ」
翌日、彼女はちゃんと先輩のプロットノートを持ってきてくれた。
私は先輩のノートを開く。……ん? なんだこれは、と思った。中はプロットじゃなくて設定案らしきものを書き連ねただけだった。世界が滅亡する原因をいくつかあげてみただけ? それとも全て詰め込むつもりだったのだろうか。
それは分からないけれど、私はやることリストに書いてあったことを実行してみることにする。
先輩が残したノートとメモを元に、私はこの小説を完成させる。先輩が書こうとしていたこの世界滅亡に向き合う人たちの小説を。先輩がやりたかったことをやり遂げるために。
それが、今私にできるただ一つのことだと思うから。
まず守屋さんに頼んで先輩の持ってる小説を全部借りた。
そしてコンビニでバイトも始めた。取材をするための費用が必要だったから。夏休みはバイトに明け暮れ、合間で小説を読んだ。たまにバイトが休みの日は映画を観た。目的はなくても散歩をしてみたりもした。どれも、今まで先輩としてきたこと。しようと言っていたこと。
夏休みが明けるとまた部室に通うようにした。土日はバイトをして、平日の放課後は先輩がいた頃と同じように過ごす。ただひたすら小説を読んでいるだけの日もある。時々、先生が部室を覗いてきては私を心配そうに見つめて去っていくこともある。何しに来たんだろうという疑問は四回目から湧かなくなった。たぶん、私の様子を見に来ているだけだ。私がなにかおかしなことをしないかとでも思っているのかもしれない。
「一花、顔怖いよ。少し休憩したら?」
声をかけられ、ページをめくる手を止めると、藍がパックのカフェオレを机に置いて渡してくれる。自分の分もあるようで、彼女もパイプ椅子に腰掛けると、パックにストローをさして飲みはじめた。
「藍、ありがとう」
小説に栞を挟んでから閉じ、私もカフェオレを飲む。
あれからお互いに名前で呼ぶようになっている。夏休み、先輩の小説を借りるために何度か家を訪ねることもあった。お葬式には行けなかったけれど、仏壇の前で先輩に手を合わせた。その流れで一緒にお昼を食べたり、お互いのことをゆっくり話すこともあった。
そうしているうちに自然と一花と呼ばれるようになった。先輩がずっと家で一花ちゃんと言っていたから、一花で定着しているそうだ。『だから、一花も藍って呼んで』そう言われてから、名前で呼ぶようになったのだ。
「ねえ、一花大丈夫?」
「え? なにが?」
「もっとさ、好きなことしていいんだよ。自分がしたいことをさ」
先輩が言っていたように、たしかに藍は感情をあまり表には出さない。でも、すごく優しくて面倒見がいい。こうやって、いつも私のことを心配してくれる。そんな藍のことが私は大好きだ。先輩と同じように私も藍を泣かせたいと思う。笑って欲しいし、時には怒って欲しい。だから、私は小説を書く。世界滅亡という心乱される物語を。たとえ高校生活、青春を全て捧げることになっても。きっとそれが私の青春になるから。
「藍、ありがとう。でも、これが私のやりたいことだから」
気がつけば、先輩が亡くなってから三度目の夏がきていた。
私はずっと、先輩の見ていた世界を追い続けている――。