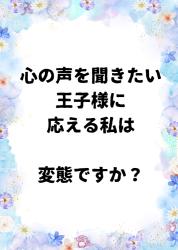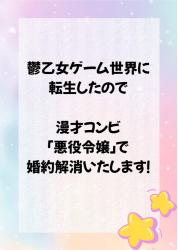神社の鳥居の前に佇む守人に声をかける。
「どうして、ここに立っているの?」
少しだけ妖の身である自分が憎らしい。
私には家がないから電話もないし……連絡をとりあったりはできない。この場所は私の一部でもあるから彼がここに来た時には分かるけれど、すぐに来れるわけではない。
待ちくたびれて彼が帰らなくてよかったと、ほっとする。
「紅羽に贈り物をしたくて」
「贈り物?」
「ああ」
彼が鞄の中からそれを取り出した。
鮮やかな赤の巾着袋には椿が描かれている。
「紅羽に似合うかなって」
丁寧な手つきで紐をほどき、中に入っていた赤い菊のかんざしを私に手渡した。
「赤が好きなの?」
「紅羽の燃えるようなその赤に、魅入られてしまったから」
妖に魅入られてしまった男の行く末は、幸か不幸か……。
髪の上半分をねじりあげて巻いて、手渡されたそれを挿し込んだ。きっともう、他の人間の目にこれは見えない。
「どう?」
「やっぱり……綺麗だ。この袋も受け取って」
赤は、人間の中にどくどくと流れている血の色。生きているとは言えない私が赤に彩られていくのは不思議な気分ね。
私も血を流そうと思えば流せるけれど、それはただの偽物で……数刻の後に消えてなくなる。人間の目には最初から存在すらしないけれど。
「ありがとう、もらっていくわ。なぜ鳥居の外で待っていたの?」
「祈りもなしに不浄な人間が中にいるのはよくないかと思って」
「私は人の穢れから生まれているのよ」
くすくすと笑う私に、他の何も目に入っていないような顔をして彼が私の髪をわずかにすくい取る。
「悪いことをしている気分になる。俺が紅羽の場所に足を踏み入れていいのかと。この美しさを知ってしまった俺は、こうしているだけで罪人になった気分だ」
――憐れな罪人に災厄を。
そんな声でも聞こえてきそうな顔をしている。
「よく買えたわね」
彼の両親は厳しかったはず。
「町まで出ることは許されている。参考書を買うためならね。小遣いはもらっているしお釣りも貯めてはいるけど……たまに部屋の中は確認される。だから直接持ってきたんだ」
「……そう」
人間から直接贈り物を手渡されるのは初めてだ。
特別な……感じがする。
「その巾着に入る贈り物を、これからも渡していいかな」
私には家がない。
神社は……誰にでも入れてしまう。
持ち歩けるものを――、そういうこと?
まさか人間に、私の行動を決められてしまうなんて……。
「いいわよ、もらってあげる」
永い永い時の中……ちっぽけな存在に左右されながら過ごすのも、また楽しきこと。
「どうして、ここに立っているの?」
少しだけ妖の身である自分が憎らしい。
私には家がないから電話もないし……連絡をとりあったりはできない。この場所は私の一部でもあるから彼がここに来た時には分かるけれど、すぐに来れるわけではない。
待ちくたびれて彼が帰らなくてよかったと、ほっとする。
「紅羽に贈り物をしたくて」
「贈り物?」
「ああ」
彼が鞄の中からそれを取り出した。
鮮やかな赤の巾着袋には椿が描かれている。
「紅羽に似合うかなって」
丁寧な手つきで紐をほどき、中に入っていた赤い菊のかんざしを私に手渡した。
「赤が好きなの?」
「紅羽の燃えるようなその赤に、魅入られてしまったから」
妖に魅入られてしまった男の行く末は、幸か不幸か……。
髪の上半分をねじりあげて巻いて、手渡されたそれを挿し込んだ。きっともう、他の人間の目にこれは見えない。
「どう?」
「やっぱり……綺麗だ。この袋も受け取って」
赤は、人間の中にどくどくと流れている血の色。生きているとは言えない私が赤に彩られていくのは不思議な気分ね。
私も血を流そうと思えば流せるけれど、それはただの偽物で……数刻の後に消えてなくなる。人間の目には最初から存在すらしないけれど。
「ありがとう、もらっていくわ。なぜ鳥居の外で待っていたの?」
「祈りもなしに不浄な人間が中にいるのはよくないかと思って」
「私は人の穢れから生まれているのよ」
くすくすと笑う私に、他の何も目に入っていないような顔をして彼が私の髪をわずかにすくい取る。
「悪いことをしている気分になる。俺が紅羽の場所に足を踏み入れていいのかと。この美しさを知ってしまった俺は、こうしているだけで罪人になった気分だ」
――憐れな罪人に災厄を。
そんな声でも聞こえてきそうな顔をしている。
「よく買えたわね」
彼の両親は厳しかったはず。
「町まで出ることは許されている。参考書を買うためならね。小遣いはもらっているしお釣りも貯めてはいるけど……たまに部屋の中は確認される。だから直接持ってきたんだ」
「……そう」
人間から直接贈り物を手渡されるのは初めてだ。
特別な……感じがする。
「その巾着に入る贈り物を、これからも渡していいかな」
私には家がない。
神社は……誰にでも入れてしまう。
持ち歩けるものを――、そういうこと?
まさか人間に、私の行動を決められてしまうなんて……。
「いいわよ、もらってあげる」
永い永い時の中……ちっぽけな存在に左右されながら過ごすのも、また楽しきこと。