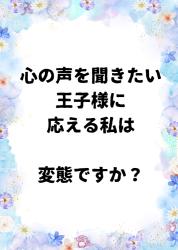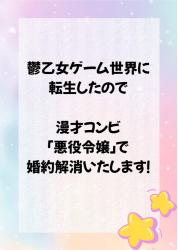「気に入ったのか」
「……上手く逃げたわね」
彼が完全に立ち去ってから、恭介が隣に現れた。
「お前が話したそうだったからな」
「ずいぶんと包容力のある愛だこと」
「炭にしてやった方がよかったか?」
「やめて。また……会いたくなったわ」
「そうか」
この鬼の語る愛に、あまり中身は感じない。
愛することに興味があるだけで、本当は愛していないんじゃないかとも思う。
――どうでもいいことだ。
好きにさせるだけ。
側に誰かがいる方が退屈は紛れる。
「止めないの?」
「好きにしたらいい。俺たちは妖。この世界に飽きて消えることを望んでしまえば消滅する。お前を永遠に失わないために、人間の男という刺激があってもいい。どうせわずかな年数しか生きられない」
「……そう」
死にたがりの人間を思い出す。
死にたがるということは生きているということ。辛いと思える日常が……変化があるということ。
ただこの場所に留まるだけで何も生み出せない私たちとは違う、死にたがるほどの絶望という名の命の輝きがあるということ。
「彼のところへ……行くわ」
「ああ、お前の帰る場所は俺だ。それだけは忘れるなよ」
そう言って、恭介も立ち去った。
しばらくの間、姿を見せないつもりかもしれない。
――私が人間の彼に飽きるまで。
「……上手く逃げたわね」
彼が完全に立ち去ってから、恭介が隣に現れた。
「お前が話したそうだったからな」
「ずいぶんと包容力のある愛だこと」
「炭にしてやった方がよかったか?」
「やめて。また……会いたくなったわ」
「そうか」
この鬼の語る愛に、あまり中身は感じない。
愛することに興味があるだけで、本当は愛していないんじゃないかとも思う。
――どうでもいいことだ。
好きにさせるだけ。
側に誰かがいる方が退屈は紛れる。
「止めないの?」
「好きにしたらいい。俺たちは妖。この世界に飽きて消えることを望んでしまえば消滅する。お前を永遠に失わないために、人間の男という刺激があってもいい。どうせわずかな年数しか生きられない」
「……そう」
死にたがりの人間を思い出す。
死にたがるということは生きているということ。辛いと思える日常が……変化があるということ。
ただこの場所に留まるだけで何も生み出せない私たちとは違う、死にたがるほどの絶望という名の命の輝きがあるということ。
「彼のところへ……行くわ」
「ああ、お前の帰る場所は俺だ。それだけは忘れるなよ」
そう言って、恭介も立ち去った。
しばらくの間、姿を見せないつもりかもしれない。
――私が人間の彼に飽きるまで。