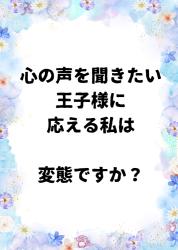「戻ってきたのか」
「三年で戻ると言ったでしょう」
宵の口、灯籠代わりに浮かせておいた赤い光の下、草の生い茂る神社の階段に前と同じように恭介が座る。
「悪い、少しは荒廃した」
「私がいないんだもの。これだけで済んで助かったわ。ありがとう」
「気は済んだか?」
「ええ、霊感を奪ってきたわ」
「それくらいにはここも荒れたか……」
「これでよかったの。私がいれば、またいつか戻るでしょう」
「そうかもな」
村の様子を見た限り、若者が前よりも減っていた。元には……戻らないかもしれない。神社の管理をする村人もきっと高齢だ。だから恭介の返事も曖昧なのだろう。
「ここでいずれ開業医をするつもりのようだけど……どうなるのかしらね」
持っていた手紙をたたんで、巾着袋に入れる。
それは彼からの最後の手紙だ。
私の姿も見えず声も聞こえなくなった守人が、私宛に書いた手紙。翌日彼の様子を見に部屋に入ったらポンと机の上に置いてあって……私はそれを持ってここへ帰ってきた。
必ずここに医者として戻ってくると書かれていた。子々孫々と、信心を忘れずに私を祀り続けると。
私の願いを――……、必ず叶えると。
「……他の男のために泣く私に、何も思わないの?」
「存在し続けるためには必要なことだ。人間の男となら何度でも」
「……妖の男なら?」
「いつの間にか、存在ごと消えているはずだ。炭も残らず青い炎で全てを焼かれて消滅する。それが分かっているから、俺が側にいる限り誰もお前に近づきはしない」
「――え。そんな状況にあったの、私」
「気付いていなかったのか」
他の妖の男とは、知り合えそうにないわね……。
「なぁ紅羽。この村が寂れて住人もいなくなって、神社も取り壊される日が来たら――」
「……私の好きだった人間の男が、その未来を阻止しようとしているんだけど」
「そうしたら、妖の学校に行こうか」
「何それ……」
「お前がいない間、昔の知り合いが訪ねてきたんだ。行き場を失った妖たちが、廃校で学校ごっこをしているとさ」
「のんきな話ね……」
「この村もいずれ消えると思って、教えに来てくれた」
「私にとっては絶望の未来ね」
それでも、そんな日がいつか来てしまうかもしれない。
「あの人間にとってはお前との別れが絶望で、お前にとってはその未来が絶望か。でも、あいつにはいい人生が、俺たちには妖だけの学校ごっこが待っているかもしれない」
左手の薬指にはめていた指輪を、右手へとはめ直す。
「永きを生きる間に記憶は薄れ、その指輪をはめている理由もいずれ忘れる」
「……ぞっとしないわね」
「それくらいに遠い先でいい。人間のような心を持つお前が好きだ。いつか人の子のように俺を愛してくれ」
時は巡りて禍福も廻る。
これからも、鬼と共に――。
「三年で戻ると言ったでしょう」
宵の口、灯籠代わりに浮かせておいた赤い光の下、草の生い茂る神社の階段に前と同じように恭介が座る。
「悪い、少しは荒廃した」
「私がいないんだもの。これだけで済んで助かったわ。ありがとう」
「気は済んだか?」
「ええ、霊感を奪ってきたわ」
「それくらいにはここも荒れたか……」
「これでよかったの。私がいれば、またいつか戻るでしょう」
「そうかもな」
村の様子を見た限り、若者が前よりも減っていた。元には……戻らないかもしれない。神社の管理をする村人もきっと高齢だ。だから恭介の返事も曖昧なのだろう。
「ここでいずれ開業医をするつもりのようだけど……どうなるのかしらね」
持っていた手紙をたたんで、巾着袋に入れる。
それは彼からの最後の手紙だ。
私の姿も見えず声も聞こえなくなった守人が、私宛に書いた手紙。翌日彼の様子を見に部屋に入ったらポンと机の上に置いてあって……私はそれを持ってここへ帰ってきた。
必ずここに医者として戻ってくると書かれていた。子々孫々と、信心を忘れずに私を祀り続けると。
私の願いを――……、必ず叶えると。
「……他の男のために泣く私に、何も思わないの?」
「存在し続けるためには必要なことだ。人間の男となら何度でも」
「……妖の男なら?」
「いつの間にか、存在ごと消えているはずだ。炭も残らず青い炎で全てを焼かれて消滅する。それが分かっているから、俺が側にいる限り誰もお前に近づきはしない」
「――え。そんな状況にあったの、私」
「気付いていなかったのか」
他の妖の男とは、知り合えそうにないわね……。
「なぁ紅羽。この村が寂れて住人もいなくなって、神社も取り壊される日が来たら――」
「……私の好きだった人間の男が、その未来を阻止しようとしているんだけど」
「そうしたら、妖の学校に行こうか」
「何それ……」
「お前がいない間、昔の知り合いが訪ねてきたんだ。行き場を失った妖たちが、廃校で学校ごっこをしているとさ」
「のんきな話ね……」
「この村もいずれ消えると思って、教えに来てくれた」
「私にとっては絶望の未来ね」
それでも、そんな日がいつか来てしまうかもしれない。
「あの人間にとってはお前との別れが絶望で、お前にとってはその未来が絶望か。でも、あいつにはいい人生が、俺たちには妖だけの学校ごっこが待っているかもしれない」
左手の薬指にはめていた指輪を、右手へとはめ直す。
「永きを生きる間に記憶は薄れ、その指輪をはめている理由もいずれ忘れる」
「……ぞっとしないわね」
「それくらいに遠い先でいい。人間のような心を持つお前が好きだ。いつか人の子のように俺を愛してくれ」
時は巡りて禍福も廻る。
これからも、鬼と共に――。