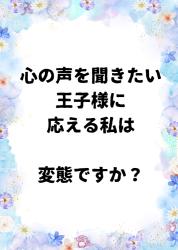「今年も誰かは来てくれるかしら」
「ああ、きっと来る。お前の美しさに恐れをなして逃げてくれるさ」
「……姿を見せるつもりはないわ」
季節が巡り、今宵も行われる灯籠流し。
優しい光を人の魂のように放ちながら、揺れて流れていく。
田舎だから参加者も多くはない。
私たちがすぐ脇の森の中で人間を驚かせたところで、大して問題にもならない。
――人ならざる者がいても、おかしくはないほどに寂れた郷だからだ。
私は禍津神の血を引いている。穢れから生まれ、人に災いをもたらす。
祀られているお陰で何十年か前までは何もせずにいられた。最近は信心を持つ若者が減って、たまに軽い悪戯くらいはしないと……いてもたってもいられない。
長い鮮やかな赤の髪が風にたなびく。
人間に姿が見えていたのなら、森の中にいても目立ったことだろう。
「今を生きる彼らには見えない私たちに、現世の風はなぜ優しく触れていくのかしら」
「俺が風でも、お前に触れたくなるさ」
「……その手の言葉は、もう聞き飽きたわ」
「愛しているんだよ、紅羽。悠久の時の流れの中、これからも永遠に口説かせてくれ」
私の名は紅羽。
なぜそんな名なのか……長く生きすぎてもう分からない。誰がつけたのかも何もかも。
私を愛していると言う彼は鬼の血を引いている。青い角と髪、青の瞳、彼の扱う炎もまた青い。その炎で何もかも焼き尽くす能力を持ってはいるはずだけれど、見たことはない。
見た目だけは涼やかなその色で、周囲を優しく照らしてくれることがあるだけだ。
名は恭介。違う名だったこともあるらしいけれど、今風に変えたと言っていた。長くは生きているものの、知り合ったのはほんの数十年前のこと。前の名は……知らない。
「あ、人間が来たわよ、恭介」
「そうだな、意味もなく隠れるか」
「そうね、意味もなく隠れましょう」
どうせ人間には姿など見えない。それでも見つかりたくない時に隠れるのは、人の世の影響か……。
「ああ、きっと来る。お前の美しさに恐れをなして逃げてくれるさ」
「……姿を見せるつもりはないわ」
季節が巡り、今宵も行われる灯籠流し。
優しい光を人の魂のように放ちながら、揺れて流れていく。
田舎だから参加者も多くはない。
私たちがすぐ脇の森の中で人間を驚かせたところで、大して問題にもならない。
――人ならざる者がいても、おかしくはないほどに寂れた郷だからだ。
私は禍津神の血を引いている。穢れから生まれ、人に災いをもたらす。
祀られているお陰で何十年か前までは何もせずにいられた。最近は信心を持つ若者が減って、たまに軽い悪戯くらいはしないと……いてもたってもいられない。
長い鮮やかな赤の髪が風にたなびく。
人間に姿が見えていたのなら、森の中にいても目立ったことだろう。
「今を生きる彼らには見えない私たちに、現世の風はなぜ優しく触れていくのかしら」
「俺が風でも、お前に触れたくなるさ」
「……その手の言葉は、もう聞き飽きたわ」
「愛しているんだよ、紅羽。悠久の時の流れの中、これからも永遠に口説かせてくれ」
私の名は紅羽。
なぜそんな名なのか……長く生きすぎてもう分からない。誰がつけたのかも何もかも。
私を愛していると言う彼は鬼の血を引いている。青い角と髪、青の瞳、彼の扱う炎もまた青い。その炎で何もかも焼き尽くす能力を持ってはいるはずだけれど、見たことはない。
見た目だけは涼やかなその色で、周囲を優しく照らしてくれることがあるだけだ。
名は恭介。違う名だったこともあるらしいけれど、今風に変えたと言っていた。長くは生きているものの、知り合ったのはほんの数十年前のこと。前の名は……知らない。
「あ、人間が来たわよ、恭介」
「そうだな、意味もなく隠れるか」
「そうね、意味もなく隠れましょう」
どうせ人間には姿など見えない。それでも見つかりたくない時に隠れるのは、人の世の影響か……。