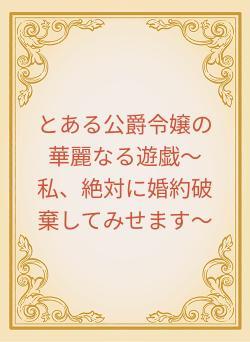この感覚には覚えがあった。
そう、武道の試合で強い相手と対峙した時の感覚だ。
思わずたらりと冷や汗が頬をつたい、緊張感がはしる。
「ねぇねぇ。そんなことより僕ね、君が知らないシュガーの秘密をいっぱい知ってるんだ!だから、詩桜ちゃんが僕の仲間になってくれたらなんでも教えてあげる。どう?」
けど、そんな私と裏腹に人懐っこく詰め寄るハル。
「良いアイデアでしょ?」と瞳を輝かせて私の顔をのぞき込む彼に私はフルフルと首を横に振った。
「他人から秘密を教えてもらったって何も嬉しくないよ。私、ちゃんと蜜生くん自身から話を聞きたいって思ってる。それに、蜜生くんが聞かれたくないことを今、無理に聞こうとは思わないから」
真っ直ぐに彼を見つめ、言い放ったその言葉に、目をしばたたかせたハルは小さくため息をついた。
「……ハァ。つまんないなぁ。詩桜ちゃんって本当に真面目だよね」
やるせなさそうなハルの態度に私は小さく首をひねる。
「まぁ、でもしょうがない。じゃ、詩桜ちゃん、そろそろ行こうか」
「え?……っ!」
慌てて、ベンチから立ち上がり、臨戦態勢をとろうとしたが気づくのが遅かった。
背後から近づいて来た誰かに羽交い締めにされ、声を上げないようにするためか口元を布で押さつけられたのだ。
懸命にもがくが、体勢的にもなかなか力が入らない。
そして、しばらくすると、だんだん意識が遠くなっていく。
薄れる意識のなか。
「……ごめんね、詩桜ちゃん」
そう悲しそう呟くハルの声が聞こえた気がした――。