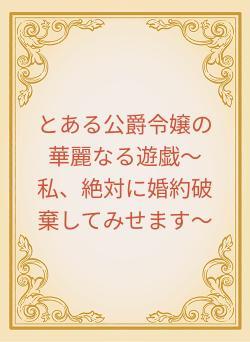「わ、マジで詩桜じゃん!懐かしいな〜。あ!俺、実は東野中でサッカー部に入ってて」
親しげに話しかけてくる加藤くん。
けど、ベンチに座ったままの私は、まるで体が石になってしまったかのように動けなかった。
何で動かないの……?
一生懸命動かそうとしているのに、自分の体じゃないみたいに自由がきかない。
指をピクリとも動かせないこの状況に、徐々に焦りを感じ始めた時。
『……え〜っと、ゴメン。詩桜のことは友達としては好きだけど、正直、女子としてはちょっと……。なんというか、そもそも俺より腕っぷしが強い子はないかな〜なんて。やっぱり女の子は守りたくなるような子の方が可愛いっていうか……』
当時加藤くんに言われた言葉が、フラッシュバックしてきて思わずギュッと胸を押さえた。
「……っ」
ドクン、ドクン。
心臓の鼓動がだんだんと早くなり、冷や汗まで出てくる。
もうどうしたらいいのかわからなくて、ギュッと目をつぶったその瞬間。
「……詩桜、お待たせ」
聞き馴染みある優しい声に、私のかたまった体の緊張がほぐれていくのを感じる。
目を開けなくても誰かわかった。
「みつ、きくん?」
バチッと目を開け、声がした方向に顔を向けると、少し息をきらした蜜生くんが立っていた。