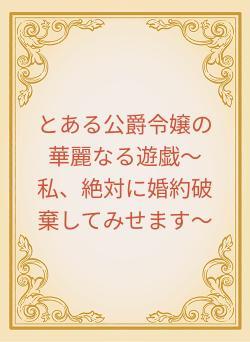「あれ、なんか詩桜ちゃん顔色悪くない?大丈夫?」
「…う、うん。ちょっとたちくらみかな?私、あっちのベンチで休んでくる。あ!少し休めば大丈夫だから、2人は私の分も青山くん達の応援お願い!」
私の様子が変なことに気づいた美春ちゃんに声をかけられて、慌ててそう答えた。
心配そうに私を見つめる2人に申し訳なさを感じつつも、
できるだけ相手校の関係者と鉢合わせないように、少し距離のあるベンチまでやって来た。
ここなら、ひとまず安心かも。
ホッと胸をなで下ろつつ、ベンチへ腰を下ろすと初夏の爽やかな風が頬をくすぐった。
梅雨があけたばかりの7月初旬。木陰に座っていても、じわりと額に汗がにじんでくる。
決めた、試合が始まったら、私も応援に戻ろう。
その時には、きっと試合の応援に夢中で相手側の応援席なんて見ないはずだもん。
そんな考えにいたり、試合が始まるまでの時間をベンチで過ごそうと決めた矢先。
「あれ、詩桜?詩桜じゃん!そっか、詩桜ってここの中学だったんだな」
私の名前を呼ぶ声に、とっさに振り返って後悔した。
そこにいたのは、私の記憶の中の姿よりも背が伸びた男子生徒。驚いたように目を丸くしている顔には当時の面影があった。
「……加藤、くん?」
一瞬でサーッと血の気が引いていくのを感じる。
そう、私の目の前に立っていたのは、小学生の時に私が好きだった男の子だった――。