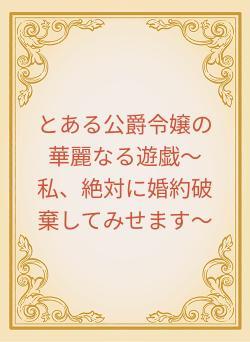動けないようにお姉さんを拘束すると、ギブアップと言うように地面を手で叩き、降参の合図をし始めた。
「さすが詩桜。やっぱり詩桜にボディーガードをお願いして正解だったよ」
「ボ、ボディーガードって何?私、そんな話聞いてないわよ!?」
蜜生くんの言葉にギョッとしたのか、目を見開くお姉さん。
たしかに普通は信じられないよね……。
私がお姉さんの立場でもびっくりすると思うもん。
「さて、これで形勢逆転。今回の黒幕しっかりはいてもらおうか?俺のこと聞いてるんでしょ?俺の技術使えば、アンタの個人情報特定するのなんか簡単だ。あ、その前に警察に連絡するのが先かな?」
フッと黒い笑顔で微笑む蜜生くんに、お姉さんはすでに顔面蒼白だ。
これじゃどっちが悪者かわからないなと、内心私も苦笑いを浮かべる。
「ちょ、ちょっと待って!警察って冗談よね?だって、これ、テレビの撮影なんでしょう?私は、SNSサイトで募集してたエキストラのバイトに応募しただけだもの。アドリブで演技をしながら、あなたを指定の場所に連れていくっていうヤツ!」
「私のスマホ見てみて!」と必死に地面に落ちているスマホを見るように促すお姉さんに、私と蜜生くんは顔を見合わせた。
「…………」
お姉さんのスマホをそっと拾い、黙ったまま中身を確認しだす蜜生くん。
「私は、この駄菓子屋で待機してたら修学旅行生にふんした子役が来るから、あなた以外の子には、この粉をいれたジュースを飲ませてって……。臨場感を出すために駄菓子屋に置かれたカメラで撮影するから、カメラマンは不在って聞いてたの!飲ませた粉だって小麦粉なんでしょう?さっきの子たちが倒れたのも演技なんでしょ?」
まくし立てるように叫ぶお姉さんは少しパニック気味になっていた。
「あのさ、このバイト怪しいと思わなかったの?それに、さっきの本当に演技?にしては、色々リアルだったけど?」
「わ、私は普段東京で舞台女優してるの。それに、私の役は、あなたを誘拐して追い詰める悪役って聞いてたから……。アドリブでなるべくそういう風に見えるよう悪役の演技をしてただけで……」
呆れたような視線をお姉さんに投げかけた蜜生くんは、やれやれと小さく首を横に振った。
「このメール見てると本当みたいだから教えるけど……。このバイトの内容は全部嘘だ。アンタは、本当の誘拐に加担させられてる。つまり、犯罪の片棒担がれたってわけ」
「え……。嘘……」
絶句するお姉さんは信じられないといった様子で、フルフルと身体を震わせている。