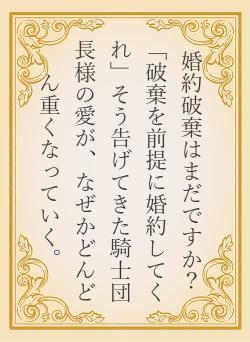「はぁ~。癒されるわ」
「もふもふでかわいいね」
お昼ご飯を食べた後、モルモットのふれあいコーナーに来ていた。
膝の上に乗せて、背中を優しく撫でる。
モルモットも慣れているのか、体を伸ばし気持ちよさそうにしている。
「蓮も触ってみろよ。かわいいぞ」
「僕はいいよ」
進藤くんはずっと見ているだけで触ろうはしない。
「動物、怖いの?」
「怖くないよ。怖くないけど、怖がられるのが怖い」
「怖いってことね」
「ほら蓮、怖くないぞ」
進藤くんはおそるおそる大崎くんが抱えているモルモットを撫でた。
モルモットは誰に撫でられようが気にすることなく受け入れている。
「かわいい……」
少しだけ顔を緩ませる進藤くんに、周りがほっこりしていた。
ちゃんと楽しめてるみたいでよかった。
園内の動物を全て見終わり、時間もいいころなので集合場所へと向かう。
なんやかんや言って、進藤くんも最後まで見て回れた。
確かに坂が多くて疲れたけど、この疲れも遠足の醍醐味だろ――
「わっ!」
「佐倉さん危ない!」
「ご、ごめん」
「大丈夫?」
なんでもないところで足がもつれ、転びそうになったところを大崎くんが抱きとめてくれた。
自分が思っている以上に、足にきてるのかな。
その時ふと、進藤くんと目が合った。
まだ大崎くんに抱きとめられたままの私を、無表情で見ている。
はっ。
ドンッ――
「えっ……」
「あっ、違うの。ありがとう。もう大丈夫だから」
「そっか、大丈夫ならよかった」
とっさに大崎くんを突き飛ばしていた。
進藤くんに見られてはいけない、無意識にそんなことを思った。
突き飛ばす、といっても私なんかが突き飛ばせるわけはなく、少し距離ができた程度だけど。
それでも大崎くんは驚いたあと、一瞬悲しそうな顔をした。
すごく、失礼なことをしてしまった。
私のことを助けてくれたのに。
でも、大崎くんの悲しそうな顔より、進藤くんの無表情の方が私は気になって仕方がなかった。
その後、集合場所で点呼を取り、バスに乗り込む。
私たちは一番後ろの席に、裕子、私、大崎くん、進藤くんの並びで座った。
「ねぇねぇ、お菓子余ってるから食べない?」
「欲しい。甘いもの食べたい気分だよ」
裕子がリュックからポッキーを取り出し配ってくれる。
四人でポッキーをぽりぽり食べる。なんかすごく、甘いものが体に染みるな。
いつものポッキーだが、いつもより美味しく感じた。
「疲れたけど楽しかったな!」
「大崎も疲れたんだ」
「そらあんだけ歩いたら疲れるだろ」
「やっぱりショートカットコースにすればよかったんじゃない?」
「それはないな」
進藤くんと大崎くんは仲良くおしゃべりをしている。
裕子はポッキーの箱を持ったまま眠ってしまっていた。
私は箱を裕子の手からそっと抜き取りリュックに入れた。
疲れたもんね。バスの振動が気持ちよくて眠ってしまうのもわかる。
てか、私も眠い……。
◇ ◇ ◇
――っ!
気がつくと私も眠っていた。裕子はまだ寝ている。クラスメイトたちもほとんど寝ているようだった。
そして私の肩には、大崎くんの頭が乗っている。
スヤスヤ寝息をたてて、気持ちよさそうに眠っている。
いくら部活で鍛えてるっていってもやっぱり疲れるよね。ちょっと重いけど、起こすのは悪いからこのままにしておこう。
大崎くんの頭をそのままに、少しだけ姿勢を正す。
そして大崎くんの反対側をちらりと覗くと、進藤くんは窓枠に頬杖をついて外を眺めていた。
学校に着き、担任の話を聞いてすぐに解散になった。
大崎くんはこれから部活があるといい、体育館に向かっていった。
大会が近いので、遠足の日でもきっちり練習があるのだそう。
バスの中で起こさなくてよかった。ゆっくり眠れただろうか。
幸人先輩を待つという裕子とも別れ、学校を出る。
私もバスで寝たからか、心なしか体がすっきりしていた。
今日の晩ご飯なに作ろうかな。昨日はからあげにしたから魚にしようかな。
そんなことを考えながら歩いていると、後ろから突然腕を掴まれる。
「ひぃっ!」
「変な声出さないでよ」
「し、進藤くん、普通に声かけてよ」
「普通に声かけたら佐倉さん逃げそうだし」
「いや別に逃げたりしないよ」
逃げられるようなことしてる自覚あるんだ?!
「行くよ」
「え、どこに?」
進藤くんは私の腕を掴んだまま無言でスタスタ歩いていく。
やっぱり逃げたいかもしれない。
着いたのはバス停だった。ちょうど来たバスにそのまま乗り込む。
「え?! 乗るの? どこ行くの?」
返事はない。
進藤くんは私の分の乗車料金も払い、二人掛けの席に座った。
さっき乗っていた観光バスとは違い、路線バスの座席は少し狭い。
触れた肩が、なんとなく小さく感じた。
「あのぉ、どこにいくんでしょうか?」
「どこにも行かない」
「どゆこと?!」
進藤くんは目を瞑り、私の肩に頭を置く。
もしかして……これも再現?
遠足の帰りのバス、進藤くんはずっと起きていたのだろうか。
肩を寄せて眠っていた私と大崎くんをどんな気持ちで見ていたのだろう。
「佐倉さんはずるいよね」
「ずるいってどういう――」
いや。どういうこと、なんて聞かなくてもわかるじゃないか。
大崎くんに好かれていて、私は好きかどうかもわからないのに付き合っている。
彼女としてそれなり仲良くしている。
もし、もしも進藤くんが女の子だったら?
大崎くんが進藤くんのことを好きじゃなくても、付き合ってみる、なんてこともありえたかもしれない。
今の私の立場は、本当にずるいと思う。
「ねえ進藤くん、もし私が大崎くんのことを好きになったらどうするの? 本気で好きになったから、もうこんなことはできないって言ったら」
「それはそれでいいんじゃない。仕方ないしね」
「仕方、ない……」
そうだ。進藤くんは初めから諦めていた。
諦めているからこそ、私とこんなことをして気持ちを誤魔化しているの?
前に言っていた、叶うことのない恋心。進藤くんの恋心は、どこにいけばいいのだろう。
「そうなったらさ、僕の代わりに大崎と二人で普通の恋をしてよ」
進藤くんは目を閉じたまま小さく告げた。
普通の恋……その言葉にすごく重みを感じる。
私にも、わかるときがくるのだろうか。
進藤くんには、普通の恋はできないのだろうか。
「ちなみに来週大崎の誕生日だよ。いくら好きではないにしろ、仮にも彼女なんだから何かしたほうがいいんじゃない?」
「え?! そうなの? 確かにそれは何かしないと」
てか、来週って! 今日金曜日なんですけど!
「来週っていつなの?」
「三日後」
「三日後?!」
月曜日じゃん! この土日でどうにかしなければ。
でも何をあげたらいいか、何をしたらいいか、全くわからない!!!!
「もふもふでかわいいね」
お昼ご飯を食べた後、モルモットのふれあいコーナーに来ていた。
膝の上に乗せて、背中を優しく撫でる。
モルモットも慣れているのか、体を伸ばし気持ちよさそうにしている。
「蓮も触ってみろよ。かわいいぞ」
「僕はいいよ」
進藤くんはずっと見ているだけで触ろうはしない。
「動物、怖いの?」
「怖くないよ。怖くないけど、怖がられるのが怖い」
「怖いってことね」
「ほら蓮、怖くないぞ」
進藤くんはおそるおそる大崎くんが抱えているモルモットを撫でた。
モルモットは誰に撫でられようが気にすることなく受け入れている。
「かわいい……」
少しだけ顔を緩ませる進藤くんに、周りがほっこりしていた。
ちゃんと楽しめてるみたいでよかった。
園内の動物を全て見終わり、時間もいいころなので集合場所へと向かう。
なんやかんや言って、進藤くんも最後まで見て回れた。
確かに坂が多くて疲れたけど、この疲れも遠足の醍醐味だろ――
「わっ!」
「佐倉さん危ない!」
「ご、ごめん」
「大丈夫?」
なんでもないところで足がもつれ、転びそうになったところを大崎くんが抱きとめてくれた。
自分が思っている以上に、足にきてるのかな。
その時ふと、進藤くんと目が合った。
まだ大崎くんに抱きとめられたままの私を、無表情で見ている。
はっ。
ドンッ――
「えっ……」
「あっ、違うの。ありがとう。もう大丈夫だから」
「そっか、大丈夫ならよかった」
とっさに大崎くんを突き飛ばしていた。
進藤くんに見られてはいけない、無意識にそんなことを思った。
突き飛ばす、といっても私なんかが突き飛ばせるわけはなく、少し距離ができた程度だけど。
それでも大崎くんは驚いたあと、一瞬悲しそうな顔をした。
すごく、失礼なことをしてしまった。
私のことを助けてくれたのに。
でも、大崎くんの悲しそうな顔より、進藤くんの無表情の方が私は気になって仕方がなかった。
その後、集合場所で点呼を取り、バスに乗り込む。
私たちは一番後ろの席に、裕子、私、大崎くん、進藤くんの並びで座った。
「ねぇねぇ、お菓子余ってるから食べない?」
「欲しい。甘いもの食べたい気分だよ」
裕子がリュックからポッキーを取り出し配ってくれる。
四人でポッキーをぽりぽり食べる。なんかすごく、甘いものが体に染みるな。
いつものポッキーだが、いつもより美味しく感じた。
「疲れたけど楽しかったな!」
「大崎も疲れたんだ」
「そらあんだけ歩いたら疲れるだろ」
「やっぱりショートカットコースにすればよかったんじゃない?」
「それはないな」
進藤くんと大崎くんは仲良くおしゃべりをしている。
裕子はポッキーの箱を持ったまま眠ってしまっていた。
私は箱を裕子の手からそっと抜き取りリュックに入れた。
疲れたもんね。バスの振動が気持ちよくて眠ってしまうのもわかる。
てか、私も眠い……。
◇ ◇ ◇
――っ!
気がつくと私も眠っていた。裕子はまだ寝ている。クラスメイトたちもほとんど寝ているようだった。
そして私の肩には、大崎くんの頭が乗っている。
スヤスヤ寝息をたてて、気持ちよさそうに眠っている。
いくら部活で鍛えてるっていってもやっぱり疲れるよね。ちょっと重いけど、起こすのは悪いからこのままにしておこう。
大崎くんの頭をそのままに、少しだけ姿勢を正す。
そして大崎くんの反対側をちらりと覗くと、進藤くんは窓枠に頬杖をついて外を眺めていた。
学校に着き、担任の話を聞いてすぐに解散になった。
大崎くんはこれから部活があるといい、体育館に向かっていった。
大会が近いので、遠足の日でもきっちり練習があるのだそう。
バスの中で起こさなくてよかった。ゆっくり眠れただろうか。
幸人先輩を待つという裕子とも別れ、学校を出る。
私もバスで寝たからか、心なしか体がすっきりしていた。
今日の晩ご飯なに作ろうかな。昨日はからあげにしたから魚にしようかな。
そんなことを考えながら歩いていると、後ろから突然腕を掴まれる。
「ひぃっ!」
「変な声出さないでよ」
「し、進藤くん、普通に声かけてよ」
「普通に声かけたら佐倉さん逃げそうだし」
「いや別に逃げたりしないよ」
逃げられるようなことしてる自覚あるんだ?!
「行くよ」
「え、どこに?」
進藤くんは私の腕を掴んだまま無言でスタスタ歩いていく。
やっぱり逃げたいかもしれない。
着いたのはバス停だった。ちょうど来たバスにそのまま乗り込む。
「え?! 乗るの? どこ行くの?」
返事はない。
進藤くんは私の分の乗車料金も払い、二人掛けの席に座った。
さっき乗っていた観光バスとは違い、路線バスの座席は少し狭い。
触れた肩が、なんとなく小さく感じた。
「あのぉ、どこにいくんでしょうか?」
「どこにも行かない」
「どゆこと?!」
進藤くんは目を瞑り、私の肩に頭を置く。
もしかして……これも再現?
遠足の帰りのバス、進藤くんはずっと起きていたのだろうか。
肩を寄せて眠っていた私と大崎くんをどんな気持ちで見ていたのだろう。
「佐倉さんはずるいよね」
「ずるいってどういう――」
いや。どういうこと、なんて聞かなくてもわかるじゃないか。
大崎くんに好かれていて、私は好きかどうかもわからないのに付き合っている。
彼女としてそれなり仲良くしている。
もし、もしも進藤くんが女の子だったら?
大崎くんが進藤くんのことを好きじゃなくても、付き合ってみる、なんてこともありえたかもしれない。
今の私の立場は、本当にずるいと思う。
「ねえ進藤くん、もし私が大崎くんのことを好きになったらどうするの? 本気で好きになったから、もうこんなことはできないって言ったら」
「それはそれでいいんじゃない。仕方ないしね」
「仕方、ない……」
そうだ。進藤くんは初めから諦めていた。
諦めているからこそ、私とこんなことをして気持ちを誤魔化しているの?
前に言っていた、叶うことのない恋心。進藤くんの恋心は、どこにいけばいいのだろう。
「そうなったらさ、僕の代わりに大崎と二人で普通の恋をしてよ」
進藤くんは目を閉じたまま小さく告げた。
普通の恋……その言葉にすごく重みを感じる。
私にも、わかるときがくるのだろうか。
進藤くんには、普通の恋はできないのだろうか。
「ちなみに来週大崎の誕生日だよ。いくら好きではないにしろ、仮にも彼女なんだから何かしたほうがいいんじゃない?」
「え?! そうなの? 確かにそれは何かしないと」
てか、来週って! 今日金曜日なんですけど!
「来週っていつなの?」
「三日後」
「三日後?!」
月曜日じゃん! この土日でどうにかしなければ。
でも何をあげたらいいか、何をしたらいいか、全くわからない!!!!