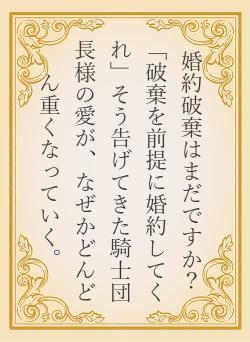「佐倉さん、ありがとう」
「えっ? なにが?」
歩いていると唐突に進藤くんからお礼を言われた。
何かお礼を言われるようなことしただろうか。もう、半年以上話もしていないのに。
「大崎のこと。佐倉さんが何か言ってくれたんだよね。もっと早くにお礼言えば良かったんだけどタイミング逃しちゃって」
「そのことは……私は何もしてないよ。ただ、私の思いを少し伝えただけ。あとは、大崎くんがそれだけ進藤くんのことを大切な友達だと思ってたってことだよ」
私は進藤くんと以前のように仲良くして欲しいとは言っていない。
このままでいいの? と聞いただけ。少し、向き合うきっかけを作っただけ。
でも、気になっていたことがある。本当にこれで良かったのだろうかと。
「私、余計なことしてないかな? 二人にはまた仲良くしてほしいと思ってたけど、もしかするとそれは進藤くんにとってつらいことなんじゃないかって」
「気にしすぎだよ。僕は嬉しかったよ。大崎が友達としてまたそばにいてくれるようになったことも、佐倉さんが僕のためにしてくれたこともね」
「そっか、なら良かった」
進藤くんはフッと笑いながらゆっくりと歩く。
この、小さく笑う表情がすごく安心する。隣にいるだけで、穏やかな気持ちになる。進藤くんはどう思っているだろう。
「佐倉さんってほんと面白いよね」
「面白い? 今の会話で面白いことあった?!」
どちらかというと、ちょっとしっとりした雰囲気だったよね?
なんでだろうと思っていると、進藤くんは私の足元を見る。
私も自分の足元を見る――
「あ゛あああああ」
「佐倉さんうるさいよ。今さらだから気にしても仕方ないよ」
「なんでずっと言ってくれなかったのぉ」
思い立って家を飛び出してきた私は、着替えの途中だった。
上はまだ制服のシャツなのに、ズボンはサテン生地のショートパンツ。白いハイソックスはしっかり履いたままで靴はスリッポンだ。
「それはそれで可愛いんじゃない」
「絶対うそだー!」
これで走ってきたとか恥ずかしすぎる。こんな格好の女が隣に並んでいて進藤くんは恥ずかしくないのだろうか。今すぐ帰って着替えて出直したい。
なんて思っていると、もうすぐ目の前にうちが見える。
「あれ? 送ってくれたの?」
「一人で帰るには危ない姿してるよね。不審者に思われそう」
「そっち?!」
なんて言っているが、きっと心配して家まで送ってくれたんだ。そういう優しさが、本当に好きだ。
家に着き、玄関の前で進藤くんと向き合う。
「佐倉さん、ほんとにありがとう」
「え? なんで? こちらこそ送ってくれてありがとう」
「僕、たぶん佐倉さんと話さなくなって寂しかったんだよね。今日、家まできてくれて嬉しかった」
進藤くんも寂しかったんだ。
衝動的に家を飛び出してしまったけど、会いにきて良かった。気持ちを知れて良かった。
クラスは違うけど、また前にみたいに一緒に過ごすことができればな。
「私も、誕生日覚えていてくれて、プレゼントももらって、すごく嬉しいよ! また、学校でも話かけていいかな?」
「学校……。その格好で話かけられるのはやだな」
「これで学校行くわけないでしょ!」
「噓だよ。どんな佐倉さんでもいいよ」
進藤くんはまたフッと笑う。
私は手を振り、玄関のドアを開ける。中に入り、ドアを閉めるまで見送ってくれた。
家に入り、改めて鏡で自分の格好を見て恥ずかしくなる。でも、心はなんだかスッキリしていた。
いつか、ちゃんと気持ちを伝えたい。
でも、今じゃない気がする。お互いに受験もあるし、私は進路さえ決まっていない。
受験を終えて、自分に自信をつけて、それから想いを伝えよう。それまでは友達としてそばにいよう。
そう、今の気持ちに結論付けた。
◇ ◇ ◇
「佐倉さんまだ進路決まってないんだ」
「やりたいことが見つからないんだよね。だから行きたい大学も見つからなくて」
「僕だってやりたいことなんてないよ。親にこの大学に行けって言われたから行くだけ」
「言われた通りにできる進藤くんはすごいよ……」
私は昼休み、勇気を出して進藤くんをご飯に誘った。
そして今、久しぶりに別館の空き教室に来ている。
大崎くんともよく過ごした場所。ここでいろいろあったけど、今はもういい思い出だ。
懐かしいこの場所に感慨深く思いながら、お弁当を食べる。
私の頭の中はやっぱり進路のことがあり、まだ決められないことをぼそりと呟いた。
進藤くんは去年から受験勉強らしきものをしていたし、そりゃ決めてるよね。
「なんの大学に行くの?」
「なんのというか、法学部だね」
「法学部?! 弁護士になるの?」
「弁護士かもしれないし、検察官かもしれないし、裁判官かもしれないし」
「すごい……」
「なにもしてないかもしれないよ」
なにもしてない、か。進藤くんは自分がなりたいわけじゃないんだよね。でもきっと、弁護士でも検察官でも裁判官でもなれる能力をもっているんだろうな。可能性がたくさんあるってすごいことだと思う。私には、なにができるだろう。
「佐倉さんはさ、自分で選択肢を選べるんだから、好きなことをすればいいんじゃない?」
「好きなことか……なんだろう」
「BL小説家になるとか」
「本気で言ってる?!」
「本気にするかは佐倉さん次第でしょ」
ずるい言い方するよなあ。小説家になるつもりはないけど。ただの趣味だし。
でも、好きなことか。将来のことばかり考えて、今の自分が何をしたいかなんて考えていなかった。お父さんは私の好きな大学に行って良いと言ってくれている。先生も高望みし過ぎなければある程度希望通りの大学に行けるだろうと。それよりも、夏休みに入るまでに決めることが重要だって言われてるんだよね。
「難しいなぁ」
「佐倉さん、今日の玉子焼きは甘いの? しょっぱいの?」
「え? しょっぱい、けど……」
「ちょーだい?」
急に可愛く首をかしげ、おねだりしてくる進藤くん。
そんなに私の玉子焼き気に入ってくれてたんだな。いつもは甘いのにしてるけど、今日はしょっぱいのにしてよかった。
「はい、どうぞ」
お弁当の蓋に乗せ差し出す。進藤くんは指でつまんで一口で食べた。口いっぱいにモグモグとさせながら目元を緩ませる。
「やっぱり玉子焼きはしょっぱいのがいいよね」
「それは良かったです」
「でも佐倉さんは甘いのが好きなのにどうしてしょっぱいの作ってきたの?」
「えっと……な、なんとなく?」
本当は、もしかしたら進藤くんが食べるかもしれないからと思って作ってきたけど、それは恥ずかしくて言えなかった。
でも、進藤くんは私を見てフッと笑う。
「佐倉さんて、可愛いとこあるよね」
まるで私の気持ちを見透かしているようだ。
ちょっと気恥ずかしさもあるけれど、それが嬉しくもあった。
「えっ? なにが?」
歩いていると唐突に進藤くんからお礼を言われた。
何かお礼を言われるようなことしただろうか。もう、半年以上話もしていないのに。
「大崎のこと。佐倉さんが何か言ってくれたんだよね。もっと早くにお礼言えば良かったんだけどタイミング逃しちゃって」
「そのことは……私は何もしてないよ。ただ、私の思いを少し伝えただけ。あとは、大崎くんがそれだけ進藤くんのことを大切な友達だと思ってたってことだよ」
私は進藤くんと以前のように仲良くして欲しいとは言っていない。
このままでいいの? と聞いただけ。少し、向き合うきっかけを作っただけ。
でも、気になっていたことがある。本当にこれで良かったのだろうかと。
「私、余計なことしてないかな? 二人にはまた仲良くしてほしいと思ってたけど、もしかするとそれは進藤くんにとってつらいことなんじゃないかって」
「気にしすぎだよ。僕は嬉しかったよ。大崎が友達としてまたそばにいてくれるようになったことも、佐倉さんが僕のためにしてくれたこともね」
「そっか、なら良かった」
進藤くんはフッと笑いながらゆっくりと歩く。
この、小さく笑う表情がすごく安心する。隣にいるだけで、穏やかな気持ちになる。進藤くんはどう思っているだろう。
「佐倉さんってほんと面白いよね」
「面白い? 今の会話で面白いことあった?!」
どちらかというと、ちょっとしっとりした雰囲気だったよね?
なんでだろうと思っていると、進藤くんは私の足元を見る。
私も自分の足元を見る――
「あ゛あああああ」
「佐倉さんうるさいよ。今さらだから気にしても仕方ないよ」
「なんでずっと言ってくれなかったのぉ」
思い立って家を飛び出してきた私は、着替えの途中だった。
上はまだ制服のシャツなのに、ズボンはサテン生地のショートパンツ。白いハイソックスはしっかり履いたままで靴はスリッポンだ。
「それはそれで可愛いんじゃない」
「絶対うそだー!」
これで走ってきたとか恥ずかしすぎる。こんな格好の女が隣に並んでいて進藤くんは恥ずかしくないのだろうか。今すぐ帰って着替えて出直したい。
なんて思っていると、もうすぐ目の前にうちが見える。
「あれ? 送ってくれたの?」
「一人で帰るには危ない姿してるよね。不審者に思われそう」
「そっち?!」
なんて言っているが、きっと心配して家まで送ってくれたんだ。そういう優しさが、本当に好きだ。
家に着き、玄関の前で進藤くんと向き合う。
「佐倉さん、ほんとにありがとう」
「え? なんで? こちらこそ送ってくれてありがとう」
「僕、たぶん佐倉さんと話さなくなって寂しかったんだよね。今日、家まできてくれて嬉しかった」
進藤くんも寂しかったんだ。
衝動的に家を飛び出してしまったけど、会いにきて良かった。気持ちを知れて良かった。
クラスは違うけど、また前にみたいに一緒に過ごすことができればな。
「私も、誕生日覚えていてくれて、プレゼントももらって、すごく嬉しいよ! また、学校でも話かけていいかな?」
「学校……。その格好で話かけられるのはやだな」
「これで学校行くわけないでしょ!」
「噓だよ。どんな佐倉さんでもいいよ」
進藤くんはまたフッと笑う。
私は手を振り、玄関のドアを開ける。中に入り、ドアを閉めるまで見送ってくれた。
家に入り、改めて鏡で自分の格好を見て恥ずかしくなる。でも、心はなんだかスッキリしていた。
いつか、ちゃんと気持ちを伝えたい。
でも、今じゃない気がする。お互いに受験もあるし、私は進路さえ決まっていない。
受験を終えて、自分に自信をつけて、それから想いを伝えよう。それまでは友達としてそばにいよう。
そう、今の気持ちに結論付けた。
◇ ◇ ◇
「佐倉さんまだ進路決まってないんだ」
「やりたいことが見つからないんだよね。だから行きたい大学も見つからなくて」
「僕だってやりたいことなんてないよ。親にこの大学に行けって言われたから行くだけ」
「言われた通りにできる進藤くんはすごいよ……」
私は昼休み、勇気を出して進藤くんをご飯に誘った。
そして今、久しぶりに別館の空き教室に来ている。
大崎くんともよく過ごした場所。ここでいろいろあったけど、今はもういい思い出だ。
懐かしいこの場所に感慨深く思いながら、お弁当を食べる。
私の頭の中はやっぱり進路のことがあり、まだ決められないことをぼそりと呟いた。
進藤くんは去年から受験勉強らしきものをしていたし、そりゃ決めてるよね。
「なんの大学に行くの?」
「なんのというか、法学部だね」
「法学部?! 弁護士になるの?」
「弁護士かもしれないし、検察官かもしれないし、裁判官かもしれないし」
「すごい……」
「なにもしてないかもしれないよ」
なにもしてない、か。進藤くんは自分がなりたいわけじゃないんだよね。でもきっと、弁護士でも検察官でも裁判官でもなれる能力をもっているんだろうな。可能性がたくさんあるってすごいことだと思う。私には、なにができるだろう。
「佐倉さんはさ、自分で選択肢を選べるんだから、好きなことをすればいいんじゃない?」
「好きなことか……なんだろう」
「BL小説家になるとか」
「本気で言ってる?!」
「本気にするかは佐倉さん次第でしょ」
ずるい言い方するよなあ。小説家になるつもりはないけど。ただの趣味だし。
でも、好きなことか。将来のことばかり考えて、今の自分が何をしたいかなんて考えていなかった。お父さんは私の好きな大学に行って良いと言ってくれている。先生も高望みし過ぎなければある程度希望通りの大学に行けるだろうと。それよりも、夏休みに入るまでに決めることが重要だって言われてるんだよね。
「難しいなぁ」
「佐倉さん、今日の玉子焼きは甘いの? しょっぱいの?」
「え? しょっぱい、けど……」
「ちょーだい?」
急に可愛く首をかしげ、おねだりしてくる進藤くん。
そんなに私の玉子焼き気に入ってくれてたんだな。いつもは甘いのにしてるけど、今日はしょっぱいのにしてよかった。
「はい、どうぞ」
お弁当の蓋に乗せ差し出す。進藤くんは指でつまんで一口で食べた。口いっぱいにモグモグとさせながら目元を緩ませる。
「やっぱり玉子焼きはしょっぱいのがいいよね」
「それは良かったです」
「でも佐倉さんは甘いのが好きなのにどうしてしょっぱいの作ってきたの?」
「えっと……な、なんとなく?」
本当は、もしかしたら進藤くんが食べるかもしれないからと思って作ってきたけど、それは恥ずかしくて言えなかった。
でも、進藤くんは私を見てフッと笑う。
「佐倉さんて、可愛いとこあるよね」
まるで私の気持ちを見透かしているようだ。
ちょっと気恥ずかしさもあるけれど、それが嬉しくもあった。