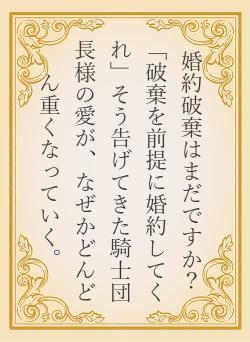季節は巡り、高校生になって三度目の夏。
新しいクラスにも慣れ、穏やかな日々を送っている。
でも、ずっと懸念していたことがすぐ目の前に押し迫り、そのことで頭はいっぱいだ。
「葉月、進路決まらないの?」
「そうなんだよね。行ける大学に行けたらいいやなんて思ってたけど、そんなんじゃ行ける大学にも行けないって先生に言われた……」
昼休み、お弁当を食べながら裕子と進路の話をしていた。
クラスは離れてしまったけど、時々どちらからともなく誘っては一緒に過ごしている。
今日は渡したいものがあるからと、裕子から誘ってくれた。
ちなみに、進藤くんと大崎くんもそれぞれ別々のクラスだ。
「成績は悪くないんだし、いい大学に決めるのかと思ってたわ」
「ちゃんと、意味を持って大学に行きたいんだよね。目標とか、就きたい職業とかを考えて」
「葉月は偉いね。将来のこと真剣に考えて」
そう言う裕子は、看護の専門学校に行くことを決めている。看護師だと就職に困らないし、産休育休を経ても復帰しやすい職場だから、なんて言っていたけど、裕子に合った職業だと思う。
人のことをよく見ていて、変化にもよく気づく。しっかりしていて何かあったときは頼りになる。
きっと良い看護師さんになるんだろうな。
私は将来、なにをしてるんだろう――。
放課後、帰ろうと靴箱へ行くと、私の棚の中に何かが入っている。
不思議に思いながら取り出すと、ちょうど一年前に進藤くんと行った雑貨屋さんのロゴの入った小さな袋だった。
「これ……」
中を開けて見てみると、そこにはヘアゴムが入っていた。
黒い丸ゴムに、小さな花が三つ並んだ、可愛らしいヘアゴム。
私好みの、控えめだけど、綺麗で大人っぽいデザインだ。
そして中にはメモ用紙も入っていた。
『隙間、ちゃんと埋めてね』
「進藤、くん?」
周りを見渡すけれど、進藤くんはいない。学校を飛び出し探すけれど、いない。
少し期待しながら横断歩道を渡った交差点の角を覗くけれど、いない。
私はブロック塀にもたれかかり、息を整える。でも、早くなった鼓動は落ち着かない。
鞄からスマホを取り出しメッセージを送る。
『進藤くん、今どこにいるの?』
返事はない。
諦めて、家へ向かって歩き出した。
結局、進藤くんとはもうずっと話をしていない。話をしていないどころか、クラスも離れて顔を合わせることさえなくなった。
今の環境に慣れてきた。それが、当たり前になった。
でも、忘れたことは一度もない。
今、進藤くんは何してるだろう。新しいクラスで馴染めているのかな。
そんなことを考えてはあの頃の思い出に浸っている。
初めてちゃんと話したとき、変な人だと思った。一緒にいる時間が増えると本当の進藤くんを知った。私のことをよく理解してくれる人だった。ちょっと意地悪だけど、それが私の心をいつも軽くしてくれた。
いつの間にか、進藤くんの存在はかげがえのないものになっていたことに、私は気づいている。
気づいたときにはもう、遅かったこともわかっている。
その時、スマホの通知が鳴った。
進藤くんだ!
『佐倉さん、誕生日おめでとう』
どこにいるの? という質問に対する返事はなかった。
家、行ってみようかな? それとも明日、教室まで会いに行く? 迷惑かな?
よく考えれば、私に会いたくないからどこにいるかの返事をくれなかったのかも。よく考えなくてもそうか。
私は『プレゼントありがとう』とだけ返事をして家へ帰った。
部屋に入ってすぐ、倒れ込むようにベッドに埋まる。
今すごく、進藤くんのことで頭がいっぱいだ。
でも着替えないと。起き上がり、ボーっと考えながら適当に部屋着を掴む。
誕生日を覚えていてくれたことが嬉しかった。
ヘアゴムも、私のことを思いながら選んでくれたんだろう。
去年の誕生日も、わざと変なシュシュを私に見せて、私の好きなものを選ばせようとしていたんだと、今ならわかる。そういうことをさらっとしてしまう進藤くんはズルい人だ。
思い出すたびに、後から後から進藤くんの存在が大きくなるんだから。
会いたい。進藤くんに会いたい。
見ないようにしていた気持ちが、開けないようにしていた蓋が、開いてしまったようだった。
私、進藤くんのことが好きなんだ。
これからどうしたらいい? 進藤くんに気持ちを伝えにいく?
そんなこと怖くてできない。自分のことを好きじゃない相手に気持ちを伝えることって、こんなにも不安で怖いものなんだ。
私が大崎くんのことを好きになったとき、好かれているという安心感があった。
それはきっと特別なことだったんだ。
じゃあ、好きになってもらうにはどうしたらいい?
私は、家を飛び出した。
進藤くんの家は一回しか行ったことがないけれど、覚えている。
無我夢中で走る。何を話そうかなんて決めていないけど、どうしても進藤くんに会いたかった。
広い庭のある、二階建ての一軒家。
玄関の前で息を整え、握りしめていたヘアゴムで髪を纏める。
汗ばんだ首筋が冷えていく。
額の汗を拭い、インターホンを押す。
応答はないまま、玄関のドアが開いた。
「佐倉さん、どうしたの」
ああ、進藤くんだ。
突然家に来たのに驚く様子もなく、少し気だるそうに私を見る。
「進藤くん、あのね、私……えっと……あ、これありがとう」
ヘアゴムを見せるように首を後ろに捻る。
「髪、ぼさぼさだけど」
フッと笑われ、鋭い突っ込みをいただいた。
今、さっと結んだだけで頭はボコボコだし、後れ毛もいっぱい出ているだろう。
なんだか急に恥ずかしくなってくる。べたついた前髪を指で撫で、なんとなく誤魔化してみる。
「ちょっと、急いでて……でも、すごく嬉しい」
「よかった。でも、それだけ言いにわざわざ家まで来たの?」
「そういう訳じゃないんだけど……」
「うち、上がる? 今だれもいないし」
どうしよう。お家にお邪魔する? 何も考えずに来てしまったけど、いいのかな。
私、 どうして進藤くんに会いに来た? 何を、伝えに来た?
「――進藤くん、私と友達になってください!」
玄関の前で勢いよく頭を下げる。伝えたかったこととは少し違うけど、今一番の願い。
好きになってもらうためにできること。
それは、そばにいることだと思った。
気持ちを伝える勇気はまだないけれど、もっとたくさん私を知ってもらいたい。そばにいたいと思ってもらえるように、できることをしたい。進藤くんに笑って欲しい。一緒に楽しいことをしたい。
「僕たちって友達じゃなかったの」
「いや、友達……だけど、友達なんだけど、もっとこう、今とは違う……なんか……」
んー、なんて言ったらいいかわからない。
悩んでいると、進藤くんはクスクスと笑い始める。
「佐倉さん、家入らないならちょっと散歩しようよ」
進藤くんは玄関の鍵を閉めると外へ出てきて、私よりも先に歩き始めた。
急いで横に並び、顔をちらりと見る。以前と変わらない、何を考えているかわからない涼しげな表情。それがなんだか安心して、スタスタと歩いていく進藤くんについていった。
新しいクラスにも慣れ、穏やかな日々を送っている。
でも、ずっと懸念していたことがすぐ目の前に押し迫り、そのことで頭はいっぱいだ。
「葉月、進路決まらないの?」
「そうなんだよね。行ける大学に行けたらいいやなんて思ってたけど、そんなんじゃ行ける大学にも行けないって先生に言われた……」
昼休み、お弁当を食べながら裕子と進路の話をしていた。
クラスは離れてしまったけど、時々どちらからともなく誘っては一緒に過ごしている。
今日は渡したいものがあるからと、裕子から誘ってくれた。
ちなみに、進藤くんと大崎くんもそれぞれ別々のクラスだ。
「成績は悪くないんだし、いい大学に決めるのかと思ってたわ」
「ちゃんと、意味を持って大学に行きたいんだよね。目標とか、就きたい職業とかを考えて」
「葉月は偉いね。将来のこと真剣に考えて」
そう言う裕子は、看護の専門学校に行くことを決めている。看護師だと就職に困らないし、産休育休を経ても復帰しやすい職場だから、なんて言っていたけど、裕子に合った職業だと思う。
人のことをよく見ていて、変化にもよく気づく。しっかりしていて何かあったときは頼りになる。
きっと良い看護師さんになるんだろうな。
私は将来、なにをしてるんだろう――。
放課後、帰ろうと靴箱へ行くと、私の棚の中に何かが入っている。
不思議に思いながら取り出すと、ちょうど一年前に進藤くんと行った雑貨屋さんのロゴの入った小さな袋だった。
「これ……」
中を開けて見てみると、そこにはヘアゴムが入っていた。
黒い丸ゴムに、小さな花が三つ並んだ、可愛らしいヘアゴム。
私好みの、控えめだけど、綺麗で大人っぽいデザインだ。
そして中にはメモ用紙も入っていた。
『隙間、ちゃんと埋めてね』
「進藤、くん?」
周りを見渡すけれど、進藤くんはいない。学校を飛び出し探すけれど、いない。
少し期待しながら横断歩道を渡った交差点の角を覗くけれど、いない。
私はブロック塀にもたれかかり、息を整える。でも、早くなった鼓動は落ち着かない。
鞄からスマホを取り出しメッセージを送る。
『進藤くん、今どこにいるの?』
返事はない。
諦めて、家へ向かって歩き出した。
結局、進藤くんとはもうずっと話をしていない。話をしていないどころか、クラスも離れて顔を合わせることさえなくなった。
今の環境に慣れてきた。それが、当たり前になった。
でも、忘れたことは一度もない。
今、進藤くんは何してるだろう。新しいクラスで馴染めているのかな。
そんなことを考えてはあの頃の思い出に浸っている。
初めてちゃんと話したとき、変な人だと思った。一緒にいる時間が増えると本当の進藤くんを知った。私のことをよく理解してくれる人だった。ちょっと意地悪だけど、それが私の心をいつも軽くしてくれた。
いつの間にか、進藤くんの存在はかげがえのないものになっていたことに、私は気づいている。
気づいたときにはもう、遅かったこともわかっている。
その時、スマホの通知が鳴った。
進藤くんだ!
『佐倉さん、誕生日おめでとう』
どこにいるの? という質問に対する返事はなかった。
家、行ってみようかな? それとも明日、教室まで会いに行く? 迷惑かな?
よく考えれば、私に会いたくないからどこにいるかの返事をくれなかったのかも。よく考えなくてもそうか。
私は『プレゼントありがとう』とだけ返事をして家へ帰った。
部屋に入ってすぐ、倒れ込むようにベッドに埋まる。
今すごく、進藤くんのことで頭がいっぱいだ。
でも着替えないと。起き上がり、ボーっと考えながら適当に部屋着を掴む。
誕生日を覚えていてくれたことが嬉しかった。
ヘアゴムも、私のことを思いながら選んでくれたんだろう。
去年の誕生日も、わざと変なシュシュを私に見せて、私の好きなものを選ばせようとしていたんだと、今ならわかる。そういうことをさらっとしてしまう進藤くんはズルい人だ。
思い出すたびに、後から後から進藤くんの存在が大きくなるんだから。
会いたい。進藤くんに会いたい。
見ないようにしていた気持ちが、開けないようにしていた蓋が、開いてしまったようだった。
私、進藤くんのことが好きなんだ。
これからどうしたらいい? 進藤くんに気持ちを伝えにいく?
そんなこと怖くてできない。自分のことを好きじゃない相手に気持ちを伝えることって、こんなにも不安で怖いものなんだ。
私が大崎くんのことを好きになったとき、好かれているという安心感があった。
それはきっと特別なことだったんだ。
じゃあ、好きになってもらうにはどうしたらいい?
私は、家を飛び出した。
進藤くんの家は一回しか行ったことがないけれど、覚えている。
無我夢中で走る。何を話そうかなんて決めていないけど、どうしても進藤くんに会いたかった。
広い庭のある、二階建ての一軒家。
玄関の前で息を整え、握りしめていたヘアゴムで髪を纏める。
汗ばんだ首筋が冷えていく。
額の汗を拭い、インターホンを押す。
応答はないまま、玄関のドアが開いた。
「佐倉さん、どうしたの」
ああ、進藤くんだ。
突然家に来たのに驚く様子もなく、少し気だるそうに私を見る。
「進藤くん、あのね、私……えっと……あ、これありがとう」
ヘアゴムを見せるように首を後ろに捻る。
「髪、ぼさぼさだけど」
フッと笑われ、鋭い突っ込みをいただいた。
今、さっと結んだだけで頭はボコボコだし、後れ毛もいっぱい出ているだろう。
なんだか急に恥ずかしくなってくる。べたついた前髪を指で撫で、なんとなく誤魔化してみる。
「ちょっと、急いでて……でも、すごく嬉しい」
「よかった。でも、それだけ言いにわざわざ家まで来たの?」
「そういう訳じゃないんだけど……」
「うち、上がる? 今だれもいないし」
どうしよう。お家にお邪魔する? 何も考えずに来てしまったけど、いいのかな。
私、 どうして進藤くんに会いに来た? 何を、伝えに来た?
「――進藤くん、私と友達になってください!」
玄関の前で勢いよく頭を下げる。伝えたかったこととは少し違うけど、今一番の願い。
好きになってもらうためにできること。
それは、そばにいることだと思った。
気持ちを伝える勇気はまだないけれど、もっとたくさん私を知ってもらいたい。そばにいたいと思ってもらえるように、できることをしたい。進藤くんに笑って欲しい。一緒に楽しいことをしたい。
「僕たちって友達じゃなかったの」
「いや、友達……だけど、友達なんだけど、もっとこう、今とは違う……なんか……」
んー、なんて言ったらいいかわからない。
悩んでいると、進藤くんはクスクスと笑い始める。
「佐倉さん、家入らないならちょっと散歩しようよ」
進藤くんは玄関の鍵を閉めると外へ出てきて、私よりも先に歩き始めた。
急いで横に並び、顔をちらりと見る。以前と変わらない、何を考えているかわからない涼しげな表情。それがなんだか安心して、スタスタと歩いていく進藤くんについていった。