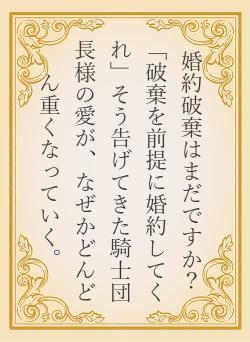大崎くんと別れてから、お互いに気を遣いながらも少しずつ普通に話すようになっていた。
そして驚いたことがある。嬉しい驚きだ。
それは、大崎くんと進藤くんがまた一緒にいるようになったこと。
以前のようにとはいかないけれど、ぎこちないながらも友達としての関係を築きつつあるみたい。
きっと、二人でたくさん話をしたのだろう。
進藤くんが吹っ切れた上で関わっているのかはわからない。
でも、もうそれは関係ない。これからも二人はきっと友達として一緒にいるだろうから。
全てが、付き合う前の関係に戻りつつある。そう、全てが。
進藤くんとはあれから特別話しをしていない。
大崎くんから、別れたことは聞いているかもしれない。
だからといって、何か言われることもなければ私から報告することもなかった。
告白される前の、友達ですらないただのクラスメイトの関係に戻っていた。
よく考えれば、進藤くんが私に声をかけてきたのは大崎くんと付き合って、それを教えて欲しいからだった。
別れてしまった今、私たちが関わる理由はないのかもしれない。
大崎くんと一緒にいる進藤くんに、私を見ない進藤くんに、私はもう必要ないように思えた。
すごく、寂しい。思っていた以上に。
私から話しかければいいのかもしれないけど、話しかける理由がないからできなかった。
こんなこと言ったら進藤くんは『佐倉さんはほんと臆病だなぁ』って言うのだろうか。
私は臆病を言い訳に、話しかけてくれるのを待っているだけなのかもしれない。
でも、戻ってしまった関係に、自分からは何も出来ずにいた。
そのうち、こんな気持ちもなくなるだろうと思っていた――。
「葉月、今日一緒に帰ろ」
放課後、珍しく裕子に誘われた。いつも幸人先輩と帰っているのに。
「幸人先輩はいいの?」
「いいの。今日は葉月と帰りたい気分だから」
そんな気分になることがあるんだ! と嬉しく思いながら、鞄に筆箱とノートを入れ、荷物の準備をする。
一緒に学校を出て歩いていると、裕子がファミレスの前で足を止めた。
「ファミレス入ろう」
「ファミレス? 裕子お腹すいたの?」
「違うよ。やっぱりゆっくり座って話そうと思って」
中に入ると四人掛けテーブルに向かい合って座り、すぐにドリンクバーを注文する。
私はオレンジジュース、裕子はメロンソーダを注いできてまた席についた。
ストローでジュースを飲みながら、視線を裕子に向ける。
「ところで今日はどうしたの?」
「んー? 葉月がなんか話たいことないかなぁと思って」
「私が?」
「元気なんだけど、空元気というか、なんか最近抜けてるというか?」
テーブルの上で手を組み、にこりと笑いかけてくる。
すごく、話を聞く体勢になってるな。こういう時の裕子は私が何か悩んでると確信している時だ。
よく見てくれていて、気にかけてくれていることにありがたく思いながらも、なんと話をしようか迷っていた。
「大崎のこと引きずってる?」
「引きずってはないと思うんだよね。もう少し上手くできたかもしれないっていう後悔はあるけど……」
「まあ、恋愛って難しいよね。私だって、何度も幸人に振られて、何度も泣いたから」
「裕子は本当にすごいよね。それでも諦めずに幸人先輩に気持ちを伝え続けたんだもん。私は、そこまでできるほど、好きじゃなかったのかも」
私がもし、みお先輩とは関わらないでって泣いてすがったら、大崎くんに別れを告げなかったら、きっと今も彼女としてそばにいただろう。
でも、そこまでする気にはなれなかった。その程度の気持ちだったのかもしれない。
「大崎ってさ、もう新しい彼女いるの? 幸人と同じクラスの人がなんかそんなこと言ってたって」
新しい彼女? みお先輩のことだろうか。大崎くんとはそんな話はしていないから二人が今どうなっているのかはわからない。でも、みお先輩がそう言っていたのだとしたらそうなんだろう。
裕子には別れたことは言ったけど、理由までは言わなかった。
私と別れてすぐに新しい彼女ができたなんて薄情だって思っただろうか。でも、弁解する義理はないよね。
「たぶん、そうなんだと思う。はっきりとは知らないけど」
「そっかー、本当なんだ。葉月はそれで落ち込んでるわけじゃないの?」
「うん、それは意外と大丈夫」
裕子は幸人先輩からその話を聞いて心配してくれたんだろう。
だから今日誘ってくれたんだ。でも、言ったように意外と大丈夫なんだよね。そのうち大崎くんとみお先輩が付き合うことはなんとなくわかっていた。
それに今、大崎くんとは友達として穏やかな関係でいられているからか、あまりショックではなかった。
「じゃあ、どうして元気ないの?」
「なんか、寂しいんだよね」
「寂しい?」
「前の環境に戻っただけなのに、なんかこう、心は順応できないというか、前と同じではいられないというか……寂しい……感じ?」
裕子は頬杖をつき、ストローで氷をカラカラと混ぜながら、「うーん」と言い何かを考えている。
自分でも上手く言い表せないことを、真剣に考えてくれる。
「一見戻ったように思えても、完全に戻ることってないと思うんだよね。元々持っていないのと、持っていたものを失くすのでは全然違うでしょ。あったものが無くなったとき、そこに隙間ができると、寂しくなるものなんじゃない?」
隙間……。私の心は今、隙間だらけなのかも。
元に戻ると思っていた。でも、ここにあったものは、居場所だけを残してなくなった。
空いてしまったこの場所は、他のものでうめることはできるのだろうか。
『必要なものばかりを並べていても、絶対に隙間はできるよ。その隙間を埋めてくれるのが無駄なものだと思うけどね』
進藤くんが言っていた言葉。
あれから、わかったことがある。
無駄なものが隙間を埋めてくれる。そして、無駄だと思っていたものが、なくてはならないものになっていく。気づけば、欠かすことのできない、かけがえのないものになっている。
それがなくなったとき、別のもので埋めても同じように心は満たされるのだろうか。
「なんか、楽しいことないかなぁ」
「どうした急に」
「隙間を埋めてくれる楽しいことないかなぁって」
「もうすぐ冬休みだし、いっぱい遊ぼうよ」
「幸人先輩と遊ばないの?」
「さすがにもう、受験直前で遊べないよ」
そっか、もう受験か。三年生は大変だな。
なんて思っている間に私たちもすぐ三年生になるんだろうな。
それで、進路のことで頭がいっぱいになって、勉強に追われて今の悩みなんて忘れてしまうのかな。
「裕子、今のうちにいっぱい遊ぼう! 楽しいこといっぱいしよう!」
「なんかテンション高いね」
「これって、現実逃避なのかな?」
「まあ、いいんじゃない」
このあと私たちはパフェを食べながら、冬休みの予定を立てた。
クリスマスパーティーをして、初詣に行って、一緒にショッピングモールで買い物をして、美味しいものを食べる。
想像するだけですごく楽しい。こんなにも楽しいことがたくさん待っているんだ。裕子のおかげでそう思えた。
きっとこれからも、上手くいかないことはたくさんある。
恋愛なんて、相手がいてはじめて始まるものなんだからなおさら。
始まりも終わりも自分で決められるものじゃない。上手くいかなくて当たり前だ。
それでも、楽しいことや苦しいことを繰り返しながら、少しずつ経験値というものが上がっていくのかもしれない。
私にとっての初めての恋は、奇妙な三角関係から始まった難易度の高い恋だった。
そして驚いたことがある。嬉しい驚きだ。
それは、大崎くんと進藤くんがまた一緒にいるようになったこと。
以前のようにとはいかないけれど、ぎこちないながらも友達としての関係を築きつつあるみたい。
きっと、二人でたくさん話をしたのだろう。
進藤くんが吹っ切れた上で関わっているのかはわからない。
でも、もうそれは関係ない。これからも二人はきっと友達として一緒にいるだろうから。
全てが、付き合う前の関係に戻りつつある。そう、全てが。
進藤くんとはあれから特別話しをしていない。
大崎くんから、別れたことは聞いているかもしれない。
だからといって、何か言われることもなければ私から報告することもなかった。
告白される前の、友達ですらないただのクラスメイトの関係に戻っていた。
よく考えれば、進藤くんが私に声をかけてきたのは大崎くんと付き合って、それを教えて欲しいからだった。
別れてしまった今、私たちが関わる理由はないのかもしれない。
大崎くんと一緒にいる進藤くんに、私を見ない進藤くんに、私はもう必要ないように思えた。
すごく、寂しい。思っていた以上に。
私から話しかければいいのかもしれないけど、話しかける理由がないからできなかった。
こんなこと言ったら進藤くんは『佐倉さんはほんと臆病だなぁ』って言うのだろうか。
私は臆病を言い訳に、話しかけてくれるのを待っているだけなのかもしれない。
でも、戻ってしまった関係に、自分からは何も出来ずにいた。
そのうち、こんな気持ちもなくなるだろうと思っていた――。
「葉月、今日一緒に帰ろ」
放課後、珍しく裕子に誘われた。いつも幸人先輩と帰っているのに。
「幸人先輩はいいの?」
「いいの。今日は葉月と帰りたい気分だから」
そんな気分になることがあるんだ! と嬉しく思いながら、鞄に筆箱とノートを入れ、荷物の準備をする。
一緒に学校を出て歩いていると、裕子がファミレスの前で足を止めた。
「ファミレス入ろう」
「ファミレス? 裕子お腹すいたの?」
「違うよ。やっぱりゆっくり座って話そうと思って」
中に入ると四人掛けテーブルに向かい合って座り、すぐにドリンクバーを注文する。
私はオレンジジュース、裕子はメロンソーダを注いできてまた席についた。
ストローでジュースを飲みながら、視線を裕子に向ける。
「ところで今日はどうしたの?」
「んー? 葉月がなんか話たいことないかなぁと思って」
「私が?」
「元気なんだけど、空元気というか、なんか最近抜けてるというか?」
テーブルの上で手を組み、にこりと笑いかけてくる。
すごく、話を聞く体勢になってるな。こういう時の裕子は私が何か悩んでると確信している時だ。
よく見てくれていて、気にかけてくれていることにありがたく思いながらも、なんと話をしようか迷っていた。
「大崎のこと引きずってる?」
「引きずってはないと思うんだよね。もう少し上手くできたかもしれないっていう後悔はあるけど……」
「まあ、恋愛って難しいよね。私だって、何度も幸人に振られて、何度も泣いたから」
「裕子は本当にすごいよね。それでも諦めずに幸人先輩に気持ちを伝え続けたんだもん。私は、そこまでできるほど、好きじゃなかったのかも」
私がもし、みお先輩とは関わらないでって泣いてすがったら、大崎くんに別れを告げなかったら、きっと今も彼女としてそばにいただろう。
でも、そこまでする気にはなれなかった。その程度の気持ちだったのかもしれない。
「大崎ってさ、もう新しい彼女いるの? 幸人と同じクラスの人がなんかそんなこと言ってたって」
新しい彼女? みお先輩のことだろうか。大崎くんとはそんな話はしていないから二人が今どうなっているのかはわからない。でも、みお先輩がそう言っていたのだとしたらそうなんだろう。
裕子には別れたことは言ったけど、理由までは言わなかった。
私と別れてすぐに新しい彼女ができたなんて薄情だって思っただろうか。でも、弁解する義理はないよね。
「たぶん、そうなんだと思う。はっきりとは知らないけど」
「そっかー、本当なんだ。葉月はそれで落ち込んでるわけじゃないの?」
「うん、それは意外と大丈夫」
裕子は幸人先輩からその話を聞いて心配してくれたんだろう。
だから今日誘ってくれたんだ。でも、言ったように意外と大丈夫なんだよね。そのうち大崎くんとみお先輩が付き合うことはなんとなくわかっていた。
それに今、大崎くんとは友達として穏やかな関係でいられているからか、あまりショックではなかった。
「じゃあ、どうして元気ないの?」
「なんか、寂しいんだよね」
「寂しい?」
「前の環境に戻っただけなのに、なんかこう、心は順応できないというか、前と同じではいられないというか……寂しい……感じ?」
裕子は頬杖をつき、ストローで氷をカラカラと混ぜながら、「うーん」と言い何かを考えている。
自分でも上手く言い表せないことを、真剣に考えてくれる。
「一見戻ったように思えても、完全に戻ることってないと思うんだよね。元々持っていないのと、持っていたものを失くすのでは全然違うでしょ。あったものが無くなったとき、そこに隙間ができると、寂しくなるものなんじゃない?」
隙間……。私の心は今、隙間だらけなのかも。
元に戻ると思っていた。でも、ここにあったものは、居場所だけを残してなくなった。
空いてしまったこの場所は、他のものでうめることはできるのだろうか。
『必要なものばかりを並べていても、絶対に隙間はできるよ。その隙間を埋めてくれるのが無駄なものだと思うけどね』
進藤くんが言っていた言葉。
あれから、わかったことがある。
無駄なものが隙間を埋めてくれる。そして、無駄だと思っていたものが、なくてはならないものになっていく。気づけば、欠かすことのできない、かけがえのないものになっている。
それがなくなったとき、別のもので埋めても同じように心は満たされるのだろうか。
「なんか、楽しいことないかなぁ」
「どうした急に」
「隙間を埋めてくれる楽しいことないかなぁって」
「もうすぐ冬休みだし、いっぱい遊ぼうよ」
「幸人先輩と遊ばないの?」
「さすがにもう、受験直前で遊べないよ」
そっか、もう受験か。三年生は大変だな。
なんて思っている間に私たちもすぐ三年生になるんだろうな。
それで、進路のことで頭がいっぱいになって、勉強に追われて今の悩みなんて忘れてしまうのかな。
「裕子、今のうちにいっぱい遊ぼう! 楽しいこといっぱいしよう!」
「なんかテンション高いね」
「これって、現実逃避なのかな?」
「まあ、いいんじゃない」
このあと私たちはパフェを食べながら、冬休みの予定を立てた。
クリスマスパーティーをして、初詣に行って、一緒にショッピングモールで買い物をして、美味しいものを食べる。
想像するだけですごく楽しい。こんなにも楽しいことがたくさん待っているんだ。裕子のおかげでそう思えた。
きっとこれからも、上手くいかないことはたくさんある。
恋愛なんて、相手がいてはじめて始まるものなんだからなおさら。
始まりも終わりも自分で決められるものじゃない。上手くいかなくて当たり前だ。
それでも、楽しいことや苦しいことを繰り返しながら、少しずつ経験値というものが上がっていくのかもしれない。
私にとっての初めての恋は、奇妙な三角関係から始まった難易度の高い恋だった。