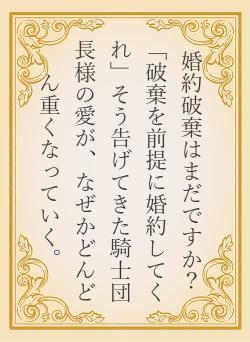「なんか、いい返事だね」
「進藤くん……」
ふいに名前を呼ばれてドキッとしたけれど、進藤くんの顔を見るとなぜか安心した。
こうやって、待ち伏せされるのも、顔を合わせて話すのも久しぶりだ。
「この感じ、すごく懐かしい気がする」
「そんなに経ってないでしょ」
「そうかな? それより、どうしたの?」
私たちは話をしながら並んで歩き出す。進藤くんは私の顔を窺うようにじっと見る。
「佐倉さん今日ずっとそわそわしてたし、なかなか帰ろうとしないしちょっと心配だったんだよね」
「私、そんな心配されるほど挙動不審だった?!」
「僕が気になるくらいにはね」
「そうなんだ……」
今日、大崎くんと話そうと決めてずっとそのことばかり考えていたから、自分では気づかないうちに挙動にでてたのかも。
それにしても進藤くんはよく見てるよな。
「さっきも、異様に暗い表情で歩いてたし、なにかあったよね?」
進藤くんは確信めいたように聞いてくる。
なにかあったわけではない。見てしまっただけだ。
そう、私はなにもしていない。なにも出来なかった。ちゃんと話をしようと思ったのに、声をかけることさえできなかった。でも、あんな二人を見て、声をかけられるはずもない。
だから、なにもなかった。
「なにもないよ」
「噓だね」
「え……?」
「なにもないはずないでしょ。なにもなかったとして、どうしてそんな暗い顔してるの? いろいろあったけど、気にならないくらいには今日まで普通だったよ」
進藤くんって、私のことよく見てくれてるんだな。気にかけてくれてるんだ。
しばらくこうやって話すことがなかったけど、それでも私たちの関係は変わらないんだと思えた。
心配してくれて、声をかけてくれた進藤くんに、甘えてもいいかな。
「今日、大崎くんと話をしようと思って部活が終わるの待ってたんだよね。そしたら……」
「あの先輩といるところを見た?」
「知ってるの?」
「どういう理由かは知らないけど、僕も二人が一緒にいるところ何度か見たから」
やっぱり、大崎くんとみお先輩が一緒にいたのは今日だけじゃないんだ。
私、なにも知らなかった。大崎くんは今、私とのことを考えてくれているのだと思っていた。
そうじゃないのかもしれない。でも、じゃあなんで私になにも言ってくれないのだろう。
先輩のほうがいいなら、そう言ってくれたらいいのに。
ちゃんと、別れようって言ってくれたらいいのに。
いや、もしかすると先輩とはただ仲良くしているだけで、そういう関係ではないのかな?
まだ、私のことを好きでいてくれてるのかな?
いや違う。そんな都合いいことあるわけない。都合の、いいこと?
これって、私と別れないまま先輩と仲良くして、都合よく扱われているのは私のほうなのかな?
ああもうなにこれ。なにこれ。こんな醜い感情知らない。ドロドロしたものが押し寄せてきて怖い。怖い――
「――さん、佐倉さん!」
はっ――
「ごめん、余計なこと言ったかも」
「ううん。そんなことないよ」
遅かれ早かれわかることだ。むしろ今日まで気づかなかった私が鈍いし。
もっと早くに私が行動してたら、なにか変わっていたのかな。
「二人のことに口出しするべきではないけど、ちゃんと大崎と話すのがいいかもね。僕が言えた立場じゃないけど」
私のことばかり気にしてくれている。つらい思いをしているのは同じなのに。
「進藤くんは、このままでいいの?」
「僕はいいんだ。もう吹っ切るしかないから。失恋するってこういうことだよ」
「でも、大崎くんとは友達だったのに……」
「それは、どうにもならないから。仕方ないよ」
本当に、どうにもならないのだろうか。
あのとき、大崎くんはどんな気持ちで“無理”と言ったのだろう。
思いに応えることができないのは、そうなのかもしれない。
でも、友達として関わっていくことさえ無理なのだろうか。
そんなに簡単に変わってしまう関係だったのかな。
だったら、私との関係なんてすぐに壊れてしまっても仕方ない。
「佐倉さん、また良くないこと考えてるでしょ」
「進藤くん、私どうしたらいいのかわからないんだよね」
「それは、みんな同じだよ。大崎だって、今自分がしてることわかってないのかもしれない」
「そうなのかな?」
「周りが見えなくなることってあると思うんだよね。だから、ちゃんと話した方がいい。勇気がいるかもしれないけど」
聞くのが怖い。でも、ずっとこのままでいるのだってよくない。
本当はどこかでわかっているのかもしれない。話をすればもう終わってしまうこと。
それでも、前に進むためには、はっきりさせなければ。
「進藤くん、私頑張る!」
「それはいいけど、変に張り切りすぎないでよ」
進藤くんはフッと笑う。
久しぶりのその表情に、もっと早く進藤くんと話をすればよかったと少し後悔した。
別に私たちは喧嘩したわけではなかったのに、なんとなく話す機会を見失っていた。
なにもかも、悪いほうに考えてしまっていたけど、そうじゃない。
進藤くんの笑った顔を見て、そう思った。
「僕、佐倉さんがいてくれてよかったと思ってるよ」
「え、なに突然?! どういう意味?」
「そのままの意味だよ」
それなら、私だってそうだ。
今日、こんな気持ちのまま一人で帰っていたら、もっと落ち込んでもっとモヤモヤしていただろう。進藤くんが私のことを気にかけてくれて、話を聞いてくれたから、少し楽になった。やっぱりちゃんと大崎くんと話をしようと思えた。
全部、進藤くんのおかげだ。私はなにもしてあげられてないけど、同じように思ってくれてるのかな。
――その日の夜、珍しく大崎くんからメッセージがきた。
『明日、部活が休みだから遊びに行かない?』
なんの変哲もないメッセージだけれど、今の私たちにとっては不自然な内容だ。
普通に付き合っていたころでさえ、二人で休日にデートをしたことなんてなかった。
誘われたことがなかった。
遊びに行くっていうのは会う口実で、話をするのかな?
私も話したいことがある。聞きたいことがたくさんある。
明日、ちゃんと自分の気持ちを伝えよう。
私は承諾の返事をして、眠りについた。
「進藤くん……」
ふいに名前を呼ばれてドキッとしたけれど、進藤くんの顔を見るとなぜか安心した。
こうやって、待ち伏せされるのも、顔を合わせて話すのも久しぶりだ。
「この感じ、すごく懐かしい気がする」
「そんなに経ってないでしょ」
「そうかな? それより、どうしたの?」
私たちは話をしながら並んで歩き出す。進藤くんは私の顔を窺うようにじっと見る。
「佐倉さん今日ずっとそわそわしてたし、なかなか帰ろうとしないしちょっと心配だったんだよね」
「私、そんな心配されるほど挙動不審だった?!」
「僕が気になるくらいにはね」
「そうなんだ……」
今日、大崎くんと話そうと決めてずっとそのことばかり考えていたから、自分では気づかないうちに挙動にでてたのかも。
それにしても進藤くんはよく見てるよな。
「さっきも、異様に暗い表情で歩いてたし、なにかあったよね?」
進藤くんは確信めいたように聞いてくる。
なにかあったわけではない。見てしまっただけだ。
そう、私はなにもしていない。なにも出来なかった。ちゃんと話をしようと思ったのに、声をかけることさえできなかった。でも、あんな二人を見て、声をかけられるはずもない。
だから、なにもなかった。
「なにもないよ」
「噓だね」
「え……?」
「なにもないはずないでしょ。なにもなかったとして、どうしてそんな暗い顔してるの? いろいろあったけど、気にならないくらいには今日まで普通だったよ」
進藤くんって、私のことよく見てくれてるんだな。気にかけてくれてるんだ。
しばらくこうやって話すことがなかったけど、それでも私たちの関係は変わらないんだと思えた。
心配してくれて、声をかけてくれた進藤くんに、甘えてもいいかな。
「今日、大崎くんと話をしようと思って部活が終わるの待ってたんだよね。そしたら……」
「あの先輩といるところを見た?」
「知ってるの?」
「どういう理由かは知らないけど、僕も二人が一緒にいるところ何度か見たから」
やっぱり、大崎くんとみお先輩が一緒にいたのは今日だけじゃないんだ。
私、なにも知らなかった。大崎くんは今、私とのことを考えてくれているのだと思っていた。
そうじゃないのかもしれない。でも、じゃあなんで私になにも言ってくれないのだろう。
先輩のほうがいいなら、そう言ってくれたらいいのに。
ちゃんと、別れようって言ってくれたらいいのに。
いや、もしかすると先輩とはただ仲良くしているだけで、そういう関係ではないのかな?
まだ、私のことを好きでいてくれてるのかな?
いや違う。そんな都合いいことあるわけない。都合の、いいこと?
これって、私と別れないまま先輩と仲良くして、都合よく扱われているのは私のほうなのかな?
ああもうなにこれ。なにこれ。こんな醜い感情知らない。ドロドロしたものが押し寄せてきて怖い。怖い――
「――さん、佐倉さん!」
はっ――
「ごめん、余計なこと言ったかも」
「ううん。そんなことないよ」
遅かれ早かれわかることだ。むしろ今日まで気づかなかった私が鈍いし。
もっと早くに私が行動してたら、なにか変わっていたのかな。
「二人のことに口出しするべきではないけど、ちゃんと大崎と話すのがいいかもね。僕が言えた立場じゃないけど」
私のことばかり気にしてくれている。つらい思いをしているのは同じなのに。
「進藤くんは、このままでいいの?」
「僕はいいんだ。もう吹っ切るしかないから。失恋するってこういうことだよ」
「でも、大崎くんとは友達だったのに……」
「それは、どうにもならないから。仕方ないよ」
本当に、どうにもならないのだろうか。
あのとき、大崎くんはどんな気持ちで“無理”と言ったのだろう。
思いに応えることができないのは、そうなのかもしれない。
でも、友達として関わっていくことさえ無理なのだろうか。
そんなに簡単に変わってしまう関係だったのかな。
だったら、私との関係なんてすぐに壊れてしまっても仕方ない。
「佐倉さん、また良くないこと考えてるでしょ」
「進藤くん、私どうしたらいいのかわからないんだよね」
「それは、みんな同じだよ。大崎だって、今自分がしてることわかってないのかもしれない」
「そうなのかな?」
「周りが見えなくなることってあると思うんだよね。だから、ちゃんと話した方がいい。勇気がいるかもしれないけど」
聞くのが怖い。でも、ずっとこのままでいるのだってよくない。
本当はどこかでわかっているのかもしれない。話をすればもう終わってしまうこと。
それでも、前に進むためには、はっきりさせなければ。
「進藤くん、私頑張る!」
「それはいいけど、変に張り切りすぎないでよ」
進藤くんはフッと笑う。
久しぶりのその表情に、もっと早く進藤くんと話をすればよかったと少し後悔した。
別に私たちは喧嘩したわけではなかったのに、なんとなく話す機会を見失っていた。
なにもかも、悪いほうに考えてしまっていたけど、そうじゃない。
進藤くんの笑った顔を見て、そう思った。
「僕、佐倉さんがいてくれてよかったと思ってるよ」
「え、なに突然?! どういう意味?」
「そのままの意味だよ」
それなら、私だってそうだ。
今日、こんな気持ちのまま一人で帰っていたら、もっと落ち込んでもっとモヤモヤしていただろう。進藤くんが私のことを気にかけてくれて、話を聞いてくれたから、少し楽になった。やっぱりちゃんと大崎くんと話をしようと思えた。
全部、進藤くんのおかげだ。私はなにもしてあげられてないけど、同じように思ってくれてるのかな。
――その日の夜、珍しく大崎くんからメッセージがきた。
『明日、部活が休みだから遊びに行かない?』
なんの変哲もないメッセージだけれど、今の私たちにとっては不自然な内容だ。
普通に付き合っていたころでさえ、二人で休日にデートをしたことなんてなかった。
誘われたことがなかった。
遊びに行くっていうのは会う口実で、話をするのかな?
私も話したいことがある。聞きたいことがたくさんある。
明日、ちゃんと自分の気持ちを伝えよう。
私は承諾の返事をして、眠りについた。