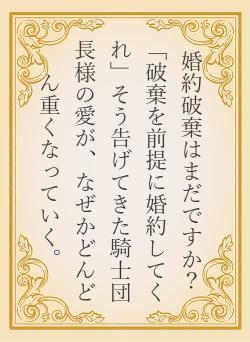なんの予定もない休日、私はふらっと本屋へ行くことにした。
予定がないと言っても、今日は私にとって特別な日。
目的の本があるわけではないけれど、なんとなく目についた本がすごく面白かったりする。その一期一会が楽しい。
今日も何かいい出会いがあればなと思っていた。
家の近くの本屋ではなく、街にある大きな店舗へ行くことにした。
少し歩くけれど、いい散歩にもなる。住宅街を抜け、大通りに出る。たくさんのお店が立ち並んでいて、休日ということもあり、人で賑わっている。
しばらく歩くと本屋が見えてきた。
中に入ろうとしたとき、少し先に見慣れた二人の姿を見つけた。
進藤くんと大崎くんだ。
私服姿の二人は楽しそうに並んで歩いている。そして、スポーツ用品店へと入っていった。
休みの日に二人で出かけたりするんだ。仲いいなぁ。
進藤くん、私にずるいなんて言ってたけど、しっかりデートしてるじゃん。
ん? デート? あれはデートなの? いやいや二人は友達だし、ただのお出かけだよね。まあ、長い付き合いだしそれくらいするか。
大崎くん、夏の大会が終わって部活も少し落ち着いたって言ってたし、私も誘えばよかったかな。
そういえば私、大崎くんと休みの日にデートしたことない。彼女なのに。今度私も誘ってみよう。
それにしても、二人ともなんかかっこよかった。
デニムと白Tシャツにキャップを被った大崎くん。シンプルな服装だけど、背が高くて体格がいいからよく似合っている。
進藤くんは黒いスキニーパンツに大きめなドルマンニットを着ていた。
タイプの違う二人だけど、それがなんだかさまになっていた。
二人のことがすごく気になる。気になるけど、我慢しよう。私は本屋へと入った。
まず、適当に新刊コーナーを見て回る。
興味を引かれるものは……特にない。それよりも進藤くんと大崎くんのことが気になって仕方がない。
その後も、店内を一通り見て回ったが、読みたいと思う本には出会わなかった。
今日はそわそわして落ち着かないからもう帰ろう、そう思って本屋を出たとき、ちょうど二人もスポーツ用品店から出てきたところだった。
え! こんなタイミングよく出てくることある?! 考えないようにしようと思ってたのに!
大崎くんはなにやら大きな袋を持ち、嬉しそうにしている。何買ったんだろう。
進藤くんはそんな大崎くんを満足気に見上げ、二人で仲良く歩いていく。
いまからどこに行くんだろう。
もう帰るのかな?
あ、進藤くんが綺麗なお姉さんに声かけられてる。無視してるけど。
大崎くんが何か言って、お姉さんは戻っていった。
お姉さんがいなくなると進藤くんは嬉しそうな顔を大崎くんに向ける。
なにあれ。まるでナンパさた彼女を助けた彼氏みたいになってる。
かっこよく助けた彼氏に惚れ直す彼女みたいな。
彼女は私だよね?! 進藤くんが彼女みたいになってるよ!
無意識に二人の後を付いていっていた。
街の大通りを抜けて裏通りに入る。通ったことのない道だ。
私、こんな尾行みたいなことをして何やってるんだろうと思いはしたけど、今さら引き返すことはできなかった。
そして二人が足を止めたのは、ブランコとバスケットゴールだけがある小さな公園だった。
大崎くんは持っていたスポーツ用品店の袋から、正方形の箱を取り出す。側面だけ露わになり見えていたのは、バスケットボールだった。
箱から出し、手のひらでボールの質感を確かめたあと、ドリブルを始める。
進藤くんはベンチに座って見ていた。
私も木陰に隠れてこっそり見る。
コンクリートの上で、ダンッダンッという音が響く。
ゴールから少し離れたところで立ち止まり、ボールを包み込むように構える。足は肩幅に開かれ、膝が曲がる。ボールが大崎くんの手から離れると、シュパッと音をたてゴールに吸い込まれていった。
すごい。綺麗なシュートだ。
「おー。めっちゃいいわ! ありがとな蓮」
「ううん。誕生日プレゼント遅くなってごめんね」
「俺が時間なくてなかなか買いにこれなかっただけだし」
「僕が勝手に選んでもよかったけど、やっぱり大崎が決めたほうがいいと思って」
あのバスケットボールは進藤くんからの誕生日プレゼントなんだ。
それで、二人で買いに出かけてたんだな。
大崎くんは何度かシュートを繰り返したあと、進藤くんの横に座った。
「ふぅ。これで自主練もはかどるよ」
「そういえばさ、大崎ってなんで佐倉さんのこと好きになったの? きっかけとかあるの?」
えー! 進藤くん急に何聞いてるの? 今そんな恋バナみたいなことする?!
でも私も好きだって言われただけでどうして好きになったかとか、私のどこが好きかとか聞いたことないな。
好きって言われたのも、告白されたときだけであれからは言われてない。
まあ、改めて言われても反応に困ったかもしれないけど。
「佐倉さんってさ、字が綺麗なんだよね」
「はあ。それだけ?」
「ち、ちがう! 料理も上手だし、髪の毛さらさらで、小さくて可愛いし、女の子らしいというか」
「ふーん」
「なんだよふーんて。聞いといてそれだけかよ!」
「ちょっと思ってたのと違うなと思って」
私も、思ってたのとなんか違った。何か、劇的なエピソードがあったわけではないのは私自身よくわかっている。二年生になって初めて顔を合わせて、隣の席でよく話すようになった。それくらいだ。でも、大崎くんにとって私の存在がなにか大きく気持ちを動かした、くらいのきっかけがあるのかと思っていたのに。好きだと思える何か大きなきっかけが。
大崎くんが言ったことは全部表面上の私だ。だって、字が綺麗で、料理ができて髪の毛がさらさらの可愛い女の子なんて私以外にもいっぱいいるだろう。
私じゃないとだめな理由はない。
これは、私の考えがおこがましいのかな? 気持ちを動かすエピソード、なんて物語の読み過ぎ?
そもそも私だって、好きだと気づいたきっかけは先輩に対する嫉妬だったじゃないか。
醜い独占欲と劣等感が湧いたことで、大崎くんのことが好きなんだと気づいた。
それも、進藤くんに言われなければ気づかなかったかもしれない。
好きじゃないけど付き合ってみる、なんて言った私がこんなこと考えるなんて都合良すぎるよね。
あ……私、まだ大崎くんに好きだって伝えてないや。
もう帰ろう。盗み聞きなんてするもんじゃないな。
なんだか、またモヤモヤが増えてしまった。
このモヤモヤが恋なんだとしたら、恋ってものすごく困難な試練を与えられているようなものだ。
だって、人の気持ちほど自分でどうにかできないものはないんだから。
私はとぼとぼ家までの道を歩いていった――と思っていたが、見覚えのない道に出てしまった。
さっきはただ付いていっただけだから、あまり道を覚えていなかった。
鞄からスマホを取り出し、位置情報を確認する。
うわ、反対方向にきてるんだ。私はスマホを見ながら歩きだす。
真っ直ぐに進み、小さな交差点を曲がったとき――
「佐倉さん」
「っうわぁ!」
「うるさいよ。今度はちゃんと声かけたのに」
「進藤くん……なんで」
すごく呆れた顔をした進藤くんがいた。大崎くんはいない。
もう帰ったのだろうか。
「ストーカーは楽しかった?」
「ス、ストーカー?!」
「気づかれてないと思ったの?」
「いつから気づいてたの?」
「佐倉さんが本屋から出てきたところ。なんかついてきてるなと思って」
「えぇ」
本屋って、はじめから気づいてたってことじゃない。
え、待って大崎くんも気づいてたの?
「あ、大崎は気づいてないから安心してよ」
「そう、なんだ」
よかった。まあ、私が聞いてるのわかってて、あんな話しないよね。
少しだけ安心していると、進藤くんが私の腕を掴む。
「じゃあ、今から僕に付き合ってね」
「え?!」
進藤くんは私の腕を掴んだままスタスタと街のほうへと歩いていく。
私はよくわからないまま付いていった。
予定がないと言っても、今日は私にとって特別な日。
目的の本があるわけではないけれど、なんとなく目についた本がすごく面白かったりする。その一期一会が楽しい。
今日も何かいい出会いがあればなと思っていた。
家の近くの本屋ではなく、街にある大きな店舗へ行くことにした。
少し歩くけれど、いい散歩にもなる。住宅街を抜け、大通りに出る。たくさんのお店が立ち並んでいて、休日ということもあり、人で賑わっている。
しばらく歩くと本屋が見えてきた。
中に入ろうとしたとき、少し先に見慣れた二人の姿を見つけた。
進藤くんと大崎くんだ。
私服姿の二人は楽しそうに並んで歩いている。そして、スポーツ用品店へと入っていった。
休みの日に二人で出かけたりするんだ。仲いいなぁ。
進藤くん、私にずるいなんて言ってたけど、しっかりデートしてるじゃん。
ん? デート? あれはデートなの? いやいや二人は友達だし、ただのお出かけだよね。まあ、長い付き合いだしそれくらいするか。
大崎くん、夏の大会が終わって部活も少し落ち着いたって言ってたし、私も誘えばよかったかな。
そういえば私、大崎くんと休みの日にデートしたことない。彼女なのに。今度私も誘ってみよう。
それにしても、二人ともなんかかっこよかった。
デニムと白Tシャツにキャップを被った大崎くん。シンプルな服装だけど、背が高くて体格がいいからよく似合っている。
進藤くんは黒いスキニーパンツに大きめなドルマンニットを着ていた。
タイプの違う二人だけど、それがなんだかさまになっていた。
二人のことがすごく気になる。気になるけど、我慢しよう。私は本屋へと入った。
まず、適当に新刊コーナーを見て回る。
興味を引かれるものは……特にない。それよりも進藤くんと大崎くんのことが気になって仕方がない。
その後も、店内を一通り見て回ったが、読みたいと思う本には出会わなかった。
今日はそわそわして落ち着かないからもう帰ろう、そう思って本屋を出たとき、ちょうど二人もスポーツ用品店から出てきたところだった。
え! こんなタイミングよく出てくることある?! 考えないようにしようと思ってたのに!
大崎くんはなにやら大きな袋を持ち、嬉しそうにしている。何買ったんだろう。
進藤くんはそんな大崎くんを満足気に見上げ、二人で仲良く歩いていく。
いまからどこに行くんだろう。
もう帰るのかな?
あ、進藤くんが綺麗なお姉さんに声かけられてる。無視してるけど。
大崎くんが何か言って、お姉さんは戻っていった。
お姉さんがいなくなると進藤くんは嬉しそうな顔を大崎くんに向ける。
なにあれ。まるでナンパさた彼女を助けた彼氏みたいになってる。
かっこよく助けた彼氏に惚れ直す彼女みたいな。
彼女は私だよね?! 進藤くんが彼女みたいになってるよ!
無意識に二人の後を付いていっていた。
街の大通りを抜けて裏通りに入る。通ったことのない道だ。
私、こんな尾行みたいなことをして何やってるんだろうと思いはしたけど、今さら引き返すことはできなかった。
そして二人が足を止めたのは、ブランコとバスケットゴールだけがある小さな公園だった。
大崎くんは持っていたスポーツ用品店の袋から、正方形の箱を取り出す。側面だけ露わになり見えていたのは、バスケットボールだった。
箱から出し、手のひらでボールの質感を確かめたあと、ドリブルを始める。
進藤くんはベンチに座って見ていた。
私も木陰に隠れてこっそり見る。
コンクリートの上で、ダンッダンッという音が響く。
ゴールから少し離れたところで立ち止まり、ボールを包み込むように構える。足は肩幅に開かれ、膝が曲がる。ボールが大崎くんの手から離れると、シュパッと音をたてゴールに吸い込まれていった。
すごい。綺麗なシュートだ。
「おー。めっちゃいいわ! ありがとな蓮」
「ううん。誕生日プレゼント遅くなってごめんね」
「俺が時間なくてなかなか買いにこれなかっただけだし」
「僕が勝手に選んでもよかったけど、やっぱり大崎が決めたほうがいいと思って」
あのバスケットボールは進藤くんからの誕生日プレゼントなんだ。
それで、二人で買いに出かけてたんだな。
大崎くんは何度かシュートを繰り返したあと、進藤くんの横に座った。
「ふぅ。これで自主練もはかどるよ」
「そういえばさ、大崎ってなんで佐倉さんのこと好きになったの? きっかけとかあるの?」
えー! 進藤くん急に何聞いてるの? 今そんな恋バナみたいなことする?!
でも私も好きだって言われただけでどうして好きになったかとか、私のどこが好きかとか聞いたことないな。
好きって言われたのも、告白されたときだけであれからは言われてない。
まあ、改めて言われても反応に困ったかもしれないけど。
「佐倉さんってさ、字が綺麗なんだよね」
「はあ。それだけ?」
「ち、ちがう! 料理も上手だし、髪の毛さらさらで、小さくて可愛いし、女の子らしいというか」
「ふーん」
「なんだよふーんて。聞いといてそれだけかよ!」
「ちょっと思ってたのと違うなと思って」
私も、思ってたのとなんか違った。何か、劇的なエピソードがあったわけではないのは私自身よくわかっている。二年生になって初めて顔を合わせて、隣の席でよく話すようになった。それくらいだ。でも、大崎くんにとって私の存在がなにか大きく気持ちを動かした、くらいのきっかけがあるのかと思っていたのに。好きだと思える何か大きなきっかけが。
大崎くんが言ったことは全部表面上の私だ。だって、字が綺麗で、料理ができて髪の毛がさらさらの可愛い女の子なんて私以外にもいっぱいいるだろう。
私じゃないとだめな理由はない。
これは、私の考えがおこがましいのかな? 気持ちを動かすエピソード、なんて物語の読み過ぎ?
そもそも私だって、好きだと気づいたきっかけは先輩に対する嫉妬だったじゃないか。
醜い独占欲と劣等感が湧いたことで、大崎くんのことが好きなんだと気づいた。
それも、進藤くんに言われなければ気づかなかったかもしれない。
好きじゃないけど付き合ってみる、なんて言った私がこんなこと考えるなんて都合良すぎるよね。
あ……私、まだ大崎くんに好きだって伝えてないや。
もう帰ろう。盗み聞きなんてするもんじゃないな。
なんだか、またモヤモヤが増えてしまった。
このモヤモヤが恋なんだとしたら、恋ってものすごく困難な試練を与えられているようなものだ。
だって、人の気持ちほど自分でどうにかできないものはないんだから。
私はとぼとぼ家までの道を歩いていった――と思っていたが、見覚えのない道に出てしまった。
さっきはただ付いていっただけだから、あまり道を覚えていなかった。
鞄からスマホを取り出し、位置情報を確認する。
うわ、反対方向にきてるんだ。私はスマホを見ながら歩きだす。
真っ直ぐに進み、小さな交差点を曲がったとき――
「佐倉さん」
「っうわぁ!」
「うるさいよ。今度はちゃんと声かけたのに」
「進藤くん……なんで」
すごく呆れた顔をした進藤くんがいた。大崎くんはいない。
もう帰ったのだろうか。
「ストーカーは楽しかった?」
「ス、ストーカー?!」
「気づかれてないと思ったの?」
「いつから気づいてたの?」
「佐倉さんが本屋から出てきたところ。なんかついてきてるなと思って」
「えぇ」
本屋って、はじめから気づいてたってことじゃない。
え、待って大崎くんも気づいてたの?
「あ、大崎は気づいてないから安心してよ」
「そう、なんだ」
よかった。まあ、私が聞いてるのわかってて、あんな話しないよね。
少しだけ安心していると、進藤くんが私の腕を掴む。
「じゃあ、今から僕に付き合ってね」
「え?!」
進藤くんは私の腕を掴んだままスタスタと街のほうへと歩いていく。
私はよくわからないまま付いていった。