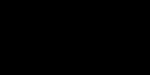悔しいけど、本当に美味しい。泣くくらい美味しいんだ。
「なあ、豊佳」
「はい。なんですか……?」
「本当は、泣くくらい好きだったのか?」
私はそう聞かれて、ついハンバーグを食べる手が止まった。
「え……?」
「ハンバーグが美味くて、泣いた訳じゃないんだろ。……そんなに好きだったのか、その男のこと」
真剣な眼差しで見つめられるから、烏丸さんから目が逸らせなくなった。
「それは……」
確かに龍樹のことが好きだった。ずっと一緒にいたいと、そう思っていた。
「なあ、そんなに好きだったのか?」
「……はい。 正直、好きでした」
龍樹と私は、今頃もしかしたら結婚の話を進めていたかもしれない。
「そうか。 泣くくらい好きだったのに、なんでフッたんだよ」
私はナイフとフォークをお皿の上に置くと「……彼に、セフレがいたんです」と話した。
「セフレ?……ってあのセフレか?」
「はい。そのセフレ……です」
烏丸さんは私の隣に移動してくると、「豊佳、セフレがいる男と付き合ってたのか?」と私に問いかけてくるから、私は「……はい」と答える。
「知らなかったんです、セフレがいるなんて。 しかも、私と付き合う前からその人とは関係があったんです。……信じられないですよね」
「なるほど、クズ男ってことね。……豊佳って、男見る目がないんだな」
そう言われると、その通りなので何も言い返せないのが悔しい。
「私の二年間……何だったんでしょうね」