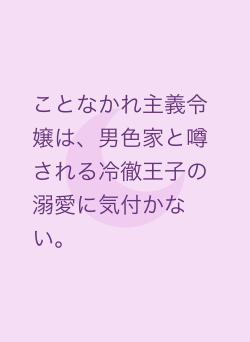「ずばり、私の匂いよ!」
「えっ、マニアック」
「いや違うから!」
マリッサの言葉に、私はすぐさまツッコミを入れた。
「なんでも私の肌には、人を魅了する花の香りがついているって旦那様に言われたの」
「へぇ、そうですか」
「反応が薄過ぎる」
なんでもないことのように受け流す彼女に、私はぱちぱちと瞬きを繰り返した。
「私も詳しくはありませんが、どうやら侍女達の間でもほとんど知られていないようです。あの花は摘み取った瞬間に枯れてしまい、加工品にすることも出来ない。遺香では効果がなく、そもそも証明のしようもありません。ヴァンドーム家の方々は、皆様美形ですから」
「確かに、誘香の必要なんてなさそうよね」
「それを抜きにしても、若旦那様が女性関係で相当なご苦労をなさったことは、屋敷の使用人からも聞きました」
だけどそうなると、私の推理が外れてしまう。旦那様が私を構うようになった原因は、これ以外に考えられないのに。
ジャラライラの香気にどんな効果があるのかは分からないけれど、私はまだ新参者でヴァンドームについては詳しくない。理由はどうあれ彼が今まで辛い思いをしてきたことは事実だし、あまり深く考えるのは止めておこう。
というか、屋敷に勤める侍女でさえ知らないことをマリッサが知っているのは、どうしてだろう。さすが冷静沈着な万能侍女だと、しみじみ感心してしまった。
「とにかく、旦那様は私の肌に香りがついていると勘違いなさっているのね。つまりは、刷り込みみたいな」
「なるほど。そうであればまだ納得が出来ます。あのふざけた手紙と結婚宣誓式での態度には、余憤を感じたままですから」
「あらら、マリッサはずっと怒っていたのね」
「当然です」
彼女の優しさに感動しつつ、この話はこれでお終い。
「この結婚に幸せを感じているのは、今のところ私だけなのよね。だから、私が旦那様の盾になれたら良いなって」
「フィリア様に幸せを与えているのはあの方ではなく、ブルーメルの環境では?」
「それも、結婚しなければ受けられなかった恩恵だもの」
パーティーは裸足で逃げ出すくらい苦手だけれど、誰かの為だと思えば頑張れる気がする。
「だから今日は、うんと可愛くしてね!」
「ご心配には及びません。フィリア様は、そのままでとてもお可愛らしいです」
「マ、マリッサ⁉︎」
「すみません、少々身内贔屓が過ぎました」
失礼なことを言われたような気がしないでもない。まぁ私と彼女の仲だし、事実なので仕方ない。
後のことは彼女のテクニックに任せて、私は今夜パーティーで振る舞われる夕食の献立に心を馳せたのだった。
「えっ、マニアック」
「いや違うから!」
マリッサの言葉に、私はすぐさまツッコミを入れた。
「なんでも私の肌には、人を魅了する花の香りがついているって旦那様に言われたの」
「へぇ、そうですか」
「反応が薄過ぎる」
なんでもないことのように受け流す彼女に、私はぱちぱちと瞬きを繰り返した。
「私も詳しくはありませんが、どうやら侍女達の間でもほとんど知られていないようです。あの花は摘み取った瞬間に枯れてしまい、加工品にすることも出来ない。遺香では効果がなく、そもそも証明のしようもありません。ヴァンドーム家の方々は、皆様美形ですから」
「確かに、誘香の必要なんてなさそうよね」
「それを抜きにしても、若旦那様が女性関係で相当なご苦労をなさったことは、屋敷の使用人からも聞きました」
だけどそうなると、私の推理が外れてしまう。旦那様が私を構うようになった原因は、これ以外に考えられないのに。
ジャラライラの香気にどんな効果があるのかは分からないけれど、私はまだ新参者でヴァンドームについては詳しくない。理由はどうあれ彼が今まで辛い思いをしてきたことは事実だし、あまり深く考えるのは止めておこう。
というか、屋敷に勤める侍女でさえ知らないことをマリッサが知っているのは、どうしてだろう。さすが冷静沈着な万能侍女だと、しみじみ感心してしまった。
「とにかく、旦那様は私の肌に香りがついていると勘違いなさっているのね。つまりは、刷り込みみたいな」
「なるほど。そうであればまだ納得が出来ます。あのふざけた手紙と結婚宣誓式での態度には、余憤を感じたままですから」
「あらら、マリッサはずっと怒っていたのね」
「当然です」
彼女の優しさに感動しつつ、この話はこれでお終い。
「この結婚に幸せを感じているのは、今のところ私だけなのよね。だから、私が旦那様の盾になれたら良いなって」
「フィリア様に幸せを与えているのはあの方ではなく、ブルーメルの環境では?」
「それも、結婚しなければ受けられなかった恩恵だもの」
パーティーは裸足で逃げ出すくらい苦手だけれど、誰かの為だと思えば頑張れる気がする。
「だから今日は、うんと可愛くしてね!」
「ご心配には及びません。フィリア様は、そのままでとてもお可愛らしいです」
「マ、マリッサ⁉︎」
「すみません、少々身内贔屓が過ぎました」
失礼なことを言われたような気がしないでもない。まぁ私と彼女の仲だし、事実なので仕方ない。
後のことは彼女のテクニックに任せて、私は今夜パーティーで振る舞われる夕食の献立に心を馳せたのだった。