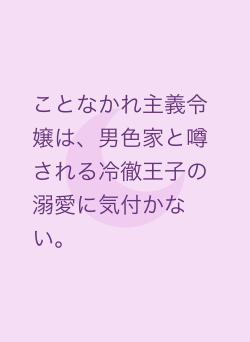不思議なことに、旦那様との王都までの旅は行きよりずっと楽だった。ヴァンドーム家の御者のスーパーなテクニックと、道を熟知している点での違いが大きかったのではと、旦那様はそう言っていた。
意外にも二人きりの空間は楽しくて、気まずくなることがほとんどなかった。それは屋敷にいる時もそうなのだけれど、旦那様は私と違ってとても聞き上手なのだ。
休憩の間も、宿泊の際も、常に気を遣ってくれる。何度も私の名前を呼んで、少しでも姿が見えなくなったら探しに来るし、夜に私の部屋をノックして「何か不便はないか」と尋ねられた時には、さすがに驚いた。
そんなこんなで無事王都に到着した私達は、揃ってヴァンドームのタウンハウスへと腰を下ろした。最初、私はマグシフォンの屋敷の方へ滞在するつもりだったのだけれど、なぜか旦那様に反対されたのだ。
「夫婦仲が悪いと思われてしまう」
「なるほど、分かりました」
その意見も最もだと思ったので、特に意見もしない。もともと私はどちらでも良くて、私がいると旦那様が長旅の疲れを癒せないのではと思ったから、提案しただけだったし。
結構な過密スケジュールの中、旦那様はさらに仕事があるといって早々に出かけてしまった。私はというと、ずらりと並んだメイド達に体をぴかぴかに磨いてもらった。旦那様からいただいたドレスを纏って、マリッサに仕上げてもらう。
「今日は落ち着いて見えるよう、髪はしっかりと上げましょう」
「ええ、私丸顔がコンプレックスなのに」
「フィリア様も見た目を気になさるお年頃になられたのですね。私は嬉しいです」
「嘘ですごめんなさい」
本当は、アップにすると引っ張られている感じがして落ち着かないからってだけの理由。彼女にはなんでもお見通しらしい。
私のオレンジ色の髪に櫛を通しながら、マリッサは「綺麗な色だ」と誉めてくれた。
「嫌いじゃないけど、目立つから嫌なのよね」
それに昔、どこぞの令嬢から「品がない」と言われたこともある。別に、それを気にしたことはない。むしろ私が悪口の対象になるほど周囲から認知されていたことに驚いて、少しだけ喜んでしまったような記憶もある。当然、その令嬢や周りにいた人たちからは引かれた。
「若旦那様って、過保護ですね」
「どうしてだと思う?からかわれている感じはしないけど」
「もともとの気質か、あるいは何かのきっかけとか」
彼女にそう言われて、私はふとあることを思い出した。
「そうか、それだわ。原因が分かった気がする」
逆に、どうして今まで忘れていたのだろう。こんなにも明確な答えが、目の前にぶら下がっていたというのに。
意外にも二人きりの空間は楽しくて、気まずくなることがほとんどなかった。それは屋敷にいる時もそうなのだけれど、旦那様は私と違ってとても聞き上手なのだ。
休憩の間も、宿泊の際も、常に気を遣ってくれる。何度も私の名前を呼んで、少しでも姿が見えなくなったら探しに来るし、夜に私の部屋をノックして「何か不便はないか」と尋ねられた時には、さすがに驚いた。
そんなこんなで無事王都に到着した私達は、揃ってヴァンドームのタウンハウスへと腰を下ろした。最初、私はマグシフォンの屋敷の方へ滞在するつもりだったのだけれど、なぜか旦那様に反対されたのだ。
「夫婦仲が悪いと思われてしまう」
「なるほど、分かりました」
その意見も最もだと思ったので、特に意見もしない。もともと私はどちらでも良くて、私がいると旦那様が長旅の疲れを癒せないのではと思ったから、提案しただけだったし。
結構な過密スケジュールの中、旦那様はさらに仕事があるといって早々に出かけてしまった。私はというと、ずらりと並んだメイド達に体をぴかぴかに磨いてもらった。旦那様からいただいたドレスを纏って、マリッサに仕上げてもらう。
「今日は落ち着いて見えるよう、髪はしっかりと上げましょう」
「ええ、私丸顔がコンプレックスなのに」
「フィリア様も見た目を気になさるお年頃になられたのですね。私は嬉しいです」
「嘘ですごめんなさい」
本当は、アップにすると引っ張られている感じがして落ち着かないからってだけの理由。彼女にはなんでもお見通しらしい。
私のオレンジ色の髪に櫛を通しながら、マリッサは「綺麗な色だ」と誉めてくれた。
「嫌いじゃないけど、目立つから嫌なのよね」
それに昔、どこぞの令嬢から「品がない」と言われたこともある。別に、それを気にしたことはない。むしろ私が悪口の対象になるほど周囲から認知されていたことに驚いて、少しだけ喜んでしまったような記憶もある。当然、その令嬢や周りにいた人たちからは引かれた。
「若旦那様って、過保護ですね」
「どうしてだと思う?からかわれている感じはしないけど」
「もともとの気質か、あるいは何かのきっかけとか」
彼女にそう言われて、私はふとあることを思い出した。
「そうか、それだわ。原因が分かった気がする」
逆に、どうして今まで忘れていたのだろう。こんなにも明確な答えが、目の前にぶら下がっていたというのに。