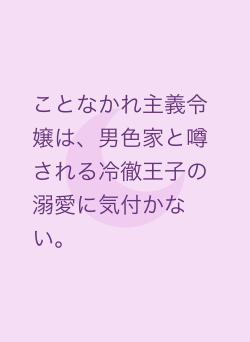「この花は《ジャラライラ》というのですね」
「変だろう」
「はい、私好みのヘンテコで可愛い名前です」
昔から、自然に囲まれた場所が大好きだった。何をするでもなく、ただそこに座ってゆっくりと呼吸を繰り返す。時には寝そべって、マリッサに怒られたり。
そうしていると、もう知っていることもまだ知らないことも、全部を受け入れられて、あちらからも受け入れてもらえるような。上手く表現出来ないけれど、とにかく好きなのだ。
「あっ、そういえば私って臭いんでしたよね⁉︎すみません、すぐ部屋に戻りま」
「違う、そうじゃない。君からこの花の香りがするんだ」
悪臭でなかったことにほっとしながら、旦那様の言葉に首を傾げた。さっきと同じように、自分の腕辺りをくんくんと嗅いでみるが、やっぱり無臭。香水は好きじゃないから、母に無理矢理振り撒かれる以外で身に纏ったことはないし。
「それはどうしてなのか、教えてくれ」
「申し訳ないのですが、旦那様のおっしゃっている意味がさっぱり分かりません。花の香りが服に移るくらい、よくあることでは?」
「いいや、それはない」
実にきっぱりと断言された為に、それ以上何も言えなくなる。
「この花は特別なんだ。意志があるという表現もおかしな話だが、気まぐれで非常に扱いにくく、こう見えて気性が荒い」
「旦那様は、花に対してまるで人間みたいな言い方をなさるのですね。とても素敵です」
「べ、別にロマンチックにさせようと思っているわけではないからな」
心外だとでも言いたげにふんと鼻を鳴らす姿は、なんだか可愛らしい。
そういえば、昨晩部屋の前でも匂いがどうのという話をしていたような。てっきり体臭を気にしているのかと思っていたけれど、どうやらそうではないらしい。
「よろしければ、もっと詳しく聞かせていただけませんか?」
「興味があるのか?」
「はい、とっても!」
希少な花の香りに関する話だなんて、わくわくするに決まってる。急に食いついてきた私を見て、旦那様は少々引いている様子だった。
「あ、すみません。口は出さない約束でしたのに」
「いや、構わない。元は僕から言い出したことだ」
「でしたら、あちらに座りましょう!」
さっきまで私が座っていた芝生。さすがに旦那様はそのままというわけにはいかないので、マリッサに目配せするとどこからかござを出してくれた。彼女のエプロンのポケットは異空間に繋がっているのではないかと、私はずっと昔から真剣に考えている。
「き、君は変わっているな。あまり出会ったことのないタイプの女性だ」
「あはは、よく言われます」
「褒められてはいませんよ、フィリア様」
恥じらうように笑った私に、すぐさまマリッサの鋭い突っ込みが入った。
「変だろう」
「はい、私好みのヘンテコで可愛い名前です」
昔から、自然に囲まれた場所が大好きだった。何をするでもなく、ただそこに座ってゆっくりと呼吸を繰り返す。時には寝そべって、マリッサに怒られたり。
そうしていると、もう知っていることもまだ知らないことも、全部を受け入れられて、あちらからも受け入れてもらえるような。上手く表現出来ないけれど、とにかく好きなのだ。
「あっ、そういえば私って臭いんでしたよね⁉︎すみません、すぐ部屋に戻りま」
「違う、そうじゃない。君からこの花の香りがするんだ」
悪臭でなかったことにほっとしながら、旦那様の言葉に首を傾げた。さっきと同じように、自分の腕辺りをくんくんと嗅いでみるが、やっぱり無臭。香水は好きじゃないから、母に無理矢理振り撒かれる以外で身に纏ったことはないし。
「それはどうしてなのか、教えてくれ」
「申し訳ないのですが、旦那様のおっしゃっている意味がさっぱり分かりません。花の香りが服に移るくらい、よくあることでは?」
「いいや、それはない」
実にきっぱりと断言された為に、それ以上何も言えなくなる。
「この花は特別なんだ。意志があるという表現もおかしな話だが、気まぐれで非常に扱いにくく、こう見えて気性が荒い」
「旦那様は、花に対してまるで人間みたいな言い方をなさるのですね。とても素敵です」
「べ、別にロマンチックにさせようと思っているわけではないからな」
心外だとでも言いたげにふんと鼻を鳴らす姿は、なんだか可愛らしい。
そういえば、昨晩部屋の前でも匂いがどうのという話をしていたような。てっきり体臭を気にしているのかと思っていたけれど、どうやらそうではないらしい。
「よろしければ、もっと詳しく聞かせていただけませんか?」
「興味があるのか?」
「はい、とっても!」
希少な花の香りに関する話だなんて、わくわくするに決まってる。急に食いついてきた私を見て、旦那様は少々引いている様子だった。
「あ、すみません。口は出さない約束でしたのに」
「いや、構わない。元は僕から言い出したことだ」
「でしたら、あちらに座りましょう!」
さっきまで私が座っていた芝生。さすがに旦那様はそのままというわけにはいかないので、マリッサに目配せするとどこからかござを出してくれた。彼女のエプロンのポケットは異空間に繋がっているのではないかと、私はずっと昔から真剣に考えている。
「き、君は変わっているな。あまり出会ったことのないタイプの女性だ」
「あはは、よく言われます」
「褒められてはいませんよ、フィリア様」
恥じらうように笑った私に、すぐさまマリッサの鋭い突っ込みが入った。