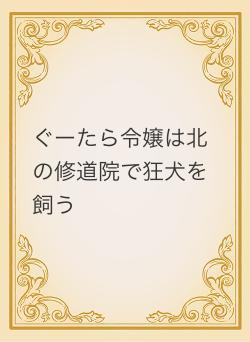医師の言葉にカタルは呆然とした。まったく身に覚えがなかったからだ。
同じベッドすら使ってたこともない夫婦のあいだに、子どもが生まれるわけがないことくらいは知っている。
何も言えずにいるカタルに医師が優しく微笑みかけた。「こんなに喜ばしいことはございません」というような言葉を言ってきたような気がする。
クロエの部屋に行くと、彼女はカタルから逃げるように視線を逸らした。
「懐妊したと聞いた」
カタルの言葉に返事はない。彼女はただ窓の外を眺めているだけだ。
ここで、「誰の子だ?」と言うべきか、どれほど葛藤しただろうか。しかし、皇族を騙し不義の子を産んだとなれば、クロエも相手の男も腹の子も生きてはいられない。
これは、愛のない結婚に妥協したカタルが背負うべき罪なのかもしれないと思った。
自分の子などほしくないと思っていたカタルに、神が罰を与えたのだろう。
カタルはクロエに「おめでとう」とだけ言って部屋を出たのだ。
カタルはその足で、オリバーの元を訪れた。
彼は皇族の中でも魔法の才に秀でている。今の魔法使いを束ねているのは、彼だと言っても過言ではないだろう。
オリバーも王宮内の皇族が暮らす場所に部屋を持っていたが、ほとんど王宮の奥にある魔法塔で生活してた。
雑多に荷物が置かれる部屋に入ると、彼は汚れた眼鏡を拭きながらカタルを迎え入れた。
「やあ、カタル。第一子懐妊だって? おめでとう」
「ああ……」
「なんだ? 子どもができたっていうのに、元気がないな」
「指一本触れていない妻に子どもができたんだ。それで笑っているほうがおかしいだろ」
「馬鹿な冗談はやめたほうがいい。閨教育は散々受けてきたんだ。それが冗談だってことくらい、誰にでもわかる」
オリバーは笑った。この帝国を守るためには多くの子孫を残すことが重要だと知っていた先祖は、閨教育を重要視していたようだ。得に婚外子を作れば、獣人が生まれることになる。だから、カタルたちは子どものころから子孫を残すための教育を受け続けてきた。
「わかっているさ。だから、笑えないんじゃないか」
同じベッドすら使ってたこともない夫婦のあいだに、子どもが生まれるわけがないことくらいは知っている。
何も言えずにいるカタルに医師が優しく微笑みかけた。「こんなに喜ばしいことはございません」というような言葉を言ってきたような気がする。
クロエの部屋に行くと、彼女はカタルから逃げるように視線を逸らした。
「懐妊したと聞いた」
カタルの言葉に返事はない。彼女はただ窓の外を眺めているだけだ。
ここで、「誰の子だ?」と言うべきか、どれほど葛藤しただろうか。しかし、皇族を騙し不義の子を産んだとなれば、クロエも相手の男も腹の子も生きてはいられない。
これは、愛のない結婚に妥協したカタルが背負うべき罪なのかもしれないと思った。
自分の子などほしくないと思っていたカタルに、神が罰を与えたのだろう。
カタルはクロエに「おめでとう」とだけ言って部屋を出たのだ。
カタルはその足で、オリバーの元を訪れた。
彼は皇族の中でも魔法の才に秀でている。今の魔法使いを束ねているのは、彼だと言っても過言ではないだろう。
オリバーも王宮内の皇族が暮らす場所に部屋を持っていたが、ほとんど王宮の奥にある魔法塔で生活してた。
雑多に荷物が置かれる部屋に入ると、彼は汚れた眼鏡を拭きながらカタルを迎え入れた。
「やあ、カタル。第一子懐妊だって? おめでとう」
「ああ……」
「なんだ? 子どもができたっていうのに、元気がないな」
「指一本触れていない妻に子どもができたんだ。それで笑っているほうがおかしいだろ」
「馬鹿な冗談はやめたほうがいい。閨教育は散々受けてきたんだ。それが冗談だってことくらい、誰にでもわかる」
オリバーは笑った。この帝国を守るためには多くの子孫を残すことが重要だと知っていた先祖は、閨教育を重要視していたようだ。得に婚外子を作れば、獣人が生まれることになる。だから、カタルたちは子どものころから子孫を残すための教育を受け続けてきた。
「わかっているさ。だから、笑えないんじゃないか」