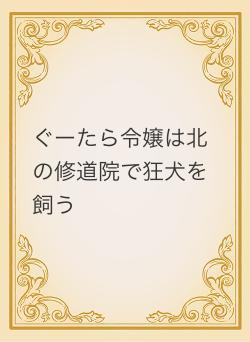火事場の馬鹿力とはこういう時に発揮させるのだろう。獣人であるディアナの力は強い。そのはずなのに、あっさりと子どもを奪い取ったのだ。
「私の赤ちゃ――……いやぁあああああっ! バケモノッ!」
クロエは叫んだ。彼女は生まれたばかりの子を放り投げる。放物線を描いて宙を舞う赤子を誰もが呆然と見ていた。
「カタルッ!」
ディアナの叫び声が部屋に響く。その声で我に返ったカタルは、ギリギリのところで赤子を抱きとめたのだ。
クロエは叫び声をあげ続けた。「あれは私の子じゃない!」「私の子を返してっ!」耳の奥が痛くなるほどの叫び声は彼女が気を失うまで続いた。
クロエが気絶すると、沈黙が訪れる。カタルとオリバー、そしてディアナは生まれたばかりの赤子に再び視線を戻した。
「どういうこと? 不義の子じゃないの?」
ディアナの言葉に、カタルは自嘲気味に笑った。
「私が神にでもなったのであれば、私の子だろうな」
「つまり、皇族の誰かと浮気をしていたということだね」
オリバーが眉尻を下げながら言った。ディアナは大きなため息を吐き出す。
「ここで暮らしていれば誰とでも会えるものね。相手の男も子ができてもカタルの子ということになるから問題ないと思ったんでしょ」
皇族は秘密を守るため、子どものころから性に関する教育を厳しく受ける。男子は特に厳しかった。婚外子を作ることは許されない。万が一、妻以外の女性に手を出した場合は報告が義務化されている。
すべては皇族の秘密を守るためだ。
「私の赤ちゃ――……いやぁあああああっ! バケモノッ!」
クロエは叫んだ。彼女は生まれたばかりの子を放り投げる。放物線を描いて宙を舞う赤子を誰もが呆然と見ていた。
「カタルッ!」
ディアナの叫び声が部屋に響く。その声で我に返ったカタルは、ギリギリのところで赤子を抱きとめたのだ。
クロエは叫び声をあげ続けた。「あれは私の子じゃない!」「私の子を返してっ!」耳の奥が痛くなるほどの叫び声は彼女が気を失うまで続いた。
クロエが気絶すると、沈黙が訪れる。カタルとオリバー、そしてディアナは生まれたばかりの赤子に再び視線を戻した。
「どういうこと? 不義の子じゃないの?」
ディアナの言葉に、カタルは自嘲気味に笑った。
「私が神にでもなったのであれば、私の子だろうな」
「つまり、皇族の誰かと浮気をしていたということだね」
オリバーが眉尻を下げながら言った。ディアナは大きなため息を吐き出す。
「ここで暮らしていれば誰とでも会えるものね。相手の男も子ができてもカタルの子ということになるから問題ないと思ったんでしょ」
皇族は秘密を守るため、子どものころから性に関する教育を厳しく受ける。男子は特に厳しかった。婚外子を作ることは許されない。万が一、妻以外の女性に手を出した場合は報告が義務化されている。
すべては皇族の秘密を守るためだ。