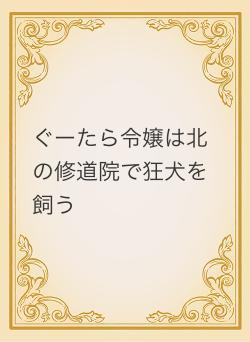ディアナは慌ててカタルとオリバーを呼んだ。叫ぶような声で呼ばれ、カタルとオリバーが部屋の中に入ると、ディアナは生まれたばかりの小さな子を抱いていた。
「カタル、どういうこと!?」
「何が?」
「何がじゃないわよ! 見て!」
ディアナが差し出した子は、どこからどう見ても狼の子どもだった。
カタルは呆然とその子どもを見下ろす。何が起こっているのかわからなかった。あり得るわけがない。クロエと見知らぬ男との不義の子だ。狼の姿で生まれることなどありえないのだ。
「カタル、本当に彼女と本当に何もなかったのか? これはどう見ても……」
「わかっている。だが、私ではない」
記憶を手繰り寄せても、クロエと一夜を共にしたことはない。
頭が混乱していた。計画ではクロエが子どもを産んですぐ、死産と発表する予定だったのだ。
(何が起こっているんだ……? この子は一体……)
クロエの体調が戻り次第、彼女と子を地方の屋敷に送り届け、相手の男と暮らせるようにする。それが、今回の計画のすべてだ。子どもは人間であるはずだった。
「私の子……。私にも抱かせて……」
クロエが弱々しく手を伸ばす。しかし、ディアナはその手を振りほどいた。
「クロエ、少し待ってちょうだい」
「もしかして、私の子に何かあったの!?」
クロエはベッドから這い出ると、ディアナから子どもを奪い取った。
「カタル、どういうこと!?」
「何が?」
「何がじゃないわよ! 見て!」
ディアナが差し出した子は、どこからどう見ても狼の子どもだった。
カタルは呆然とその子どもを見下ろす。何が起こっているのかわからなかった。あり得るわけがない。クロエと見知らぬ男との不義の子だ。狼の姿で生まれることなどありえないのだ。
「カタル、本当に彼女と本当に何もなかったのか? これはどう見ても……」
「わかっている。だが、私ではない」
記憶を手繰り寄せても、クロエと一夜を共にしたことはない。
頭が混乱していた。計画ではクロエが子どもを産んですぐ、死産と発表する予定だったのだ。
(何が起こっているんだ……? この子は一体……)
クロエの体調が戻り次第、彼女と子を地方の屋敷に送り届け、相手の男と暮らせるようにする。それが、今回の計画のすべてだ。子どもは人間であるはずだった。
「私の子……。私にも抱かせて……」
クロエが弱々しく手を伸ばす。しかし、ディアナはその手を振りほどいた。
「クロエ、少し待ってちょうだい」
「もしかして、私の子に何かあったの!?」
クロエはベッドから這い出ると、ディアナから子どもを奪い取った。