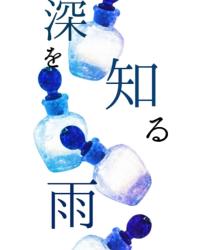シャロンの顔が頭に浮かんで遅れた涙が出そうになった時、ブラッドさんがもう片方の手を私の頬に当て、私の視線を自分の方へと戻させる。
「なら、約束します。俺が死ぬ時は、君も一緒に連れていく」
――真っ直ぐな青色の瞳が綺麗だと思った。
死ぬ時は一緒だというその言葉が酷く私を安心させる。
…この人はいつもそうだ。
どんな状況でも私を安心させることができる。
その馬鹿みたいな一途さに何度私が救われたか、この人はきっと分かっていない。
“好きになってはくれませんか”?
………そんなの、とっくに。
「私が…私が貴方を好きではないと仮定すると、今貴方を抱きしめたい衝動に駆られることに矛盾するわ」
素直じゃない私の、精一杯の遠回しな告白。
いつからブラッドさんに対して他の人に向けるそれとは違う感情を抱くようになったのかは分からない。
今まではっきりした形を持たない靄のようだったそれは、今この瞬間においてくっきりとその輪郭を描き、“恋”という名前を持って私にその存在を自覚させた。
「背理法みたいでしょう?」
力無く笑って言ってみせると、その意味を少し遅れて捉えたらしいブラッドさんは今更少し頬を染め、それを隠すようにして私に顔を近付けてくる。
私もそれに合わせて目を閉じ、唇が重なりかけた―――その時だった。
「あーずるーい。ぶらりんが抜け駆けしてるぅ」
「…お前ら、そんな顔近付けて何やってんだ?」
思わずブラッドさんを突き飛ばして距離を取りすぐさま後ろを振り向いた私だが、キスする以外であんな体勢になる理由が思い浮かばず、何の言い訳もできない。
ジャックめ、わざと扉開けて行ったんじゃないでしょうね。
ブラッドさんが残念そうな表情で私を見ているのが分かるが、突き飛ばしてしまったことを謝る前に目に入ったのはラスティ君の腕。
あの夜からラスティ君とは会っていなかったし、どんな状態なのか知らなかったし、――死んでいるんじゃないかとも思っていた。
足が勝手に動いてラスティ君の方へ向かう。
片方の腕がないラスティ君を見て色んな感情が湧き上がってきたのは事実だが、何よりも思うことが1つあった。
タックルするような勢いで抱き着いた私に、ラスティ君は「うわっ」と驚きながらも踏ん張って受け止める。
「……った…」
「ちょ、何アリスちゃん」
「良かった…っ…生きてて…!」
「……」
どうして腕が無くなったのとか、大丈夫なのとか、もっと聞くべきことはあるんだろうけれど、今私が最も感じるのはこれだった。
あんなこれからいよいよ死にますみたいな別れ方しといて、片腕だけで済んだのなら良い方だ。
酷くほっとして柄にもなくメソメソ泣く私の腕の中で、ラスティ君は楽しそうにからかってくる。
「アリスちゃんってばだいたーん。欲情しちゃうよ、僕」
顔を上げたくないから見えないけれど、ニヤニヤしているであろうラスティ君の表情は容易に想像できる。
離れなければいけないことは分かっているのだが今離れたら泣き顔を見られるため、とりあえずその前に涙を引っ込める努力をする。
「ぶらりんとアランの目が怖いなぁ……」
怖いとか言いながら満更でもなさそうな声だ。
色々と言いたいことはあるが、今喋ったら涙声になるため言いたくない。
「生きてて良かった。…死んでたら、こんな風に泣くアリスちゃん見れなかったもんね」
ラスティ君はそう囁いて私の後頭部を撫で、それでも離れない私を片手でぎゅ~っと締め付けるような強さで抱きしめたかと思えば、クスッと笑って謎の宣言をする。
「アランもぶらりんもごめん。僕、今ちょっとマジでアリスちゃん欲しくなっちゃった」
「は?」
「あ?」
「今日から晴れて恋敵だね!僕ら」
冗談だか本気だか分からないラスティ君の言葉により、場の空気が凍るのが分かる。
そこに春の暖かい風が窓から吹き抜けて行き、春の訪れを知らせた。
新しい季節がやってくる。
新しい人生が始まる予感がする。
そこで私は思い出した。
―――まだ1つ、クリミナルズの人達に伝えなければならないことがあることを。
クリミナルズのリーダーが新しくなる時は、必ず構成員を集めての挨拶が行われる。
強制力は無いが、来ない人はほとんどいないと言われていて、その日は普段集まることのない人数が集まるらしい。
陽のリーダー就任の挨拶を聞きに来るよう誘われたのは、桜の咲く時期だった。
私はもうクリミナルズの人間じゃないからと言ってもキャシーは聞いてくれなかった。
私にクリミナルズの行く先を見てほしい、と真剣な声で言ってきたので、仕方なくもう戻るつもりの無かったクリミナルズの滞在地へと足を運んだ。
屋内競技場のように広い空間の1番前には、演壇がある。
一応部外者という立場なので、クリミナルズのメンバーが集まっている場所とは違い、人のいない少し高い場所から見下げた。
人、人、人。沢山の頭がごちゃごちゃと並んでいる。
―――陽が現れると、それまでザワザワしていた会場内が一気に静かになった。
しかしそれは一瞬のことで、すぐに何かの音――啜り泣く音が僅かに聞こえてきた。
「何でシャロンさん死んじゃったの?」
「シャロンさんじゃないとやだよう」
納得できない様子で泣いていたのは、多くの子供。
それも、最前列に並んでいる子達だった。
どの子も見覚えがある。シャロンに懐いていた子供達だ。
「シャロンさんは僕たちを捨てたの?」
「あんなに仲良くしてくれたのに!」
「殺されちゃったの?」
「クリミナルズのリーダーはシャロンさんだよ…」
「俺達を置いて死ぬなんて酷い!」
一人、一人と、泣きながら気持ちを訴える子が増えていく。
私が驚いたのは、そんな人達の多さだった。
最前列を始めとして、子供に限らず、多くの人間が泣き始める。
シャロンが死んだという事実は、陽が壇上に立った今この瞬間において彼らにようやく実感を与えたらしい。
……これじゃあ、皆陽を歓迎していないと言っているようなものだ。
陽にとっても辛いことなのでは…と心配になりながら目を凝らして壇上の陽を見ると――意外なことに、陽は冷たい目で群集を見ていた。
「――――思い上がるな」
いつもの陽にはない威圧感が場を静める。
「彼は自分で選んで死んだんだ。それを否定するな。人の選んだ道を否定する権利なんて誰にも無い」
再び訪れた静寂。
普段とは違う陽の雰囲気に驚き、誰も言い返すことができない様子だった。
それを合図に、陽は数千人を超える群集に対し語り始める。
「俺はここにいるお前らに…クリミナルズという集団に言いたいことがある。
本当にどうしようもない時――あるいは本当に心から自ら望んだ時以外は死ぬな。
「なら、約束します。俺が死ぬ時は、君も一緒に連れていく」
――真っ直ぐな青色の瞳が綺麗だと思った。
死ぬ時は一緒だというその言葉が酷く私を安心させる。
…この人はいつもそうだ。
どんな状況でも私を安心させることができる。
その馬鹿みたいな一途さに何度私が救われたか、この人はきっと分かっていない。
“好きになってはくれませんか”?
………そんなの、とっくに。
「私が…私が貴方を好きではないと仮定すると、今貴方を抱きしめたい衝動に駆られることに矛盾するわ」
素直じゃない私の、精一杯の遠回しな告白。
いつからブラッドさんに対して他の人に向けるそれとは違う感情を抱くようになったのかは分からない。
今まではっきりした形を持たない靄のようだったそれは、今この瞬間においてくっきりとその輪郭を描き、“恋”という名前を持って私にその存在を自覚させた。
「背理法みたいでしょう?」
力無く笑って言ってみせると、その意味を少し遅れて捉えたらしいブラッドさんは今更少し頬を染め、それを隠すようにして私に顔を近付けてくる。
私もそれに合わせて目を閉じ、唇が重なりかけた―――その時だった。
「あーずるーい。ぶらりんが抜け駆けしてるぅ」
「…お前ら、そんな顔近付けて何やってんだ?」
思わずブラッドさんを突き飛ばして距離を取りすぐさま後ろを振り向いた私だが、キスする以外であんな体勢になる理由が思い浮かばず、何の言い訳もできない。
ジャックめ、わざと扉開けて行ったんじゃないでしょうね。
ブラッドさんが残念そうな表情で私を見ているのが分かるが、突き飛ばしてしまったことを謝る前に目に入ったのはラスティ君の腕。
あの夜からラスティ君とは会っていなかったし、どんな状態なのか知らなかったし、――死んでいるんじゃないかとも思っていた。
足が勝手に動いてラスティ君の方へ向かう。
片方の腕がないラスティ君を見て色んな感情が湧き上がってきたのは事実だが、何よりも思うことが1つあった。
タックルするような勢いで抱き着いた私に、ラスティ君は「うわっ」と驚きながらも踏ん張って受け止める。
「……った…」
「ちょ、何アリスちゃん」
「良かった…っ…生きてて…!」
「……」
どうして腕が無くなったのとか、大丈夫なのとか、もっと聞くべきことはあるんだろうけれど、今私が最も感じるのはこれだった。
あんなこれからいよいよ死にますみたいな別れ方しといて、片腕だけで済んだのなら良い方だ。
酷くほっとして柄にもなくメソメソ泣く私の腕の中で、ラスティ君は楽しそうにからかってくる。
「アリスちゃんってばだいたーん。欲情しちゃうよ、僕」
顔を上げたくないから見えないけれど、ニヤニヤしているであろうラスティ君の表情は容易に想像できる。
離れなければいけないことは分かっているのだが今離れたら泣き顔を見られるため、とりあえずその前に涙を引っ込める努力をする。
「ぶらりんとアランの目が怖いなぁ……」
怖いとか言いながら満更でもなさそうな声だ。
色々と言いたいことはあるが、今喋ったら涙声になるため言いたくない。
「生きてて良かった。…死んでたら、こんな風に泣くアリスちゃん見れなかったもんね」
ラスティ君はそう囁いて私の後頭部を撫で、それでも離れない私を片手でぎゅ~っと締め付けるような強さで抱きしめたかと思えば、クスッと笑って謎の宣言をする。
「アランもぶらりんもごめん。僕、今ちょっとマジでアリスちゃん欲しくなっちゃった」
「は?」
「あ?」
「今日から晴れて恋敵だね!僕ら」
冗談だか本気だか分からないラスティ君の言葉により、場の空気が凍るのが分かる。
そこに春の暖かい風が窓から吹き抜けて行き、春の訪れを知らせた。
新しい季節がやってくる。
新しい人生が始まる予感がする。
そこで私は思い出した。
―――まだ1つ、クリミナルズの人達に伝えなければならないことがあることを。
クリミナルズのリーダーが新しくなる時は、必ず構成員を集めての挨拶が行われる。
強制力は無いが、来ない人はほとんどいないと言われていて、その日は普段集まることのない人数が集まるらしい。
陽のリーダー就任の挨拶を聞きに来るよう誘われたのは、桜の咲く時期だった。
私はもうクリミナルズの人間じゃないからと言ってもキャシーは聞いてくれなかった。
私にクリミナルズの行く先を見てほしい、と真剣な声で言ってきたので、仕方なくもう戻るつもりの無かったクリミナルズの滞在地へと足を運んだ。
屋内競技場のように広い空間の1番前には、演壇がある。
一応部外者という立場なので、クリミナルズのメンバーが集まっている場所とは違い、人のいない少し高い場所から見下げた。
人、人、人。沢山の頭がごちゃごちゃと並んでいる。
―――陽が現れると、それまでザワザワしていた会場内が一気に静かになった。
しかしそれは一瞬のことで、すぐに何かの音――啜り泣く音が僅かに聞こえてきた。
「何でシャロンさん死んじゃったの?」
「シャロンさんじゃないとやだよう」
納得できない様子で泣いていたのは、多くの子供。
それも、最前列に並んでいる子達だった。
どの子も見覚えがある。シャロンに懐いていた子供達だ。
「シャロンさんは僕たちを捨てたの?」
「あんなに仲良くしてくれたのに!」
「殺されちゃったの?」
「クリミナルズのリーダーはシャロンさんだよ…」
「俺達を置いて死ぬなんて酷い!」
一人、一人と、泣きながら気持ちを訴える子が増えていく。
私が驚いたのは、そんな人達の多さだった。
最前列を始めとして、子供に限らず、多くの人間が泣き始める。
シャロンが死んだという事実は、陽が壇上に立った今この瞬間において彼らにようやく実感を与えたらしい。
……これじゃあ、皆陽を歓迎していないと言っているようなものだ。
陽にとっても辛いことなのでは…と心配になりながら目を凝らして壇上の陽を見ると――意外なことに、陽は冷たい目で群集を見ていた。
「――――思い上がるな」
いつもの陽にはない威圧感が場を静める。
「彼は自分で選んで死んだんだ。それを否定するな。人の選んだ道を否定する権利なんて誰にも無い」
再び訪れた静寂。
普段とは違う陽の雰囲気に驚き、誰も言い返すことができない様子だった。
それを合図に、陽は数千人を超える群集に対し語り始める。
「俺はここにいるお前らに…クリミナルズという集団に言いたいことがある。
本当にどうしようもない時――あるいは本当に心から自ら望んだ時以外は死ぬな。