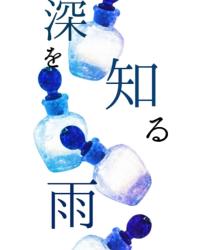そこでエレベーターのドアが開く。
私にはそれが妙に、未来への道が開かれたようにも見えて。
エレベーターから降りたジャックは、動かない私を振り返って「どうしたの?」と不思議そうに聞いてくる。
私は【開】のボタンを押しドアが閉じないようにして、静かにジャックに手を伸ばす。
ジャックはわけが分からないであろうまま自然と私の手を取り、それでも動かない私の次の言葉を待った。
「ジャック」
「ん?」
「私も連れてって」
その言葉を聞いたジャックは少し瞠目したが、すぐに可笑しそうにクスクス笑い、私の手をやや強引に引っ張ってエレベーターから連れ出す。
「分かったよ、お姫様」
『オレも行くゾ!』
「きゃあああっ!」
あまりにも唐突に背後から機械音がしたため、思わずジャックにしがみついた。
エレベーターの中から一匹のヤモリ――知能を持つヤモリであるヤモが出てくる。
もう冬眠から目覚めて日本へ来たというのか。
「び、びっくりした………」
そっと近付いていきなり話し掛けてくるのいい加減やめてくれないかしら、不覚にも今までで1番驚いたわ。
「…俺はアリスの反応が意外と女の子っぽいことに驚いたな」
どういう意味?それ。
『へへん、この時を待ってエレベーターで待機してたんだ』
このヤモリ、こうやって人間を驚かすことで快感を得ているんじゃないのかしら。
そうだとしたら悪趣味な変態だ。
「“オレも行く”ってどういう意味?まさか…」
『オレも世界各国を旅したいゾ』
やはりさっきの会話を盗み聞きしていたうえでの要望か……。
まぁヤモもクリミナルズの一員として長年働いてきているわけだし、役に立たないというわけではないだろう。
ジャックさえ良いなら私は別にいいけれど、と思いちらりとジャックを見ると、ジャックは爽やかスマイルでヤモの願いを受け入れた。
「ヤモ君もいるなら心強いな。ただし、何が起こっても知らないよ?男を守る義理はないからね」
加えてさらりと冷たいことを言ってブラッドさんの病室へと歩き出すジャックだが、ヤモはそんな言葉聞こえていないかのように喜びながら素早くジャックの肩に乗る。
優しいようでいて冷酷な部分もあるジャックのことだ、本当に何かあってもヤモを守ることはしないだろう。
自分の身は自分で守ってきたヤモのことだし、そんなの今まで通りだって思ってるのかもしれないけれど、新しい仕事では何が起こるか分からない。
危なくなった時は助けられる範囲で私が助けてやるか、と思いながらジャックの肩の上のヤモを見ると、その瞳と目が合って。
『泣いてなくて良かった』
変わらない機械音だが、そのいつもより幾分か小さな音が優しい声のように聞こえた。
もしかしてこのヤモリ、私のことを心配してこの病院に来たんだろうか。
……守られてるのはお互い様、か。
思わずクスッと笑った時、ジャックが急に立ち止まる。
その視線の先に目を向けると、―――ブラッドさんの病室から数人の看護師さんが出たり入ったりしていた。
状態が悪化したのでは、と思いジャックを見上げると、ジャックも険しい表情をしていて。
思わずまたブラッドさんの病室の方に視線を戻し、怖くて動けなくなった。
立ち止まる私の背中をジャックが優しく押してくる。
「行こう。最期は君に傍にいてほしいはずだ」
「……酷なことを言うわね」
シャロンのことでまだショックを受けている今の私に、ブラッドさんの最期を看取れと言うのか。死に逝く様見ろと言うのか。
「ブラッドの為だ」
見たくないというのが正直なところだったが、見上げたジャックが渋い表情をしているのを見て、怖いのは私だけじゃないことを知る。
……行こう。ブラッドさんの最期を私たちで見届けるんだ。
覚悟を決め、ジャックの手を引っ張って病室まで走る。
しかし。
緊張しながら病室に辿り着いた時―――そこにいたのは、何でもない顔でベッドの上に座っているブラッドさんだった。
「お知り合いですか?ちょうど今目を覚ましたんです!」
「……へ、」
看護師さんの言葉に思わず間抜けな声が出た。
「状態もかなり良くなっています!」
私はジャックと顔を見合わせ、その後もう一度久しぶりに目を開けているブラッドさんを見る。
少し痩せたような気もするが…見た感じ元気そうだ。
「……凄い生命力だな。正直もう無理だと思っていた」
呆れたようなほっとしたような声を出したジャックは、目を閉じて大きな溜め息を吐く。
ジャックもジャックでかなり焦っていたらしい。
一通り作業を終えたらしい看護師さん達が部屋を出て行く。
私とブラッドさんを交互に見て、「俺は邪魔だね」と苦笑して出て行こうとするジャックの背中に、「助かりました」とブラッドさんが声を掛けた。
ジャックは返事をせず部屋を出て行ったが、聞こえてはいただろう。
ブラッドさんは、どうやらあの時運んでくれたのがジャックだということを分かっているらしかった。
私はブラッドさんのベッドの隣、窓側にある椅子に座って、何から話そうか迷った結果まず謝罪をすることにした。
「ごめんなさい。私のせいでこんなことに…」
「いえ。寧ろ君には助けられたと思います。あの時は高熱で気を失っていましたから。君が起こしてくれなければ、俺は死んでいたかもしれない」
「高熱?じゃあ、あの日顔色が悪かったのってやっぱり、」
「自分では問題ないと思ったんですけどね」
「……二度とあんなことしないで。死んだかと思ったのよ?」
無理矢理私を眠らせたこと。
私のために無理をしてまで戦いに行ったこと。
私を庇ったこと。
“あんなこと”には色々なことが含まれている。
「すみません。でも、少し嬉しいんです」
ブラッドさんは私から視線を外し、窓の外の梅の花を見て微笑を浮かべる。
その眼にいつもの冷たさは無く、不覚にもどきりとさせられた。
「矛盾していますよね。君を危険に晒したくないと思っているのに、あんな火の中君が俺を助けに来てくれたことが何より嬉しいんです。今も、そうして俺が死にかけたことを怒ってくれている君が愛しい」
こっちは怒ってるのに嬉しいとはどういうことよと言おうとしたが、ちょうどその時ブラッドさんの視線がこちらに戻ってきて、言おうとした言葉は何故か引っ込んでしまう。
ブラッドさんの手が伸びてきて、私の頬に触れた。
「好きです。俺を好きになってはくれませんか」
……馬鹿だ、この人は。
ずっと一途に私だけを想い続けて、こんな状態になってまで私に愛の言葉を囁く。
「…少なくとも、命をかけてまで私を守ろうとする人は嫌。私より先に死ぬ人も嫌」
もう……大切な人に先立たれるのは嫌だ。
私にはそれが妙に、未来への道が開かれたようにも見えて。
エレベーターから降りたジャックは、動かない私を振り返って「どうしたの?」と不思議そうに聞いてくる。
私は【開】のボタンを押しドアが閉じないようにして、静かにジャックに手を伸ばす。
ジャックはわけが分からないであろうまま自然と私の手を取り、それでも動かない私の次の言葉を待った。
「ジャック」
「ん?」
「私も連れてって」
その言葉を聞いたジャックは少し瞠目したが、すぐに可笑しそうにクスクス笑い、私の手をやや強引に引っ張ってエレベーターから連れ出す。
「分かったよ、お姫様」
『オレも行くゾ!』
「きゃあああっ!」
あまりにも唐突に背後から機械音がしたため、思わずジャックにしがみついた。
エレベーターの中から一匹のヤモリ――知能を持つヤモリであるヤモが出てくる。
もう冬眠から目覚めて日本へ来たというのか。
「び、びっくりした………」
そっと近付いていきなり話し掛けてくるのいい加減やめてくれないかしら、不覚にも今までで1番驚いたわ。
「…俺はアリスの反応が意外と女の子っぽいことに驚いたな」
どういう意味?それ。
『へへん、この時を待ってエレベーターで待機してたんだ』
このヤモリ、こうやって人間を驚かすことで快感を得ているんじゃないのかしら。
そうだとしたら悪趣味な変態だ。
「“オレも行く”ってどういう意味?まさか…」
『オレも世界各国を旅したいゾ』
やはりさっきの会話を盗み聞きしていたうえでの要望か……。
まぁヤモもクリミナルズの一員として長年働いてきているわけだし、役に立たないというわけではないだろう。
ジャックさえ良いなら私は別にいいけれど、と思いちらりとジャックを見ると、ジャックは爽やかスマイルでヤモの願いを受け入れた。
「ヤモ君もいるなら心強いな。ただし、何が起こっても知らないよ?男を守る義理はないからね」
加えてさらりと冷たいことを言ってブラッドさんの病室へと歩き出すジャックだが、ヤモはそんな言葉聞こえていないかのように喜びながら素早くジャックの肩に乗る。
優しいようでいて冷酷な部分もあるジャックのことだ、本当に何かあってもヤモを守ることはしないだろう。
自分の身は自分で守ってきたヤモのことだし、そんなの今まで通りだって思ってるのかもしれないけれど、新しい仕事では何が起こるか分からない。
危なくなった時は助けられる範囲で私が助けてやるか、と思いながらジャックの肩の上のヤモを見ると、その瞳と目が合って。
『泣いてなくて良かった』
変わらない機械音だが、そのいつもより幾分か小さな音が優しい声のように聞こえた。
もしかしてこのヤモリ、私のことを心配してこの病院に来たんだろうか。
……守られてるのはお互い様、か。
思わずクスッと笑った時、ジャックが急に立ち止まる。
その視線の先に目を向けると、―――ブラッドさんの病室から数人の看護師さんが出たり入ったりしていた。
状態が悪化したのでは、と思いジャックを見上げると、ジャックも険しい表情をしていて。
思わずまたブラッドさんの病室の方に視線を戻し、怖くて動けなくなった。
立ち止まる私の背中をジャックが優しく押してくる。
「行こう。最期は君に傍にいてほしいはずだ」
「……酷なことを言うわね」
シャロンのことでまだショックを受けている今の私に、ブラッドさんの最期を看取れと言うのか。死に逝く様見ろと言うのか。
「ブラッドの為だ」
見たくないというのが正直なところだったが、見上げたジャックが渋い表情をしているのを見て、怖いのは私だけじゃないことを知る。
……行こう。ブラッドさんの最期を私たちで見届けるんだ。
覚悟を決め、ジャックの手を引っ張って病室まで走る。
しかし。
緊張しながら病室に辿り着いた時―――そこにいたのは、何でもない顔でベッドの上に座っているブラッドさんだった。
「お知り合いですか?ちょうど今目を覚ましたんです!」
「……へ、」
看護師さんの言葉に思わず間抜けな声が出た。
「状態もかなり良くなっています!」
私はジャックと顔を見合わせ、その後もう一度久しぶりに目を開けているブラッドさんを見る。
少し痩せたような気もするが…見た感じ元気そうだ。
「……凄い生命力だな。正直もう無理だと思っていた」
呆れたようなほっとしたような声を出したジャックは、目を閉じて大きな溜め息を吐く。
ジャックもジャックでかなり焦っていたらしい。
一通り作業を終えたらしい看護師さん達が部屋を出て行く。
私とブラッドさんを交互に見て、「俺は邪魔だね」と苦笑して出て行こうとするジャックの背中に、「助かりました」とブラッドさんが声を掛けた。
ジャックは返事をせず部屋を出て行ったが、聞こえてはいただろう。
ブラッドさんは、どうやらあの時運んでくれたのがジャックだということを分かっているらしかった。
私はブラッドさんのベッドの隣、窓側にある椅子に座って、何から話そうか迷った結果まず謝罪をすることにした。
「ごめんなさい。私のせいでこんなことに…」
「いえ。寧ろ君には助けられたと思います。あの時は高熱で気を失っていましたから。君が起こしてくれなければ、俺は死んでいたかもしれない」
「高熱?じゃあ、あの日顔色が悪かったのってやっぱり、」
「自分では問題ないと思ったんですけどね」
「……二度とあんなことしないで。死んだかと思ったのよ?」
無理矢理私を眠らせたこと。
私のために無理をしてまで戦いに行ったこと。
私を庇ったこと。
“あんなこと”には色々なことが含まれている。
「すみません。でも、少し嬉しいんです」
ブラッドさんは私から視線を外し、窓の外の梅の花を見て微笑を浮かべる。
その眼にいつもの冷たさは無く、不覚にもどきりとさせられた。
「矛盾していますよね。君を危険に晒したくないと思っているのに、あんな火の中君が俺を助けに来てくれたことが何より嬉しいんです。今も、そうして俺が死にかけたことを怒ってくれている君が愛しい」
こっちは怒ってるのに嬉しいとはどういうことよと言おうとしたが、ちょうどその時ブラッドさんの視線がこちらに戻ってきて、言おうとした言葉は何故か引っ込んでしまう。
ブラッドさんの手が伸びてきて、私の頬に触れた。
「好きです。俺を好きになってはくれませんか」
……馬鹿だ、この人は。
ずっと一途に私だけを想い続けて、こんな状態になってまで私に愛の言葉を囁く。
「…少なくとも、命をかけてまで私を守ろうとする人は嫌。私より先に死ぬ人も嫌」
もう……大切な人に先立たれるのは嫌だ。