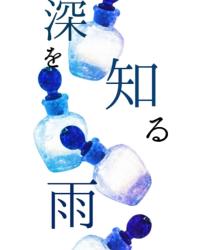だから正直聞きたくないと思ったが、ジャックが言葉を放ったのは私が耳を塞ぐより早かった。
「シャロン君のことだ。――死んでいる可能性が高い」
そしてそれは、思っていたよりもずっと嫌な知らせだった。
「士巳豆を殺したのは俺達の中の人間じゃなかった。陽くんに話をしたんだが、このことを言うとシャロン君じゃないかと言っていたよ。日本のお偉いさん方は、犯罪組織のリーダーと士巳豆が密会していたことを隠したがっている。“士巳豆が殺された部屋に、もう1つ遺体があった”ことは公にならないだろう」
公になっていないのに何故ジャックが知っているのか。
いや……ジャックのことだから、日本の裏社会とも繋がりがあるのかもしれない。
そしてその裏社会と繋がりのある政治家から話を聞き出した、というところだろう。
「その遺体は高確率でシャロン君だと陽くんは言ってる」
あのシャロンが他人に殺されるとは思えない。
死んだとしたら自分の意思だ。
何故シャロンが死のうと思ったのかと、考えているうちに眩暈がした。
私があんなことを、言ったからじゃないだろうか。
私があんなことを言ったから、シャロンは必要以上に自分を責めてしまったんじゃないだろうか。
あの時、あの船で、私は心から彼を『嘘つき』と言って責めたのだ。
どうしよう、と思ってうまく呼吸ができなくなった時、
「陽くんは君のせいじゃないとも言っていた。選んだのはシャロン君だと」
ジャックが私をあやすように言った。
陽は1番シャロンのことを理解していると私は前から勝手に思ってる。
陽はリバディーにいたし、シャロンと陽が一緒にいるところを実際に見た期間は少なかったけど……それでも2人の間の空気感を見ていてそう思った。
だからその言葉は私の中にすっと入ってきて、不思議と私を落ち着かせた。
「…キャシーは…どんな感じなの?」
あの子はシャロンをずっと慕っていた。
シャロンに感謝していて、きっと誰よりもシャロンを尊敬していて、シャロンを救おうとしていた女の子だ。
キャシーの様子を想像するだけで胸が痛くなる。
「みんなの前では強がってるけど、ショックは大きいだろうね。バズ君が慰めてるってところかな」
「そう…」
現実味がない。でも現実だ。
シャロンはもうどこにもいない。
―――そう思うと、次の瞬間酷い喪失感が襲ってきた。
心臓をえぐられたような、体の一部が無くなったような喪失感だった。
シャロンは私の一部だったのだと、今更ながら痛感させられた。
もうあの人に触れられることはないのだと思うと寒気すら感じた。
「泣かないんだね。もっと、取り乱すかと思った」
「多分……言い残したことがないからだと思うわ」
――それでも、後悔だけは感じなかった。
「お父さんに会いに行く前、偶然シャロンに会ったの。その時、言いたいことを言ったのよ。“ありがとう”って。何故かあの時、言わなきゃいけない気がして」
この先一生、シャロンに会うことはない。
あんな偶然は二度と起きない。
この世界のどこにもシャロンはいない。
「……頼み事をしてもいいかしら」
「俺にできることなら何でも」
「シャロンの遺体を回収してほしいの」
無理なことを言っているのは分かっている。
だけど、どうしてもそうしてほしい。
「難しいことを言うね」
「骨だけでも、お願い。それで……お墓をつくってほしい。それで、」
嗚呼どうしよう、やっぱり少し泣きそうだ。
「私が死んだら、彼と同じ墓に入れて」
私がシャロンにしてあげられること、もうこれしか無い気がする。
「あの人、ずっと私と一緒にいたいって言ったの」
彼がどんなに嘘つきだったとしても、多分あの言葉に嘘は無いから。
ジャックは暫く考えるように沈黙して私を見ていたが、その後ふう、と溜め息混じりの苦笑を浮かべ、椅子から立ち上がる。
その仕草が何だか大人っぽくて、頼れる大人を思わせた。
「分かったよ。また色々と犯罪に手を染めなきゃいけないけど、君のためだし仕方ない。それに、今更だしね」
いくらジャックでも、今どこで管理されているのか分からない、いやもう処分されているかもしれない死体を回収するのは難しいだろう。
それでもジャックはそれを感じさせない空気を作る。
「ジャック」
「ん?」
「…ありがとう」
立ち上がってジャックの隣を歩きながらぽつりと言ったが、我ながら小さな声になってしまい、聞こえているか心配になった。
ジャックが何も答えないのでもしかしてもう一回言わなきゃいけないのかと不安になっていると、
「こちらこそ」
ジャックらしい優しい声音でそう返された。
「珍しいね。君も君で、随分変わったように思うよ」
「……言える時に、言わなきゃ駄目だもの」
ジャックはわざわざ私をブラッドさんの病室まで送り届けてくれるらしく、エレベーターに乗ってブラッドさんの階のボタンを押す。
エレベーターの中には誰もおらず、ふわりとジャック独特のお菓子みたいな香りが広がった。
「じゃあ、俺も。ありがとう」
別にお礼を言われるようなことは何もしていない気がして、それどころかジャックには無理ばかり言っている気しかしなくて戸惑っていると、ジャックがふふっと柔らかく笑う。
「俺は振り回されるのが好きらしい。君のおかげで久しぶりに人生が楽しいよ」
「…そ、…そう言ってくれてありがとう?」
「いえいえ、こちらこそありがとう」
謎のありがとうの連鎖に心がムズムズしてクスッと笑うと、「やっと笑った」と言ってジャックは嬉しそうに私の頭をくしゃりと撫でた。
「君はこれからどうするつもりなの?」
クリミナルズを抜けたことはキャシーに報告しておいたから、これはそれを知ったうえでの質問だろう。
私はクリミナルズ以外で活動の場を作らなければならない。
そしてその前に、子供も作らなきゃいけない。
「手段はともかくとして、あの国で子供を産むことは決めてるわ」
「あの国で?何でわざわざ」
「あそこなら基本的に親と子の関係が薄いじゃない?子供を早くから自立させるのが当たり前な傾向があるし、その分子供を預けられる組織も充実してる。…私みたいな、“親”になりきれそうにない人間が、親子の繋がりを大切にする日本で子育てするのって難しいと思うの」
ここ数日考えて出した結論だが、あの国なら幼い頃から子供を組織に預け、そこでそこにいる仲間と共に成長させることができる。
勿論生まれてすぐの間は私が面倒を見るつもりだし、そのための勉強もしようと思っているわけだけれど。
「その後は……そうね。そっちはこれからどうするつもりなの?」
「今まで通り、世界各国を飛び回って仕事かな。ただ少し変わることはある。アンナと一緒だ」
「…“アンナ”?誰よ?」
「シャロン君のことだ。――死んでいる可能性が高い」
そしてそれは、思っていたよりもずっと嫌な知らせだった。
「士巳豆を殺したのは俺達の中の人間じゃなかった。陽くんに話をしたんだが、このことを言うとシャロン君じゃないかと言っていたよ。日本のお偉いさん方は、犯罪組織のリーダーと士巳豆が密会していたことを隠したがっている。“士巳豆が殺された部屋に、もう1つ遺体があった”ことは公にならないだろう」
公になっていないのに何故ジャックが知っているのか。
いや……ジャックのことだから、日本の裏社会とも繋がりがあるのかもしれない。
そしてその裏社会と繋がりのある政治家から話を聞き出した、というところだろう。
「その遺体は高確率でシャロン君だと陽くんは言ってる」
あのシャロンが他人に殺されるとは思えない。
死んだとしたら自分の意思だ。
何故シャロンが死のうと思ったのかと、考えているうちに眩暈がした。
私があんなことを、言ったからじゃないだろうか。
私があんなことを言ったから、シャロンは必要以上に自分を責めてしまったんじゃないだろうか。
あの時、あの船で、私は心から彼を『嘘つき』と言って責めたのだ。
どうしよう、と思ってうまく呼吸ができなくなった時、
「陽くんは君のせいじゃないとも言っていた。選んだのはシャロン君だと」
ジャックが私をあやすように言った。
陽は1番シャロンのことを理解していると私は前から勝手に思ってる。
陽はリバディーにいたし、シャロンと陽が一緒にいるところを実際に見た期間は少なかったけど……それでも2人の間の空気感を見ていてそう思った。
だからその言葉は私の中にすっと入ってきて、不思議と私を落ち着かせた。
「…キャシーは…どんな感じなの?」
あの子はシャロンをずっと慕っていた。
シャロンに感謝していて、きっと誰よりもシャロンを尊敬していて、シャロンを救おうとしていた女の子だ。
キャシーの様子を想像するだけで胸が痛くなる。
「みんなの前では強がってるけど、ショックは大きいだろうね。バズ君が慰めてるってところかな」
「そう…」
現実味がない。でも現実だ。
シャロンはもうどこにもいない。
―――そう思うと、次の瞬間酷い喪失感が襲ってきた。
心臓をえぐられたような、体の一部が無くなったような喪失感だった。
シャロンは私の一部だったのだと、今更ながら痛感させられた。
もうあの人に触れられることはないのだと思うと寒気すら感じた。
「泣かないんだね。もっと、取り乱すかと思った」
「多分……言い残したことがないからだと思うわ」
――それでも、後悔だけは感じなかった。
「お父さんに会いに行く前、偶然シャロンに会ったの。その時、言いたいことを言ったのよ。“ありがとう”って。何故かあの時、言わなきゃいけない気がして」
この先一生、シャロンに会うことはない。
あんな偶然は二度と起きない。
この世界のどこにもシャロンはいない。
「……頼み事をしてもいいかしら」
「俺にできることなら何でも」
「シャロンの遺体を回収してほしいの」
無理なことを言っているのは分かっている。
だけど、どうしてもそうしてほしい。
「難しいことを言うね」
「骨だけでも、お願い。それで……お墓をつくってほしい。それで、」
嗚呼どうしよう、やっぱり少し泣きそうだ。
「私が死んだら、彼と同じ墓に入れて」
私がシャロンにしてあげられること、もうこれしか無い気がする。
「あの人、ずっと私と一緒にいたいって言ったの」
彼がどんなに嘘つきだったとしても、多分あの言葉に嘘は無いから。
ジャックは暫く考えるように沈黙して私を見ていたが、その後ふう、と溜め息混じりの苦笑を浮かべ、椅子から立ち上がる。
その仕草が何だか大人っぽくて、頼れる大人を思わせた。
「分かったよ。また色々と犯罪に手を染めなきゃいけないけど、君のためだし仕方ない。それに、今更だしね」
いくらジャックでも、今どこで管理されているのか分からない、いやもう処分されているかもしれない死体を回収するのは難しいだろう。
それでもジャックはそれを感じさせない空気を作る。
「ジャック」
「ん?」
「…ありがとう」
立ち上がってジャックの隣を歩きながらぽつりと言ったが、我ながら小さな声になってしまい、聞こえているか心配になった。
ジャックが何も答えないのでもしかしてもう一回言わなきゃいけないのかと不安になっていると、
「こちらこそ」
ジャックらしい優しい声音でそう返された。
「珍しいね。君も君で、随分変わったように思うよ」
「……言える時に、言わなきゃ駄目だもの」
ジャックはわざわざ私をブラッドさんの病室まで送り届けてくれるらしく、エレベーターに乗ってブラッドさんの階のボタンを押す。
エレベーターの中には誰もおらず、ふわりとジャック独特のお菓子みたいな香りが広がった。
「じゃあ、俺も。ありがとう」
別にお礼を言われるようなことは何もしていない気がして、それどころかジャックには無理ばかり言っている気しかしなくて戸惑っていると、ジャックがふふっと柔らかく笑う。
「俺は振り回されるのが好きらしい。君のおかげで久しぶりに人生が楽しいよ」
「…そ、…そう言ってくれてありがとう?」
「いえいえ、こちらこそありがとう」
謎のありがとうの連鎖に心がムズムズしてクスッと笑うと、「やっと笑った」と言ってジャックは嬉しそうに私の頭をくしゃりと撫でた。
「君はこれからどうするつもりなの?」
クリミナルズを抜けたことはキャシーに報告しておいたから、これはそれを知ったうえでの質問だろう。
私はクリミナルズ以外で活動の場を作らなければならない。
そしてその前に、子供も作らなきゃいけない。
「手段はともかくとして、あの国で子供を産むことは決めてるわ」
「あの国で?何でわざわざ」
「あそこなら基本的に親と子の関係が薄いじゃない?子供を早くから自立させるのが当たり前な傾向があるし、その分子供を預けられる組織も充実してる。…私みたいな、“親”になりきれそうにない人間が、親子の繋がりを大切にする日本で子育てするのって難しいと思うの」
ここ数日考えて出した結論だが、あの国なら幼い頃から子供を組織に預け、そこでそこにいる仲間と共に成長させることができる。
勿論生まれてすぐの間は私が面倒を見るつもりだし、そのための勉強もしようと思っているわけだけれど。
「その後は……そうね。そっちはこれからどうするつもりなの?」
「今まで通り、世界各国を飛び回って仕事かな。ただ少し変わることはある。アンナと一緒だ」
「…“アンナ”?誰よ?」