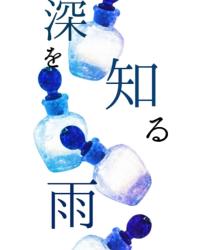そう思って研究所の周りをうろうろしていると、私より先にバズ君が何かに気付いたようで。
「あの人じゃない?」
「え?」
「ほら、あそこに人が2人いるでしょ」
バズ君が指差したのは、窓から見える研究所の中だった。
火が燃え盛る中、マッシュルームカットの長身の男と、先程見たブラッドとかいう人が向かい合って立っている。
「あれですわ…!もう1人は…研究員でしょうか?ファッションセンス無さ過ぎですわ!」
「初対面の相手のファッションセンス馬鹿にしちゃ駄目だよ…」
ブラッドとかいう方、どうやって外に出て来るおつもりですの?
火に囲まれていますわ。
と――そんなことを思っていた時、そのブラッドが床に倒れるのが分かった。
「え……っ…死…!?」
「よく分かんないけど、あの人はキャシーの協力者なの?」
「そ、そうですわ!どうしましょう、このままじゃ死……っていうかあれ、もう死んでません!?全然動きませんわ!」
窓を壊して入っていこうとする私の腕をバズ君が掴んで止める。
「ここからじゃ無理だよ。ていうか、どこからも無理。この火じゃ近付けない」
「でもあれ、リバディーの重要な人っぽいですわよ!?」
「リバディーは敵組織でしょ」
「でも今は協力してるんです!」
「もう死んでるっぽいけど?」
「ま、まだ分かりませんわ!早く行かなきゃ――」
「この火の中行ったらキャシーが死ぬよ。まずは消火」
「そんなことしてる暇、」
私を無理矢理引っ張って引き戻すバズ君は、落ち着いた声で言う。
「こういう状況でこそ冷静さが必要。そんなに助けに行きたいなら、遠回りしなきゃね」
バズ君の言葉によって何とか冷静になった私は、今すべきことを考えた。
火を消さなければ安全に向こうには近付けない。
となると……。
「消火器があったはずですわ!あれを持ってきましょう!」
助けられるかは分からない。
もう手遅れかもしれない。
でも、それでも――私に今できることを。
《《<--->》》
さぁ、ラストスパートだ。
《《<--->》》
物語は繋がっていく。
《《<--->》》
たとえそれが―――
《《<--->》》
『 背理法みたいでしょう? 』
《《<--->》》
episode13
《《<--->》》
〈 アリスサイド 〉
頭痛がする。
体が重い。
眩しい。
五月蝿い。
強い光が上から私を照らしている。
アラームの音も必要以上に大きい。
「悪いね、無理矢理起こしてしまって」
音が止まったかと思うと、誰かに話し掛けられた。
何度も聞いたことのある声であるのは分かるのに、声の主が誰だか分からず、私は視線だけをゆっくりと声のする方向に向けた。
私の寝転がるベッドの隣に、ジャックが座っている。
ここは……どこかのホテルの一室?
そこで状況を思い出した私は、勢いよく身を起こした。
聞きたいことは山ほどあるのに質問を整理できず、口から言葉が出て来ない私に、ジャックはゆっくりと伝えてきた。
「ブラッドに場所を教えられてね。全て終われば迎えに行く予定だが、もし自分が何らかの理由で来られなくなった場合、俺に君を迎えに行ってほしいと言われた」
「じゃあもう…」
「いや、まだ終わっていない。俺はブラッドからそれを聞いてすぐこっちに来たからね」
そう言われて顔を上げると、ジャックが私を見て苦笑していた。
ジャックがよくする苦笑だが、いつになく格好良く見えた。
「まったく、あの弟は何も分かってないな。君は最後まで尽力したがっているのに」
「…ジャック……」
「おいで。連れていくよ」
ジャックは私に手を差し伸べる。
その頼もしさに泣きそうになりながら、迷うことなく手を取った。
「小さいエマさんはどうしたの?」
「面白い言い方だね。あの子なら他の被害者と一緒に安全な場所にいるよ」
「そっちには行かないの…?折角会えたんだから様子見てたいんじゃないの?」
私の当然の疑問に対し、ジャックは愚問だとでも言うようにクスリと笑う。
「―――言っただろ?俺の生きる意味を君に譲渡すると」
ジャックに連れられて研究所の裏の出口付近まで走ると、キャシーとバズ先生が消火器を持って火を消そうとしていた。
ドアが開かないのか、この辺で唯一の窓を割ってそこから火を消している。
何故そんなことをしているのかと思ったが、2人の視線の先にいる人達を見てすぐに理由が分かった。
研究員らしき人物と、その前に倒れているのは――ブラッドさんだ。
この窓からは結構遠い。
でも、火さえ消せば走っていける距離ではある。
「アリス!?来てくれたんですの!?」
消火器を持ったままこちらを振り向くキャシーとバズ先生。
「良かった…そこに消火器が何本かあるから、手伝ってくれる?」
バズ先生が目線だけで消火器の位置を伝えてくる。
急いでジャックと私でそれを手に持ち、消火しようとしたが。
―――間に合わない。そう思った。
ここからこの4人で火を消そうとしたって間に合わない。
もうすぐ火はあの2人に燃え移る。
研究員の方は逃げようとしているようだが、おそらくブラッドさんの方に意識はない。
意識がないどころか、死んでいるようにも見える。
「……どいて」
「え?」
「どいて!!」
私の大声を聞いて反射的に手を引っ込めた2人の間を通り抜け、窓から中へ飛び込む。
「アリス!?」
キャシーの悲鳴にも似た声が届いたが、構ってはいられなかった。
消火器を持って火の海の中を駆ける。
熱い。熱い。熱い―――。
熱が私を覆い尽くし、痛みが走る。
しかしその痛みはすぐに消え、直後また痛みが走る。
私の体は再生を繰り返し、何度めかの再生の後、2人のいる場所へと辿り着いた。
「ブラッドさん!」
駆け寄って頬を叩くと、小さな呻き声と共にブラッドさんが薄く目を開ける。
酷くほっとしたが、ほっとしている場合ではない。
ブラッドさんに迫る火に向かって消火器で防炎性の液体を放ち、問い掛ける。
「酸素は足りてるの?」
「…それは、大丈夫です…。…それより、何故君が…? 」
「説明は後よ。あと少し、頑張れる?」
「……少し体が重い程度です」
ブラッドさんの無事を確認した私は、すぐさま立ち上がってマッシュルームカットの研究員を睨んだ。
「覚悟は出来てるんでしょうね?」
「は?」
「ッこの人をこんな状態にして!覚悟は出来てるんでしょうね!?」
「いや違う!オレはまだ何もしてない!彼が急に倒れたんだ!」
「その手に持ってる薬品は何なのよ!」
「掛けようとしてるところで倒れたんだよ!」
「言い訳も大概にしなさい!」
「あの人じゃない?」
「え?」
「ほら、あそこに人が2人いるでしょ」
バズ君が指差したのは、窓から見える研究所の中だった。
火が燃え盛る中、マッシュルームカットの長身の男と、先程見たブラッドとかいう人が向かい合って立っている。
「あれですわ…!もう1人は…研究員でしょうか?ファッションセンス無さ過ぎですわ!」
「初対面の相手のファッションセンス馬鹿にしちゃ駄目だよ…」
ブラッドとかいう方、どうやって外に出て来るおつもりですの?
火に囲まれていますわ。
と――そんなことを思っていた時、そのブラッドが床に倒れるのが分かった。
「え……っ…死…!?」
「よく分かんないけど、あの人はキャシーの協力者なの?」
「そ、そうですわ!どうしましょう、このままじゃ死……っていうかあれ、もう死んでません!?全然動きませんわ!」
窓を壊して入っていこうとする私の腕をバズ君が掴んで止める。
「ここからじゃ無理だよ。ていうか、どこからも無理。この火じゃ近付けない」
「でもあれ、リバディーの重要な人っぽいですわよ!?」
「リバディーは敵組織でしょ」
「でも今は協力してるんです!」
「もう死んでるっぽいけど?」
「ま、まだ分かりませんわ!早く行かなきゃ――」
「この火の中行ったらキャシーが死ぬよ。まずは消火」
「そんなことしてる暇、」
私を無理矢理引っ張って引き戻すバズ君は、落ち着いた声で言う。
「こういう状況でこそ冷静さが必要。そんなに助けに行きたいなら、遠回りしなきゃね」
バズ君の言葉によって何とか冷静になった私は、今すべきことを考えた。
火を消さなければ安全に向こうには近付けない。
となると……。
「消火器があったはずですわ!あれを持ってきましょう!」
助けられるかは分からない。
もう手遅れかもしれない。
でも、それでも――私に今できることを。
《《<--->》》
さぁ、ラストスパートだ。
《《<--->》》
物語は繋がっていく。
《《<--->》》
たとえそれが―――
《《<--->》》
『 背理法みたいでしょう? 』
《《<--->》》
episode13
《《<--->》》
〈 アリスサイド 〉
頭痛がする。
体が重い。
眩しい。
五月蝿い。
強い光が上から私を照らしている。
アラームの音も必要以上に大きい。
「悪いね、無理矢理起こしてしまって」
音が止まったかと思うと、誰かに話し掛けられた。
何度も聞いたことのある声であるのは分かるのに、声の主が誰だか分からず、私は視線だけをゆっくりと声のする方向に向けた。
私の寝転がるベッドの隣に、ジャックが座っている。
ここは……どこかのホテルの一室?
そこで状況を思い出した私は、勢いよく身を起こした。
聞きたいことは山ほどあるのに質問を整理できず、口から言葉が出て来ない私に、ジャックはゆっくりと伝えてきた。
「ブラッドに場所を教えられてね。全て終われば迎えに行く予定だが、もし自分が何らかの理由で来られなくなった場合、俺に君を迎えに行ってほしいと言われた」
「じゃあもう…」
「いや、まだ終わっていない。俺はブラッドからそれを聞いてすぐこっちに来たからね」
そう言われて顔を上げると、ジャックが私を見て苦笑していた。
ジャックがよくする苦笑だが、いつになく格好良く見えた。
「まったく、あの弟は何も分かってないな。君は最後まで尽力したがっているのに」
「…ジャック……」
「おいで。連れていくよ」
ジャックは私に手を差し伸べる。
その頼もしさに泣きそうになりながら、迷うことなく手を取った。
「小さいエマさんはどうしたの?」
「面白い言い方だね。あの子なら他の被害者と一緒に安全な場所にいるよ」
「そっちには行かないの…?折角会えたんだから様子見てたいんじゃないの?」
私の当然の疑問に対し、ジャックは愚問だとでも言うようにクスリと笑う。
「―――言っただろ?俺の生きる意味を君に譲渡すると」
ジャックに連れられて研究所の裏の出口付近まで走ると、キャシーとバズ先生が消火器を持って火を消そうとしていた。
ドアが開かないのか、この辺で唯一の窓を割ってそこから火を消している。
何故そんなことをしているのかと思ったが、2人の視線の先にいる人達を見てすぐに理由が分かった。
研究員らしき人物と、その前に倒れているのは――ブラッドさんだ。
この窓からは結構遠い。
でも、火さえ消せば走っていける距離ではある。
「アリス!?来てくれたんですの!?」
消火器を持ったままこちらを振り向くキャシーとバズ先生。
「良かった…そこに消火器が何本かあるから、手伝ってくれる?」
バズ先生が目線だけで消火器の位置を伝えてくる。
急いでジャックと私でそれを手に持ち、消火しようとしたが。
―――間に合わない。そう思った。
ここからこの4人で火を消そうとしたって間に合わない。
もうすぐ火はあの2人に燃え移る。
研究員の方は逃げようとしているようだが、おそらくブラッドさんの方に意識はない。
意識がないどころか、死んでいるようにも見える。
「……どいて」
「え?」
「どいて!!」
私の大声を聞いて反射的に手を引っ込めた2人の間を通り抜け、窓から中へ飛び込む。
「アリス!?」
キャシーの悲鳴にも似た声が届いたが、構ってはいられなかった。
消火器を持って火の海の中を駆ける。
熱い。熱い。熱い―――。
熱が私を覆い尽くし、痛みが走る。
しかしその痛みはすぐに消え、直後また痛みが走る。
私の体は再生を繰り返し、何度めかの再生の後、2人のいる場所へと辿り着いた。
「ブラッドさん!」
駆け寄って頬を叩くと、小さな呻き声と共にブラッドさんが薄く目を開ける。
酷くほっとしたが、ほっとしている場合ではない。
ブラッドさんに迫る火に向かって消火器で防炎性の液体を放ち、問い掛ける。
「酸素は足りてるの?」
「…それは、大丈夫です…。…それより、何故君が…? 」
「説明は後よ。あと少し、頑張れる?」
「……少し体が重い程度です」
ブラッドさんの無事を確認した私は、すぐさま立ち上がってマッシュルームカットの研究員を睨んだ。
「覚悟は出来てるんでしょうね?」
「は?」
「ッこの人をこんな状態にして!覚悟は出来てるんでしょうね!?」
「いや違う!オレはまだ何もしてない!彼が急に倒れたんだ!」
「その手に持ってる薬品は何なのよ!」
「掛けようとしてるところで倒れたんだよ!」
「言い訳も大概にしなさい!」