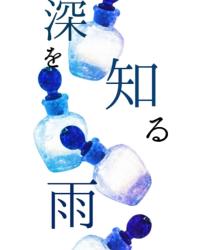episode08
〈 シャロンサイド 〉
「どうしたんすか、ボスから来るなんて」
怪我人だろうが何だろうがいつもなら呼び出すところだが、今日はそんな気分ではなかった。
待つよりも動きたい気分だった。
俺は陽の座っているベッドの隣の椅子に腰をかけ、ゆっくり伝えた。
「如月から貰った薬の副作用が出てる」
「薬って…例の試作品の…?」
俺の体でも不老不死になれるよう、如月はいくつか薬をつくってくれていた。
どうなっても責任は持たないと言いながら。
「俺は、もうすぐまともに動けなくなると思う」
だからこれは如月のせいじゃない。
リスクを理解していて手を出した俺の責任だ。
「なぁ陽、託してもいいかなぁ?」
俺の言葉の意味するところを、陽はすぐに汲み取ったようだった。
一瞬にして渋い顔になり、不快そうに俺から視線を逸らす。
「お断りします」
「頼むよ」
「……あんたは何も分かってない。この組織の連中がどれだけあんたを慕ってるか。責任ある行動を取ってください。如月に言ってどうにか、」
「俺は医者だよ?自分の体がやばいことくらい分かる。もう手遅れだ」
いくら如月でも、短期間でこんな得体の知れない副作用を抑えるのは無理だろう。
あの如月が俺のために一生懸命になるとも思えないしねぇ。
「なぁ、頼むよ。―――“クリミナルズの次期リーダー”」
陽を次のリーダーにすることは、随分前から考えていた。
今がその時だと俺は思う。
「冗談じゃないっす。そんな適当に組織を抜ける気なら、殺してでも止めますよ」
「怪我してる奴に俺を殺せると思えないけどぉ?」
リバディーの人間に刺された陽の傷は深く、まだ完治には程遠い。
本来なら痛み止めを飲んで寝ているべきだ。
「俺だって、お前を殺してでも行くよ。お前を殺して別の奴に任せる。ねぇ、どっちがいい?」
「―――…」
「お前がクリミナルズを背負うか、今死んで他の奴に背負わせるか。選ばせてあげる」
陽が俺以外にクリミナルズを任せたくないと思っていることを、俺は知ってる。
そして他の奴に任せるくらいなら自分がすると言うであろうことも知ってる。
「……ッほんと…どこまでも残酷ですね」
俺が分かっていることを分かっているらしい陽は、俺のことを残酷だと言った。
外は酷く雪が降っていた。
当然ながら空気は冷たく、吐く息が白くなる。
時間帯のせいかそもそもこの辺りには人があまりいないのか、電車は空いている様子だった。
数人程度しかいないな、と思いながら車内を見ていると、ふと見慣れた金髪を見つけた。
目を離せずにいると、向こうもこちらに気付いたようだった。
―――これはきっと、罰だ。
何故今会わなければならないのか。
何故何もかも終わりにしようとしている今、この広い世界で待ち合わせをしたわけでもなく会ってしまうのか。
何て残酷な再会なんだろう。
「ブラッドさんに会いに行くの?」
アリスは座席から立ち上がり、こちらへ近付いてくる。
しかし電車からは出ず、ホームにいる俺の方を真っ直ぐ見てくる。
「…行くよ。でも、この電車じゃない」
「そう。でも、どっちにしろここから行くには時間掛かると思うわよ。この電車も雪で暫く出発できないみたいなの」
変わらない様子で俺に接するアリスを見て胸が痛んだ。
いっそ責められた方が良かった。
話もしたくないと怒ってくれた方が楽だった。
こんなにもいつも通りなのに明確な距離を感じる。
それが実際のものなのかそのように感じるだけなのかは分からない。
しかし確実なのは、もう二度と昔のような関係には戻れないということだ。
「陽の怪我は大丈夫?」
「安静にしてたらそのうち治るよぉ」
きっとこれが最後になる。
いっそ今ここで俺の罪を告白すれば楽になれるのだろうかと、
ずっと隠しつづけてきた胸の内にある重りを吐き出してしまえばこの息苦しさから解放されるのではないかと、
そんな考えが一瞬頭を過ぎった。
「…貴方は、元気?」
「元気だよ」
でも、すぐにそんなことはできないと冷静になった。
「…なら、良かった」
少しでも―――この子の目に映る自分は、綺麗なままにしておきたい。
「ねぇシャロン、私、クリミナルズ抜けるわね」
「うん」
嗚呼、その腕を掴んで、引き寄せて、攫ってしまいたい。
この子はこれからどんな風に生きていくんだろう。
俺のいない世界で、どんな風に生きていくんだろう。
どんな人間と人生を共にするんだろう。
ずっと隣にいるのが……俺なら良かったのに。
『―――長らくお待たせしました。まもなく発車致します』
終わりを告げるアナウンスが響いた。
ドアが閉まろうとする。
引き寄せて抱き締めたいと、強い衝動が襲ってくる。
確かに手を伸ばそうとしたはずなのに、手はポケットの中にあるままだった。
同時に、ドアが閉まった。
電車の中のアリスはまだこちらを見ている。
その瞳は、拾った時とは比べものにならないほど強い輝きを持っていた。
電車がゆっくり走り出す。
人は変わる。
変わってしまう。
どんなに変わってほしくなくても。
思い出の中の彼女はもういない。
俺を頼りにしていた彼女はもういない。
―――彼女に、もう俺は必要ない。
元々冷たい冬の空気が、より冷たく感じた。
走り去る電車から目を逸らし、暗い空を見上げた―――その時だった。
アリスが換気用の窓を開けて、こちらに向かって叫んだ。
「……ッ私!クリミナルズが……貴方のつくる組織が大好きだった!」
最低な俺が罪悪感に苛まれながら作った組織を、君は好きだと言う。
「今までありがとう…!!」
最低なことをした俺に、泣きそうな顔で謝礼を述べる。
電車が走り去っていく。
見えなくなっていく。
「――――…ほんと、やめてよねぇ…」
手放したくなくなっちゃうじゃん。
柄にもなく涙が頬を伝っていることに気付き、笑ってしまった。
俺って泣けたんだ。
ちゃんと“人間らしい”とこあるんだ。
もっと早くこの人間らしさに気付けていたら、
俺にもまだ救いようはあったのかもしれない。
―――――俺も好きだったよ、
愛してた。
声にならない告白は、冬の空気に触れずに消えていった。
男はその男が自分に似ていると思っていた。
その眼が自分に似ていると思っていた。
何の確証もなくそう思っていた。