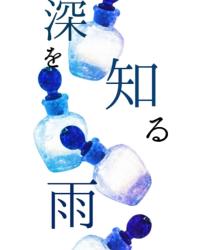どれくらい時間が経ったか分からない。
ようやく落ち着いた私は、ティッシュで鼻をかみながらお礼を言った。
「その……どうもありがとう。すっきりしたわ」
「そうかよ。礼ならキスでいいぞ?」
「馬鹿」
「つれねぇの」
「うるさい、馬鹿、馬鹿、馬鹿」
アランに泣いてるところを見られたことが何だか悔しい。
すっきりしたけど、負けたような気分だ。
「お前、子供みてぇ」
冗談っぽく笑うアランがいつもより頼もしく見えて、何だか別の人みたいに見えて、……何となく、その唇に唇を重ねた。
泣き疲れたせいで判断力が低下しているのか、スキンシップの延長のような感覚だった。
「…………は?」
軽く触れるだけですぐ離れたのだが、アランは面白いくらい驚いた顔をしている。
……勝った。
「…じゃあ、そろそろ戻るわね」
「おいコラ、待て。今の何だ」
「お礼」
「礼ってお前…」
「あなたが言ったんじゃない」
「そうだけど、」
「ラスティ君に言わせれば、キスなんてただの唇と唇の接触らしいし」
「ラスティの悪い教育に惑わされんな。いつからそんな女になったんだよ」
「自分からしたのはあなたが初めてなんだけど?」
「……状況考えて発言しろ。マジで―――抱くぞ」
アランは怒っているような焦っているような、それでいてどうしていいか分からず戸惑っているような表情で私の頬に触れる。
でも、不思議と危機感を抱かない。
「そろそろ本当に戻らなきゃ。チャロさんが待ってるわ」
「あ?帰すわけねぇだろ。大体な、お前無防備なんだよ。ノコノコ部屋ん中まで入ってきて平気な顔で電話しやがって、ここ誰の部屋だか分かってんのか?」
「あなたの部屋でしょ?」
「……俺が過去に何してたか知らねぇわけじゃねぇんだろ」
「秘書に手を出してたって話?」
「知ってんなら、」
「でも私には何もしない気がするわ」
「……」
「アランは優しいもの」
その一言でアランは舌打ちし、頭を掻いた。
「あーーー…くそ、分かったよ。部屋まで連れてってやるからさっさと寝ろ」
勝った。
アランは手が早いっていう周りの意見はやっぱり間違いだと思った。
アランは同意無しに行為に及ぶような人間じゃない。
同意の上だからって女の子に酷いことしてたのはどうかと思うけど、今のアランは変わってる。
私が立ち上がると、アランも立ち上がる。
「優秀組3人全員とキスした女なんて、お前くらいだろうな」
アランは怒っているくせに可笑しそうに笑って、ちゃんと私をチャロさんの部屋まで送ってくれた。
男は体の異変に気付いた。
痛みに鈍いその男は、それに気付くまで時間が掛かった。
男にはそれが体の痛みなのか心の痛みなのか分からなかった。
■
episode04
〈 ラスティサイド 〉
「ねぇねぇ、知ってること全部教えてよ」
木製の椅子に縛り付けた女は、目隠しされたまま涙を流している。
「あんた……ッ新入りのくせにこんなことしていいと思ってんの!?」
保身のためならペラペラ情報を吐くだろうと思っていたが、この女は意外と口がかたいようだ。
「質問してるのはこっちだよ?全部教えるのが嫌ならあのデータを保護してるパスワードだけでも答えてくれる?」
「教えるわけないでしょ!?さっさと解放しなさいよ!!!」
「僕だって解放してあげたいよ?もう6時間も経ってるし、定期的に様子見に来るのも面倒だしね。でもオバサン何にも話してくれないじゃん」
「話さないって分かってんならこの縄を外しなさい!!」
「それはやだ。」
せめて少しでも情報を引き出したい。
まぁこの煩い女に大した使い道があるとは思えないし、それほど期待はしてないけど。
「トイレに行きたいんだけど!?」
「あ、そう。どうぞ?」
「………ハァ!?」
「この部屋もう使われてないみたいだし、君がそこを汚そうが僕はどうでもいいから。我慢できないならどーぞ」
「……ッ…」
「あ、そーだ。オバサンお腹空いてると思って、ご飯も持ってきてあげたんだよ」
残飯を入れた皿を持って女に近付き、
「僕って優しいでしょ?感謝してね」
女の頭の上でそれを傾けた。
「熱……ッ」
勿論温めておいてあげたアッツアツのご飯。
「さてと。ご飯もあげてやったんだし、お礼にパスワード教えてくんない?」
「……っ…ひ、酷い……」
「うん、そうだね。でも酷い目に合うのはオバサンが何も話さないからだよ」
「だ、だから、話す気はないって、」
――ガンッと勢い良く女の座っている椅子を蹴飛ばした。
おかげで椅子が倒れ、女は頭を床に強く打ち苦痛の声を上げる。
「優しく聞いてやってるうちに答えろよ」
研究員としての仕事もあるから、ゆっくり拷問している暇はない。
拷問し出すと萌えてきて止まらなくなる性分だから、仕方なくソフトな聞き方をしてやってるってのに。
「答えてさえくれれば楽にしてあげるって言ってんの」
このままじゃ気分が乗ってきてハードなやり方になっちゃうかもしんないじゃん。どうしてくれんの?
「3秒以内に答えて?答えなかったら指の骨折っていくね」
「ひッ…」
「はいさーん、にーい、」
「……ッ……」
「いー…」
「分かった!言う!言うから!!」
なーんだ、言うんだ。つまんないの。
口かたいって言ってもこの程度か。
拷問経験のない単なる研究員なんだから当然っちゃ当然だけど。
ガクガク震えながらパスワードを答えた女に、
「ありがと」
そうお礼を言って音もなく即死させてあげた。
この研究所の人間は残さず殺す予定なのだから、今死ぬか後で死ぬかだ。
爆弾は既に用意している。
ある程度準備が整えば、この研究所ごと爆破するつもりだ。
研究所内で殺した人間の死体は処分していない。というか、できない。
死体を処分して行方不明扱いにするのがベストなのだが、研究員として限られた動きしかできない今は、隠すと言っても研究所内の限られた空間にしか死体を置けない。
そんな中途半端な隠し方だから次々と死体が発見されて、研究員の間に警戒が広がっている。
「最近この研究所で連続殺人が行われているの……」
当然それは如月の耳にも入ったらしく、研究室に戻るとすぐさまそう報告された。
こんな広い研究所でも、噂が広まるのは早いらしい。
「へぇ?物騒だね」
「あなたも警戒した方がいい……。警備は強化したけど、殺人鬼がどう出てくるか分からない……」
ようやく落ち着いた私は、ティッシュで鼻をかみながらお礼を言った。
「その……どうもありがとう。すっきりしたわ」
「そうかよ。礼ならキスでいいぞ?」
「馬鹿」
「つれねぇの」
「うるさい、馬鹿、馬鹿、馬鹿」
アランに泣いてるところを見られたことが何だか悔しい。
すっきりしたけど、負けたような気分だ。
「お前、子供みてぇ」
冗談っぽく笑うアランがいつもより頼もしく見えて、何だか別の人みたいに見えて、……何となく、その唇に唇を重ねた。
泣き疲れたせいで判断力が低下しているのか、スキンシップの延長のような感覚だった。
「…………は?」
軽く触れるだけですぐ離れたのだが、アランは面白いくらい驚いた顔をしている。
……勝った。
「…じゃあ、そろそろ戻るわね」
「おいコラ、待て。今の何だ」
「お礼」
「礼ってお前…」
「あなたが言ったんじゃない」
「そうだけど、」
「ラスティ君に言わせれば、キスなんてただの唇と唇の接触らしいし」
「ラスティの悪い教育に惑わされんな。いつからそんな女になったんだよ」
「自分からしたのはあなたが初めてなんだけど?」
「……状況考えて発言しろ。マジで―――抱くぞ」
アランは怒っているような焦っているような、それでいてどうしていいか分からず戸惑っているような表情で私の頬に触れる。
でも、不思議と危機感を抱かない。
「そろそろ本当に戻らなきゃ。チャロさんが待ってるわ」
「あ?帰すわけねぇだろ。大体な、お前無防備なんだよ。ノコノコ部屋ん中まで入ってきて平気な顔で電話しやがって、ここ誰の部屋だか分かってんのか?」
「あなたの部屋でしょ?」
「……俺が過去に何してたか知らねぇわけじゃねぇんだろ」
「秘書に手を出してたって話?」
「知ってんなら、」
「でも私には何もしない気がするわ」
「……」
「アランは優しいもの」
その一言でアランは舌打ちし、頭を掻いた。
「あーーー…くそ、分かったよ。部屋まで連れてってやるからさっさと寝ろ」
勝った。
アランは手が早いっていう周りの意見はやっぱり間違いだと思った。
アランは同意無しに行為に及ぶような人間じゃない。
同意の上だからって女の子に酷いことしてたのはどうかと思うけど、今のアランは変わってる。
私が立ち上がると、アランも立ち上がる。
「優秀組3人全員とキスした女なんて、お前くらいだろうな」
アランは怒っているくせに可笑しそうに笑って、ちゃんと私をチャロさんの部屋まで送ってくれた。
男は体の異変に気付いた。
痛みに鈍いその男は、それに気付くまで時間が掛かった。
男にはそれが体の痛みなのか心の痛みなのか分からなかった。
■
episode04
〈 ラスティサイド 〉
「ねぇねぇ、知ってること全部教えてよ」
木製の椅子に縛り付けた女は、目隠しされたまま涙を流している。
「あんた……ッ新入りのくせにこんなことしていいと思ってんの!?」
保身のためならペラペラ情報を吐くだろうと思っていたが、この女は意外と口がかたいようだ。
「質問してるのはこっちだよ?全部教えるのが嫌ならあのデータを保護してるパスワードだけでも答えてくれる?」
「教えるわけないでしょ!?さっさと解放しなさいよ!!!」
「僕だって解放してあげたいよ?もう6時間も経ってるし、定期的に様子見に来るのも面倒だしね。でもオバサン何にも話してくれないじゃん」
「話さないって分かってんならこの縄を外しなさい!!」
「それはやだ。」
せめて少しでも情報を引き出したい。
まぁこの煩い女に大した使い道があるとは思えないし、それほど期待はしてないけど。
「トイレに行きたいんだけど!?」
「あ、そう。どうぞ?」
「………ハァ!?」
「この部屋もう使われてないみたいだし、君がそこを汚そうが僕はどうでもいいから。我慢できないならどーぞ」
「……ッ…」
「あ、そーだ。オバサンお腹空いてると思って、ご飯も持ってきてあげたんだよ」
残飯を入れた皿を持って女に近付き、
「僕って優しいでしょ?感謝してね」
女の頭の上でそれを傾けた。
「熱……ッ」
勿論温めておいてあげたアッツアツのご飯。
「さてと。ご飯もあげてやったんだし、お礼にパスワード教えてくんない?」
「……っ…ひ、酷い……」
「うん、そうだね。でも酷い目に合うのはオバサンが何も話さないからだよ」
「だ、だから、話す気はないって、」
――ガンッと勢い良く女の座っている椅子を蹴飛ばした。
おかげで椅子が倒れ、女は頭を床に強く打ち苦痛の声を上げる。
「優しく聞いてやってるうちに答えろよ」
研究員としての仕事もあるから、ゆっくり拷問している暇はない。
拷問し出すと萌えてきて止まらなくなる性分だから、仕方なくソフトな聞き方をしてやってるってのに。
「答えてさえくれれば楽にしてあげるって言ってんの」
このままじゃ気分が乗ってきてハードなやり方になっちゃうかもしんないじゃん。どうしてくれんの?
「3秒以内に答えて?答えなかったら指の骨折っていくね」
「ひッ…」
「はいさーん、にーい、」
「……ッ……」
「いー…」
「分かった!言う!言うから!!」
なーんだ、言うんだ。つまんないの。
口かたいって言ってもこの程度か。
拷問経験のない単なる研究員なんだから当然っちゃ当然だけど。
ガクガク震えながらパスワードを答えた女に、
「ありがと」
そうお礼を言って音もなく即死させてあげた。
この研究所の人間は残さず殺す予定なのだから、今死ぬか後で死ぬかだ。
爆弾は既に用意している。
ある程度準備が整えば、この研究所ごと爆破するつもりだ。
研究所内で殺した人間の死体は処分していない。というか、できない。
死体を処分して行方不明扱いにするのがベストなのだが、研究員として限られた動きしかできない今は、隠すと言っても研究所内の限られた空間にしか死体を置けない。
そんな中途半端な隠し方だから次々と死体が発見されて、研究員の間に警戒が広がっている。
「最近この研究所で連続殺人が行われているの……」
当然それは如月の耳にも入ったらしく、研究室に戻るとすぐさまそう報告された。
こんな広い研究所でも、噂が広まるのは早いらしい。
「へぇ?物騒だね」
「あなたも警戒した方がいい……。警備は強化したけど、殺人鬼がどう出てくるか分からない……」