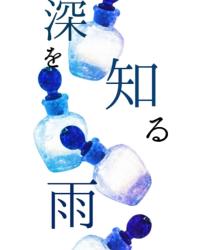キャシーに電話して、今他の人の部屋にいることを伝えた。
シャロンと同じ部屋にいるのは気まずいから、別の人の部屋で生活するつもりだとキャシーに話した。
連絡しておかないと、キャシーは私を探し続けるかもしれないから。
そうなると危険だ。
何かあった時のために部屋の番号も教えた。
「シャロン達には、部屋の番号は内緒にしてもらえるかしら。安全な知り合いの部屋に泊まってるとだけ言っておいて」
『…分かりましたわ。伝えておきます』
「ありがとう。それじゃあ…」
『…あ…待ってくださいな、アリス』
「どうしたの?」
『その……今シャロン様を庇うようなことを言われるのは不快だとは思うのですが、言っておきたくて…、…シャロン様は、ただただ不器用なんだと思いますわ…』
私を勝手に恋敵だと言うキャシーにとって、私とシャロンの仲が悪くなることはチャンスであるはずなのに、キャシーは私たちの関係の悪化を心配しているようだった。
『正直、シャロン様がしてきたことを聞いた時、そのことに関してだけは酷い人だと思いました。アリスがショックを受けるのも、許せないのも分かります。でも…誰かがあの方を変えられるとしたら、それはあなたしかいないと思うんです。あの方がうまく表現できない愛情のはけ口としている唯一の相手が、きっとあなただから』
長い時間シャロンの傍にいた私より、キャシーの方がシャロンのことを分かっているんじゃないかと思った。
私はシャロンのことを何も知らないんじゃないかと思った。
私が今まで見てきたシャロンは、誰だったんだろうか。
「………今はやっぱり許せない。もう少し時間をくれないかしら」
『…ええ、それはそうだと思います。裏切りと言っていいほどのことをされたんですから。今は距離を置いてじっくり考える時ですわ。シャロン様もアリスがいなくなればさすがに反省するでしょうし』
シャロンが反省している姿なんて想像つかないわね…と思っていると、キャシーは先程よりも弱々しい声で聞いてきた。
『……戻ってきますわよね?』
「え?」
『…この、組織に。…戻ってきますわよね…?』
「……」
『…これっきりなんてことありませんわよね…?』
「……ちょっと、泣いてるの?」
『泣いてませんわっ!!!』
「そ、そう…」
『……安全な知り合いって、リバディーの人でしょう?』
「…ええ」
『…いつ戻ってきますの?べ、別に急かしてるんじゃありませんけど…シャロン様と距離を置きたいなら私の部屋もありますし……』
「…ごめんなさい。どれくらいで気持ちの整理がつくかは、正直まだ分からない。でも…組織に戻る戻らない関係なく、キャシー達と縁を切ることはないと思うわよ。バズ先生にも、まだ教えてほしいことが沢山あるし」
『そう…ですの。………ま、まぁ…それなら良しとしますわ』
「キャシーって本当私のこと好きよね」
『ッな、何言ってますの!?そんなことは!!!全然!!!全く!!!ないですわ!!!!べ、別にあなたと会えなくても困らないのですけれどやはりいつもいるはずの人間がいないというのはそれが誰であっても寂しいというかいや寂しいってそうじゃなくてえっと、そもそも私とあなたはライバ、』
プツリ。
長くなりそうなので通話を切り、後ろにいる男に目を向けた。
「もう終わりましたか?」
ブラッドさんはベッドに腰をかけている私の手から電話を奪い取ってちゅっと首筋にキスをし、愛しそうにこちらを見つめてくる。
「…ちょっと……近い」
熱っぽい視線を送ってくるブラッドさんは必要以上に私に密着している。
「すみません…あまりに久しぶりなのでつい男としての本能が」
「お、抑えて」
何やら静かに興奮している様子のブラッドさんから少し距離を取り、我ながら何をしているのだろうと反省した。
さっきキャシーが言ったから気付いたけど、そう言われてみればキャシーの部屋に泊まるという手もあったのだ。
いやでも、キャシーの部屋だとシャロンが簡単に来れるし…今はシャロンの手の届かないところにいたいし。
心の中で精一杯の言い訳をして、部屋にあったお水を飲んだ。
―――1時間ほど前。
「するなら今よ。慰めて。あなたに抱き締められるの――好きなの」
下を向いて言ったのでブラッドさんの表情は分からない。
少しの沈黙の後、ブラッドさんはふざけたことを抜かす。
「…もう一度言ってくれませんか」
「……二度は言わないわ」
「聞こえなかったんです」
「ッ抱きしめてって言ったのよ!1回で聞き取りなさいよ!」
半ば叫ぶように言った私にブラッドさんはふふっと柔らかく笑って、
「はい、分かりました」
私を優しく抱きしめた。
「君におねだりしてもらえるなんて、俺は夢でも見てるんでしょうか?」
「撫でて」
「え?」
「……」
「………今、撫でてって言いました?」
「だから、二度は言わないって言ってるでしょ」
「…今日の君は甘えたさんですね。可愛い、本当可愛い……好きです…」
甘い声で狂おしそうに囁きながら撫でてくれるブラッドさんに安心している私は、確かに冷静じゃないと思う。
「俺がこうすることで君の悲しみが消えるなら、いくらでもこうしていますから、してほしいことがあれば何でも言ってくださいね」
「…じゃあ、キス」
「え、…」
「冗談よ。…間抜け面」
フッと得意げに笑ってやると、ブラッドさんは深い溜め息を吐いた。
「君は俺を厄介だと言いますが、そうさせているのは君なんですよ?君がそんな風に俺を弄ぶからいけない」
「あら、嫌なの?」
「…まさか。君になら何をされたって嬉しいです」
「重症ね」
くすくす笑えば、ブラッドさんも嬉しそうに笑う。
「良かった。少し元気が出てきたみたいですね」
その優しい笑顔を見て、シャロンとは違う笑い方を見て…この人は本当に私のことを考えてくれてるんだと思った。
「………あなたの気持ち、利用してごめんなさい」
急に罪悪感が湧いてきて、思わず敵にする必要のない謝罪をしてしまった。
「そんなの気にしないでください。人を利用すべき時に利用しようとするのは君の個性ですし、賢い判断です」
利用しようとしたことは今だけじゃなく以前もあった。
なのにこの人は、何でこんなに変わらないんだろう。
どうしてずっと私に優しくしてくれるんだろう。
何でそんなに……私のこと好きなのよ。
「……そろそろ行かなくちゃ」
この温もりから離れることが寂しいと思う自分がいる。
それは、この手を離したとして行く場所がないからだと思う。
「どこへ行くんですか」
しかし、離れようとする私を、ブラッドさんが強い力で抱きしめた。
「君を悲しませるような男の元へ行くんですか?」
「………っ」
シャロンと同じ部屋にいるのは気まずいから、別の人の部屋で生活するつもりだとキャシーに話した。
連絡しておかないと、キャシーは私を探し続けるかもしれないから。
そうなると危険だ。
何かあった時のために部屋の番号も教えた。
「シャロン達には、部屋の番号は内緒にしてもらえるかしら。安全な知り合いの部屋に泊まってるとだけ言っておいて」
『…分かりましたわ。伝えておきます』
「ありがとう。それじゃあ…」
『…あ…待ってくださいな、アリス』
「どうしたの?」
『その……今シャロン様を庇うようなことを言われるのは不快だとは思うのですが、言っておきたくて…、…シャロン様は、ただただ不器用なんだと思いますわ…』
私を勝手に恋敵だと言うキャシーにとって、私とシャロンの仲が悪くなることはチャンスであるはずなのに、キャシーは私たちの関係の悪化を心配しているようだった。
『正直、シャロン様がしてきたことを聞いた時、そのことに関してだけは酷い人だと思いました。アリスがショックを受けるのも、許せないのも分かります。でも…誰かがあの方を変えられるとしたら、それはあなたしかいないと思うんです。あの方がうまく表現できない愛情のはけ口としている唯一の相手が、きっとあなただから』
長い時間シャロンの傍にいた私より、キャシーの方がシャロンのことを分かっているんじゃないかと思った。
私はシャロンのことを何も知らないんじゃないかと思った。
私が今まで見てきたシャロンは、誰だったんだろうか。
「………今はやっぱり許せない。もう少し時間をくれないかしら」
『…ええ、それはそうだと思います。裏切りと言っていいほどのことをされたんですから。今は距離を置いてじっくり考える時ですわ。シャロン様もアリスがいなくなればさすがに反省するでしょうし』
シャロンが反省している姿なんて想像つかないわね…と思っていると、キャシーは先程よりも弱々しい声で聞いてきた。
『……戻ってきますわよね?』
「え?」
『…この、組織に。…戻ってきますわよね…?』
「……」
『…これっきりなんてことありませんわよね…?』
「……ちょっと、泣いてるの?」
『泣いてませんわっ!!!』
「そ、そう…」
『……安全な知り合いって、リバディーの人でしょう?』
「…ええ」
『…いつ戻ってきますの?べ、別に急かしてるんじゃありませんけど…シャロン様と距離を置きたいなら私の部屋もありますし……』
「…ごめんなさい。どれくらいで気持ちの整理がつくかは、正直まだ分からない。でも…組織に戻る戻らない関係なく、キャシー達と縁を切ることはないと思うわよ。バズ先生にも、まだ教えてほしいことが沢山あるし」
『そう…ですの。………ま、まぁ…それなら良しとしますわ』
「キャシーって本当私のこと好きよね」
『ッな、何言ってますの!?そんなことは!!!全然!!!全く!!!ないですわ!!!!べ、別にあなたと会えなくても困らないのですけれどやはりいつもいるはずの人間がいないというのはそれが誰であっても寂しいというかいや寂しいってそうじゃなくてえっと、そもそも私とあなたはライバ、』
プツリ。
長くなりそうなので通話を切り、後ろにいる男に目を向けた。
「もう終わりましたか?」
ブラッドさんはベッドに腰をかけている私の手から電話を奪い取ってちゅっと首筋にキスをし、愛しそうにこちらを見つめてくる。
「…ちょっと……近い」
熱っぽい視線を送ってくるブラッドさんは必要以上に私に密着している。
「すみません…あまりに久しぶりなのでつい男としての本能が」
「お、抑えて」
何やら静かに興奮している様子のブラッドさんから少し距離を取り、我ながら何をしているのだろうと反省した。
さっきキャシーが言ったから気付いたけど、そう言われてみればキャシーの部屋に泊まるという手もあったのだ。
いやでも、キャシーの部屋だとシャロンが簡単に来れるし…今はシャロンの手の届かないところにいたいし。
心の中で精一杯の言い訳をして、部屋にあったお水を飲んだ。
―――1時間ほど前。
「するなら今よ。慰めて。あなたに抱き締められるの――好きなの」
下を向いて言ったのでブラッドさんの表情は分からない。
少しの沈黙の後、ブラッドさんはふざけたことを抜かす。
「…もう一度言ってくれませんか」
「……二度は言わないわ」
「聞こえなかったんです」
「ッ抱きしめてって言ったのよ!1回で聞き取りなさいよ!」
半ば叫ぶように言った私にブラッドさんはふふっと柔らかく笑って、
「はい、分かりました」
私を優しく抱きしめた。
「君におねだりしてもらえるなんて、俺は夢でも見てるんでしょうか?」
「撫でて」
「え?」
「……」
「………今、撫でてって言いました?」
「だから、二度は言わないって言ってるでしょ」
「…今日の君は甘えたさんですね。可愛い、本当可愛い……好きです…」
甘い声で狂おしそうに囁きながら撫でてくれるブラッドさんに安心している私は、確かに冷静じゃないと思う。
「俺がこうすることで君の悲しみが消えるなら、いくらでもこうしていますから、してほしいことがあれば何でも言ってくださいね」
「…じゃあ、キス」
「え、…」
「冗談よ。…間抜け面」
フッと得意げに笑ってやると、ブラッドさんは深い溜め息を吐いた。
「君は俺を厄介だと言いますが、そうさせているのは君なんですよ?君がそんな風に俺を弄ぶからいけない」
「あら、嫌なの?」
「…まさか。君になら何をされたって嬉しいです」
「重症ね」
くすくす笑えば、ブラッドさんも嬉しそうに笑う。
「良かった。少し元気が出てきたみたいですね」
その優しい笑顔を見て、シャロンとは違う笑い方を見て…この人は本当に私のことを考えてくれてるんだと思った。
「………あなたの気持ち、利用してごめんなさい」
急に罪悪感が湧いてきて、思わず敵にする必要のない謝罪をしてしまった。
「そんなの気にしないでください。人を利用すべき時に利用しようとするのは君の個性ですし、賢い判断です」
利用しようとしたことは今だけじゃなく以前もあった。
なのにこの人は、何でこんなに変わらないんだろう。
どうしてずっと私に優しくしてくれるんだろう。
何でそんなに……私のこと好きなのよ。
「……そろそろ行かなくちゃ」
この温もりから離れることが寂しいと思う自分がいる。
それは、この手を離したとして行く場所がないからだと思う。
「どこへ行くんですか」
しかし、離れようとする私を、ブラッドさんが強い力で抱きしめた。
「君を悲しませるような男の元へ行くんですか?」
「………っ」