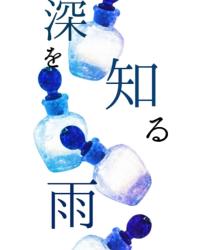れんを助けなければと思うのに、俺は何故かれんではない人間のことを考えていた。
アリスに俺の過去がバレる可能性があるとすれば、れんからだ。
『私…あの研究所の連中みたいに、人を必要以上に苦しめた後で殺す人間は嫌い』
れんがいなくなれば、俺は彼女に嫌われなくて済む
と、
魔物が俺の傍で囁いた。
そしてたどり着いてはいけない結論に達したのだ。
―――どうして組織を出て行った人間の犯した罪の尻拭いまで俺がしなけりゃいけない?
今でも覚えている。
これが俺だった。
この時の俺の冷たい心こそが俺という人間の本質だった。
愚かな俺は、後に来る冷えた罪悪感の恐ろしさを知らなかった。
罪悪なんて、それが初めて襲ってくるまで知らなかった。
何人も殺してきた俺がこのことに関してだけは重たく感じるようになったのだ。
それは今でも変わらない。
しかし例え今あの時間に戻れたとしても、別の道を辿る自信はない。
またあの冷たい心が怠惰を許すに違いない。
俺という人間はどう足掻いたって変えられない。
俺の中に魔物が住んでいると言っても過言ではないのだ。
その魔物は時折俺の体を乗っ取っては、お前はオレだと言って笑うのだ。
1時間後、電話がかかってきた。
画面に映るれんは疲弊しきっていた。
相当暴力を振るわれたのか、血を流し虚ろな目をしている。
それを見ても俺は何も感じなかったのだ。
守るべき幼い子供が、誕生日だと言う子供が酷い目にあっていても、俺に行動を起こさせるほどの感情は湧いてこなかったのだ。
通話はすぐに切られた。
二時間経とうとした頃、また電話がかかってきた。
『シャロンさ……たす、け、て…………』
縛られたままのれんが俺に助けを求めている。
『もしもし?今どこにいんのー?もう来てる?』
画面に顔を出したガキが、愉しそうに聞いてくる。
「自分の部屋」
淡々と答えた俺に、電話の向こうのガキは吹き出した。
『マッジで言ってんの?ウケんだけど。お前本当に血も涙もないね』
『…ッシャロンさん!?シャロンさんシャロンさんっ………助けて!助けて……』
「ごめんねぇ、れん」
包み隠さず言ってしまうなら、俺はこの時、れんに対して憐憫の情すら抱いていなかった。
『シャロンさ……』
「人間はいつか死ぬものだからさ」
画面の向こうにいるれんが、妙に画面の中だけの存在のように思われたのだ。
この世に存在しない物に助けを乞われたってどうしようもない。
『……っうそだ!嘘だ嘘だ嘘だ嘘だ嘘だ!シャロンさんは助けてくれるよ!ねぇそうなんでしょ!?だってシャロンさん優しいもん!』
画面の向こうで、ガキが凶器を持ち上げた。
『―――――信じてたのに!!』
ドシャッと、人を殴り殺す時の、聞き慣れた音がした。
さっきまで俺に向かって叫んでいたれんは動かなくなっていた。
『あーあ。見殺しかー』
ガキはつまらなさそうに凶器を置く。
『まーそういう奴だとは思ってたけどね。この子も、信じちゃって馬鹿みたい』
「……」
『僕が殺しといてこんなこと言うのも変だけど、この子ずっとお前のこと待ってたよ?シャロンさんなら絶対助けに来てくれる、お前なんかシャロンさんがすぐやっつけるってずーーーっと言ってた。どんなに殴っても敵意むき出しの目で見てくるからさ、久しぶりにゾクゾクしたなぁ』
「……」
『ねぇ、可哀想だって思わない?小さい子供が目の前で死んでどんな気持ち?つーかお前って感情あんの?そんな風に麻痺してるから僕の妹にあんな猛毒打てたのかな?……なぁ、おい。聞いてんだろうが。答えろよ』
俺は携帯を机に置き、懐から銃を取り出した。
「言いたいことはそれだけぇ?」
『……は?』
「じゃーね、バイバイ」
その銃で携帯を撃ち、窓から捨てた。
そしてその時初めて、れんが死んだことを実感したのだ。
それから俺は、組織の子供にそれまで以上に優しく接するようになった。
俺が少しでも間違った触れ方をすれば壊してしまいそうで。
本当は子供達に触れる資格なんてないのに、俺は毎日偽りの仮面で彼らと接する。
俺に擦り寄ってくる子供達に、声を大にして言いたかった。
『お前ら俺がどういう人間か知ってんの?』
『やたら懐いてくるけど、俺はお前らが思ってるほど優しくないんだよ?』
『哀れだねぇ。こんな大人に騙されて』
『お前らもれんと一緒だよ。いざという時に裏切られる』
でも言えなかった。
俺は自分の罪を消そうとしていた。
自分が組織の子供達を大切にする人間だと、自分さえも騙して楽になりたかった。
「れん、最近来ないわね」
俺の膝の上にいるアリスが、考え事をしていた俺を見上げてふと言う。
「あいつ、この組織やめたよ」
「えっそうなの?」
「預かるって言う人が出てきたからねぇ。今は幸せに暮らしてるんじゃない?」
最低なことは分かってる。
俺は誰にも自分の罪を告白するつもりがなかった。
いつも一番近くにいるアリスも例外ではなかった。
罪悪感に苛まれる日々の中、アリスだけが俺の癒しだった。
俺はアリスが自分から離れることを許せなくなった。
アリスがバズに勉強を教えてもらっている時も、同じ部屋にいさせなければ気が済まなくなった。
そんな俺の変化を感じ取ったバズは不思議そうにしていた。
「…ねぇアリス」
「何?」
「アリスは俺のこと、良い人だと思う?悪い人だと思う?」
アリスの耳についたピアスを指でなぞりながら問う。
俺の開けた穴に、俺と同じピアスが入っている。
「良い人なんじゃないの?知らないけど」
質問の意図をよく分かっていない様子のアリスだったが、俺はその言葉でいくらか気持ちが楽になった。
「…アリスが言うなら、そうなんだろうねぇ」
そうだ、この子に愛情を注げばいい。
死んでしまったれんの分、この子を愛せばいい。
そうすればきっと――――俺は罪を忘れられる。
俺は許される。
《《<--->》》
「陽、如月が指定した時刻と場所のメモ、まだ持ってる?」
《《<--->》》
俺はただアリスを愛してるだけなのに、
《《<--->》》
みんな俺のこと歪んでるって言うんだ。
「まさか、本当に来るとは思わなかった……」
隣町の人の少ない喫茶店。
俺が約束の場所に足を運んだことには、呼んだ本人さえ驚いていた。
大抵あまり表情の変化のない如月だが、驚いているのは分かる。
いや、こうも簡単にやって来たことについて怪しんでるのか。
「護衛はつけさせてもらったよぉ」
俺は隣にいる陽の肩に手を回して言った。
如月が今何をしているのか知らなければ、何を仕掛けてくるかも分からない。
アリスに俺の過去がバレる可能性があるとすれば、れんからだ。
『私…あの研究所の連中みたいに、人を必要以上に苦しめた後で殺す人間は嫌い』
れんがいなくなれば、俺は彼女に嫌われなくて済む
と、
魔物が俺の傍で囁いた。
そしてたどり着いてはいけない結論に達したのだ。
―――どうして組織を出て行った人間の犯した罪の尻拭いまで俺がしなけりゃいけない?
今でも覚えている。
これが俺だった。
この時の俺の冷たい心こそが俺という人間の本質だった。
愚かな俺は、後に来る冷えた罪悪感の恐ろしさを知らなかった。
罪悪なんて、それが初めて襲ってくるまで知らなかった。
何人も殺してきた俺がこのことに関してだけは重たく感じるようになったのだ。
それは今でも変わらない。
しかし例え今あの時間に戻れたとしても、別の道を辿る自信はない。
またあの冷たい心が怠惰を許すに違いない。
俺という人間はどう足掻いたって変えられない。
俺の中に魔物が住んでいると言っても過言ではないのだ。
その魔物は時折俺の体を乗っ取っては、お前はオレだと言って笑うのだ。
1時間後、電話がかかってきた。
画面に映るれんは疲弊しきっていた。
相当暴力を振るわれたのか、血を流し虚ろな目をしている。
それを見ても俺は何も感じなかったのだ。
守るべき幼い子供が、誕生日だと言う子供が酷い目にあっていても、俺に行動を起こさせるほどの感情は湧いてこなかったのだ。
通話はすぐに切られた。
二時間経とうとした頃、また電話がかかってきた。
『シャロンさ……たす、け、て…………』
縛られたままのれんが俺に助けを求めている。
『もしもし?今どこにいんのー?もう来てる?』
画面に顔を出したガキが、愉しそうに聞いてくる。
「自分の部屋」
淡々と答えた俺に、電話の向こうのガキは吹き出した。
『マッジで言ってんの?ウケんだけど。お前本当に血も涙もないね』
『…ッシャロンさん!?シャロンさんシャロンさんっ………助けて!助けて……』
「ごめんねぇ、れん」
包み隠さず言ってしまうなら、俺はこの時、れんに対して憐憫の情すら抱いていなかった。
『シャロンさ……』
「人間はいつか死ぬものだからさ」
画面の向こうにいるれんが、妙に画面の中だけの存在のように思われたのだ。
この世に存在しない物に助けを乞われたってどうしようもない。
『……っうそだ!嘘だ嘘だ嘘だ嘘だ嘘だ!シャロンさんは助けてくれるよ!ねぇそうなんでしょ!?だってシャロンさん優しいもん!』
画面の向こうで、ガキが凶器を持ち上げた。
『―――――信じてたのに!!』
ドシャッと、人を殴り殺す時の、聞き慣れた音がした。
さっきまで俺に向かって叫んでいたれんは動かなくなっていた。
『あーあ。見殺しかー』
ガキはつまらなさそうに凶器を置く。
『まーそういう奴だとは思ってたけどね。この子も、信じちゃって馬鹿みたい』
「……」
『僕が殺しといてこんなこと言うのも変だけど、この子ずっとお前のこと待ってたよ?シャロンさんなら絶対助けに来てくれる、お前なんかシャロンさんがすぐやっつけるってずーーーっと言ってた。どんなに殴っても敵意むき出しの目で見てくるからさ、久しぶりにゾクゾクしたなぁ』
「……」
『ねぇ、可哀想だって思わない?小さい子供が目の前で死んでどんな気持ち?つーかお前って感情あんの?そんな風に麻痺してるから僕の妹にあんな猛毒打てたのかな?……なぁ、おい。聞いてんだろうが。答えろよ』
俺は携帯を机に置き、懐から銃を取り出した。
「言いたいことはそれだけぇ?」
『……は?』
「じゃーね、バイバイ」
その銃で携帯を撃ち、窓から捨てた。
そしてその時初めて、れんが死んだことを実感したのだ。
それから俺は、組織の子供にそれまで以上に優しく接するようになった。
俺が少しでも間違った触れ方をすれば壊してしまいそうで。
本当は子供達に触れる資格なんてないのに、俺は毎日偽りの仮面で彼らと接する。
俺に擦り寄ってくる子供達に、声を大にして言いたかった。
『お前ら俺がどういう人間か知ってんの?』
『やたら懐いてくるけど、俺はお前らが思ってるほど優しくないんだよ?』
『哀れだねぇ。こんな大人に騙されて』
『お前らもれんと一緒だよ。いざという時に裏切られる』
でも言えなかった。
俺は自分の罪を消そうとしていた。
自分が組織の子供達を大切にする人間だと、自分さえも騙して楽になりたかった。
「れん、最近来ないわね」
俺の膝の上にいるアリスが、考え事をしていた俺を見上げてふと言う。
「あいつ、この組織やめたよ」
「えっそうなの?」
「預かるって言う人が出てきたからねぇ。今は幸せに暮らしてるんじゃない?」
最低なことは分かってる。
俺は誰にも自分の罪を告白するつもりがなかった。
いつも一番近くにいるアリスも例外ではなかった。
罪悪感に苛まれる日々の中、アリスだけが俺の癒しだった。
俺はアリスが自分から離れることを許せなくなった。
アリスがバズに勉強を教えてもらっている時も、同じ部屋にいさせなければ気が済まなくなった。
そんな俺の変化を感じ取ったバズは不思議そうにしていた。
「…ねぇアリス」
「何?」
「アリスは俺のこと、良い人だと思う?悪い人だと思う?」
アリスの耳についたピアスを指でなぞりながら問う。
俺の開けた穴に、俺と同じピアスが入っている。
「良い人なんじゃないの?知らないけど」
質問の意図をよく分かっていない様子のアリスだったが、俺はその言葉でいくらか気持ちが楽になった。
「…アリスが言うなら、そうなんだろうねぇ」
そうだ、この子に愛情を注げばいい。
死んでしまったれんの分、この子を愛せばいい。
そうすればきっと――――俺は罪を忘れられる。
俺は許される。
《《<--->》》
「陽、如月が指定した時刻と場所のメモ、まだ持ってる?」
《《<--->》》
俺はただアリスを愛してるだけなのに、
《《<--->》》
みんな俺のこと歪んでるって言うんだ。
「まさか、本当に来るとは思わなかった……」
隣町の人の少ない喫茶店。
俺が約束の場所に足を運んだことには、呼んだ本人さえ驚いていた。
大抵あまり表情の変化のない如月だが、驚いているのは分かる。
いや、こうも簡単にやって来たことについて怪しんでるのか。
「護衛はつけさせてもらったよぉ」
俺は隣にいる陽の肩に手を回して言った。
如月が今何をしているのか知らなければ、何を仕掛けてくるかも分からない。