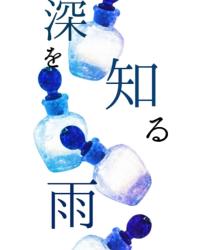――アタシは目の前のこの男を殺さなければならない。
「……っ!」
陽に蹴りを入れようとしたが、少し驚いた顔をされただけでやはりかわされた。
すかさず殴りかかろうとすると、陽もこちらを押さえ付けようとしてくる。
アタシはそれを避け、距離を置いた。
本気の陽と戦って勝てる気はしない。
リバディーの戦闘訓練で相手をしてもらった時勝てたことはあるが、本気だとは感じなかった。
おそらくずっと…リバディーにいる間ずっと、陽は自分の能力を最低限隠して生活していたのだと思う。
でも、いくら陽が強くても、アタシだって今回ばかりは負けるわけにはいかない。
今度こそ油断なんてしない。
最初は全て避けていたものの、陽は徐々にアタシの攻撃を受け始めた。
連続で攻撃されて疲れが出てきたのだろう。
……それにしても、なぜこちらを攻撃してこないんだろう?
もしかして――どうせアタシは丸腰だと思って手を抜いてるんだろうか。
…笑わせるな。
アタシは隙をついて隠し持っていた殺人用のナイフで―――陽を刺した。
殺傷力を追求してつくられたナイフだ。
陽は崩れ落ちるように床に倒れ込む。
咄嗟に避けられたため急所は外してしまったものの、この傷なら放っておいたって死ぬのは時間の問題だろう。
「さようなら。―――ずっと好きだったよ」
陽が敵だと知ったあの日、陽がアタシを油断させるために使った言葉を残し、アタシはその場を去った。
「シャロン、治療!」
人気のない廊下に倒れ込んでいた陽を私とキャシーでシャロンの部屋まで運んだ。
見たところ傷は深い。
即死を免れただけでも幸いだろう。
腹部から多量の血が出ている陽を見てシャロンは眉を寄せた。
「そこのベッドに横にして」
シャロンの指示通り、私たちは陽をベッドにおろす。
陽はとても苦しそうだが、シャロンの元へ届けられた時点で、私は既にいくらか安心していた。
シャロンなら、これほどの傷を負った人間でも生きてさえいれば治せるからだ。
もちろん陽自身の気力も必要だけど…戦闘で負った傷を診ることにおいて、シャロンほど慣れている者はいない。
処置をしながら、シャロンは私たちに聞いた。
「どういう状況なのぉ?」
「アリスとはぐれたのですけれど、アリスを探している最中に倒れている陽を見つけましたの。私1人で運べば不安定になると思いましたので、近くに仲間がいないか確認しているとアリスを見つけましたのよ」
陽を運ばずにシャロンを呼ぼうかとも思ったけれど、攻撃的なリバディーの人間が近くにいるかもしれない状況で、シャロンを部屋の外に出すわけにはいかない。
「リバディーの連中が来てる……裏切り者の俺を殺そうとしたんすよ」
辛うじて喋る余力はあるらしく、陽はシャロンにそう伝えた。
「何人?」
「すんません、分からないっす…。でも、こっちが何人いるか知らないようだったんで…偶然この船に乗ってるだけでしょう」
それを聞き、シャロンは「今度からは貸し切るか」と面倒くさそうに言った。
アランは私と一緒にいた。
その間に陽がやられた。
リバディーの人間が他にも来てるってことだ。
アランの言っていた、プライベートで来てるっていうのは嘘?
…分からない。
でも、アランに聞けば何か分かるかもしれない。
もしかしたら、こちらの組織の人間には手を出させないようにしてくれるかも………いや、それは期待しすぎね。
いくらアランでも、一応敵組織の人間だ。
そこまで協力してくれるとは思えない。
「それにしても、派手にやられたねぇ」
シャロンが陽の傷口を見て言う。
「誰にやられたのぉ?陽でもこうなっちゃうってことは相当強いんだろうねぇ?俺もそいつに会ったら負けちゃうかもぉー」
「……いや、ボスは負けないっすよ。俺がやられたのは、手加減してしまったからです。俺は、……相手を殺す勢いでは戦わなかった」
「手加減、ねぇ」
シャロンの目がすうっと冷たくなり、次の瞬間、シャロンは立ち上がって――陽の腕を勢いよく踏み付けた。
「……ッ!」
陽は顔を歪ませ、声にならない悲鳴を上げた。
こうして見るとシャロンって足長いわね…。
「お前、自分がどこの組織の人間だと思ってんのぉ?」
「……ッ、…っボスの、組織、っす……」
「だよねぇ。」
にこり、とかわいらしく笑うシャロンだが、その足は容赦なく陽の腕を蹂躙する。
「シャロン様、やりすぎですわ!」
「どうせ刺されてんだよぉ?痛いところが1つ2つ増えたところで変わらないでしょ」
キャシーの言葉に対して淡々と言うシャロンは、こう形容するのが正しいのかは分からないが、犯罪組織のリーダーらしい顔をしていた。
「リバディーには長年いたから懐かしくなっちゃった?困るなぁ、そんなんじゃ」
「すんません………次は、殺します」
苦しそうな顔をしながら陽がそう言うと、シャロンはようやく足を退けた。
「ったく、“手加減した”で陽が死んだら困るんだよぉ?俺」
「はい……すんません」
「陽には、いつか頼みたいことがあるからねぇ」
「はぁ…」
「勝手に死ぬなってのぉ」
いつものぶりっ子モードでぷんぷん怒り始めたシャロン。
ようやく場が冗談っぽい雰囲気になったが、陽はまだ痛いらしく腕を押さえている。
「…チャロさんね」
私の言葉に、陽がわずかに目を開いた。
「チャロさんのこと、好きだったの?」
この場でこんなことを聞くのはどうかと思う。
でも、陽なら弱っている今でなければ本音を吐露しないと思った。
「…そんな風に見えんの、俺」
「好きだったの?」
繰り返し問うと、陽は困ったように目を閉じた。
「………あぁ。本人には、信じてもらえねーけど」
やっぱり、そうだったのか。
……どうして私はこんなことを聞いたんだろう。
どうして陽の答えを聞いてほっとしたのだろう。
…あぁ、もしかして。
自分が許容されたように感じたのではないだろうか。
陽でも敵に好意を抱く。
それが普通のことなのだと、私だけではないのだと、人間だから仕方がないのだと、許された気がしたのだ。
「つっても、怒らないでくださいよボス。次はマジで殺しますんで!」
へらっと軽く笑ってシャロンにウインクする陽。
明るく見せようとしているが、傷が酷いのは見れば分かる。
……これからもっと怪我人が増えるかもしれない。
「…船内に、アランがいたわ」
「アランさんが?」
陽が次の言葉に警戒するように私を見た。
「私、もう一度彼に会ってくる」
陽は眉を寄せ、私に忠告する。
「やめとけ。確実に面が割れてる俺やアリスちんは……船内を動き回らない方がいい」
「……っ!」
陽に蹴りを入れようとしたが、少し驚いた顔をされただけでやはりかわされた。
すかさず殴りかかろうとすると、陽もこちらを押さえ付けようとしてくる。
アタシはそれを避け、距離を置いた。
本気の陽と戦って勝てる気はしない。
リバディーの戦闘訓練で相手をしてもらった時勝てたことはあるが、本気だとは感じなかった。
おそらくずっと…リバディーにいる間ずっと、陽は自分の能力を最低限隠して生活していたのだと思う。
でも、いくら陽が強くても、アタシだって今回ばかりは負けるわけにはいかない。
今度こそ油断なんてしない。
最初は全て避けていたものの、陽は徐々にアタシの攻撃を受け始めた。
連続で攻撃されて疲れが出てきたのだろう。
……それにしても、なぜこちらを攻撃してこないんだろう?
もしかして――どうせアタシは丸腰だと思って手を抜いてるんだろうか。
…笑わせるな。
アタシは隙をついて隠し持っていた殺人用のナイフで―――陽を刺した。
殺傷力を追求してつくられたナイフだ。
陽は崩れ落ちるように床に倒れ込む。
咄嗟に避けられたため急所は外してしまったものの、この傷なら放っておいたって死ぬのは時間の問題だろう。
「さようなら。―――ずっと好きだったよ」
陽が敵だと知ったあの日、陽がアタシを油断させるために使った言葉を残し、アタシはその場を去った。
「シャロン、治療!」
人気のない廊下に倒れ込んでいた陽を私とキャシーでシャロンの部屋まで運んだ。
見たところ傷は深い。
即死を免れただけでも幸いだろう。
腹部から多量の血が出ている陽を見てシャロンは眉を寄せた。
「そこのベッドに横にして」
シャロンの指示通り、私たちは陽をベッドにおろす。
陽はとても苦しそうだが、シャロンの元へ届けられた時点で、私は既にいくらか安心していた。
シャロンなら、これほどの傷を負った人間でも生きてさえいれば治せるからだ。
もちろん陽自身の気力も必要だけど…戦闘で負った傷を診ることにおいて、シャロンほど慣れている者はいない。
処置をしながら、シャロンは私たちに聞いた。
「どういう状況なのぉ?」
「アリスとはぐれたのですけれど、アリスを探している最中に倒れている陽を見つけましたの。私1人で運べば不安定になると思いましたので、近くに仲間がいないか確認しているとアリスを見つけましたのよ」
陽を運ばずにシャロンを呼ぼうかとも思ったけれど、攻撃的なリバディーの人間が近くにいるかもしれない状況で、シャロンを部屋の外に出すわけにはいかない。
「リバディーの連中が来てる……裏切り者の俺を殺そうとしたんすよ」
辛うじて喋る余力はあるらしく、陽はシャロンにそう伝えた。
「何人?」
「すんません、分からないっす…。でも、こっちが何人いるか知らないようだったんで…偶然この船に乗ってるだけでしょう」
それを聞き、シャロンは「今度からは貸し切るか」と面倒くさそうに言った。
アランは私と一緒にいた。
その間に陽がやられた。
リバディーの人間が他にも来てるってことだ。
アランの言っていた、プライベートで来てるっていうのは嘘?
…分からない。
でも、アランに聞けば何か分かるかもしれない。
もしかしたら、こちらの組織の人間には手を出させないようにしてくれるかも………いや、それは期待しすぎね。
いくらアランでも、一応敵組織の人間だ。
そこまで協力してくれるとは思えない。
「それにしても、派手にやられたねぇ」
シャロンが陽の傷口を見て言う。
「誰にやられたのぉ?陽でもこうなっちゃうってことは相当強いんだろうねぇ?俺もそいつに会ったら負けちゃうかもぉー」
「……いや、ボスは負けないっすよ。俺がやられたのは、手加減してしまったからです。俺は、……相手を殺す勢いでは戦わなかった」
「手加減、ねぇ」
シャロンの目がすうっと冷たくなり、次の瞬間、シャロンは立ち上がって――陽の腕を勢いよく踏み付けた。
「……ッ!」
陽は顔を歪ませ、声にならない悲鳴を上げた。
こうして見るとシャロンって足長いわね…。
「お前、自分がどこの組織の人間だと思ってんのぉ?」
「……ッ、…っボスの、組織、っす……」
「だよねぇ。」
にこり、とかわいらしく笑うシャロンだが、その足は容赦なく陽の腕を蹂躙する。
「シャロン様、やりすぎですわ!」
「どうせ刺されてんだよぉ?痛いところが1つ2つ増えたところで変わらないでしょ」
キャシーの言葉に対して淡々と言うシャロンは、こう形容するのが正しいのかは分からないが、犯罪組織のリーダーらしい顔をしていた。
「リバディーには長年いたから懐かしくなっちゃった?困るなぁ、そんなんじゃ」
「すんません………次は、殺します」
苦しそうな顔をしながら陽がそう言うと、シャロンはようやく足を退けた。
「ったく、“手加減した”で陽が死んだら困るんだよぉ?俺」
「はい……すんません」
「陽には、いつか頼みたいことがあるからねぇ」
「はぁ…」
「勝手に死ぬなってのぉ」
いつものぶりっ子モードでぷんぷん怒り始めたシャロン。
ようやく場が冗談っぽい雰囲気になったが、陽はまだ痛いらしく腕を押さえている。
「…チャロさんね」
私の言葉に、陽がわずかに目を開いた。
「チャロさんのこと、好きだったの?」
この場でこんなことを聞くのはどうかと思う。
でも、陽なら弱っている今でなければ本音を吐露しないと思った。
「…そんな風に見えんの、俺」
「好きだったの?」
繰り返し問うと、陽は困ったように目を閉じた。
「………あぁ。本人には、信じてもらえねーけど」
やっぱり、そうだったのか。
……どうして私はこんなことを聞いたんだろう。
どうして陽の答えを聞いてほっとしたのだろう。
…あぁ、もしかして。
自分が許容されたように感じたのではないだろうか。
陽でも敵に好意を抱く。
それが普通のことなのだと、私だけではないのだと、人間だから仕方がないのだと、許された気がしたのだ。
「つっても、怒らないでくださいよボス。次はマジで殺しますんで!」
へらっと軽く笑ってシャロンにウインクする陽。
明るく見せようとしているが、傷が酷いのは見れば分かる。
……これからもっと怪我人が増えるかもしれない。
「…船内に、アランがいたわ」
「アランさんが?」
陽が次の言葉に警戒するように私を見た。
「私、もう一度彼に会ってくる」
陽は眉を寄せ、私に忠告する。
「やめとけ。確実に面が割れてる俺やアリスちんは……船内を動き回らない方がいい」