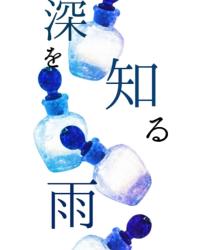「…マジで言ってんの?」
「偽ったって意味ないでしょう」
「俺も4月3日なんだけど」
「真似すんじゃないわよ」
「生まれる日まで真似できねぇよ」
アランと私は同い年。
つまり、私たちはまったく同じ日に生まれたということだ。
アランはまたククッと楽しそうに笑う。
「これも何かの縁かもな」
「誕生日が同じくらいで?確率的に言えばそう珍しくないわ」
「可愛くねぇな、ちょっとは喜べよ」
「あなたはなぜそんなに喜べるの?」
「好きな女と同じ誕生日だからだよ」
…こいついきなりぶっこんでくるわね…。
どう返していいか分からないからやめてくれないかしら。
アランから目を逸らし、話を変えるためにクレープ屋のメニューを指差した。
「お詫びにあの子にも1つ買っていこうかしら」
私と一緒にこの船を回ろうと言ってくれたのに、あっさりさらわれてしまったし。
「それは俺が買う」
「何よ、自分で買えって言っておいて」
「あいつの分だろ?それなら俺も礼がしたい」
礼?アランがキャシーに?なぜ?
「あいつには、お前のこと頼んだからな」
「え?」
「お前が無事で良かった」
話しているうちに順番が回ってきたので、どういうことか聞くタイミングを無くしてしまった。
アランがキャシーに私のことを頼んだ…?
もしかして、クリミナルズがリバディーを襲撃した日にどこかで会ったのだろうか。
……そこで私のことを頼むほど、私のこと心配だったわけ?
本当、変なやつ。
お店で人気No.1のクレープを購入して早速食べることにした。
アランはまだ食べないらしく袋に入れたままだが、私は食べる。お腹空いてるし。
と、アランに肩を引き寄せられた。
「この人混みで立ち食いは危ねぇぞ」
……これほんとにアラン?こんな気遣いできるなんて。
どうやら私が人にぶつからないようにしてくれているらしい。
アランの顔を見上げるが、いつも通りだ。別人ではない。
アランが優しいなんてやっぱり変だ。
変な奴相手なんだから…ちょっとくらい変なことを言ってもいいような気がしてくる。
「……こんなこと言ったことなかったけど、私、あなたのこと少しだけ好きよ。自分がクリミナルズの人間じゃなければ、友達になってたと思ってる」
言った後、二度と言わないでおこうと思った。
敵相手に友達だなんて言うもんじゃない。
感謝の気持ちを好意の言葉で示す必要はないってのに。
「……友達、なぁ」
アランはつまらなそうに目を細め、私に顔を近付けた。
「…っ…、」
そして、あろうことか私の口元についた生クリームをぺろっと舐めた。舐めやがった。
「な、何すんのよ」
慌ててティッシュを取り出して残りの生クリームを拭く。
これくらい自分でどうにかできるわ!
「俺は友達止まりでいるつもりねぇし」
「な…、な、」
何か言い返そうとするのに、何も出てこなくて口をパクパクさせるだけになってしまう。
「…お前、耳赤くね?」
「赤くないわよ!」
「照れてんの?」
「照れてないわよ」
ふざけるな、別にこのくらい何でもない。赤くなってもない。
「へぇ…いいこと知ったな」
意味ありげな笑みを浮かべて見下ろしてくるアラン。
「お前、押しに弱いんだ?」
「ッんなことな、」
「アリス!!」
「っ、」
こちらへ走ってくるキャシーの叫び声が聞こえ、誤解を招かないようにさっとアランと距離を置く。
「……ごめんなさい、ちょうど探しに行こうとしてたの。回る時間が少なくなったお詫びにクレープを…」
「回るのは後ですわ!大変ですのよ!」
「…え?」
キャシーはアランのことを気にも留めずに私を引っ張って早足で人と人の間を歩いて行く。
…ただ事じゃない、そう感じた。
アランとかなり離れた後、「何があったの?」と小声でキャシーに問うと、キャシーは険しい顔で振り向き言った。
「リバディーの人間に、陽が刺されましたの」
――数十分前、船内廊下。
この船に乗ったのは単なる気まぐれ。
折角の休暇だし、気分転換に海外旅行でも行こうと思っただけだった。
だから―――こんな場所でこの男と会うなんて、少しも予想していなかった。
なぜ自分は船内で迷子になんてなってしまったのだろう、と深く後悔した。
迷子にならなければこんな場所に来ることも、何も考えずに船旅を楽しむこともできたかもしれないのに。
「…髪、切ったんだな」
懐かしい声が、まるで久しぶりに旧友に会ったかのような調子で言ってくる。
この男が以前より大人っぽく見えるのはなぜだろう。
以前と雰囲気がどれだけ変わっていても…何年も一緒にいたのだから、嫌でも一目で分かる。
「……陽…」
アタシは目の前にいる元同僚の名前を呟いた。
「ここにはリバディーの連中が他に何人来てる?」
まさか他の客全員とか言わないよな、とでも言いたげな目。
全員だったらまた乱闘になりかねないもんね?船上だから逃げ場ないし。
とはいえ、今日来てるのはアタシも含めてたったの3人。
それも、別に任務で来ているというわけじゃない。
たまたま行く方向が同じだったから同じ船を予約しただけのこと。
このことを伝えれば、陽はきっと安心するだろう。…でも。
「あんたに教える義理はない」
そう答えたアタシの声は随分低いものだった。
こちらの敵意を感じ取ったのか、陽は苦笑いする。
「……なぁ、駄目元で聞くけど、他の奴らをこっちと鉢合わせしないようにとか…してくれねーよな?」
は?アタシのことなんだと思ってるの?
そんなことするわけないでしょ。
「チャロの力が必要なんだ」
「馬鹿言わないで。敵であるあんたの言うことは聞けない」
「頼む。お前の協力次第では、こっちもお前らの組織の人間には手を出さない。利害の一致じゃね?だから――」
「そうやって利用するんだね」
「……、」
「そういう男だってことはもう分かった。…それに、アタシにはもうリバディーの人間に指示する権利なんてない」
「え…?」
「指揮官、やめさせられたの」
あんたのせいでね。…いや…あんたに油断したアタシのせいで。
「人の恋心につけ込んで、油断させて、どんな気分だった?」
「……」
「好きって言われた時、アタシがどれだけ嬉しかったか分かる?それが油断させるための嘘だと分かって、どれだけ悲しかったか分かる?」
「…ッ違うチャロ、そうじゃない」
「何が違うの!!!」
陽に怒りたいわけじゃない。
本当に悪いのは、判断を誤った自分だって分かってる。
そんな自分が腹立たしくて……陽が敵であるこの状況が苦しくて、声を荒げてしまった。
「偽ったって意味ないでしょう」
「俺も4月3日なんだけど」
「真似すんじゃないわよ」
「生まれる日まで真似できねぇよ」
アランと私は同い年。
つまり、私たちはまったく同じ日に生まれたということだ。
アランはまたククッと楽しそうに笑う。
「これも何かの縁かもな」
「誕生日が同じくらいで?確率的に言えばそう珍しくないわ」
「可愛くねぇな、ちょっとは喜べよ」
「あなたはなぜそんなに喜べるの?」
「好きな女と同じ誕生日だからだよ」
…こいついきなりぶっこんでくるわね…。
どう返していいか分からないからやめてくれないかしら。
アランから目を逸らし、話を変えるためにクレープ屋のメニューを指差した。
「お詫びにあの子にも1つ買っていこうかしら」
私と一緒にこの船を回ろうと言ってくれたのに、あっさりさらわれてしまったし。
「それは俺が買う」
「何よ、自分で買えって言っておいて」
「あいつの分だろ?それなら俺も礼がしたい」
礼?アランがキャシーに?なぜ?
「あいつには、お前のこと頼んだからな」
「え?」
「お前が無事で良かった」
話しているうちに順番が回ってきたので、どういうことか聞くタイミングを無くしてしまった。
アランがキャシーに私のことを頼んだ…?
もしかして、クリミナルズがリバディーを襲撃した日にどこかで会ったのだろうか。
……そこで私のことを頼むほど、私のこと心配だったわけ?
本当、変なやつ。
お店で人気No.1のクレープを購入して早速食べることにした。
アランはまだ食べないらしく袋に入れたままだが、私は食べる。お腹空いてるし。
と、アランに肩を引き寄せられた。
「この人混みで立ち食いは危ねぇぞ」
……これほんとにアラン?こんな気遣いできるなんて。
どうやら私が人にぶつからないようにしてくれているらしい。
アランの顔を見上げるが、いつも通りだ。別人ではない。
アランが優しいなんてやっぱり変だ。
変な奴相手なんだから…ちょっとくらい変なことを言ってもいいような気がしてくる。
「……こんなこと言ったことなかったけど、私、あなたのこと少しだけ好きよ。自分がクリミナルズの人間じゃなければ、友達になってたと思ってる」
言った後、二度と言わないでおこうと思った。
敵相手に友達だなんて言うもんじゃない。
感謝の気持ちを好意の言葉で示す必要はないってのに。
「……友達、なぁ」
アランはつまらなそうに目を細め、私に顔を近付けた。
「…っ…、」
そして、あろうことか私の口元についた生クリームをぺろっと舐めた。舐めやがった。
「な、何すんのよ」
慌ててティッシュを取り出して残りの生クリームを拭く。
これくらい自分でどうにかできるわ!
「俺は友達止まりでいるつもりねぇし」
「な…、な、」
何か言い返そうとするのに、何も出てこなくて口をパクパクさせるだけになってしまう。
「…お前、耳赤くね?」
「赤くないわよ!」
「照れてんの?」
「照れてないわよ」
ふざけるな、別にこのくらい何でもない。赤くなってもない。
「へぇ…いいこと知ったな」
意味ありげな笑みを浮かべて見下ろしてくるアラン。
「お前、押しに弱いんだ?」
「ッんなことな、」
「アリス!!」
「っ、」
こちらへ走ってくるキャシーの叫び声が聞こえ、誤解を招かないようにさっとアランと距離を置く。
「……ごめんなさい、ちょうど探しに行こうとしてたの。回る時間が少なくなったお詫びにクレープを…」
「回るのは後ですわ!大変ですのよ!」
「…え?」
キャシーはアランのことを気にも留めずに私を引っ張って早足で人と人の間を歩いて行く。
…ただ事じゃない、そう感じた。
アランとかなり離れた後、「何があったの?」と小声でキャシーに問うと、キャシーは険しい顔で振り向き言った。
「リバディーの人間に、陽が刺されましたの」
――数十分前、船内廊下。
この船に乗ったのは単なる気まぐれ。
折角の休暇だし、気分転換に海外旅行でも行こうと思っただけだった。
だから―――こんな場所でこの男と会うなんて、少しも予想していなかった。
なぜ自分は船内で迷子になんてなってしまったのだろう、と深く後悔した。
迷子にならなければこんな場所に来ることも、何も考えずに船旅を楽しむこともできたかもしれないのに。
「…髪、切ったんだな」
懐かしい声が、まるで久しぶりに旧友に会ったかのような調子で言ってくる。
この男が以前より大人っぽく見えるのはなぜだろう。
以前と雰囲気がどれだけ変わっていても…何年も一緒にいたのだから、嫌でも一目で分かる。
「……陽…」
アタシは目の前にいる元同僚の名前を呟いた。
「ここにはリバディーの連中が他に何人来てる?」
まさか他の客全員とか言わないよな、とでも言いたげな目。
全員だったらまた乱闘になりかねないもんね?船上だから逃げ場ないし。
とはいえ、今日来てるのはアタシも含めてたったの3人。
それも、別に任務で来ているというわけじゃない。
たまたま行く方向が同じだったから同じ船を予約しただけのこと。
このことを伝えれば、陽はきっと安心するだろう。…でも。
「あんたに教える義理はない」
そう答えたアタシの声は随分低いものだった。
こちらの敵意を感じ取ったのか、陽は苦笑いする。
「……なぁ、駄目元で聞くけど、他の奴らをこっちと鉢合わせしないようにとか…してくれねーよな?」
は?アタシのことなんだと思ってるの?
そんなことするわけないでしょ。
「チャロの力が必要なんだ」
「馬鹿言わないで。敵であるあんたの言うことは聞けない」
「頼む。お前の協力次第では、こっちもお前らの組織の人間には手を出さない。利害の一致じゃね?だから――」
「そうやって利用するんだね」
「……、」
「そういう男だってことはもう分かった。…それに、アタシにはもうリバディーの人間に指示する権利なんてない」
「え…?」
「指揮官、やめさせられたの」
あんたのせいでね。…いや…あんたに油断したアタシのせいで。
「人の恋心につけ込んで、油断させて、どんな気分だった?」
「……」
「好きって言われた時、アタシがどれだけ嬉しかったか分かる?それが油断させるための嘘だと分かって、どれだけ悲しかったか分かる?」
「…ッ違うチャロ、そうじゃない」
「何が違うの!!!」
陽に怒りたいわけじゃない。
本当に悪いのは、判断を誤った自分だって分かってる。
そんな自分が腹立たしくて……陽が敵であるこの状況が苦しくて、声を荒げてしまった。