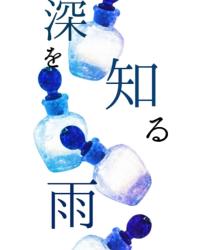「私のスタイル、バストが変に大きくて全体的にアンバランスでしょう?水着になるとそれが更に強調されて、怖いって言われたこともあるわ」
「そ、そんな…豊満なお胸も女性らしくて私はいいと思いますわよ…?」
気を遣って励ましてくれるのはありがたいけれど、キャシーが良くても私は嫌だ。
バランスの良いスタイルをしたキャシーの隣に水着でいるなんて、余計に私のアンバランスさを思い知ってしまう。
「そうですわ!水着と言っても色々ありますし、似合いそうな水着を一緒に探すのはどうでしょう?」
「サイズの合う水着も少ないのよ。種類が限られてくる」
「で、でも」
「プールなんて行ったってどうせからかわれるだけよ……」
「わ、分かりました、分かりましたわ!遠い目をしないでくださいまし!そんなに嫌ならプールはやめにしましょう」
キャシーは焦って私の肩を揺らしながら言う。
諦めてくれて助かった……水着を着るのが嫌ってのもそうだけど、私泳げないし。
「ぶはっ」
…………ぶは?
後ろから吹き出すような笑いが聞こえたので振り返ると。
「……っ」
会ってはならない人物がそこにいた。
茶髪の、立っているだけで妖しい色気を放っている男。
―――まずい。今は変装すらしてないのに。
こう近距離じゃごまかせもしない。
「あらあらあら~?こんなところでまで会うなんて、運命感じちゃいますわね。ね、アリス」
にやにやと私を肘でつついてくるキャシーは、私とそこの男―――アランとの仲を何か誤解しているようにも思う。
そんな楽しそうにしてる場合じゃないでしょ、敵が同じ船に乗ってんのよ?
クリミナルズがこの船で移動するって情報を嗅ぎ付けて私たちを捕まえにきたのかもしれない。
「…なぜここに?」
私はキャシーを庇うようにしてアランに向き直った。
「偶然だよ。今日は一般客としてこの船に乗ってる」
「…信用できないわ」
第一、これは日本行きの船だ。
アランが個人的に日本へ行く理由なんて想像がつかない。
「俺も信じらんねぇよ。こう偶然が重なると本当に運命なんじゃねぇかと思っちまう」
…確かに、アランとはよく会う。遭遇率が高すぎる。
ってそうじゃなくて。
「この船内には私の組織の連中が沢山いるわ。それに、こっちはこの船にいる他の一般客を人質にすることもできる。ここで私たちを捕まえるのは賢明な判断じゃないわよ」
真剣に脅してるってのに、アランはニヤニヤしながら私を見下ろしている。
「何笑ってんのよ?」
「お前も女みたいな悩み抱えてんだなって」
…さっきの水着の話のこと?
みたいなって何よみたいなって。失礼な。
「なぁ、こいつもらっていいか?」
アランが私を指差し、キャシーに向かって聞く。
「…は、はぁ!?あなたのことは利害の一致ということで応援していますけれど、それはだめですわ!アリスは今日は私と買い物す、」
「つーか、もらうわ」
言うが早いか、アランは私を抱き上げた。
「ちょっ…」
「俺を捕まえられたら返してやるよ」
アランは自信ありげにキャシーにそう言って走り出した。
それ返さないって言ってるようなもんじゃない…。
いくらキャシーでも、アランの速さには勝てないだろう。
「ちょっと、あの子怒ったら厄介だから今すぐ止まった方がいいわよ」
ていうかおろしてくれないかしら。
これじゃ目立ってしょうがない。
「暴れねぇのな」
「え?」
「連れ去られてんのに暴れねぇってことは、ちょっとは俺に気ぃ許してるって解釈していいわけ?」
無駄に色っぽい目付きで私を見てくるアランはご機嫌だ。
…そう言われてみれば、アランを敵だと認識してはいるものの危機感はない。
「何よ、暴れてほしいの?」
開き直ってそう言えば、アランは楽しそうにククッと笑った。
結局おろしてもらえたのは、キャシーが見えなくなった後だった。
「本当にはぐれちゃったじゃない。今日は一緒に買い物する予定だったのに…」
見事に予定が崩れてしまったと思いアランを睨むが、効果はない。
「お前、友達いたんだな」
「あら、どういう意味かしら?」
「犯罪組織にいても、案外元気そうでよかったと思ったんだよ。良い組織なんだな」
「……」
リバディーの人間が、クリミナルズを肯定している。
敵のくせに、変な奴ね。
「……………あの子を探すの、手伝ってくれる?」
気付けばそんなことを言ってしまっていた。
別に今ここでこいつから離れて1人でキャシーを探すことだってできるのに。
リバディーの人間がクリミナルズの良さを理解してくれたからって、喜びすぎかしら。
来た道をお互いしばらく無言で歩いた。
人が多いこともあってキャシーはなかなか見つからない。
ゴシックファッションだから目立つとは思うんだけど…こういう時連絡手段がないのは不便ね。
きょろきょろしていると、ふとクレープ屋さんが目に入った。
無言で立ち止まってメニューを見ていると、アランが聞いてくる。
「食いたいのか?」
「あなたが奢ってくれるなら」
「お前……またそれか」
アランは溜め息をつき、いきなり私の額を中指で弾いてきた。
「っ」
「どこの誰に甘やかされて生きてきたんだ?たまには自分で払え、バカ」
「な、何よ…あなたならお金くらい有り余るほど持ってるんでしょ」
リバディーの給料がいいことくらい知ってんのよ?
「持ってる持ってないの話じゃねぇっつの。そうやって奢られ癖がつくのはよくねぇって言ってんだよ」
「…なんでよ」
「ちゃんと自分で稼いだ金で買え。その方が達成感あるぞ。どんな仕事内容であれ、お前が労働した結果として得られたものだろ?」
うっ……。
そんなふうに言われると言い返せなくなってしまう。
アランは私のような守銭奴ではないのだ。
消費はしたいけど自分の所持金は使いたくない!!
なんて気持ち、アランには分かってもらえないだろう。
「…………………分かったわよ、払うわよ」
なんだか屈辱的だ。
説教されてしまったうえに、自分のお金を使う羽目になった。
まぁ元々キャシーとの買い物のためにある程度財布に入れてきてたし、ここで使ったって問題はないんだけど。
渋々財布をポケットから取り出してクレープ屋さんの列に並ぶと、アランはにやにや笑いながら私の後ろを付いてきた。
「可愛いやつ」
「……、」
そういえばこいつ、私のこと好きなんだった。
そう思うとどう接していいか分からなくなり黙り込んでしまった私だが、アランの方は何でもない様子でふと聞いてくる。
「お前、誕生日いつだ?」
「…なぜ?」
「今月が誕生日なら割引らしいぞ」
「残念、私は4月3日だからまだまだよ」
「そ、そんな…豊満なお胸も女性らしくて私はいいと思いますわよ…?」
気を遣って励ましてくれるのはありがたいけれど、キャシーが良くても私は嫌だ。
バランスの良いスタイルをしたキャシーの隣に水着でいるなんて、余計に私のアンバランスさを思い知ってしまう。
「そうですわ!水着と言っても色々ありますし、似合いそうな水着を一緒に探すのはどうでしょう?」
「サイズの合う水着も少ないのよ。種類が限られてくる」
「で、でも」
「プールなんて行ったってどうせからかわれるだけよ……」
「わ、分かりました、分かりましたわ!遠い目をしないでくださいまし!そんなに嫌ならプールはやめにしましょう」
キャシーは焦って私の肩を揺らしながら言う。
諦めてくれて助かった……水着を着るのが嫌ってのもそうだけど、私泳げないし。
「ぶはっ」
…………ぶは?
後ろから吹き出すような笑いが聞こえたので振り返ると。
「……っ」
会ってはならない人物がそこにいた。
茶髪の、立っているだけで妖しい色気を放っている男。
―――まずい。今は変装すらしてないのに。
こう近距離じゃごまかせもしない。
「あらあらあら~?こんなところでまで会うなんて、運命感じちゃいますわね。ね、アリス」
にやにやと私を肘でつついてくるキャシーは、私とそこの男―――アランとの仲を何か誤解しているようにも思う。
そんな楽しそうにしてる場合じゃないでしょ、敵が同じ船に乗ってんのよ?
クリミナルズがこの船で移動するって情報を嗅ぎ付けて私たちを捕まえにきたのかもしれない。
「…なぜここに?」
私はキャシーを庇うようにしてアランに向き直った。
「偶然だよ。今日は一般客としてこの船に乗ってる」
「…信用できないわ」
第一、これは日本行きの船だ。
アランが個人的に日本へ行く理由なんて想像がつかない。
「俺も信じらんねぇよ。こう偶然が重なると本当に運命なんじゃねぇかと思っちまう」
…確かに、アランとはよく会う。遭遇率が高すぎる。
ってそうじゃなくて。
「この船内には私の組織の連中が沢山いるわ。それに、こっちはこの船にいる他の一般客を人質にすることもできる。ここで私たちを捕まえるのは賢明な判断じゃないわよ」
真剣に脅してるってのに、アランはニヤニヤしながら私を見下ろしている。
「何笑ってんのよ?」
「お前も女みたいな悩み抱えてんだなって」
…さっきの水着の話のこと?
みたいなって何よみたいなって。失礼な。
「なぁ、こいつもらっていいか?」
アランが私を指差し、キャシーに向かって聞く。
「…は、はぁ!?あなたのことは利害の一致ということで応援していますけれど、それはだめですわ!アリスは今日は私と買い物す、」
「つーか、もらうわ」
言うが早いか、アランは私を抱き上げた。
「ちょっ…」
「俺を捕まえられたら返してやるよ」
アランは自信ありげにキャシーにそう言って走り出した。
それ返さないって言ってるようなもんじゃない…。
いくらキャシーでも、アランの速さには勝てないだろう。
「ちょっと、あの子怒ったら厄介だから今すぐ止まった方がいいわよ」
ていうかおろしてくれないかしら。
これじゃ目立ってしょうがない。
「暴れねぇのな」
「え?」
「連れ去られてんのに暴れねぇってことは、ちょっとは俺に気ぃ許してるって解釈していいわけ?」
無駄に色っぽい目付きで私を見てくるアランはご機嫌だ。
…そう言われてみれば、アランを敵だと認識してはいるものの危機感はない。
「何よ、暴れてほしいの?」
開き直ってそう言えば、アランは楽しそうにククッと笑った。
結局おろしてもらえたのは、キャシーが見えなくなった後だった。
「本当にはぐれちゃったじゃない。今日は一緒に買い物する予定だったのに…」
見事に予定が崩れてしまったと思いアランを睨むが、効果はない。
「お前、友達いたんだな」
「あら、どういう意味かしら?」
「犯罪組織にいても、案外元気そうでよかったと思ったんだよ。良い組織なんだな」
「……」
リバディーの人間が、クリミナルズを肯定している。
敵のくせに、変な奴ね。
「……………あの子を探すの、手伝ってくれる?」
気付けばそんなことを言ってしまっていた。
別に今ここでこいつから離れて1人でキャシーを探すことだってできるのに。
リバディーの人間がクリミナルズの良さを理解してくれたからって、喜びすぎかしら。
来た道をお互いしばらく無言で歩いた。
人が多いこともあってキャシーはなかなか見つからない。
ゴシックファッションだから目立つとは思うんだけど…こういう時連絡手段がないのは不便ね。
きょろきょろしていると、ふとクレープ屋さんが目に入った。
無言で立ち止まってメニューを見ていると、アランが聞いてくる。
「食いたいのか?」
「あなたが奢ってくれるなら」
「お前……またそれか」
アランは溜め息をつき、いきなり私の額を中指で弾いてきた。
「っ」
「どこの誰に甘やかされて生きてきたんだ?たまには自分で払え、バカ」
「な、何よ…あなたならお金くらい有り余るほど持ってるんでしょ」
リバディーの給料がいいことくらい知ってんのよ?
「持ってる持ってないの話じゃねぇっつの。そうやって奢られ癖がつくのはよくねぇって言ってんだよ」
「…なんでよ」
「ちゃんと自分で稼いだ金で買え。その方が達成感あるぞ。どんな仕事内容であれ、お前が労働した結果として得られたものだろ?」
うっ……。
そんなふうに言われると言い返せなくなってしまう。
アランは私のような守銭奴ではないのだ。
消費はしたいけど自分の所持金は使いたくない!!
なんて気持ち、アランには分かってもらえないだろう。
「…………………分かったわよ、払うわよ」
なんだか屈辱的だ。
説教されてしまったうえに、自分のお金を使う羽目になった。
まぁ元々キャシーとの買い物のためにある程度財布に入れてきてたし、ここで使ったって問題はないんだけど。
渋々財布をポケットから取り出してクレープ屋さんの列に並ぶと、アランはにやにや笑いながら私の後ろを付いてきた。
「可愛いやつ」
「……、」
そういえばこいつ、私のこと好きなんだった。
そう思うとどう接していいか分からなくなり黙り込んでしまった私だが、アランの方は何でもない様子でふと聞いてくる。
「お前、誕生日いつだ?」
「…なぜ?」
「今月が誕生日なら割引らしいぞ」
「残念、私は4月3日だからまだまだよ」