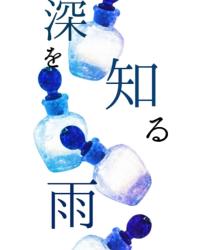「あらあらあら~?馴れ合うつもりはないだとかなんとか言っておいて、私たちのこと気になってるんですのねぇ」
ニヤニヤしながら口元に手をやるキャシーを一瞬睨んだ後、フォックスは続けた。
「一般的な犯罪組織のものならぬ絆を感じて、少々戸惑っている」
…絆…?
そう言われてみれば、スパイとして所属したことのある別の犯罪組織は、クリミナルズよりも仲間同士のプライベートな関わりがなかった気がする。
仕事のためにお互い一緒にいるというだけだったような…。
それがフォックスの言う一般的な犯罪組織なんだろうか。
「まぁ確かに私たち、やってることは犯罪でも柄は悪くないですものね」
犯罪やってて柄悪くないってどういうことよ。…まぁ言いたいことは分からなくもないけど。
「きっと、この組織を仕切ってるのがシャロン様だからですわ。シャロン様の組織だからこそ、私たち良い子で仲良くしていられるんですのよ」
「ボクもそうだと思う。全員が全員そうってわけじゃないだろうけど…少なくともボク達は、リーダーへの尊敬や忠誠心、感謝の気持ちで繋がってる。アリスもそう思うでしょ?」
確かに、同意見ではある。
「…そうなんじゃない?私だって…私を拾ってくれたのが、シャロンでよかったって思ってる」
私がこんなことを言うのが珍しかったからか、場に沈黙が走る。
ちょっと、何よ誰か何か言ってよ。恥ずかしいじゃない。
「………あっそぉ」
「あっれ?どうしたんすかボス、酔ってます?ほんのり顔が赤いような~?」
「うっさいなぁ」
「いって!すんませんすんません」
シャロンの顔をからかうように覗き込む陽の足を、テーブルの下でシャロンが蹴った。
そういえば、立場的にシャロンが上とはいえ年齢的には陽が上だ。
ジャックにもよくからかわれてるし…シャロンって年上にからかわれやすいのかしら。
「アリスは私と同じ気持ち……つまり、やっぱりアリスはライバルですわ!」
「いや、そういわけじゃ…」
「負けませんわよ~~~っ!」
飲んでないのに酔ってるのかしら、この子。
―――
―――――――
そうこうしているうちに、すっかり日が暮れてきた。
冬だから日暮れが早いとはいえ、ここに来たのお昼時よ?何時間いるのよ、私たち。
どんちゃん騒ぎも終結し、店内はいくらか静かになった。
というのも、私とジャックを残してみんな寝てしまったのだ。
今朝のこともあって疲れているのだろう。
「アリス、向こうで立ち飲みでもしないか?」
ジャックが場所を変えることを提案してきた。
「やっぱり。シャロンを寝かせようとしたのは、私に何か話したいことがあったのね」
「あぁ。君が仲間の元を離れて俺と2人になるのが不安ならここで話してもいいけど…君との話の途中でシャロン君に起きられると少々困る」
「…分かったわ」
途中で起きられるどころか、寝ているふりをしている人がいる可能性だってあるしね。
フォックスなんて目を瞑ってるだけのように見えるし、陽もなんだかんだ警戒心の強い人だから、人前で寝るとは思えない。
ジャックのことはもう、ある程度信用している。
ずっと私に協力してくれているし、私の仲間に対しても優しく接しているから。
もちろん信用しすぎもよくないから多少の警戒はしているけれど、この店を出るわけではないのだし仲間が他に5人もいるのだから、2人になったって問題はないだろう。
私は立ち上がってジャックに付いていった。
店の更に奥、円形のテーブルがいくつも並ぶ場所で、ジャックは私にはよく分からない名前の酒を頼んだ。
私はレモネードを頼み、テーブルに置いてまったり飲む。
周りに人はいない。
「お酒強いのね。全然酔ってないじゃない」
「俺はそういう体質なのかもね。たまには思いっきり酔ってみたいもんだよ」
曇っていることもあり、窓の外はすっかり暗くなっている。
寝ているみんなは一体いつ帰るつもりなのかしら?
ここから本拠地までもある程度時間掛かるし、もう少ししたら起こした方がいいわね。
「それで、話って?」
テーブルに肘をついて問うと、ジャックは飲んでいたお酒をテーブルに置き、私に向き直った。
これまでにないくらい真剣味を帯びた表情は、何を話されるのかと心配になるほどだ。
数秒経った後、ジャックは口を開いた。
「組織を抜けて、俺と一緒に来ないか」
「…え?」
「君がこの組織を気に入っていることは分かってる。でも、数分だけでいい。俺の話を聞いてくれ」
こんな話をされるだなんて思いもしなかったから、返事に窮する。
「日本へ行ったところで、今のようにシャロン君に縛られたままでは君はうまく動けないと思う。今は無所属になってでも解毒剤探しに狂奔すべきだと思わないか。組織を抜けたってシャロン君達に全く会えなくなるわけじゃないしね」
おかしな話だ。
ジャックは何を思ってこんなことを言ってくるのだろう。
「あなたが私を連れて行ってくれるの?どこまでも?私という負担を1人で背負ったって、あなたに相応の利益があるとは思えない」
「利益ならあるさ。君は多言語学習の飲み込みが早い。ちょうどそういう仕事仲間が欲しいところなんだ。あと数ヶ月、俺に付いて世界各国を飛び回り、優秀な科学者を探して解毒剤をつくってもらうよう仕向けることだってできるんじゃないか?」
……私にとって悪い話じゃない。
不老不死の体を捨てられる可能性があるのなら、どこへだって行きたい。
「でも私、あなたがどんな仕事をしているのか知らないわ」
「詐欺師として有名になったからか、裏の人間の間でも有名になってね。今じゃその手の連中から依頼が来るようになってる。仕事内容は君んとこの組織がやってるようなこととおおかた同じだ。仕事のために色んな国へ移動するから、俺に付いてくれば君は多くの地域に行ける」
ジャックは私の手を取って、私に顔を近付けた。
「もちろん本当に危険な仕事には君を関わらせないし、危険度で言えば今まで君がしてきたスパイ活動の方が高い」
いつもの軽いテンションじゃない。
「君を飢えさせるようなことは絶対にしない。安全も保障する。君が指名手配人だろうと何だろうと、自由に生きさせてみせるよ」
こんなことを言ってくれる人なんて、今までいなかった。
「俺と一緒に来てくれ」
もう一度言うジャックの目は――…本気だった。
私は目を瞑り、そして目を開けた。
「そうね。クリミナルズを抜けた後は…そういう人生も、悪くないかもしれないわね」
ジャックは私に未来の可能性をくれた。
クリミナルズでの自由しか知らない私に、クリミナルズ以外の居場所をプレゼントしてくれようとした。今までにないことだった。
……でも。
ニヤニヤしながら口元に手をやるキャシーを一瞬睨んだ後、フォックスは続けた。
「一般的な犯罪組織のものならぬ絆を感じて、少々戸惑っている」
…絆…?
そう言われてみれば、スパイとして所属したことのある別の犯罪組織は、クリミナルズよりも仲間同士のプライベートな関わりがなかった気がする。
仕事のためにお互い一緒にいるというだけだったような…。
それがフォックスの言う一般的な犯罪組織なんだろうか。
「まぁ確かに私たち、やってることは犯罪でも柄は悪くないですものね」
犯罪やってて柄悪くないってどういうことよ。…まぁ言いたいことは分からなくもないけど。
「きっと、この組織を仕切ってるのがシャロン様だからですわ。シャロン様の組織だからこそ、私たち良い子で仲良くしていられるんですのよ」
「ボクもそうだと思う。全員が全員そうってわけじゃないだろうけど…少なくともボク達は、リーダーへの尊敬や忠誠心、感謝の気持ちで繋がってる。アリスもそう思うでしょ?」
確かに、同意見ではある。
「…そうなんじゃない?私だって…私を拾ってくれたのが、シャロンでよかったって思ってる」
私がこんなことを言うのが珍しかったからか、場に沈黙が走る。
ちょっと、何よ誰か何か言ってよ。恥ずかしいじゃない。
「………あっそぉ」
「あっれ?どうしたんすかボス、酔ってます?ほんのり顔が赤いような~?」
「うっさいなぁ」
「いって!すんませんすんません」
シャロンの顔をからかうように覗き込む陽の足を、テーブルの下でシャロンが蹴った。
そういえば、立場的にシャロンが上とはいえ年齢的には陽が上だ。
ジャックにもよくからかわれてるし…シャロンって年上にからかわれやすいのかしら。
「アリスは私と同じ気持ち……つまり、やっぱりアリスはライバルですわ!」
「いや、そういわけじゃ…」
「負けませんわよ~~~っ!」
飲んでないのに酔ってるのかしら、この子。
―――
―――――――
そうこうしているうちに、すっかり日が暮れてきた。
冬だから日暮れが早いとはいえ、ここに来たのお昼時よ?何時間いるのよ、私たち。
どんちゃん騒ぎも終結し、店内はいくらか静かになった。
というのも、私とジャックを残してみんな寝てしまったのだ。
今朝のこともあって疲れているのだろう。
「アリス、向こうで立ち飲みでもしないか?」
ジャックが場所を変えることを提案してきた。
「やっぱり。シャロンを寝かせようとしたのは、私に何か話したいことがあったのね」
「あぁ。君が仲間の元を離れて俺と2人になるのが不安ならここで話してもいいけど…君との話の途中でシャロン君に起きられると少々困る」
「…分かったわ」
途中で起きられるどころか、寝ているふりをしている人がいる可能性だってあるしね。
フォックスなんて目を瞑ってるだけのように見えるし、陽もなんだかんだ警戒心の強い人だから、人前で寝るとは思えない。
ジャックのことはもう、ある程度信用している。
ずっと私に協力してくれているし、私の仲間に対しても優しく接しているから。
もちろん信用しすぎもよくないから多少の警戒はしているけれど、この店を出るわけではないのだし仲間が他に5人もいるのだから、2人になったって問題はないだろう。
私は立ち上がってジャックに付いていった。
店の更に奥、円形のテーブルがいくつも並ぶ場所で、ジャックは私にはよく分からない名前の酒を頼んだ。
私はレモネードを頼み、テーブルに置いてまったり飲む。
周りに人はいない。
「お酒強いのね。全然酔ってないじゃない」
「俺はそういう体質なのかもね。たまには思いっきり酔ってみたいもんだよ」
曇っていることもあり、窓の外はすっかり暗くなっている。
寝ているみんなは一体いつ帰るつもりなのかしら?
ここから本拠地までもある程度時間掛かるし、もう少ししたら起こした方がいいわね。
「それで、話って?」
テーブルに肘をついて問うと、ジャックは飲んでいたお酒をテーブルに置き、私に向き直った。
これまでにないくらい真剣味を帯びた表情は、何を話されるのかと心配になるほどだ。
数秒経った後、ジャックは口を開いた。
「組織を抜けて、俺と一緒に来ないか」
「…え?」
「君がこの組織を気に入っていることは分かってる。でも、数分だけでいい。俺の話を聞いてくれ」
こんな話をされるだなんて思いもしなかったから、返事に窮する。
「日本へ行ったところで、今のようにシャロン君に縛られたままでは君はうまく動けないと思う。今は無所属になってでも解毒剤探しに狂奔すべきだと思わないか。組織を抜けたってシャロン君達に全く会えなくなるわけじゃないしね」
おかしな話だ。
ジャックは何を思ってこんなことを言ってくるのだろう。
「あなたが私を連れて行ってくれるの?どこまでも?私という負担を1人で背負ったって、あなたに相応の利益があるとは思えない」
「利益ならあるさ。君は多言語学習の飲み込みが早い。ちょうどそういう仕事仲間が欲しいところなんだ。あと数ヶ月、俺に付いて世界各国を飛び回り、優秀な科学者を探して解毒剤をつくってもらうよう仕向けることだってできるんじゃないか?」
……私にとって悪い話じゃない。
不老不死の体を捨てられる可能性があるのなら、どこへだって行きたい。
「でも私、あなたがどんな仕事をしているのか知らないわ」
「詐欺師として有名になったからか、裏の人間の間でも有名になってね。今じゃその手の連中から依頼が来るようになってる。仕事内容は君んとこの組織がやってるようなこととおおかた同じだ。仕事のために色んな国へ移動するから、俺に付いてくれば君は多くの地域に行ける」
ジャックは私の手を取って、私に顔を近付けた。
「もちろん本当に危険な仕事には君を関わらせないし、危険度で言えば今まで君がしてきたスパイ活動の方が高い」
いつもの軽いテンションじゃない。
「君を飢えさせるようなことは絶対にしない。安全も保障する。君が指名手配人だろうと何だろうと、自由に生きさせてみせるよ」
こんなことを言ってくれる人なんて、今までいなかった。
「俺と一緒に来てくれ」
もう一度言うジャックの目は――…本気だった。
私は目を瞑り、そして目を開けた。
「そうね。クリミナルズを抜けた後は…そういう人生も、悪くないかもしれないわね」
ジャックは私に未来の可能性をくれた。
クリミナルズでの自由しか知らない私に、クリミナルズ以外の居場所をプレゼントしてくれようとした。今までにないことだった。
……でも。