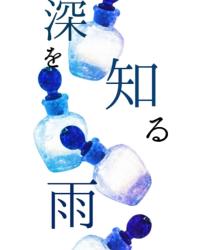そこでふと、バズ君の向こう側の二の腕に血が滲んでいることに気付いた。返り血じゃない。
「…バズ君、その腕……」
思い当たる節がある。
……あの時、私を庇って撃たれたのだ。
銃弾全てがこちらへ来なかったというわけではないらしい。
「別に、かすっただけだよ」
「かすっただけに見えませんわ。処置はしましたの?」
「気にしなくていいって」
「私のせいで怪我したなら気にするに決まってますわ!」
「キャシーのために怪我できるなら本望だよ」
しん、と車内に静寂が訪れる。
え、っと………これは、どういう意味でしょう……。
「……そんなに私のことを、」
「好きだよ」
「ギャアアアアアアアさらっと言わないでくださいまし!」
「前も言ったじゃん」
「やっぱり本気でしたの!?」
そうか。こんなに動揺するのは……男の人にこんなことを言われたのが初めてだからだ。
落ち着け私…!アリスに言われた通り、1人の女性としてきちんとお断りするのですわ。
「……あの、」
「ん?」
「その…」
「うん」
「…私はシャロン様が………好きなんですのよ…」
「……あぁ、なんだ。もしかしてここ最近よそよそしかったのって、返事しなきゃいけないって思って焦ってただけ?それでボクとの関係崩れるかもしれないって思って怖がってたの?」
1人納得したように頷いたバズ君は、その後こちらを馬鹿にするように鼻で笑った。
「そんなことで悩んでたの」
「そ、そりゃ悩みますわ…」
「ってことは、デートなんて言ったのもボクに一歩引かせるためか」
うわあああああバレましたわ!いや、バレても問題ないんですけれど!むしろバレるべきなんですけれど!
「うん、まぁ、ちゃんと言わなかったボクも悪いね。別に返事なんて求めてないよ。ただ好きだなって思ってるだけだから。恋人になりたいとも思ってない」
「……へ?」
「手を出そうなんて思ってないし、キャシーがリーダーを好きってことは知ってるし。想うだけならタダでしょ?」
「………」
「ボクはただ、キャシーを守りたいだけだよ。キャシーの隣で、キャシーの味方でいたい」
かっこいいことを言わないでほしい。
いつも私のことを困らせて楽しんでいるくせに、こういう時は困らせないように気を遣うだなんて。
悔しいけれど、今はバズ君に救われた。
何も考えなくていいと言われたみたいで、胸のすく思いがした。
「で、どうだったの?素敵だった?今回の“デート”のお相手だったフォックスは」
からかうように聞いてくるバズ君は、デートだなんて言った私をまだ面白がっているようだ。
「………シャロン様には劣りますわ。やはり私の理想の男性は、シャロン様しかおりませんのよ」
「そっか。キャシーらしいね」
ふふっと笑うバズ君は、いつもと違って見えた。
ただの兄妹と言われれば違う。ただの仲間と言われれば違う。恋人と言われればもちろん違う。
私たちの関係は、筆舌に尽くし難い。
――…でも、この名も無き関係が、私達2人の間にずっと有り続けますように。
私たちを良いところへ連れていってくれると言うジャックの車に付いていき、雪の積もった駐車場らしき場所に降りた。
少し高めの場所に位置するその駐車場からは、小さな街の雪景色が見下ろせた。
真っ白な粉で化粧したかのようなお洒落な建物が並んでいて、なかなか幻想的だ。
雪がキラキラ光って見える。
「綺麗…」
「こんな場所があったなんて知らなかったわ」
「観光地として有名ってわけでもないんだけどね。おとぎ話の中の世界に来たみたいだろ?」
私たちが喜んでいるのが分かるのか、得意げに話すジャック。
シャロンは携帯で写真を撮っていて、陽はそんなシャロンの隣で「おー」と感嘆の声を上げていて、フォックスは無表情で、バズ先生は感心したように頷いている。
キャシーはめちゃくちゃ嬉しそうな表情で頬をピンク色に染め、キャーキャー言いながらあっちへ行ったりこっちへ行ったり。
……この中で一番感情が表に出るのはキャシーみたい。
「車で行くには特別な許可が必要だから、ここからは歩いて街まで行こう」
ジャックが先頭を歩き、他は二列になって街まで降りていく。
街が近付くにつれて、通りには自家用車がほとんど走っておらず、大型バスが人を沢山乗せて走っているのが見えた。
「この街ではバスを使うことが多いの?」
「あぁ、数年前に都市計画事業があってね。自動車による大気汚染軽減のために公共交通システムを主に使うようになったんだよ。実はここ、最近じゃこの国で最も環境に優しい街として知られてるんだ」
へえ、と思ったのは私だけではないらしく、後ろでバズ先生が「興味深い取り組みだね」と言う。
街まで辿り着くと、上から見た時よりも建物が大きく感じられた。
通りには様々な店が並び、景観も優れている。
オペラ劇場や植物園もあるようで、“オペラ劇場は200m先”や“植物園は100m先”などと色んな言語で書かれた看板がある。栄えてるのねー。
「キャーッ!見てくださいまし!噴水につららがっ!!」
「はいはい、ちょっと落ち着こうねキャシー」
「だってこんな美しい街初めて来ましたのよ!バズ君もそうでしょう!?」
後ろの2人の間に気まずさはもうない。どうやらうまくいったみたいね。
嫌がるキャシーをバズ先生と同じ車に乗せたのはちょっと強引すぎたかもしれないと心配していたけれど、結果オーライだわ。
それにしても。
「さっきからチラチラ見られてる気がするのだけれどなぜかしら?」
道行く人々が私たちを見てはぽおっとした表情をしている。
「ジャックが先頭だからじゃね。色男オーラ醸し出してるし、そら気になるわ」
陽の推察が正しければ、ジャックは不必要なまでに女性を誘惑しているということになる。
「迷惑な男ね。そのオーラとやら抑えられないのかしら」
「いや、俺だけのせいじゃないと思うんだけど……」
ジャックは困ったようにちらりとシャロン達の方を見た。
「確かにこのメンツ、なんだかんだモテそうな男性ばかりですものね」
そう言うキャシーの言葉に、フォックスが否定する。
「おれは別にモテん」
「そうですの?…まぁ、フォックスさんは天然たらしですものね。気付いてないだけじゃありません?」
「たらし…?どこをどう見てそう思った」
「お姫様抱っこしたり抱き締めたり…あんな風に守られると女性はきゅんとくるものですのよ」
さっきの任務での話だろうか。フォックスはわけが分からんという顔をしているが、キャシーはからかうようにニヤニヤ笑っている。
「まぁ…フォックスがどうかは知らないけれど、ジャックがモテそうっていうのは私にもなんとなく分かる気がするわ」
「え?」
「…バズ君、その腕……」
思い当たる節がある。
……あの時、私を庇って撃たれたのだ。
銃弾全てがこちらへ来なかったというわけではないらしい。
「別に、かすっただけだよ」
「かすっただけに見えませんわ。処置はしましたの?」
「気にしなくていいって」
「私のせいで怪我したなら気にするに決まってますわ!」
「キャシーのために怪我できるなら本望だよ」
しん、と車内に静寂が訪れる。
え、っと………これは、どういう意味でしょう……。
「……そんなに私のことを、」
「好きだよ」
「ギャアアアアアアアさらっと言わないでくださいまし!」
「前も言ったじゃん」
「やっぱり本気でしたの!?」
そうか。こんなに動揺するのは……男の人にこんなことを言われたのが初めてだからだ。
落ち着け私…!アリスに言われた通り、1人の女性としてきちんとお断りするのですわ。
「……あの、」
「ん?」
「その…」
「うん」
「…私はシャロン様が………好きなんですのよ…」
「……あぁ、なんだ。もしかしてここ最近よそよそしかったのって、返事しなきゃいけないって思って焦ってただけ?それでボクとの関係崩れるかもしれないって思って怖がってたの?」
1人納得したように頷いたバズ君は、その後こちらを馬鹿にするように鼻で笑った。
「そんなことで悩んでたの」
「そ、そりゃ悩みますわ…」
「ってことは、デートなんて言ったのもボクに一歩引かせるためか」
うわあああああバレましたわ!いや、バレても問題ないんですけれど!むしろバレるべきなんですけれど!
「うん、まぁ、ちゃんと言わなかったボクも悪いね。別に返事なんて求めてないよ。ただ好きだなって思ってるだけだから。恋人になりたいとも思ってない」
「……へ?」
「手を出そうなんて思ってないし、キャシーがリーダーを好きってことは知ってるし。想うだけならタダでしょ?」
「………」
「ボクはただ、キャシーを守りたいだけだよ。キャシーの隣で、キャシーの味方でいたい」
かっこいいことを言わないでほしい。
いつも私のことを困らせて楽しんでいるくせに、こういう時は困らせないように気を遣うだなんて。
悔しいけれど、今はバズ君に救われた。
何も考えなくていいと言われたみたいで、胸のすく思いがした。
「で、どうだったの?素敵だった?今回の“デート”のお相手だったフォックスは」
からかうように聞いてくるバズ君は、デートだなんて言った私をまだ面白がっているようだ。
「………シャロン様には劣りますわ。やはり私の理想の男性は、シャロン様しかおりませんのよ」
「そっか。キャシーらしいね」
ふふっと笑うバズ君は、いつもと違って見えた。
ただの兄妹と言われれば違う。ただの仲間と言われれば違う。恋人と言われればもちろん違う。
私たちの関係は、筆舌に尽くし難い。
――…でも、この名も無き関係が、私達2人の間にずっと有り続けますように。
私たちを良いところへ連れていってくれると言うジャックの車に付いていき、雪の積もった駐車場らしき場所に降りた。
少し高めの場所に位置するその駐車場からは、小さな街の雪景色が見下ろせた。
真っ白な粉で化粧したかのようなお洒落な建物が並んでいて、なかなか幻想的だ。
雪がキラキラ光って見える。
「綺麗…」
「こんな場所があったなんて知らなかったわ」
「観光地として有名ってわけでもないんだけどね。おとぎ話の中の世界に来たみたいだろ?」
私たちが喜んでいるのが分かるのか、得意げに話すジャック。
シャロンは携帯で写真を撮っていて、陽はそんなシャロンの隣で「おー」と感嘆の声を上げていて、フォックスは無表情で、バズ先生は感心したように頷いている。
キャシーはめちゃくちゃ嬉しそうな表情で頬をピンク色に染め、キャーキャー言いながらあっちへ行ったりこっちへ行ったり。
……この中で一番感情が表に出るのはキャシーみたい。
「車で行くには特別な許可が必要だから、ここからは歩いて街まで行こう」
ジャックが先頭を歩き、他は二列になって街まで降りていく。
街が近付くにつれて、通りには自家用車がほとんど走っておらず、大型バスが人を沢山乗せて走っているのが見えた。
「この街ではバスを使うことが多いの?」
「あぁ、数年前に都市計画事業があってね。自動車による大気汚染軽減のために公共交通システムを主に使うようになったんだよ。実はここ、最近じゃこの国で最も環境に優しい街として知られてるんだ」
へえ、と思ったのは私だけではないらしく、後ろでバズ先生が「興味深い取り組みだね」と言う。
街まで辿り着くと、上から見た時よりも建物が大きく感じられた。
通りには様々な店が並び、景観も優れている。
オペラ劇場や植物園もあるようで、“オペラ劇場は200m先”や“植物園は100m先”などと色んな言語で書かれた看板がある。栄えてるのねー。
「キャーッ!見てくださいまし!噴水につららがっ!!」
「はいはい、ちょっと落ち着こうねキャシー」
「だってこんな美しい街初めて来ましたのよ!バズ君もそうでしょう!?」
後ろの2人の間に気まずさはもうない。どうやらうまくいったみたいね。
嫌がるキャシーをバズ先生と同じ車に乗せたのはちょっと強引すぎたかもしれないと心配していたけれど、結果オーライだわ。
それにしても。
「さっきからチラチラ見られてる気がするのだけれどなぜかしら?」
道行く人々が私たちを見てはぽおっとした表情をしている。
「ジャックが先頭だからじゃね。色男オーラ醸し出してるし、そら気になるわ」
陽の推察が正しければ、ジャックは不必要なまでに女性を誘惑しているということになる。
「迷惑な男ね。そのオーラとやら抑えられないのかしら」
「いや、俺だけのせいじゃないと思うんだけど……」
ジャックは困ったようにちらりとシャロン達の方を見た。
「確かにこのメンツ、なんだかんだモテそうな男性ばかりですものね」
そう言うキャシーの言葉に、フォックスが否定する。
「おれは別にモテん」
「そうですの?…まぁ、フォックスさんは天然たらしですものね。気付いてないだけじゃありません?」
「たらし…?どこをどう見てそう思った」
「お姫様抱っこしたり抱き締めたり…あんな風に守られると女性はきゅんとくるものですのよ」
さっきの任務での話だろうか。フォックスはわけが分からんという顔をしているが、キャシーはからかうようにニヤニヤ笑っている。
「まぁ…フォックスがどうかは知らないけれど、ジャックがモテそうっていうのは私にもなんとなく分かる気がするわ」
「え?」