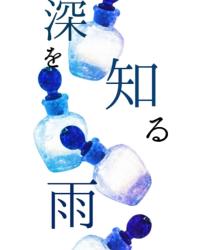―――
――――――
リバディーの9階から見たあの景色とは違い、今歩いている夜道はそう明るくはない。
しかし意外にもこの辺りの夜は騒がしいらしく、人通りはそこそこ多い。開いている店もちらほら見かける。
真冬の夜というだけあって風がとても冷たい。
今着ているトレンチコートとムートンブーツはお気に入りで、色がお揃いだ。
寒さ対策も兼ねて、万が一リバディーの誰かがいた場合にも私だと分かりにくくするためニット帽も被った。
「どうするぅ?なんか食べる?」
「この時刻に食べるはちょっと…」
「あぁ、太りそうだもんねぇ。大変だね?そういうの気にして生きるって」
嫌味かしら?シャロンは食べても太らないタイプだ。
嘲笑うような可愛い笑顔に軽く怒りを覚える。
「それで?買い物って言ったって何買うのよ」
「それだよねぇ。特に決めてないからぶらぶら歩こうよ。良さそうな物が目に留まったら買うってことで」
「なんの計画性もないわね…」
「深く考えずに気分で動くのも楽しいよぉ?」
にこ~っと笑うシャロンは今にも鼻歌でも歌い出しそうなくらいご機嫌。いつもこうだったら可愛いのに。
……この国でぶらぶらできるのも最後かもしれないし、私も楽しむべきね、こういう時は。
どこかの組織の人々だろうか、同じような制服を着た集団や、酔っぱらいの集団とすれ違う。
夜のさざめきとはこういう音を言うんだろうかと思う。
見つかってはいけない立場でありながら、シャロンが隣にいることで随分と安心している自分。…悔しいけど、この人が頼りになることは誰よりも分かっているのだ。
暫く並んで歩いていると、小さな手芸店が目に入った。
店の中の棚にあるヘアゴムには、紺色の上品なリボンがついている。一目で気に入ってしまった私はその店の前で立ち止まった。
と、ほぼ同時にシャロンも立ち止まる。
「あのヘアゴム、アリスに買ってあげたいなぁ」
まだ何も言っていないのに私の気に入ったヘアゴムを指差すシャロン。さすが、私の好みを分かっている。
「ちょうど私も欲しいと思ってたところよ」
「そお?似合いそうだよねぇ」
「でももうこの店閉まっちゃってるわね」
ドアには“closed”と書かれた看板がぶら下がっている。
「ざーんねん。…あ、でも人はいるみたいだからちょっと頼んでみようよぉ」
「え?…ちょっと、」
言うが早いか、シャロンはお店のドアをこんこんとノックした。
後片付けをしていたらしい女性店員が顔を上げこちらへやってくる。
「なんでしょう?」
女性店員はドアを開けてこちらに聞いてきた。
「あのヘアゴムがほしいんですけど、今買うことってできますかぁ?閉店時間過ぎてるのに申し訳ないんですけどぉ、俺らもうすぐ引っ越すんですよぉ。もうこの辺に来る機会ないでしょうしぃ、最後にどうしても買いたくってぇ」
頼み事する奴がそんなゆるゆるした喋り方するんじゃないわよ…。
しかし女性店員は私とシャロンを交互に見て、にっこり笑って「どうぞ」と中に入れてくれた。
「すいません、ありがとうございます」
シャロンってばそこまでしなくていいのにと思いながらも、折角買わせてもらえることになったので女性店員に頭を下げる。
「やっぱ紺色がいいよねぇ」
いくつか色がある中で、私がいいと思った色の物を選んでカウンターへ持って行くシャロン。
私の意見は聞かないのね…。まぁ、欲しいのはそれで合ってるからいいんだけど。
女性店員は微笑みながら会計をし、ふと聞いてくる。
「新婚さんですか?」
「え…いや、」
「まぁそんなところですよぉ」
何がそんなところよ。全く違うじゃない。
「奥さん思いなんですね~微笑ましいです」
女性店員はニコニコしながら可愛らしい袋にヘアゴムを入れてシャロンに渡す。
シャロンはそれを受け取りながらクスッと笑った。
「本当、目に入れても痛くないくらい可愛いですよ、うちの嫁さん」
……それ、孫とかによく言う言葉じゃないの。
店から出ると、激しい雪と風。音がうるさい。
あれだけ多かった人通りも今は殆どない。
「…まいったなぁ。天気予報見てなかった」
「思い付きで行動するからよ」
「そういうのいちいち確認すんの面倒じゃあん?あ、あそこ入ろ」
シャロンは私の手を引っ張って近くにあったホテルに入った。
ここ、そこそこ高級そうね…まぁ、シャロンが払ってくれるからいいんだけど。
お気に入りのトレンチコートがびしょびしょだ。とりあえず脱いで腕にかけた。
シャロンが部屋を取り、カードキーを受け取ってエレベーターに乗る。
他の宿泊客はもう寝ているのか、誰とも会わなかった。
こういう天気の悪い夜にいつもとは違う場所で寝るって、なんだかわくわくする。
鼻歌を歌いながらシャロンより先に部屋に入った。
ベージュとグレーを主体とした広い部屋だ。ダークブラウンのテーブルやローボードが高級感を出している。
添い寝好きのシャロンはダブルが良かったらしいが、ツインルームしか空いていなかったらしい。
「楽しそうだねぇ」
椅子に腰をかけてその座り心地を確認する私を見ながら、シャロンはクスクス笑って中へ入ってくる。
「そっちこそ楽しそうね。そんなに私を見るのが面白い?」
「可愛いなって思ってぇ」
シャロンはそう言っていつもの如く必要以上に私に近付き、水の滴る髪に触れた。
「随分濡れちゃったねぇ。風邪ひくとだめだからお風呂入っておいで」
…なんか子供扱いされてる気もするけど、非常に珍しいシャロンの気遣いだ。今は機嫌が良いらしい。お言葉に甘えさせてもらおう。
「濡れてるのはあなたもよ。ちゃんと拭いときなさいよね」
私はバスルームに重ねて置いてあったバスタオルをシャロンに投げて渡し、シャワーを浴びることにした。
―――
――――――
お風呂から上がり、体を拭いて髪を乾かした後バスタオルを巻いて部屋に戻った。
こうなるとは思ってなかったから、寝間着なんて用意してない。
まぁ、シャロンはいるけど布団被っとけば大丈夫でしょ。
「……アリスは俺が異性だって意識し始めたように見えて実は全く意識してないのかなぁ?」
シャロンは私の姿を見て溜め息を吐いた。
「は?」
「その格好で戻ってくるとは思わなかったぁ。何か着る物持ってきてって可愛くおねだりさせたかったのに」
「着る物があるなら着るわよ。でもないから仕方ないじゃない」
一応私だって女としての恥じらいくらい持っている。
でも状況に応じて諦めも必要だということもスパイ活動を通して知っている。
私はそのままベッドに入り、文句を言いたげなシャロンに目をやった。
メープルブラウンの髪。
女の子みたいに可愛い顔。
やや猫背な座り方。
私のよく知るシャロンがそこにいる。
――――――
リバディーの9階から見たあの景色とは違い、今歩いている夜道はそう明るくはない。
しかし意外にもこの辺りの夜は騒がしいらしく、人通りはそこそこ多い。開いている店もちらほら見かける。
真冬の夜というだけあって風がとても冷たい。
今着ているトレンチコートとムートンブーツはお気に入りで、色がお揃いだ。
寒さ対策も兼ねて、万が一リバディーの誰かがいた場合にも私だと分かりにくくするためニット帽も被った。
「どうするぅ?なんか食べる?」
「この時刻に食べるはちょっと…」
「あぁ、太りそうだもんねぇ。大変だね?そういうの気にして生きるって」
嫌味かしら?シャロンは食べても太らないタイプだ。
嘲笑うような可愛い笑顔に軽く怒りを覚える。
「それで?買い物って言ったって何買うのよ」
「それだよねぇ。特に決めてないからぶらぶら歩こうよ。良さそうな物が目に留まったら買うってことで」
「なんの計画性もないわね…」
「深く考えずに気分で動くのも楽しいよぉ?」
にこ~っと笑うシャロンは今にも鼻歌でも歌い出しそうなくらいご機嫌。いつもこうだったら可愛いのに。
……この国でぶらぶらできるのも最後かもしれないし、私も楽しむべきね、こういう時は。
どこかの組織の人々だろうか、同じような制服を着た集団や、酔っぱらいの集団とすれ違う。
夜のさざめきとはこういう音を言うんだろうかと思う。
見つかってはいけない立場でありながら、シャロンが隣にいることで随分と安心している自分。…悔しいけど、この人が頼りになることは誰よりも分かっているのだ。
暫く並んで歩いていると、小さな手芸店が目に入った。
店の中の棚にあるヘアゴムには、紺色の上品なリボンがついている。一目で気に入ってしまった私はその店の前で立ち止まった。
と、ほぼ同時にシャロンも立ち止まる。
「あのヘアゴム、アリスに買ってあげたいなぁ」
まだ何も言っていないのに私の気に入ったヘアゴムを指差すシャロン。さすが、私の好みを分かっている。
「ちょうど私も欲しいと思ってたところよ」
「そお?似合いそうだよねぇ」
「でももうこの店閉まっちゃってるわね」
ドアには“closed”と書かれた看板がぶら下がっている。
「ざーんねん。…あ、でも人はいるみたいだからちょっと頼んでみようよぉ」
「え?…ちょっと、」
言うが早いか、シャロンはお店のドアをこんこんとノックした。
後片付けをしていたらしい女性店員が顔を上げこちらへやってくる。
「なんでしょう?」
女性店員はドアを開けてこちらに聞いてきた。
「あのヘアゴムがほしいんですけど、今買うことってできますかぁ?閉店時間過ぎてるのに申し訳ないんですけどぉ、俺らもうすぐ引っ越すんですよぉ。もうこの辺に来る機会ないでしょうしぃ、最後にどうしても買いたくってぇ」
頼み事する奴がそんなゆるゆるした喋り方するんじゃないわよ…。
しかし女性店員は私とシャロンを交互に見て、にっこり笑って「どうぞ」と中に入れてくれた。
「すいません、ありがとうございます」
シャロンってばそこまでしなくていいのにと思いながらも、折角買わせてもらえることになったので女性店員に頭を下げる。
「やっぱ紺色がいいよねぇ」
いくつか色がある中で、私がいいと思った色の物を選んでカウンターへ持って行くシャロン。
私の意見は聞かないのね…。まぁ、欲しいのはそれで合ってるからいいんだけど。
女性店員は微笑みながら会計をし、ふと聞いてくる。
「新婚さんですか?」
「え…いや、」
「まぁそんなところですよぉ」
何がそんなところよ。全く違うじゃない。
「奥さん思いなんですね~微笑ましいです」
女性店員はニコニコしながら可愛らしい袋にヘアゴムを入れてシャロンに渡す。
シャロンはそれを受け取りながらクスッと笑った。
「本当、目に入れても痛くないくらい可愛いですよ、うちの嫁さん」
……それ、孫とかによく言う言葉じゃないの。
店から出ると、激しい雪と風。音がうるさい。
あれだけ多かった人通りも今は殆どない。
「…まいったなぁ。天気予報見てなかった」
「思い付きで行動するからよ」
「そういうのいちいち確認すんの面倒じゃあん?あ、あそこ入ろ」
シャロンは私の手を引っ張って近くにあったホテルに入った。
ここ、そこそこ高級そうね…まぁ、シャロンが払ってくれるからいいんだけど。
お気に入りのトレンチコートがびしょびしょだ。とりあえず脱いで腕にかけた。
シャロンが部屋を取り、カードキーを受け取ってエレベーターに乗る。
他の宿泊客はもう寝ているのか、誰とも会わなかった。
こういう天気の悪い夜にいつもとは違う場所で寝るって、なんだかわくわくする。
鼻歌を歌いながらシャロンより先に部屋に入った。
ベージュとグレーを主体とした広い部屋だ。ダークブラウンのテーブルやローボードが高級感を出している。
添い寝好きのシャロンはダブルが良かったらしいが、ツインルームしか空いていなかったらしい。
「楽しそうだねぇ」
椅子に腰をかけてその座り心地を確認する私を見ながら、シャロンはクスクス笑って中へ入ってくる。
「そっちこそ楽しそうね。そんなに私を見るのが面白い?」
「可愛いなって思ってぇ」
シャロンはそう言っていつもの如く必要以上に私に近付き、水の滴る髪に触れた。
「随分濡れちゃったねぇ。風邪ひくとだめだからお風呂入っておいで」
…なんか子供扱いされてる気もするけど、非常に珍しいシャロンの気遣いだ。今は機嫌が良いらしい。お言葉に甘えさせてもらおう。
「濡れてるのはあなたもよ。ちゃんと拭いときなさいよね」
私はバスルームに重ねて置いてあったバスタオルをシャロンに投げて渡し、シャワーを浴びることにした。
―――
――――――
お風呂から上がり、体を拭いて髪を乾かした後バスタオルを巻いて部屋に戻った。
こうなるとは思ってなかったから、寝間着なんて用意してない。
まぁ、シャロンはいるけど布団被っとけば大丈夫でしょ。
「……アリスは俺が異性だって意識し始めたように見えて実は全く意識してないのかなぁ?」
シャロンは私の姿を見て溜め息を吐いた。
「は?」
「その格好で戻ってくるとは思わなかったぁ。何か着る物持ってきてって可愛くおねだりさせたかったのに」
「着る物があるなら着るわよ。でもないから仕方ないじゃない」
一応私だって女としての恥じらいくらい持っている。
でも状況に応じて諦めも必要だということもスパイ活動を通して知っている。
私はそのままベッドに入り、文句を言いたげなシャロンに目をやった。
メープルブラウンの髪。
女の子みたいに可愛い顔。
やや猫背な座り方。
私のよく知るシャロンがそこにいる。