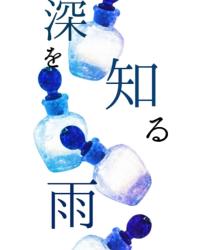「これはだな…その…」
「プレゼントですか?」
「…まぁ、そんな感じだ」
やっぱり。
「いつもいつも、そんなに沢山いりませんよ」
「いや、これだけは本当にニーナにあげるべきだと思ったんだ」
「前もそう言って高い物買ってきたじゃないですか」
「でもこれだけは…」
「ハイハイ。一体今度はなんなんですか?」
「…今見るのか?」
「もったいぶらないでくださいよ」
そう言って急かせば、エリックは渋々袋からプレゼント用にラッピングされた箱を出し、私に渡した。
開けてみれば、靴が入っていた。
薄水色と白色のリボンが巻かれたガラスの靴。
レーザークリスタルだろうか、ハート型の世界地図が描かれている。
光が当たってキラキラ光るそのハイヒールに見とれてしまう。
「不思議な形の地図ですね」
「これは正積図法の一つだ。頼んで彫り込んでもらった。…履いてくれるか?」
「もちろんですよ。素敵な靴をありがとうございます」
どうしよう、純粋に凄く嬉しい。おそるおそる靴に足を入れると…ぴったり。私の足のサイズを知っているとは、なかなか怖い。
「似合うな」
「そうですか?こういうのって、パーティーなんかでドレスを着る時に履く方が合ってると思うんですけど」
あいにく今着ているのは普段着だ。靴が綺麗すぎる分、全体的なバランスは悪い。
「いや。ニーナはそのままでも十分綺麗だ」
「そう…ですか」
頬と耳が熱くなって、今自分は顔が赤いのではないかと心配になってきた。こうもド直球に言われるとやはり照れるものがある。
私は俯き、ガラスの靴に目を向けた。こんなものを私にくれる人が現れるなんて、幼い頃は夢にも思わなかった。私はなんて幸せ者なんだろう。
「エリック。あなたと出会えて良かったです」
少々照れくさいけれど、今伝えておくべきだと思った。
顔を上げると、エリックは真っ直ぐこちらを見ていた。
「私は、今後お前を振り回すかもしれない」
「え?どうしたんですか急に。いつものことじゃないですか」
「……。これまで以上にだ」
「今更、何があったって付いていきますよ」
世界の果てまででも。
潮の香りを含む軽風が通り過ぎた。
繰り返す波音と自分の心臓の音が確かに聞こえる。
「ニーナ。私と―――結婚してくれないか」
!?
えっ…待って、私達まだ付き合ってもないのに。
この人色んな段階をぶっ飛ばした…仕事人間だし女性を口説いたことないんだろうなぁ…。
エリックのあまりに真剣な表情を見て思わず口角が上がりそうになるのを抑えるのに精一杯だ。いや、別に嘲笑っているわけではなく、純粋に可愛いなと思って。
「…えっと…結婚って、具体的に何をしたいんですか?今までと何かが変わるとは思えないんですが」
嫌だと言っているわけではなく、結婚というものが想像できない。
エリックが何をしたいのかにもよるけど、場合によっては期待に添えないかもしれない。
「私、子供ができない体なんです。過去にそういう調整を施されたので」
子供のいる家庭を築きたいという意味で言っているのなら、相手は私じゃいけない。瞬間、自分の体を疎ましく思った。
憎しみの感情がまた込み上げてきそうになった時、
「なんだ、そんなことか。結婚と言っても、別に子が欲しいわけではない。お前と家族になりたいんだ」
エリックがあっさりと言い放った。
家族……その特別な響きに、ほんわかとした温かさが胸に広がる。
「お前が欲しいと言うのなら、養子をもらうのもいいんじゃないか?犬や猫を飼うのもいいな。私は忙しくてなかなか相手ができないかもしれないが、時間をつくれる時はちゃんとつくるようにする。お前が辛い時は支える」
私に温もりを教えてくれた人。
過去にいた閉鎖的な世界から連れ出してくれた人。
私を家族にしたいと言ってくれる人。
私のことを、受け入れてくれる人。
「…好きです」
感情を口に出したら最後、溢れて止まらない。
好き。好き。好き好き好き好き。
私はもう奴隷じゃない。今なら自信を持って言える。
「私も、あなたと家族になりたいです…っ…」
“優雅な生活こそ最高の復讐である”
ということわざがある。
この人ならきっと私を、私が憎んでいる人たちよりも幸せにしてくれる。そう思うのだ。
「ありがとう」
エリックは嬉しそうに私を抱き締めた。
その温もりは、昔からずっと変わらない。
人の体温は温かいものなのだと再確認し、涙が溢れた。
《《<--->》》
-winter-
冬も本番といったところか、外に出ると吐く息が白くなる季節になった。
窓の外を見ればはらはらと雪が降っていて、木の枝に乗る雪が白い華のようにも見える。
「アリス、今日の夜どっかに買い物行かなぁい?」
そんなある日。いつもの如く外国語の勉強をしていると、不意にシャロンがそう提案してきた。
いきなりどうしたというのだろう。
「私は外出禁止じゃなかったのかしら?」
「俺が一緒に行くから問題ないよぉ。近々この国出るつもりだしぃ、最後に思い出づくりしとこうかなって思って」
「ボスが同行してくれりゃ百人力っすね」
今日は部屋に陽も来ている。陽とシャロンは付き合いが長いこともあってなかなか気心の知れた仲らしく、お互い信頼し合っているみたいだ。
…って、そんなことより。
「この国を出る?」
「リバディー襲撃した件でこの国じゃ警戒されまくりだしねぇ。久しぶりに大移動といこうよ」
元々どこかの国1つを拠点とした組織ではない。今までも国から国へ構成員全員を連れて移動したことは何度かあった。
…この国に来て印象深かったことと言えば、やっぱりあのリバディーで仕事をしたことかしら。
思えば去年の春、私はリバディーという組織の本拠地に初めて足を踏み入れた。
あれから一年が経とうとしてるのね…。
あの任務を最後に、私はスパイ活動をしていない。
今後するつもりもない。
今は目的を果たすことに集中したいのだ。
春が来れば私の20歳の誕生日もやってくる。
タイムリミットは近付いている。
ジャックからもらった薬を飲んだから、正確には20歳と半年。
ただ、研究者達の言っていた予定日は“20歳前後”と曖昧。
前後という言葉にどれほどの範囲が含まれているのか分からないものだから、半年延びたと言っても油断はできない。
協力者も増やしたいし…やることは山積み。
ジャックやフォックスが動いてくれているから、私の知らないところで何か進展があったかもしれない。
ジャックとゆっくり2人で話す機会が欲しいのに、シャロンが最近その時間を与えてくれない。
だから今のところ間接的にしか意味のない語学の勉強を毎日淡々と続けるしかないのだ。