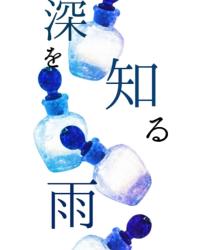俺は喜んでそれを受け入れた。
エマに触れるだけで生きていけるような気がした。
………満足、だった。
それからまた、2年ほどの月日が経った頃だった。
俺とエマの関係は変わらない。
ただ、月日が流れるにつれ俺の虚しさが増していった。
俺をブラッドと呼ぶエマに、自分は何をしているのだろうとふと我に返る時があった。
“身代わり”にも限界が来ていた。
――――その日は、日曜日だった。
「…手、繋いで」
俺はエマの擦れた声を聞いて、その手を縋るように握り締める。
喧嘩に強かったエマの手は、もう折れそうに細かった。
「何か話そうか」
「うん」
「俺ね、いつか妹に会いに行こうと思ってるんだ」
「うん」
「改めて兄妹としてやり直したい」
「……ん」
「今は無理かもしれないけど…何とかしてブラッドにも会うよ」
「……」
「その時はエマも一緒に行こうね」
「……」
「エマは前よりもブラッドと仲良くなれるかもね」
「……」
「…それはちょっと嫌だなぁ」
「……」
「本当はね、」
「……」
「代わりでなんかいたくないんだ」
「……」
「君に“俺”を見て欲しいんだ」
「……」
「でも、そんなこと頼んだりしないよ」
「……」
「俺は奴隷だから。君に飼われてるから。君が一番満たされることをする」
「……」
「…好きだよ」
「……」
「……エマ?」
「……」
「寝ちゃった?」
「……」
「…ねぇ、エマ」
「……」
「――…返事しろよっ…」
エマは眠ったように目を閉じていた。
どうしてそう思ったのか分からない。
でも、すぐにそうだと思った。
手が。手が。握り締めた手が。生きてないって伝えてた。温もりはまだあるのに。死人の手だと、そう思った。
「エマ…、」
怖かった。それまでに無いくらい、怖かった。
幼い頃強制労働させられたあの場所での暴力よりも、ずっとずっと恐ろしく感じた。
握り締めた手から。
温もりが消えていく。
深沈と、冬の夜が更けていった。
それからのことはあまり覚えていない。
現実感を得られないまま事が運び、多くの使用人がエマの部屋に集まった。
俺は主人の部屋に呼び出され、事情を話した。
「そうか」
主人のことを久しぶりに見たような気がした。
エマが俺達を飼うと言ったあの日から、この男とは擦れ違う程度だった。
少し老けたように感じる。
「死んだのか」
淡々と言うその横顔からは、動揺は読み取れなかった。
「最後は、一緒にいたのか?」
「…はい」
「あいつはお前達のことを気に入っていたからな」
「……」
「良い表情だ」
「…は?」
「まるで飼い主を亡くした犬だな」
床に向けていた視線を主人の方へ向ける。
――酷く。怪しげに笑っていた。
「あいつが死んだのだから、君の所有権は僕に戻ってくる」
こいつは何を言ってる?
「死に損ないの駒にしては良い仕事をしてくれた。あいつのおかげで、君に人間味が増したよ。これからそれを壊せると思うとたまらない」
こいつは、何を、言っている?
「…エマが、死んだんですよ。分かってますか」
「あぁ。それがどうした。所詮娘だろう」
――…殴ってしまおうかと思った。
憎たらしいこの男をこの手で痛め付けるのはどんなに気持ち良いだろうと思った。
でも、そうはしなかった。
俺にはまだやることがある。
ブラッドとエマを会わせなければならない。
殴ればすぐに使用人が来て、俺は捕まってしまう。
エマの葬式の日、俺は1人屋敷へ戻り、誰もいない空っぽの屋敷に火をつけた。
この屋敷にいる人間は、思い返せばまるで機械のようだった。
使用人も、あの主人も。
エマに温かい愛情を与えてやった人間は誰1人いない。
消えてしまえばいいと思った。
エマの過ごしたであろう冷たい時間を、その痕跡を、消してしまいたかった。
それは衝動的で、しかし計画的な行為だった。
赤い炎が広がっていく様を見て、物狂おしい感じがした。
「…さよなら」
俺はその日、屋敷とエマに別れを告げた。
逃げ出した俺は、ブラッドと連絡を取ることを試みた。
しかし、何度リバディーの本拠地を訪れても連絡を取ることはできなかった。
何を言ってもブラッドが応答しないため受付を強行突破して会いに行こうとしたが、それからは施設内に入ることも許されなくなった。
俺が出入り口付近の監視カメラに映ると容赦なく銃口を突き付けられるようになった。
個人的な理由で俺を出入り禁止にできるということは、どうやらブラッドはリバディーでそれなりの地位にいるらしい。
そのうち屋敷を燃やす前に盗んだ金も底を突き、俺は自然と非合法的な社会で生きる人間と関わりを持つようになった。
ブラッドが絶対に俺の申し出に応じないことを悟り、こうなってしまっては手段を選ぶべきではないと思った。
この社会で力を付け、ブラッドとの交渉材料をゆっくり探していこうと思った。
それに、俺に必要なのは金だけでなく情報もだった。
当たり前のように人権のある表社会の人々の空気はどうしても肌に合わなかった。
奴隷として生きていた時間分失った、世の中の常識や最低限の知識を得る必要があると感じていた。
非合法的な社会で俺のような人間はそう珍しくないようで、知っていて当たり前のことを聞いても特に気にする様子もなく応えてくれる人間がわんさといた。
おかげで新聞の内容も理解できるようになり、自分がどんな世界で、どんな国で生きていたのかを把握することができた。
マルチリンガルである俺には、様々な国での仕事が回ってきた。
俺は多くの人間と知り合い、情報を共有した。
しばらくこの社会で生きているだけで、より上手い生き方を覚えることができた。
人を騙すのは造作ないことだった。
人を壊すのも造作ないことだった。
本来の目的を忘れたわけではなかったが、俺は確かに歪んでいった。
人を騙して。
罪を犯して。
捕まって。
逃げて。
国から国へと移動して。
その途中だった――ブラッドが“春”という女の子を探していることを知ったのは。
兄弟だからこそ分かったのかもしれない、それが執着だということに。
俺は俺なりに春のことについて調べた。
それでも春の情報は見つからなかった。
詳しいことはどうしても分からなかった。
それでも俺は探した。
全てはエマの為だった。
あのブラッドが唯一執着した人間を利用すれば、ブラッドは俺からの頼みを聞いてくれるかもしれない。
俺との縁を切っているあいつでも、もう一度会ってくれるかもしれない。
エマの願いを――エマの墓場まで、付いてきてくれるかもしれない。
エマに触れるだけで生きていけるような気がした。
………満足、だった。
それからまた、2年ほどの月日が経った頃だった。
俺とエマの関係は変わらない。
ただ、月日が流れるにつれ俺の虚しさが増していった。
俺をブラッドと呼ぶエマに、自分は何をしているのだろうとふと我に返る時があった。
“身代わり”にも限界が来ていた。
――――その日は、日曜日だった。
「…手、繋いで」
俺はエマの擦れた声を聞いて、その手を縋るように握り締める。
喧嘩に強かったエマの手は、もう折れそうに細かった。
「何か話そうか」
「うん」
「俺ね、いつか妹に会いに行こうと思ってるんだ」
「うん」
「改めて兄妹としてやり直したい」
「……ん」
「今は無理かもしれないけど…何とかしてブラッドにも会うよ」
「……」
「その時はエマも一緒に行こうね」
「……」
「エマは前よりもブラッドと仲良くなれるかもね」
「……」
「…それはちょっと嫌だなぁ」
「……」
「本当はね、」
「……」
「代わりでなんかいたくないんだ」
「……」
「君に“俺”を見て欲しいんだ」
「……」
「でも、そんなこと頼んだりしないよ」
「……」
「俺は奴隷だから。君に飼われてるから。君が一番満たされることをする」
「……」
「…好きだよ」
「……」
「……エマ?」
「……」
「寝ちゃった?」
「……」
「…ねぇ、エマ」
「……」
「――…返事しろよっ…」
エマは眠ったように目を閉じていた。
どうしてそう思ったのか分からない。
でも、すぐにそうだと思った。
手が。手が。握り締めた手が。生きてないって伝えてた。温もりはまだあるのに。死人の手だと、そう思った。
「エマ…、」
怖かった。それまでに無いくらい、怖かった。
幼い頃強制労働させられたあの場所での暴力よりも、ずっとずっと恐ろしく感じた。
握り締めた手から。
温もりが消えていく。
深沈と、冬の夜が更けていった。
それからのことはあまり覚えていない。
現実感を得られないまま事が運び、多くの使用人がエマの部屋に集まった。
俺は主人の部屋に呼び出され、事情を話した。
「そうか」
主人のことを久しぶりに見たような気がした。
エマが俺達を飼うと言ったあの日から、この男とは擦れ違う程度だった。
少し老けたように感じる。
「死んだのか」
淡々と言うその横顔からは、動揺は読み取れなかった。
「最後は、一緒にいたのか?」
「…はい」
「あいつはお前達のことを気に入っていたからな」
「……」
「良い表情だ」
「…は?」
「まるで飼い主を亡くした犬だな」
床に向けていた視線を主人の方へ向ける。
――酷く。怪しげに笑っていた。
「あいつが死んだのだから、君の所有権は僕に戻ってくる」
こいつは何を言ってる?
「死に損ないの駒にしては良い仕事をしてくれた。あいつのおかげで、君に人間味が増したよ。これからそれを壊せると思うとたまらない」
こいつは、何を、言っている?
「…エマが、死んだんですよ。分かってますか」
「あぁ。それがどうした。所詮娘だろう」
――…殴ってしまおうかと思った。
憎たらしいこの男をこの手で痛め付けるのはどんなに気持ち良いだろうと思った。
でも、そうはしなかった。
俺にはまだやることがある。
ブラッドとエマを会わせなければならない。
殴ればすぐに使用人が来て、俺は捕まってしまう。
エマの葬式の日、俺は1人屋敷へ戻り、誰もいない空っぽの屋敷に火をつけた。
この屋敷にいる人間は、思い返せばまるで機械のようだった。
使用人も、あの主人も。
エマに温かい愛情を与えてやった人間は誰1人いない。
消えてしまえばいいと思った。
エマの過ごしたであろう冷たい時間を、その痕跡を、消してしまいたかった。
それは衝動的で、しかし計画的な行為だった。
赤い炎が広がっていく様を見て、物狂おしい感じがした。
「…さよなら」
俺はその日、屋敷とエマに別れを告げた。
逃げ出した俺は、ブラッドと連絡を取ることを試みた。
しかし、何度リバディーの本拠地を訪れても連絡を取ることはできなかった。
何を言ってもブラッドが応答しないため受付を強行突破して会いに行こうとしたが、それからは施設内に入ることも許されなくなった。
俺が出入り口付近の監視カメラに映ると容赦なく銃口を突き付けられるようになった。
個人的な理由で俺を出入り禁止にできるということは、どうやらブラッドはリバディーでそれなりの地位にいるらしい。
そのうち屋敷を燃やす前に盗んだ金も底を突き、俺は自然と非合法的な社会で生きる人間と関わりを持つようになった。
ブラッドが絶対に俺の申し出に応じないことを悟り、こうなってしまっては手段を選ぶべきではないと思った。
この社会で力を付け、ブラッドとの交渉材料をゆっくり探していこうと思った。
それに、俺に必要なのは金だけでなく情報もだった。
当たり前のように人権のある表社会の人々の空気はどうしても肌に合わなかった。
奴隷として生きていた時間分失った、世の中の常識や最低限の知識を得る必要があると感じていた。
非合法的な社会で俺のような人間はそう珍しくないようで、知っていて当たり前のことを聞いても特に気にする様子もなく応えてくれる人間がわんさといた。
おかげで新聞の内容も理解できるようになり、自分がどんな世界で、どんな国で生きていたのかを把握することができた。
マルチリンガルである俺には、様々な国での仕事が回ってきた。
俺は多くの人間と知り合い、情報を共有した。
しばらくこの社会で生きているだけで、より上手い生き方を覚えることができた。
人を騙すのは造作ないことだった。
人を壊すのも造作ないことだった。
本来の目的を忘れたわけではなかったが、俺は確かに歪んでいった。
人を騙して。
罪を犯して。
捕まって。
逃げて。
国から国へと移動して。
その途中だった――ブラッドが“春”という女の子を探していることを知ったのは。
兄弟だからこそ分かったのかもしれない、それが執着だということに。
俺は俺なりに春のことについて調べた。
それでも春の情報は見つからなかった。
詳しいことはどうしても分からなかった。
それでも俺は探した。
全てはエマの為だった。
あのブラッドが唯一執着した人間を利用すれば、ブラッドは俺からの頼みを聞いてくれるかもしれない。
俺との縁を切っているあいつでも、もう一度会ってくれるかもしれない。
エマの願いを――エマの墓場まで、付いてきてくれるかもしれない。