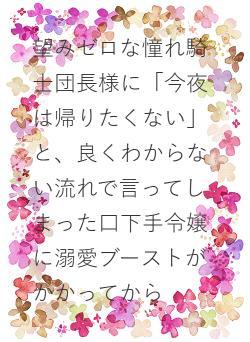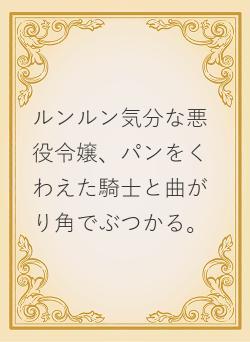ぼろぼろと泣き崩れるジェレミアは、今まで違うご令嬢を伴いすましていた王太子の威厳などもなく、ただ私のことが好きなんだとそういう気持ちが溢れて来ていた。
「ごめんなさい。私……それを咎めたら、嫌われてしまうと思ったの。けど、それは違ったのね」
私はジェレミアの気持ちを勝手に想像して、決めつけて……彼側から助けを求めている行動を、間違えて解釈していた。
「違う。君以外好きになったことなんて、ないよ。相手が皇帝でも、俺は関係ない」
そう言って私の背後に居たチェーザレを睨み付けたので、私は彼の勘違いを察して両手を振った。
「ジェレミア! 何を勘違いしているのか知らないけれど、チェーザレは何の関係もないただの従兄弟よ! 貴方も知っての通り、トリエヴァン帝国は血で血を洗うような継承権争いで、チェーザレが心安まるのは私の母……つまり、叔母の家であるアレイスター公爵邸に居る時だけだったのです」
チェーザレはとても苦しい立場で、母も大事にしてくれた兄の子である彼を心配していた。
「ごめんなさい。私……それを咎めたら、嫌われてしまうと思ったの。けど、それは違ったのね」
私はジェレミアの気持ちを勝手に想像して、決めつけて……彼側から助けを求めている行動を、間違えて解釈していた。
「違う。君以外好きになったことなんて、ないよ。相手が皇帝でも、俺は関係ない」
そう言って私の背後に居たチェーザレを睨み付けたので、私は彼の勘違いを察して両手を振った。
「ジェレミア! 何を勘違いしているのか知らないけれど、チェーザレは何の関係もないただの従兄弟よ! 貴方も知っての通り、トリエヴァン帝国は血で血を洗うような継承権争いで、チェーザレが心安まるのは私の母……つまり、叔母の家であるアレイスター公爵邸に居る時だけだったのです」
チェーザレはとても苦しい立場で、母も大事にしてくれた兄の子である彼を心配していた。