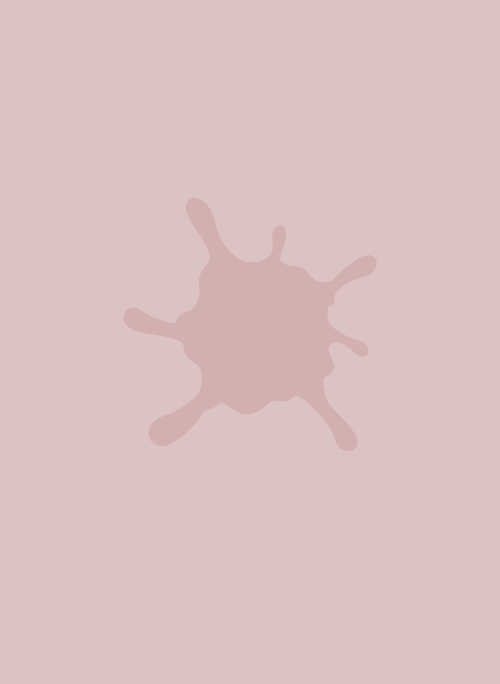「んんっ」
「痛む?本当に痛いのか?
演技じゃねぇよな?」
グリグリと力を入れられ、あまりの痛みにベッドシーツを握りしめる。
舌が抵抗するようにのたうつ。
ぼたぼたと唾液が垂れるのをながめながら、ポピィはいやらしく目尻を下げた。
「演技じゃあ…なさそうだな」
ぱっと舌が解放される。
痛みと苦しみで咳き込めば、シーツに染みた唾液には赤黒い血が混じっていた。
いったいなんのつもりなの…?
ポピィをにらみつけると、その顔はすっかり元の無表情に戻っていて
動きを見せたのは
彼の手に収まっている銃だった。
ぬらりと銃口が持ち上げられ、毛布越しに、わたしの足の膝部分へと下ろされる。
───ドンッ
前触れなく、引鉄がひかれた。