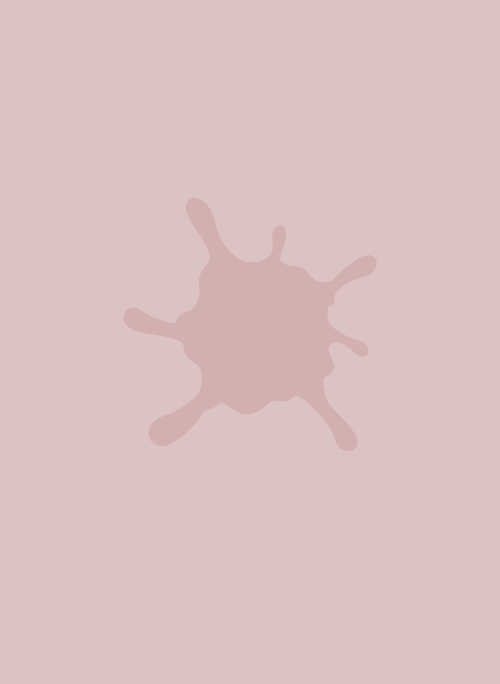すると、ポピィがおもむろにこちらへと歩いてくる。
「……っ?!」
その手には──銃が握られていた。
戦慄が走った体は石のように固まってしまう。
平和な世界で生きていたただの女子高生がお目にかかる機会などそうそうない物騒すぎる代物。
なぜそんなモノを持っているのか、なんて、考える間もなく、ポピィがベッドサイドまで来てしまう。
「生きてるか…ベンタ」
不思議な声音だった。
たずねているようで、どこかひとりごとのような…
「舌はどうだ。痛むか。見せてみろ」
遠慮のない手つきで顎をつかんでくる。
力の入らない唇はあっさりと開いてしまい、恥ずかしいくらいじっくり口内をのぞきこまれた。
「まだ再生しきれてねーな。
もっとよく見せろ」
ポピィはそのまま中に指を突っ込むと、わたしの欠損した舌をつまんで引っ張った。