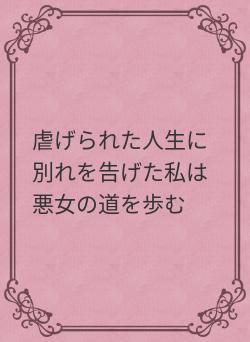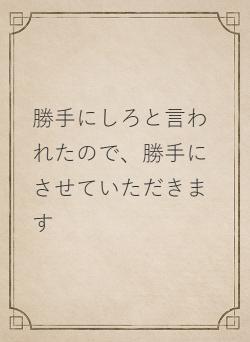「珍しいな?お前がそんな事言うなんて…」
亮平が私のベッドのそばに座りこむ。
「ごめんなさい…」
私は布団をかぶった。どうしよう、こんな事言うつもりなかったのに…気づけば勝手に口が動いていた。きっと呆れられたに違いない。
すると――
「分かったよ…」
「え?」
布団から顔を出すと亮平の顔を見た。
「いいの?本当に…?」
「何だよ?鈴音。そんな顔して…まるで子供の頃に戻ったみたいだな?泣きそうな顔して。大丈夫だよ、お前が寝るまではここにいるから、だから早く良くなれよ?」
「うん…ごめんね。ありがとう…」
「気にするなって。考えてみれば俺はここ最近、お前に自分の要求ばかり突き付けていたもんな?お前の都合なんか考えもしないで」
「…」
私は目を閉じて亮平の話を聞いていた。亮平の声は聞いていると心地いい。だから私はこの際だから、もう少しだけ我がままを言ってみたくなった。
「ねえ…亮平」
「何だ?」
「何か…話してよ…」
「ええ?何か話してって急にそんな事言われてもな…」
参ったなと言いながら亮平は床の上に座り、私のベッドに寄り掛かりながらポツリポツリと話し出した。
「鈴音…覚えてるか?高校生だった頃良く2人で部活の帰りカラオケに行ったよな?」
「うん。そうだったね。だってあの頃…カラオケブームだったじゃない」
「ああ‥翌日練習がない金曜日とかに行ってたな?」
「そうだったね…」
「それでさぁ…あれは高2の時だったかなぁ…鈴音、フリードリンク取りに行ったとき、他校の奴らからナンパされていただろう?」
「そんな事あったっけ…?」
「ああ、そうさ。お前がいつまでたっても戻ってこないから心配して見に行ったら、お前、ナンパされているから驚きだった」
「ふ~ん…」
「何だよ、随分他人ごとだな?自分の事なのに…。まあいいか、それで俺が様子を見にったらお前、腕を掴まれてたじゃないか。それで俺がその手を離せって言ったら喧嘩になって…」
あ…そう言えば何となく覚えている…。あの時、亮平すごくあの人たちに激怒してたっけ…。
「結局大騒ぎになって、店の人たちがやってきてさ。俺達、あいつらも含めて出禁にされてしまっただろう?」
「うん、そうだったね」
ようやく全部思い出せた。
「それで俺達、2人でカラオケ行くのやめたよな?」
「うん…やめちゃったね」
「だから、俺はあの日以来一度もカラオケにはもう行ってないんだ」
「え…?ど、どうして…」
しかし、亮平はそれには答えない。
「ほら、鈴音…眠そうだ。寝ろよ」
亮平は振り向くと私の頭を撫でてきた。フフ…気持ちいな…。どうして今夜はこんなに優しくしてくれるんだろう?やっぱりこれは夢なのかな?でもこんな幸せな夢なら…夢から覚めたくない…。
そして私は眠りについた―。
****
…どこかで人の話し声が聞こえてくる。
「ああ…分かってるって…だから泣くなって…。今帰るから…」
え…亮平の声…?
「当り前だろう?俺が好きなのは忍だけなんだから、だから泣きやめよ。ああ…もちろんだよ、忍。俺も…愛してるよ」
そして電話を切ると亮平がため息をついた。
「亮平…?」
うすぼんやりと目を開けると、亮平が驚いたように振り返った。
「あ…。お前、目が覚めたのか?」
「うん。ひょっとしてお姉ちゃんからなの?」
「あ、ああ…。クリスマスなのに…どうして1人きりにさせるんだって泣いているんだ。俺…行かないと」
亮平は私の返事も聞かずに立ちあがった。うん…そうだよね。亮平はお姉ちゃんの恋人なんだから…。
「じゃあね…ありがとう、亮平」
私はベッドから起き上がった。
「お、おい?!何で起き上がるんだよっ?!寝てればいいだろう?」
「だって…亮平が帰った後…鍵かけて戸締りしないといけないから…」
熱で頭がフラフラするけど、何とかベッドから起き上がった。
「…悪いな…」
私は黙って首を振った。
亮平はコートを着て、カバンを持った。
「じゃあな。冷蔵庫に色々食べ物用意しておいたから…食べろよ?」
玄関まで来ると亮平は振り返って私を見る。
「うん。色々ありがとう…」
壁に寄り掛かっているけれど身体がだるくて立っているだけでもやっとだった。
「それじゃ…」
そして亮平が玄関から出て行って、ドアが閉まると私はガチャリと鍵をかけ…壁に手を置きながらベッドまで何とかたどり着き…布団に入ったところで私の意識は無くなった――
亮平が私のベッドのそばに座りこむ。
「ごめんなさい…」
私は布団をかぶった。どうしよう、こんな事言うつもりなかったのに…気づけば勝手に口が動いていた。きっと呆れられたに違いない。
すると――
「分かったよ…」
「え?」
布団から顔を出すと亮平の顔を見た。
「いいの?本当に…?」
「何だよ?鈴音。そんな顔して…まるで子供の頃に戻ったみたいだな?泣きそうな顔して。大丈夫だよ、お前が寝るまではここにいるから、だから早く良くなれよ?」
「うん…ごめんね。ありがとう…」
「気にするなって。考えてみれば俺はここ最近、お前に自分の要求ばかり突き付けていたもんな?お前の都合なんか考えもしないで」
「…」
私は目を閉じて亮平の話を聞いていた。亮平の声は聞いていると心地いい。だから私はこの際だから、もう少しだけ我がままを言ってみたくなった。
「ねえ…亮平」
「何だ?」
「何か…話してよ…」
「ええ?何か話してって急にそんな事言われてもな…」
参ったなと言いながら亮平は床の上に座り、私のベッドに寄り掛かりながらポツリポツリと話し出した。
「鈴音…覚えてるか?高校生だった頃良く2人で部活の帰りカラオケに行ったよな?」
「うん。そうだったね。だってあの頃…カラオケブームだったじゃない」
「ああ‥翌日練習がない金曜日とかに行ってたな?」
「そうだったね…」
「それでさぁ…あれは高2の時だったかなぁ…鈴音、フリードリンク取りに行ったとき、他校の奴らからナンパされていただろう?」
「そんな事あったっけ…?」
「ああ、そうさ。お前がいつまでたっても戻ってこないから心配して見に行ったら、お前、ナンパされているから驚きだった」
「ふ~ん…」
「何だよ、随分他人ごとだな?自分の事なのに…。まあいいか、それで俺が様子を見にったらお前、腕を掴まれてたじゃないか。それで俺がその手を離せって言ったら喧嘩になって…」
あ…そう言えば何となく覚えている…。あの時、亮平すごくあの人たちに激怒してたっけ…。
「結局大騒ぎになって、店の人たちがやってきてさ。俺達、あいつらも含めて出禁にされてしまっただろう?」
「うん、そうだったね」
ようやく全部思い出せた。
「それで俺達、2人でカラオケ行くのやめたよな?」
「うん…やめちゃったね」
「だから、俺はあの日以来一度もカラオケにはもう行ってないんだ」
「え…?ど、どうして…」
しかし、亮平はそれには答えない。
「ほら、鈴音…眠そうだ。寝ろよ」
亮平は振り向くと私の頭を撫でてきた。フフ…気持ちいな…。どうして今夜はこんなに優しくしてくれるんだろう?やっぱりこれは夢なのかな?でもこんな幸せな夢なら…夢から覚めたくない…。
そして私は眠りについた―。
****
…どこかで人の話し声が聞こえてくる。
「ああ…分かってるって…だから泣くなって…。今帰るから…」
え…亮平の声…?
「当り前だろう?俺が好きなのは忍だけなんだから、だから泣きやめよ。ああ…もちろんだよ、忍。俺も…愛してるよ」
そして電話を切ると亮平がため息をついた。
「亮平…?」
うすぼんやりと目を開けると、亮平が驚いたように振り返った。
「あ…。お前、目が覚めたのか?」
「うん。ひょっとしてお姉ちゃんからなの?」
「あ、ああ…。クリスマスなのに…どうして1人きりにさせるんだって泣いているんだ。俺…行かないと」
亮平は私の返事も聞かずに立ちあがった。うん…そうだよね。亮平はお姉ちゃんの恋人なんだから…。
「じゃあね…ありがとう、亮平」
私はベッドから起き上がった。
「お、おい?!何で起き上がるんだよっ?!寝てればいいだろう?」
「だって…亮平が帰った後…鍵かけて戸締りしないといけないから…」
熱で頭がフラフラするけど、何とかベッドから起き上がった。
「…悪いな…」
私は黙って首を振った。
亮平はコートを着て、カバンを持った。
「じゃあな。冷蔵庫に色々食べ物用意しておいたから…食べろよ?」
玄関まで来ると亮平は振り返って私を見る。
「うん。色々ありがとう…」
壁に寄り掛かっているけれど身体がだるくて立っているだけでもやっとだった。
「それじゃ…」
そして亮平が玄関から出て行って、ドアが閉まると私はガチャリと鍵をかけ…壁に手を置きながらベッドまで何とかたどり着き…布団に入ったところで私の意識は無くなった――